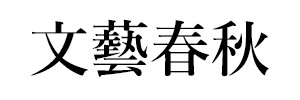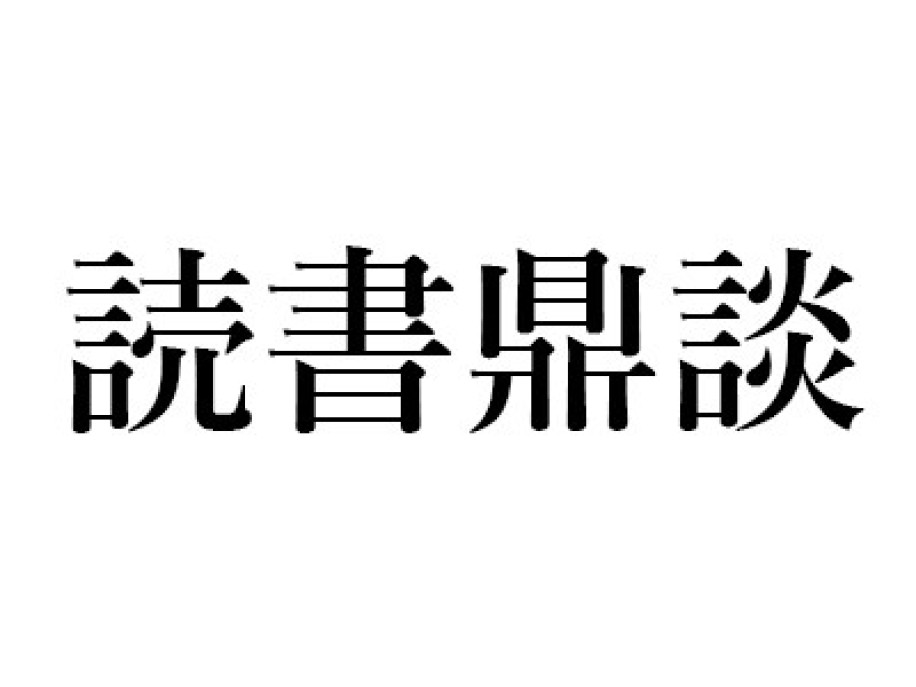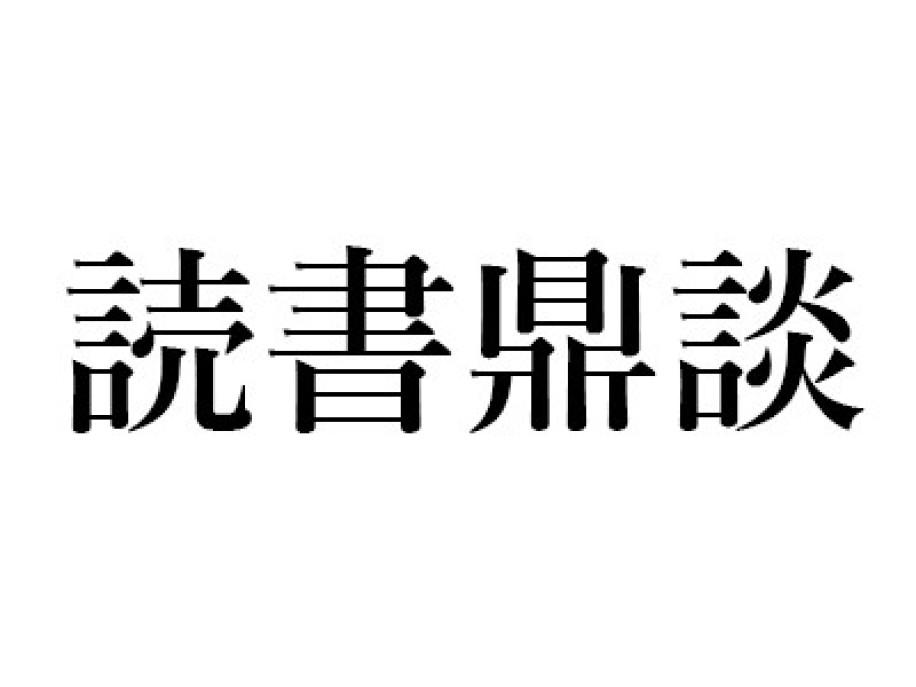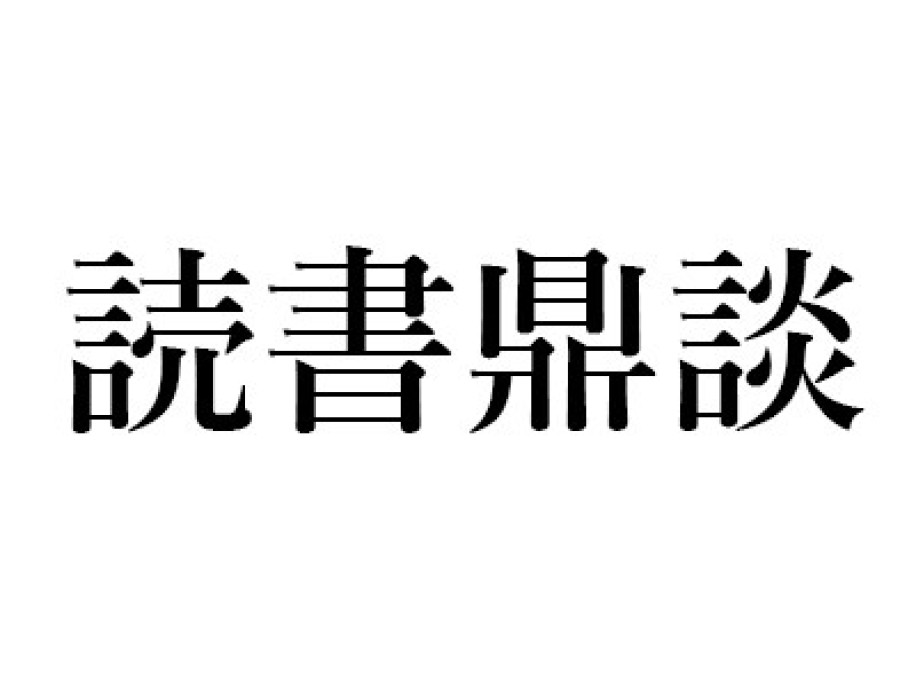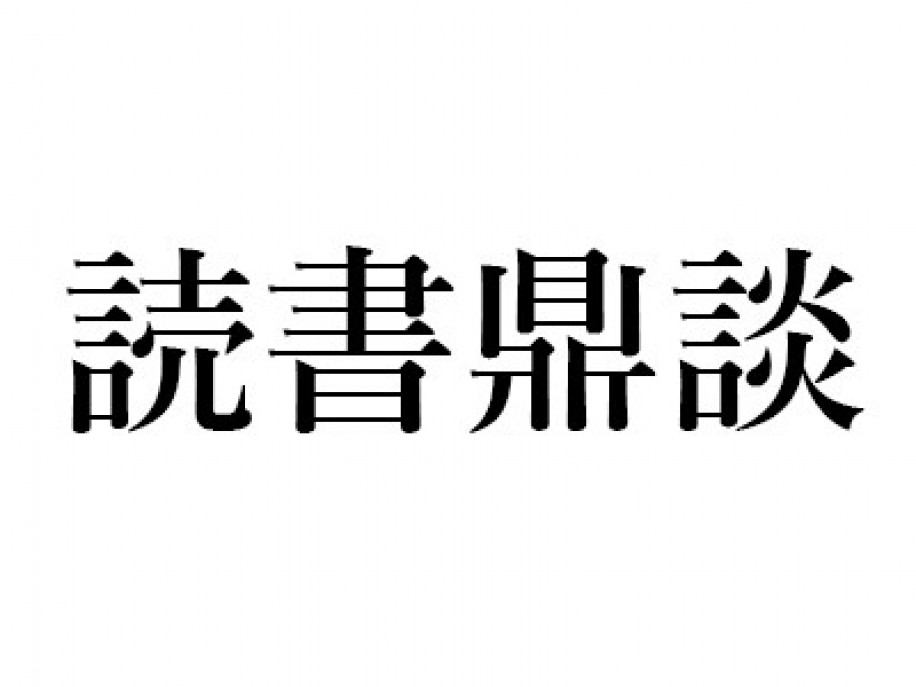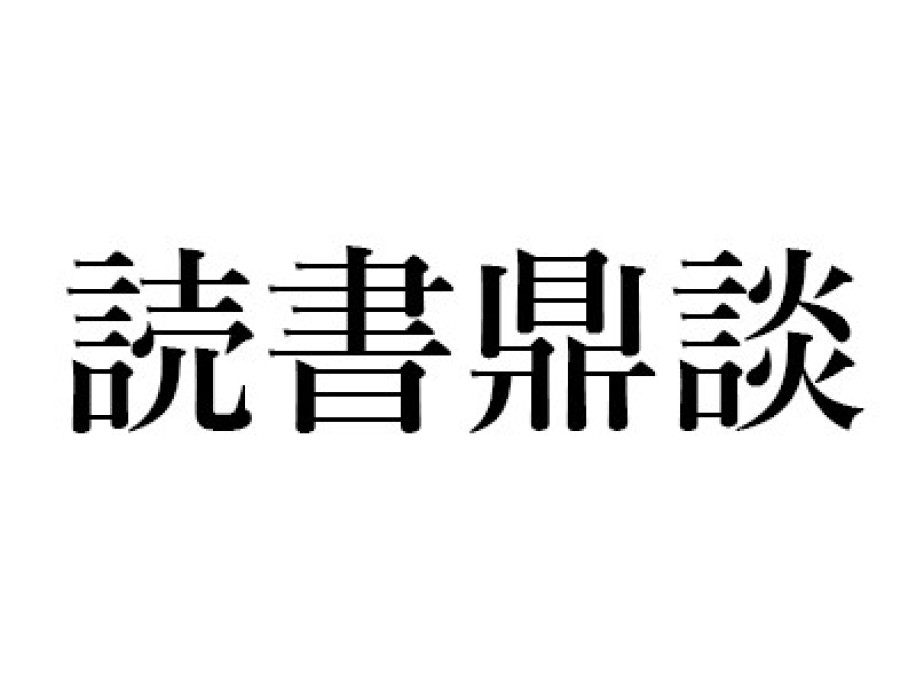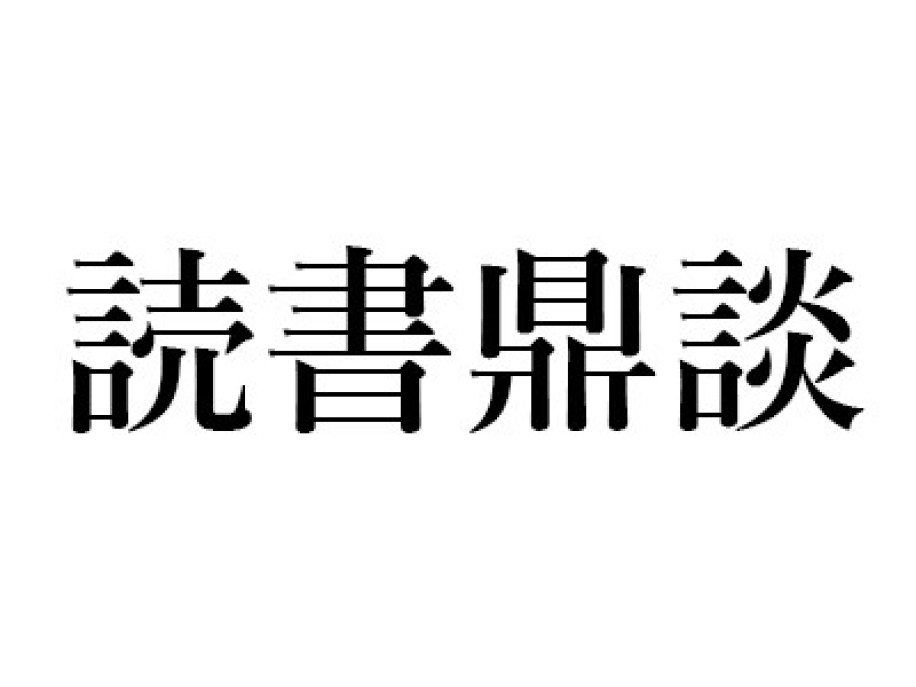対談・鼎談
良知力『向う岸からの世界史』(筑摩書房)
丸谷 良知力(らちつとむ)さんは一橋大学の教授だそうです。ドイツ社会思想史の専門家で、へーゲル左派、ことに初期マルクスの研究者であります。
この本は、第一部と第二部が哲学論ないし史論でかなりむずかしい。第三部が「ウィーン便り」になっていて、これがわりあいわかり易い。その中でも、「ガスト・アルバイターとしての社会主義」が、かなり鮮明に著者の考え方を示していて、いわばこの本全体を読む手がかりになります。
ガスト・アルバイターというのは、外国からきた出稼ぎ労働者のことで、ユーゴ、トルコ、ギリシャなどの貧民なんですね。たとえば一人が契約して家を借りると、そこに三家族も四家族も入りこみ、ベッドを二交替か三交替で使う。彼らは西欧の「きたない仕事」を一手に引き受け、その一方、社会の混乱や犯罪の温床になっている面もかなりある。「ウィーンのオーストリア人労働者がプロレタリアなら、彼らはプロレタリア以下」といわれています。そして著者は、
〈いまやガスト・アルバイターが西欧のプロレタリアートの代役を勤めているのじゃないか〉
という感想をもった。
そのあとで、良知さんはこう考えるんです。社会主義の土台となるプロレタリアートは、都市共同体としての市民社会から出てきたものじゃなくて、市民社会の外から、深い底のほうから「死霊」のように出てきて、西欧市民社会を脅かしたのじゃないだろうか。
この考え方の前提として一八四八年の革命におけるスラブ系の難民たちの姿があるわけです。
著者によれば、プロレタリアートを手工業職人や工場労働者とほぼ同一視する規定のしかたは、当時の人々のプロレタリア観と違うし、当時のいわゆるプロレタリアの実態とも違う。むしろ実態としては、プロレタリアートは「廃疾者、労働不能者、怠け者、放浪者、乞食、やくざ、売春婦、犯罪者等々」であった。
こういう指摘は、マルクシズムが生まれ、形成される地盤を非常によく説明してくれるんです。つまり、ぼくの考えでは、西欧市民社会の抱いた恐怖感を、マルクスが天才的に利用したということになるんじゃないか。そのへんの呼吸を、良知さんは、ガスト・アルバイターの群れに接することで感じ取った。それは一種の史眼であるといっていい。
この本の論旨はゴタゴタしていて、まとめにくいし、論理は途中で停滞したり旋回したりしていて、模索の連続という感じがします。しかし、マルクシズムという思想の成立の背景を知るためには、いわば資料集として絶好の本ではないかと思いました。
山崎 遠藤さんの本が日本人の立場から見たキリスト教へのアピールであるとすると、この本は日本人の立場から見たマルクス主義に対する悲しき訴えであるという感じがしました。
マルクスをふくめていわゆるヘーゲル左派の歴史家たちは、非常に強烈な差別思想の持ち主であって、「アジア的停滞」という有名な言葉で象徴されるように、ヨーロッパでないものに対する激烈な蔑視の上に成り立っていたことを、まず著者は指摘します。その上で、ウィーン革命の原動力が、当時の概念によるプロレタリアートでもなんでもない、ただのクズであったという事実を指摘している。そのクズの中身を洗ってみれば、実は広義のアジア人ではなかったか。したがって、ヨーロッパの正統革命家が見落としていたところに、西洋の革命の芽があって、その中身になっているのは、スラブをふくめたアジアである、ということなのだろうと思います。
著者の執念深さたるや、現代までおよんでいまして、彼は、六〇年代の学生運動のリーダーであるルーディ・ドゥチュケを引き出してくる。ドゥチュケがレーニンを批判するときに、「ロシアの半アジア的性格を認識しなかったのがレーニンの誤りである」といっている。要するに、マルクス主義の世界にも、帝国主義者と同じ程度に民族的偏見が根強いわけで、そのことに対する反感が、この本にははっきり出ている。
それにしても、この中で比較的学問的に書かれている第一部には、かなり問題があると思いました。文章の表面を読む限り、何を書こうとされているのか一向にわからない。まず文章の上で一例を挙げますと、
〈だが彼らはなお依然として理論的であった。彼らが理論的であらざるをえなかったのは、彼らの発想が世界史的だったからである。あるいは、彼らは世界史的であったために理論的であらざるをえなかったのである〉
これはタウトロジー(同語反復)つまり、同じことの繰り返しなんですね。
たとえば、
〈彼らが理論的であらざるを得なかったのは、彼らの発想が世界史的だったからである。あるいは、彼らが世界史的であったのは、理論的であったからである〉
というのならわかる。しかし、これはただ同じ言葉をひっくり返しているだけです。
そういうような文章が随所にありまして、どうも筋を追ってゆくのがたいへん苦しい。それから当時の社会民主主義者の立場からいえば、労働者以下の人たちの発生の理由として、十九世紀半ばの人口の急増を、著者はあげているわけですが、人口の急増がどうして起こったのかということは何ら触れられていない。その前に、著者は問題を提起しているわけです。つまり、工業化が興ったからプロレタリアートができたのか、工業化が未発達だったからプロレタリアートができたのか、という大事な議論をもち出しながら、人口急増の原因に少しも触れていないので、何やらキツネにつままれたような気がする。そうすると、それをめぐって、当時の革命家のあいだで意見が分かれた、といわれても、どっちが正しかったのかさっぱりわからない。
したがって、素人が見ると、これは歴史学者の書く文章なのだろうかと、ちょっと疑わしくなりました。
木村 わたしは、日本のキリスト教徒の書く本と同じように、日本のマルクシストの書く本も好きじゃない(笑)。
つまり、非常に型どおりの書き方をして、そこにイマジナティブ・パワーの豊かに働いた、自分なりの目で書いたものが見られないからおもしろくないんです。
ところが、この本はそうじゃないですね。ご自身、一八四八年のウィーン革命を、「プロレタリアート革命」といっていながら、しかもそのプロレタリアートが怠け者だったり、売春婦だったり、ばくち打ちだったりするような、そういう現実をちゃんと書いている。その点、非常に正直な方ですし、資料も丹念に読んでいらっしゃる。
その意味では、ある程度の共感をもって読めました。
一八四八年の革命はブルジョア革命といわれているけれども、実は、革命側の人間も反革命側の人間も市民じゃなかった。革命側は、どうしようもないプロレタリアートで、おそらくスラブ人ではなかったか。反革命の側はクロアチア人であった。こういう人たちが体制側にも反体制側にも、実質的に大きな力を果たしながら、歴史の上では無視されて消えてしまっている。そのことに対する無限の恨みが、著者にはあるんですね。
そこまでは、わたしもわかる。ところがそれから先がわかりません。
それではなぜ、四八年のウィーンでの事実上は暴動にすぎないものをプロレタリア革命、あるいは「意識せざるプロレタリア革命」などと、著者はいうのでしょうか。
つまり、釜ヶ崎とかニューヨークで夏起きる暴動みたいなものと、ウィーン暴動はどこが違うのか、そこには革命といわなければいけないどのような特性があるのかといった積極的な理論づけが、この本にはまったく欠如していると思うんです。
そういう意味では、きわめてロマンチックな、またマルクシストとしてのいらだちの表明じゃないかという気がしました。
山崎 この本のタイトルにある“向う岸”という言葉は、たいへん大事な用語であるらしいですね。アレクサンドル・ゲルツェンに『向う岸から』という本があるんですね。しかし、その紹介はこの文章のどこにもない。ずうっと読んでいきますと、突然、〈ゲルツェンの作品『向う岸から』をマルヴィーダが読むのは〉という形で出てくる。
これはやはり、作文の書き方として非常にまずい。つまり、「向う岸から」という言葉をよく知っている仲間内に対して書かれた文章であるならともかく、不特定多数の読者のために出版されているんですから。
丸谷 いや、ぼくは、これは仲間内のために書かれた本だと思います。この本の書き方が、よくいえば奔放、悪くいえば乱雑なのは、ごく狭いサークルのために書かれている本だからだと思う。
木村 これはきわめてパセティックな本で、自分自身の激情が抑えられない、自分の思いこみが前提にあって書いているから、仲間にもわからない面があるんじゃないかという気がしますね。
丸谷 仲間というものは、了解事項があるから、わかってくれるわけですね。わかってくれなければ仲間じゃなくなる(笑)。
木村 御説ごもっともですが、自分がわかっていることと、自分以外の人がわかっていることの区別がついてないと思うんですね。
山崎 少し同情的にいいますと、日本のマルクス主義者が現在辿り着いている、ある一つの地点というものは、はっきり読みとれると思うんです。
「あとがき」にこういうことが書いてある。
心情的には、なるほど、こういう地点に日本のマルクス主義者のある種の人たちはいるのかな、ということはよくわかります。その意味では、ぼくは、知らない世界の地図を見せてもらったような、ある感慨はあるんです。
木村 わたしも、一つまったく共感したところがあります。
これは非常に大事な指摘だと思うんです。つまり、自分をあちら側から、別の世界から見てみる、そういう態度があってはじめて客観的な認識もできるし、自分の考え方を普遍化し得る。著者が、その意味でガスト・アルバイターないしはプロレタリアートの世界に大きな関心を懐くこと自体は、まことに大切なことで、そこから市民の世界とか革命の全体像をいま一歩はっきりと見せてほしかったと思うんですよ。
山崎 いまは世界的に民族主義が非常な勢いで擡頭しているんですね。これは考えてみると、たいへん不思議なことです。かつて人類は民族主義を叫んで、お互いに血を流し合っていた。そこヘマルクスが現われて、大ざっぱにいえば「本質的な戦いは民族の争いではなく、階級の争いなんだ」といったはずなんですね。それから何十年か経ち、社会主義社会ができてみれば、その中でも民族同士の争いをやっていて、いまや世界は民族の争いのほうが深刻でしょう。
木村 そうそう。
丸谷 だから、大抵のマルクス主義者は民族問題を考えないふりをしてすませているわけね。ところが、この本の著者は多少は考えている。
山崎 おまけに、この著者の文章を素直に読むと、当時集まったプロレタリアートの要求がかなり無茶だ、というふうにも書いてあるんですよ。それまで政府は一所懸命、貧民救済をやってきたのに、民衆がどんどんつけあがって、いくらでも給料を要求するからこんなことになったんだ、と書いてある。
木村 そこは本当に読ませるところですね。
丸谷 マルキシズムの歴史家にしては、こんなことに触れていいんだろうかと思うようなことに触れている。そこがぼくは、非常におもしろかった。
木村 そう。本当に正直な方です。
【この対談・鼎談が収録されている書籍】
この本は、第一部と第二部が哲学論ないし史論でかなりむずかしい。第三部が「ウィーン便り」になっていて、これがわりあいわかり易い。その中でも、「ガスト・アルバイターとしての社会主義」が、かなり鮮明に著者の考え方を示していて、いわばこの本全体を読む手がかりになります。
ガスト・アルバイターというのは、外国からきた出稼ぎ労働者のことで、ユーゴ、トルコ、ギリシャなどの貧民なんですね。たとえば一人が契約して家を借りると、そこに三家族も四家族も入りこみ、ベッドを二交替か三交替で使う。彼らは西欧の「きたない仕事」を一手に引き受け、その一方、社会の混乱や犯罪の温床になっている面もかなりある。「ウィーンのオーストリア人労働者がプロレタリアなら、彼らはプロレタリア以下」といわれています。そして著者は、
〈いまやガスト・アルバイターが西欧のプロレタリアートの代役を勤めているのじゃないか〉
という感想をもった。
そのあとで、良知さんはこう考えるんです。社会主義の土台となるプロレタリアートは、都市共同体としての市民社会から出てきたものじゃなくて、市民社会の外から、深い底のほうから「死霊」のように出てきて、西欧市民社会を脅かしたのじゃないだろうか。
この考え方の前提として一八四八年の革命におけるスラブ系の難民たちの姿があるわけです。
著者によれば、プロレタリアートを手工業職人や工場労働者とほぼ同一視する規定のしかたは、当時の人々のプロレタリア観と違うし、当時のいわゆるプロレタリアの実態とも違う。むしろ実態としては、プロレタリアートは「廃疾者、労働不能者、怠け者、放浪者、乞食、やくざ、売春婦、犯罪者等々」であった。
こういう指摘は、マルクシズムが生まれ、形成される地盤を非常によく説明してくれるんです。つまり、ぼくの考えでは、西欧市民社会の抱いた恐怖感を、マルクスが天才的に利用したということになるんじゃないか。そのへんの呼吸を、良知さんは、ガスト・アルバイターの群れに接することで感じ取った。それは一種の史眼であるといっていい。
この本の論旨はゴタゴタしていて、まとめにくいし、論理は途中で停滞したり旋回したりしていて、模索の連続という感じがします。しかし、マルクシズムという思想の成立の背景を知るためには、いわば資料集として絶好の本ではないかと思いました。
山崎 遠藤さんの本が日本人の立場から見たキリスト教へのアピールであるとすると、この本は日本人の立場から見たマルクス主義に対する悲しき訴えであるという感じがしました。
マルクスをふくめていわゆるヘーゲル左派の歴史家たちは、非常に強烈な差別思想の持ち主であって、「アジア的停滞」という有名な言葉で象徴されるように、ヨーロッパでないものに対する激烈な蔑視の上に成り立っていたことを、まず著者は指摘します。その上で、ウィーン革命の原動力が、当時の概念によるプロレタリアートでもなんでもない、ただのクズであったという事実を指摘している。そのクズの中身を洗ってみれば、実は広義のアジア人ではなかったか。したがって、ヨーロッパの正統革命家が見落としていたところに、西洋の革命の芽があって、その中身になっているのは、スラブをふくめたアジアである、ということなのだろうと思います。
著者の執念深さたるや、現代までおよんでいまして、彼は、六〇年代の学生運動のリーダーであるルーディ・ドゥチュケを引き出してくる。ドゥチュケがレーニンを批判するときに、「ロシアの半アジア的性格を認識しなかったのがレーニンの誤りである」といっている。要するに、マルクス主義の世界にも、帝国主義者と同じ程度に民族的偏見が根強いわけで、そのことに対する反感が、この本にははっきり出ている。
それにしても、この中で比較的学問的に書かれている第一部には、かなり問題があると思いました。文章の表面を読む限り、何を書こうとされているのか一向にわからない。まず文章の上で一例を挙げますと、
〈だが彼らはなお依然として理論的であった。彼らが理論的であらざるをえなかったのは、彼らの発想が世界史的だったからである。あるいは、彼らは世界史的であったために理論的であらざるをえなかったのである〉
これはタウトロジー(同語反復)つまり、同じことの繰り返しなんですね。
たとえば、
〈彼らが理論的であらざるを得なかったのは、彼らの発想が世界史的だったからである。あるいは、彼らが世界史的であったのは、理論的であったからである〉
というのならわかる。しかし、これはただ同じ言葉をひっくり返しているだけです。
そういうような文章が随所にありまして、どうも筋を追ってゆくのがたいへん苦しい。それから当時の社会民主主義者の立場からいえば、労働者以下の人たちの発生の理由として、十九世紀半ばの人口の急増を、著者はあげているわけですが、人口の急増がどうして起こったのかということは何ら触れられていない。その前に、著者は問題を提起しているわけです。つまり、工業化が興ったからプロレタリアートができたのか、工業化が未発達だったからプロレタリアートができたのか、という大事な議論をもち出しながら、人口急増の原因に少しも触れていないので、何やらキツネにつままれたような気がする。そうすると、それをめぐって、当時の革命家のあいだで意見が分かれた、といわれても、どっちが正しかったのかさっぱりわからない。
したがって、素人が見ると、これは歴史学者の書く文章なのだろうかと、ちょっと疑わしくなりました。
木村 わたしは、日本のキリスト教徒の書く本と同じように、日本のマルクシストの書く本も好きじゃない(笑)。
つまり、非常に型どおりの書き方をして、そこにイマジナティブ・パワーの豊かに働いた、自分なりの目で書いたものが見られないからおもしろくないんです。
ところが、この本はそうじゃないですね。ご自身、一八四八年のウィーン革命を、「プロレタリアート革命」といっていながら、しかもそのプロレタリアートが怠け者だったり、売春婦だったり、ばくち打ちだったりするような、そういう現実をちゃんと書いている。その点、非常に正直な方ですし、資料も丹念に読んでいらっしゃる。
その意味では、ある程度の共感をもって読めました。
一八四八年の革命はブルジョア革命といわれているけれども、実は、革命側の人間も反革命側の人間も市民じゃなかった。革命側は、どうしようもないプロレタリアートで、おそらくスラブ人ではなかったか。反革命の側はクロアチア人であった。こういう人たちが体制側にも反体制側にも、実質的に大きな力を果たしながら、歴史の上では無視されて消えてしまっている。そのことに対する無限の恨みが、著者にはあるんですね。
そこまでは、わたしもわかる。ところがそれから先がわかりません。
それではなぜ、四八年のウィーンでの事実上は暴動にすぎないものをプロレタリア革命、あるいは「意識せざるプロレタリア革命」などと、著者はいうのでしょうか。
つまり、釜ヶ崎とかニューヨークで夏起きる暴動みたいなものと、ウィーン暴動はどこが違うのか、そこには革命といわなければいけないどのような特性があるのかといった積極的な理論づけが、この本にはまったく欠如していると思うんです。
そういう意味では、きわめてロマンチックな、またマルクシストとしてのいらだちの表明じゃないかという気がしました。
山崎 この本のタイトルにある“向う岸”という言葉は、たいへん大事な用語であるらしいですね。アレクサンドル・ゲルツェンに『向う岸から』という本があるんですね。しかし、その紹介はこの文章のどこにもない。ずうっと読んでいきますと、突然、〈ゲルツェンの作品『向う岸から』をマルヴィーダが読むのは〉という形で出てくる。
これはやはり、作文の書き方として非常にまずい。つまり、「向う岸から」という言葉をよく知っている仲間内に対して書かれた文章であるならともかく、不特定多数の読者のために出版されているんですから。
丸谷 いや、ぼくは、これは仲間内のために書かれた本だと思います。この本の書き方が、よくいえば奔放、悪くいえば乱雑なのは、ごく狭いサークルのために書かれている本だからだと思う。
木村 これはきわめてパセティックな本で、自分自身の激情が抑えられない、自分の思いこみが前提にあって書いているから、仲間にもわからない面があるんじゃないかという気がしますね。
丸谷 仲間というものは、了解事項があるから、わかってくれるわけですね。わかってくれなければ仲間じゃなくなる(笑)。
木村 御説ごもっともですが、自分がわかっていることと、自分以外の人がわかっていることの区別がついてないと思うんですね。
山崎 少し同情的にいいますと、日本のマルクス主義者が現在辿り着いている、ある一つの地点というものは、はっきり読みとれると思うんです。
「あとがき」にこういうことが書いてある。
おまえたちは川向うじゃないか、なに言ってやがる、こっちから見りゃてめえたちこそ川向うじゃねえか、というわけで、悪童どもは罵りあい、石を投げあう。だがここでは、自分が川向うの住民だからといって(つまり東洋人だからといって)川をはさんで石を投げあうわけにはいかない。むしろ、自分が川のこちら側に身を置いているからこそ、自覚的には、そして理念的には向う岸に達しうるのだということ、そのことをひたすら主張しなければならぬ。
心情的には、なるほど、こういう地点に日本のマルクス主義者のある種の人たちはいるのかな、ということはよくわかります。その意味では、ぼくは、知らない世界の地図を見せてもらったような、ある感慨はあるんです。
木村 わたしも、一つまったく共感したところがあります。
普遍性とは自己を限定しうる能力のことだ、ともいえよう。他者のなかで、他者をとおして自己限定しうる能力こそが普遍性につながるのであろう。
これは非常に大事な指摘だと思うんです。つまり、自分をあちら側から、別の世界から見てみる、そういう態度があってはじめて客観的な認識もできるし、自分の考え方を普遍化し得る。著者が、その意味でガスト・アルバイターないしはプロレタリアートの世界に大きな関心を懐くこと自体は、まことに大切なことで、そこから市民の世界とか革命の全体像をいま一歩はっきりと見せてほしかったと思うんですよ。
山崎 いまは世界的に民族主義が非常な勢いで擡頭しているんですね。これは考えてみると、たいへん不思議なことです。かつて人類は民族主義を叫んで、お互いに血を流し合っていた。そこヘマルクスが現われて、大ざっぱにいえば「本質的な戦いは民族の争いではなく、階級の争いなんだ」といったはずなんですね。それから何十年か経ち、社会主義社会ができてみれば、その中でも民族同士の争いをやっていて、いまや世界は民族の争いのほうが深刻でしょう。
木村 そうそう。
丸谷 だから、大抵のマルクス主義者は民族問題を考えないふりをしてすませているわけね。ところが、この本の著者は多少は考えている。
山崎 おまけに、この著者の文章を素直に読むと、当時集まったプロレタリアートの要求がかなり無茶だ、というふうにも書いてあるんですよ。それまで政府は一所懸命、貧民救済をやってきたのに、民衆がどんどんつけあがって、いくらでも給料を要求するからこんなことになったんだ、と書いてある。
木村 そこは本当に読ませるところですね。
丸谷 マルキシズムの歴史家にしては、こんなことに触れていいんだろうかと思うようなことに触れている。そこがぼくは、非常におもしろかった。
木村 そう。本当に正直な方です。
【この対談・鼎談が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする