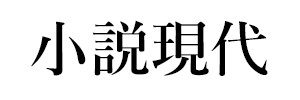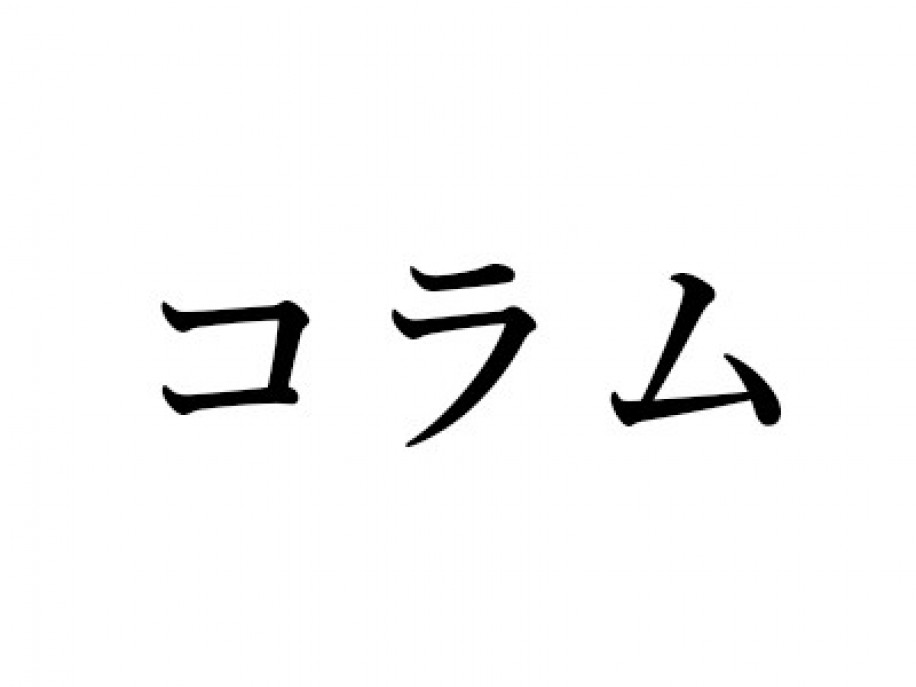読書日記
鹿島茂『衝動買い日記』(中央公論新社)、中村うさぎ『だって、欲しいんだもん!』(角川書店)、ポール・ラドニック『これいただくわ』(白水社)ほか
これ、いただくわ
タイトルからして、大興奮、読む前からすでに「私に言わせろ」状態になってしまった。鹿島茂著『衝動買い日記』(中央公論新社)。ショッピングの女王ならぬ、安物買いの銭失いの女王の私としては、そのテーマならもう任せて、なのだ。目次を開けば、あるあるある、似たようなものを買った覚えのある商品が。
(先生、あなたもこんなモノによろめいてしまったのですね!)
心の中で叫んだ。
「腹筋マシーン」。そう、美容&健康関係は、誰もが気になるところ。私も運動不足の解消に、ウォーキングマシーンを買ったが、バスタオル干しと化した後、親の家、知人の家を転々、おそらく粗大ゴミという末路をたどった。著者の腹筋マシーンも、いずれ処分する運命にあるとはわかっているが、「もうすこしの間だけ置いておきたいような気持ちもする」。捨てどきを待っているのですね。
資源節約が求められる中、一度使っただけでゴミ捨て場行きなんて、罪な私をぶって……、とは書いていなかったが、そのような心境でしょう。
「ふくらはぎ暖房器」。ふくらはぎの寒さに弱く、ふつうの足温器では物足りない著者が飛びついてしまったようだが。
(ならば、石井スポーツで冬の登山用のハイソックスを買うのよ。あるいはサロンシップ「直貼」をふくらはぎに張るのよ!)
と、おたよりしたい「衝動」に駆られたが、変人と思われてはいけないので、がまんした。
このテの話には、読む側の日常生活に埋もれた同様のエピソードを、次々と掘り起こさせる、連鎖反応的な作用が、たしかにあるな。ありふれた経験が、楽しい話題に変わる瞬間の快感だ。
それにしても「ごろねスコープ」とは。潜望鏡のしくみを用いた特殊メガネで、仰向けの腹の上に立てた本が読めるそうだが、よくも、考えつく人がいるものだ。しかも少なくともひとりは買った人がいたわけだから、どんな品でも、作れば売れるということか。
十九世紀フランスの小説、社会を専門とする著者のこと、パリの古書店で高価な挿絵本を買ってしまった話も出てくるが、基本は、凡人がいわくありげな文句につられ、つい買ってしまった物のお話。お値段も、挿絵本を除いては、いかにも惑わされそうなものばかりだ。要するに「あれやこれやと棚を物色し、なにかおもしろいものはないかと探すのが好き」なのだと、著者。
十九世紀のパリ風俗を微に入り細をうがって活写する、研究者としてのお仕事の方も、興味の持ち方は同じかも、と想像する。
買い物と言えば、この人抜きには語れないのが、中村うさぎ。本業はファンタジー作家だが、今や無駄遣いエッセイストとして、散財し続けることを、読者から期待されているのだから、因果である。
この人のえらさは、平等幻想にはっきりとノーを言うところだ。『だって、欲しいんだもん!』(角川文庫)の文庫版あとがきに表明される。
競争原理により成り立つ資本主義社会で「勝ちたい」と思うのは当然。人間は平等には満足しないようにできている。誰だってシンデレラになりたい、人から認められたい、金持ちになりたい、世間のすみっこでくすぶる今の自分は「ほんとの私」じゃないと思っている。そうか、流行りの「自分探し」と、おおもとは共通か。で、もっともてっとり早くシンデレラ気分を味わえるのが、買い物なのだと、著者は述べる。
この人の、自分に、そして世の中のしくみに対する分析は、鋭い。精神科医の斎藤学(さとる)の解説が、裏付けている。
斎藤によれば、借金を抱えながら「誰か止めて~」と心の中で悲鳴を上げつつカードの支払いにサインするのは、かなりのストレス。ストレスが蓄積し続けると、依存症者は死ぬか、あるいはその依存症を断念する。なので、ますます買い物を重ね、キャッシングの女王への道を歩みつつある著者は、はからずも治療の正道を行っているのである。読者のみならず、専門家からも「もっともっと買ってよし」とのお墨付きをもらったわけだ。
ポール・ラドニック著、小川高義訳『これいただくわ』(白水社)は、全編これ買い物小説。イエール大卒のいい坊ちゃんなのに、働くのが何より嫌いな若者ジョーが、母、伯母二人と車で一週間の旅に出る。欲しいモノをがまんできないのが、一家の血筋。回転ドアから店に入ると、目がくらむ。
「頭上から降りかかるばかりに狂喜乱舞する商品の群れ」、そう、その高揚感が、たまらなく刺激的。買い物道中をくり広げ、資金調達のため、L・L・ビーン本店の強盗を企てる。
ブルーミングデールズ、エスティ・ローダーといった実名がばんばん出てきて、知っている人には面白さ倍増だろう。しかし、日本人の私にも、ショップやブランド名とわかるのは、円高と情報化のたまものか。
ストーリーそのものよりも、そこに描かれる買い物の心理が、面白い。今どきの客は物が必要で店に来るのではない、「客の必要はショッピングなのである」。
ショッピングは「夢見る行為の一形態」、この品を購入したら自分はさらに美しく、ますます幸せになる。「世界の可能性を究め尽くしたいのだ」。
欲望は果てしなく、刺激は刺激を呼ぶ。終わりのない買い物に、強引に結末をつけたところが、この作品の弱さではあるのだが。
彼らの好きなのは、ブルジョワらしい生活。母たちは、不況時代の貧困のまっただ中に育ち、息子は、一ドルの金も無駄にしないようしつけられた。訳者の解説によれば、主人公たちは典型的な移民系低所得者からスタートし、そこそこの暮らしぶりを得るにいたったユダヤ人一家だ。が、そうした背景ははるか後ろに押しやって、買い物道中を楽しむ方を、訳者は読者にすすめている。
思えば、私がその昔、最初にふれた「買い物小説」はオー・ヘンリーの「賢者の贈り物」(『オー・ヘンリー傑作選』大津栄一郎訳・岩波文庫に収録)だ。貧しい夫婦が、相手へのプレゼントを買うため、妻は自分の髪を、夫は時計を売ったが、プレゼントを開いてみれば、妻からは時計につける鎖、夫からは櫛だった。かつて、買い物にはこんなドラマがあった。つましく、清く、美しく。
消費社会もここまで進むと、「あの頃」にはもう戻れないのか。
ALL REVIEWSをフォローする