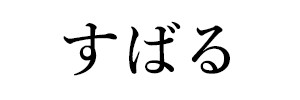作家論/作家紹介
ジャン=パトリック・マンシェット『殺しの挽歌』(学習研究社)、『殺戮の天使』(学習研究社)
同時代人としてのマンシェット
「フランス文学」と交錯させながら「ロマン・ノワール」を語ることが許されるようになったのは、おそらくジャン・ヴォートランがゴンクール賞を受賞した一九八〇年代末あたりからだろう。それまで「セリ・ノワール」や「フルーヴ・ノワール」などの著名なミステリ叢書を基盤に活動していた作家たちが純文学の領域へ越境し、社会からはじかれた下層労働者や移民街の庶民を主人公に仕立てて、物語性に満ちた力強い声を響かせるようになったのだ。また、それとは逆に、フランソワ・ボンやジャン・エシュノーズのような、癖のある書き手たちがミステリへの親炙を公然と語りはじめ、せいぜいヌーヴェル・ヴァーグとのかねあいで言及されるに留まっていたひとつのジャンルに、俄然あたらしい光が当てられることになった。なかでも最大級の敬意を払う作家として挙げられていたのが、ジャン=パトリック・マンシェットである。一九四二年生まれ、ソルボンヌ大学英文科卒の経歴を持つこの現代文学の隠れた教祖は、極左運動に身を投じたのち、ジャズ・ミュージシャンを志したり、映画の脚本を書いたりしながら、一九七一年、ジャン=ピエール・バスティッドとの共作『死体なんざ日干しにしておけ』でデビューする。同年、モロッコの革命運動指導者ベン・バルカの誘拐殺人事件を下敷きにした『ヌ・ギュストロ事件』を単独作品として刊行、自身もその翻訳と批評を手がけていた米国産ハードボイルドを範とする乾いた文体で、どんよりしたブルジョワ社会の安寧を糾弾した。暗黒街の友情と裏切りを語って満足していたフランス任俠物を一挙に過去へ追いやり、ネオ・ポラールの旗手として、揺るぎない地位を確立したのである。
頁の隅々に行き渡った非情なまでのリリシズム。そんなマンシェットの資質をみごとに提示する二作が、たてつづけに邦訳された。殺し屋に狙われたエリート会社員が、優柔不断なこれまでの人生を吹っ切るかのように過激な報復を行う『殺しの挽歌』、完璧な仕事を成し遂げてきた女の殺し屋が、暴力と愛と性のすべてを、最初にして最後の失敗に、つまり死にむけて爆発させる『殺戮の天使』。登場人物をそうした行動に駆り立てる「暗い」情念こそ、マンシェットの作品における真の原動力なのだ。
だがマンシェットは、一九八一年、傑作の誉れ高い『眠りなき狙撃者』を境に筆を断ち、ついに新作を完成させることなく十四年後に急逝した。ながい沈黙の果てに訪れた死が、彼をあらたな神話に取り込もうとしている。盲目的な顕揚に陥らないためにも、いまこそマンシェットを同時代人として享受しなければならない。
【この作家論/作家紹介が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする