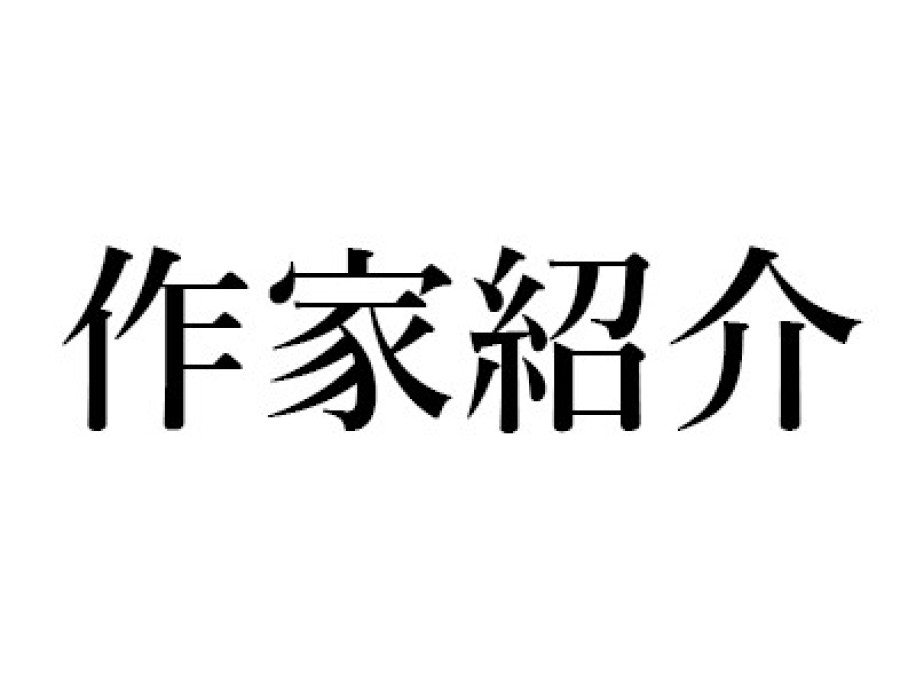書評
『殺戮の天使』(学習研究社)
マンシェットと「殺しの理由」
ジャン=パトリック・マンシェットの『殺戮の天使』(野崎歓訳、学研)を読んで唸った。解説によると、この作品は「新ミステリー」の傑作らしい。しかし「ミステリー」にしろ「新ミステリー」にしろ、それがどういうものなのか、ぼくはよく知らない。たぶん、その「ミステリー」という分野では、人が殺されて、その犯人を推理したり、追いかけたり捕まえたりするのではないかと思う。そういう小説なら、ぼくもよく楽しんで読んでいる。楽しんで読んでいるのだから、不満がないかというと、そうじゃない。ぼくには、「殺しの理由」がよくわからないのである。
もちろん、どの「ミステリー」にも「殺しの理由」は書いてある。無動機の殺人や、意味のない殺人はあまり出てこない。カミュの『異邦人』のムルソーは、太陽があまり眩しいので殺した(というようなことが書いてあったと思う)が、こんなふざけた動機では「ミステリー」ファンは満足してくれまい。だから、『異邦人』は純文学ということになっているのである。
しかし、「ミステリー」の中に書いてある「殺しの理由」が、ぼくにはピンとこない。前回、ぼくは京極夏彦の『絡新婦(じょろうぐも)の理(ことわり)』のことを面白かったと書いた。それはほんとうだ。でも、そこで犯人の「絡新婦」の「殺す理由」を納得したかというと、そうではない。「これはこのミステリーという世界の中の殺しに限り有効なのだ」と自分にいい聞かせる。そうして、やっとぼくは自分を納得させてきたのだった。『殺戮の天使』で、ヒロインのエメは、大量殺人を企て実行する。とんでもない殺人鬼だ。たった一人を殺すために悩んで悩んで悩み抜く。そういう小説を読んでも、ちっともその「殺しの理由」がわからないぼくなのだから、そんなおよそ現実離れした小説の中の「殺しの理由」が理解できるわけがない、と思って、ぼくは読んでいった。
しかし、予想ははずれた。ぼくには、エメの「殺しの理由」がわかったのである。
「ミステリー」において、作者は読者を説得するため、堅固な「殺す理由」を構築しようとする。その構築は、当然のことながら作品の中で行われ、だから読者はその作品の固い枠の中でだけ通じる論理に則って、説得されたりされなかったりする。
だが、『殺戮の天使』でエメの「殺す理由」は作品の中にはない。もちろん、外にあるはずもない。それは、その間にある。直接には作者マンシェットの怒りと哀しみに発する。そのことを伝えるために、あえてマンシェットは小説としての枠を壊し、外から中へ侵入するため突然「私」として発言する。最後の部分を引用する。
少しすると、出血したがゆえの幻覚だったのか、それとも何か別の理由からなのか私は知らないが、しかし私の見るところ今や彼女は真紅の素晴らしいドレスを身にまとっていた。それはイブニングドレスで、おそらくはスパンコールで飾られている。そこに夜明けの輝かしい黄金の光が射してきた。ハイヒールを履き真紅のイブニングドレスを着たエメは、傷一つない驚くべき美しさを湛えて、モンブランの山塊の斜面にも似た雪の斜面を足取りも軽く登っていった。淫蕩にして冷徹な女たちよ、この書物をあなたたちに捧げる。
最後の頁を読み終えて、ぼくは作者と共にエメに恋していることを知る。つまり、ぼくはエメと「殺す理由」を共有してしまったのだ。それが「わかる」ということなのである。
ALL REVIEWSをフォローする