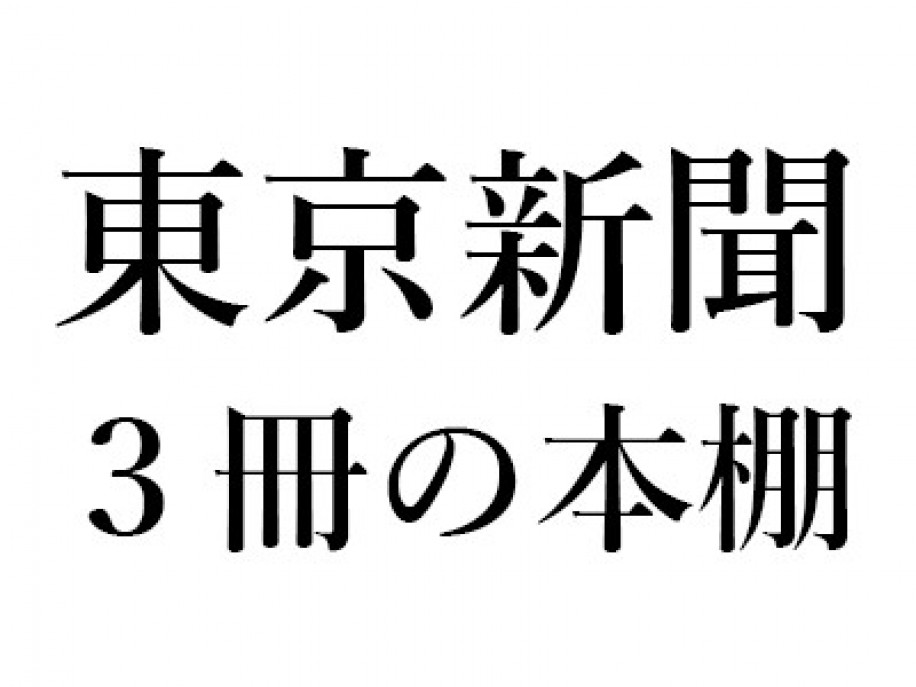読書日記
森伸之監修・内田静枝編著『ニッポン制服百年史』(河出書房新社)、安城寿子『1964東京五輪ユニフォームの謎』(光文社)、グレアム・スウィフト『マザリング・サンデー』(新潮社)
制服のもつ意味考える
日本で初めて女学生の制服に洋装が取り入れられてから、百年。〔1〕森伸之監修・内田静枝編著『ニッポン制服百年史 女学生服がポップカルチャーになった!』(河出書房新社・1,998円)は、百年の歴史を振り返り、日本の女学生達が今まで、制服をどう咀嚼してきたかをひもときます。「平成は制服の時代だった!?」と帯にありますが、昭和末から制服のモデルチェンジブームが起こると、女子高生たちは制服を喜んで着るようになりました。制服は、自分が女子高生であることを証明するしるし。制服のない学校の生徒も“なんちゃって制服”を着るようになり、日本の制服風ファッションは、海外にも広がったのです。
制服という“縛り”に反発するのでなく、したたかに利用するようになった女子高生達。この内向きのパワーは、確かに平成という時代ならではなのでしょう。
令和で注目される制服といったら、東京オリンピックのそれ。〔2〕安城寿子(ひさこ)『1964東京五輪ユニフォームの謎』(光文社新書・950円)では、前回の東京五輪の開会式ユニフォームは石津謙介デザイン、という俗説の誤りを指摘。さらには、日本選手団の歴代ユニフォームを振り返り、問題点を洗い出します。
シドニー五輪開会式における、「国辱ユニフォーム」とまでいわれた虹色マントのトラウマはいまだ我々から消えず、来年の東京ではどうなるのか、という不安が渦巻きます。JOCの発表によると、パラリンピック選手団も五輪選手団と同デザインのユニフォームになったり、ジャケットに限定しなかったり等、著者が指摘する問題点は改善されるようですが、「世界の人たちにオッと思ってもらえるデザインにしてもらえれば」というJOC担当者の言葉に、やはり不安は拭えない…。
しかしどんなデザインであれ、ある団体に属したならば着なくてはならないのが、制服。〔3〕グレアム・スウィフト『マザリング・サンデー』(真野泰訳、新潮クレスト・ブックス・1,836円)は、制服を着る職業の代表格であるメイドが主人公の物語です。
年に一度、メイドたちが仕事から解放されて里帰りをすることができるマザリング・サンデーという日に起きた出来事を描く、この物語。制服を着せる側と着せられる側がその日には一時的にフラットな関係性になり、主人公は、やがて制服と無縁な世界へと旅立っていく…。
制服は一度も登場しない、この物語。しかしこれは確かに制服を着ることと脱ぐことの意味を考えさせる「制服小説」なのだと、私は思います。
ALL REVIEWSをフォローする