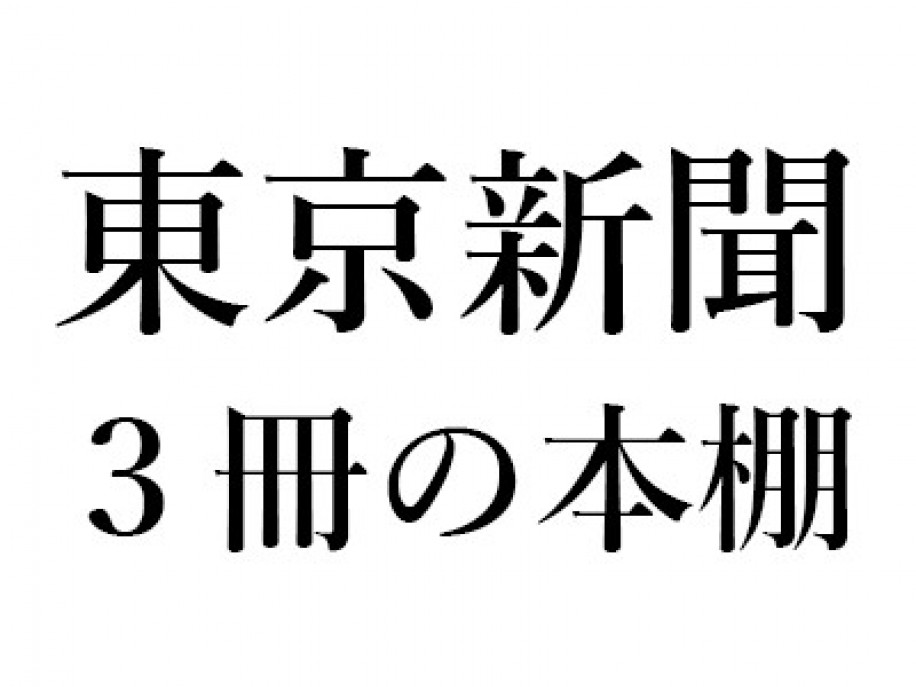書評
『ウォーターランド』(新潮社)
ユーゴスラビアの作家ダニロ・キシュに、『死者の百科事典』(東京創元社)という素晴らしい短篇がある。無名の人々の人生の全てを記載した百科事典をめぐる物語だ。キシュは書く。「人間の歴史には何ひとつ繰り返されるものはない、一見同じに見えるものも、せいぜい似ているかどうか、人はだれもが自分自身の星で、すべてはいつでも起きることで二度と起きないことなのです、すべては繰り返される、限りなく、類なく」と。
物語るという行為は弔いの一種だと思う。人間は過去を物語ることによって、刻一刻と“今”ではなくなっていく時間を弔っている。刻一刻と記憶の輪郭を失いつつある死者を弔っている。弔い続けることで過去を、死者を、忘却の淵から救い、と同時に生者もまた自らが物語る死者の思い出によって慰撫(いぶ)されもする。現在と過去、此岸(しがん)と彼岸はそうして手を差しのべあっているのではないだろうか。
「子供たちよ」、グレアム・スウィフトの長篇小説『ウォーターランド』の語部(かたりべ)たる歴史教師のトムは生徒たちに呼びかける。「〈いま、ここ〉に生きているのは動物だけである。記憶も歴史も知らぬのは自然だけである。これに対して人間は物語を語る動物である。……人間は物語を語りつづけずにはいられない。物語をでっちあげつづけずにはいられない。物語がある限りは大丈夫なのだ」と。
妻のメアリが赤ん坊を誘拐するという事件を起こしてしまったがために退職を迫られているトムは、こうして語り始める。イングランド東部のフェンズと呼ばれる沼沢地帯の歴史を、そこで水門の番人をしていた父とビール醸造業者の娘だった母の家系をめぐる物語を、その二人から生まれた自分の人生を。
物語の発端は、トムが十六歳だった夏に、水門に流れついた水死体。事故なのか、殺人なのか。ミステリータッチの謎をめぐって、物語は過去へと遡行(そこう)し、またメアリの嬰児(えいじ)誘拐事件という現在へも流れていく。トムが生徒に向かって話す物語は、フェンズに流れる川のように蛇行し、時には思わぬ脱線という形で支流へと流れ込んでいくのだ。その語り口の巧さといったら!
たとえば、母方の祖父が作った「ジョージ五世戴冠記念ビール」の強烈な酩酊効果がもたらす町の大混乱をめぐるエピソードは、ガルシア=マルケスの『百年の孤独』を彷彿させる賑やかさと面白さ。また、フェンズに棲息するウナギの生態をめぐる生真面目な考察はビュフォンの『博物誌』のパロディのごとし。こうした、それ自体独立した物語として読んでも愉しい一見閑話休題のような章が、実はこの長い物語にとってなくてはならない重要な挿話であり、水死体の謎ともちゃんとリンクしていることがわかる瞬間の驚きと喜び。物語るテクニックの素晴らしさを十二分に堪能できる、これは傑作中の傑作なんである。
「子供たちよ」、トムは呼びかける。「(歴史上の事件という舞台にいままで登場した主役以外の)現実の処理という退屈な仕事をこなす人たちがいた……たとえ歴史が上演する大がかりな芝居に参加できなくても……人間は歴史を小規模な形で模倣し、歴史が充実を、変化を、目的を、中身を希求することに、小規模な形で同調する」と。
限りなく、比類なき個人の生について心をこめて物語る。それが歴史であることを、この傑作は教えてくれる。川面に浮かぶちっぽけな水泡のように儚い存在にすぎないわたしたちを励ましてくれる。物語り続ける限り、わたしたちは歴史の中に確かに存在するのだ、と。そして、世界もまた「物語がある限りは大丈夫なのだ」。そう、スウィフトのような作家がいる限りは。
【この書評が収録されている書籍】
物語るという行為は弔いの一種だと思う。人間は過去を物語ることによって、刻一刻と“今”ではなくなっていく時間を弔っている。刻一刻と記憶の輪郭を失いつつある死者を弔っている。弔い続けることで過去を、死者を、忘却の淵から救い、と同時に生者もまた自らが物語る死者の思い出によって慰撫(いぶ)されもする。現在と過去、此岸(しがん)と彼岸はそうして手を差しのべあっているのではないだろうか。
「子供たちよ」、グレアム・スウィフトの長篇小説『ウォーターランド』の語部(かたりべ)たる歴史教師のトムは生徒たちに呼びかける。「〈いま、ここ〉に生きているのは動物だけである。記憶も歴史も知らぬのは自然だけである。これに対して人間は物語を語る動物である。……人間は物語を語りつづけずにはいられない。物語をでっちあげつづけずにはいられない。物語がある限りは大丈夫なのだ」と。
妻のメアリが赤ん坊を誘拐するという事件を起こしてしまったがために退職を迫られているトムは、こうして語り始める。イングランド東部のフェンズと呼ばれる沼沢地帯の歴史を、そこで水門の番人をしていた父とビール醸造業者の娘だった母の家系をめぐる物語を、その二人から生まれた自分の人生を。
物語の発端は、トムが十六歳だった夏に、水門に流れついた水死体。事故なのか、殺人なのか。ミステリータッチの謎をめぐって、物語は過去へと遡行(そこう)し、またメアリの嬰児(えいじ)誘拐事件という現在へも流れていく。トムが生徒に向かって話す物語は、フェンズに流れる川のように蛇行し、時には思わぬ脱線という形で支流へと流れ込んでいくのだ。その語り口の巧さといったら!
たとえば、母方の祖父が作った「ジョージ五世戴冠記念ビール」の強烈な酩酊効果がもたらす町の大混乱をめぐるエピソードは、ガルシア=マルケスの『百年の孤独』を彷彿させる賑やかさと面白さ。また、フェンズに棲息するウナギの生態をめぐる生真面目な考察はビュフォンの『博物誌』のパロディのごとし。こうした、それ自体独立した物語として読んでも愉しい一見閑話休題のような章が、実はこの長い物語にとってなくてはならない重要な挿話であり、水死体の謎ともちゃんとリンクしていることがわかる瞬間の驚きと喜び。物語るテクニックの素晴らしさを十二分に堪能できる、これは傑作中の傑作なんである。
「子供たちよ」、トムは呼びかける。「(歴史上の事件という舞台にいままで登場した主役以外の)現実の処理という退屈な仕事をこなす人たちがいた……たとえ歴史が上演する大がかりな芝居に参加できなくても……人間は歴史を小規模な形で模倣し、歴史が充実を、変化を、目的を、中身を希求することに、小規模な形で同調する」と。
限りなく、比類なき個人の生について心をこめて物語る。それが歴史であることを、この傑作は教えてくれる。川面に浮かぶちっぽけな水泡のように儚い存在にすぎないわたしたちを励ましてくれる。物語り続ける限り、わたしたちは歴史の中に確かに存在するのだ、と。そして、世界もまた「物語がある限りは大丈夫なのだ」。そう、スウィフトのような作家がいる限りは。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
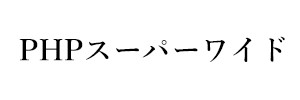
PHPスーパーワイド(終刊) 2002年7月号
ALL REVIEWSをフォローする