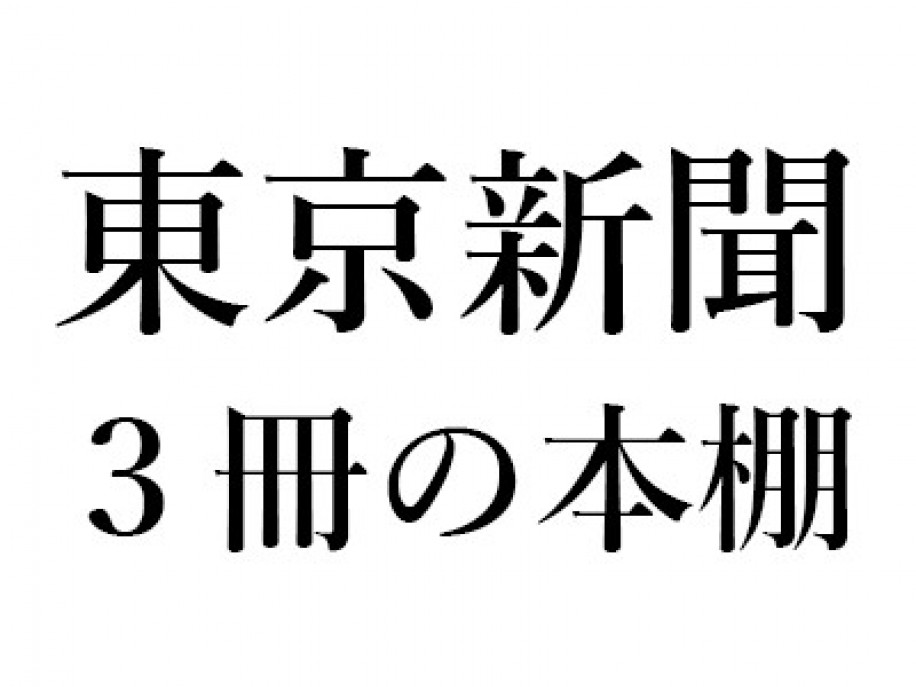書評
『奇跡も語る者がいなければ』(新潮社)
トヨザキ的評価軸:
◎「金の斧(親を質に入れても買って読め)」
「銀の斧(図書館で借りられたら読めば―)」
「鉄の斧(ブックオフで100円で売っていても読むべからず)」
重病にかかっていることを妻に打ち明けられない二十番地の二階の老人。その一階に住み、裏庭に粗大ゴミが捨てられている苦境を留守番電話に向かって訴えかける男。二十二番地に住む四角い小さな眼鏡の女の子のことを考えている十八番地のドライアイの男の子。十九番地の双子の兄弟。火事で妻を救えなかった上、重度の火傷を負った十六番地の男とその幼い娘。
そうした大勢の名もなき人々の朝から夕刻にかけての日常を描くパートに、作者はもうひとつの物語をよりあわせています。語り手は二十二番地に住んでいた眼鏡の女の子。彼女は今は別の街で暮らしていて、予定外の妊娠に動揺しています。あの八月三十一日に目の当たりにした出来事を今も思い出す彼女が、彼女にとって、そして読者にとっても意外な人物と出会いを果たすあたりから、交互に語られるふたつの物語は結びつきをより緊密にしていくのです。
気持ちに余裕がない時、人は小さなものから犠牲にしていきます。ダイアナ元妃の死に涙しながら、理不尽な戦争によって失われていく多くの無辜の命に心を留めない。自分以外の人間にもかけがえのない生活があり、愛する者がいることを忘れてしまう。美術館に展示されている〈十五センチほどの赤い素焼きの人形が、何千体も何万体も並〉べられた作品を見て〈どれもこれもほとんど同じで、どれもこれもみんな特別〉と思う二十二番地の女の子や、〈何もかもが無視され、失われ、捨て去られるのが嫌〉でいろんなものを集めてしまう十八番地のドライアイの男の子のような、小さなものを慈しむ気持ちをなくした時、人は、気をつけていないと見失ってしまうたくさんの奇跡と無縁の冷たい存在になることを、作者は穏やかな語り口で伝えてくれるのです。
この物語の最後にはサプライズが用意されています。報道陣も野次馬も涙にくれる人もいないまま、誰に知られることもなく起こった、ひとつの奇跡が。そして、この平凡な一日の中で起きる奇跡を知りうるのは読者だけ、という仕掛けを作者は用意しているのです。作中、火事で妻を失った十六番地の男は娘にこう語りかけます。〈奇跡も語る者がいなければ、どうしてそれを奇跡と呼ぶことができるだろう〉。この小説の中で起きた奇跡を語る者、それは――。一人でも多くの“あなた”に語り部になってほしい。そんな共感の輪を静かに広げる作品なのです。
【この書評が収録されている書籍】
◎「金の斧(親を質に入れても買って読め)」
「銀の斧(図書館で借りられたら読めば―)」
「鉄の斧(ブックオフで100円で売っていても読むべからず)」
それを知りうるのは読者だけなのです
ダイアナ元妃が死亡した一九九七年八月三十一日。そんな特別な一日を背景に、しかし、この小説はイングランド北部のある通りで起こった平凡な出来事について丁寧に語り起こしています。重病にかかっていることを妻に打ち明けられない二十番地の二階の老人。その一階に住み、裏庭に粗大ゴミが捨てられている苦境を留守番電話に向かって訴えかける男。二十二番地に住む四角い小さな眼鏡の女の子のことを考えている十八番地のドライアイの男の子。十九番地の双子の兄弟。火事で妻を救えなかった上、重度の火傷を負った十六番地の男とその幼い娘。
そうした大勢の名もなき人々の朝から夕刻にかけての日常を描くパートに、作者はもうひとつの物語をよりあわせています。語り手は二十二番地に住んでいた眼鏡の女の子。彼女は今は別の街で暮らしていて、予定外の妊娠に動揺しています。あの八月三十一日に目の当たりにした出来事を今も思い出す彼女が、彼女にとって、そして読者にとっても意外な人物と出会いを果たすあたりから、交互に語られるふたつの物語は結びつきをより緊密にしていくのです。
気持ちに余裕がない時、人は小さなものから犠牲にしていきます。ダイアナ元妃の死に涙しながら、理不尽な戦争によって失われていく多くの無辜の命に心を留めない。自分以外の人間にもかけがえのない生活があり、愛する者がいることを忘れてしまう。美術館に展示されている〈十五センチほどの赤い素焼きの人形が、何千体も何万体も並〉べられた作品を見て〈どれもこれもほとんど同じで、どれもこれもみんな特別〉と思う二十二番地の女の子や、〈何もかもが無視され、失われ、捨て去られるのが嫌〉でいろんなものを集めてしまう十八番地のドライアイの男の子のような、小さなものを慈しむ気持ちをなくした時、人は、気をつけていないと見失ってしまうたくさんの奇跡と無縁の冷たい存在になることを、作者は穏やかな語り口で伝えてくれるのです。
この物語の最後にはサプライズが用意されています。報道陣も野次馬も涙にくれる人もいないまま、誰に知られることもなく起こった、ひとつの奇跡が。そして、この平凡な一日の中で起きる奇跡を知りうるのは読者だけ、という仕掛けを作者は用意しているのです。作中、火事で妻を失った十六番地の男は娘にこう語りかけます。〈奇跡も語る者がいなければ、どうしてそれを奇跡と呼ぶことができるだろう〉。この小説の中で起きた奇跡を語る者、それは――。一人でも多くの“あなた”に語り部になってほしい。そんな共感の輪を静かに広げる作品なのです。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする