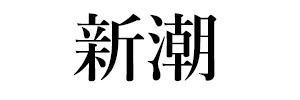書評
『奇跡も語る者がいなければ』(新潮社)
一九九七年のまだ残暑厳しい晩、テレビをつけると世界で一番有名な皇太子妃の荘厳な葬儀の模様が映し出されて、そこにはエルトン・ジョンがいて、その他大勢の有名人がいて、泣いてる人がいて、泣いてるふりをする人も多分いて、でも彼らの誰とも会ったことや喋ったことのないわたしにはその判別はつかなくて、そしてそんなわたしと同じ名もなき多くの人々がその夜テレビの画面に釘づけになっていたのである。その映像をとてもとても遠くに、あるいは我が事のように身近に感じながら、全世界が一人の人間をあの世に送る儀式に注視していたのである。
一九七六年生まれの作家ジョン・マグレガーのデビュー作『奇跡も語る者がいなければ』は、イギリスの地方都市の平凡な住宅街のある一日の出来事を描いている。一九九七年八月三十一日。ダイアナ妃がパパラッチの追跡を振り切ろうとして自動車事故に遭い、死亡した日だ。おそらくその日、イギリスではどのチャンネルを回しても、この報道ばかりが流れていたことだろう。まるでその日死亡したのが世界でダイアナ妃ただ一人であるかのように。事故の原因を探り、状況を語り、死の直前の様子を想像し、皇太子妃にまつわる過去のゴシップを洗い直し、共に死んだ大富豪の恋人の情報を集め、やがてその興奮は世界中に伝染していったのである。
そんな一日を背景に、しかし、マグレガーはイングランド北部のある通りで起こった出来事について丁寧に語り起こしていく。報道記者も、テレビ局のカメラクルーも、野次馬も、事件現場に花束を投げ涙にくれる人もないまま、ひっそりと密やかに誰に知られることもなく起こった、ひとつの奇跡のことを。
ドラッグと酒で千鳥足になって朝帰りした十七番地の騒々しい若者たち。肺に重大な疾患を抱えていることを妻に打ち明けることができないでいる二十番地の二階の老人。その一階に住み、自分の家の裏庭に粗大ゴミが捨てられ放置されている苦境を留守番電話に向かって訴えかける、よく手入れされた口ひげの男。二十二番地に住む四角い小さな眼鏡の女の子のことを考えている十八番地のドライアイの男の子。十三番地の赤い三輪車をこぐのに夢中な男の子。十九番地の元気があり余っている双子の兄弟。その妹でフラミンゴみたいに一本足で立ってばかりいる無口な女の子。十二番地の年中洗車ばかりしている父親と、ようやく貯めた千ポンドで車を買う今日という日に胸ときめかしている若者。口汚くののしりあう喧嘩をしてはセックスで仲直りする二十一番地の三十代カップル。二十四番地のスニーカーを洗う男の子。窓枠を青いペンキで塗っている二十五番地のおじいさん。この通りの建物をスケッチしている十一番地の建築学の学生。火事で妻を救えなかった手に重度の火傷を負っている十六番地の男とその幼い娘。
そうした大勢の名もなき人々の生活を、朝からある悲劇的な出来事が起こる夕刻まで描く三人称語りによる現在時制のパートに、作者はもうひとつの物語をよりあわせる。その語り手は、二十二番地に住んでいた四角い小さな眼鏡の女の子。あの八月三十一日から三年後、彼女は別の街で一人暮らしをしていて、予定外の妊娠に動揺している。けれど、そのことを両親や友人になかなか打ち明けることができない。三年前にあの通りで目の当たりにした出来事をなぜかよく思い出す彼女が、彼女にとって、そして読者にとっても意外な人物と出会いを果たすあたりから、交互に語られるふたつの物語は互いの結びつきをより緊密にしていくのだ。この仕掛けといい、物語全体にとっての大きな意味を持つ三組の双子の存在といい、新人作家らしからぬ巧みな語り口でマグレガーは敬虔な驚きを伴う三四五ページ以降のある出来事へと読者を導いてくれるのである。
気持ちに余裕がない時、わたしたちはいつだって小さなものから犠牲にしていく。ダイアナ妃の死に涙しながら、理不尽な戦争によって毎日失われていく名もなき人々の命に心を留めない。自分以外のあらゆる人にもかけがえのない生活があり、思いがあり、感情があり、主義主張があり、大事にしている何かや誰かがあり、生があり、死があることを、つい忘れてしまう。美術館に展示されている「十五センチほどの赤い素焼きの人形が、何千体も何万体も並んで」いるインスタレーションを見て「どれもこれもほとんど同じで、どれもこれもみんな特別」と思う「わたし」や、「何もかもが無視され、失われ、捨て去られるのが嫌」で通りで見かけたいろんなものを集めてしまう十八番地のドライアイの男の子のような気持ちを見失った時、人は奇跡と無縁の存在になってしまうことを、奇跡というものが小さなものをおろそかにしない共感と愛情に満ちた心によってしか見つけられないことを、この小説は強く、しかし、とても穏やかな口調で伝えてくれるのだ。
作中、火事で妻を救えなかった十六番地の男は幼い娘にこう語りかける。
マグレガーは、この小説の最後に読者だけが知りうる奇跡を用意している。あの通りの住民の誰も知りえなかった奇跡を、だ。その奇跡はわたしたちの胸のもっとも奥深いところへと届き、そしてわたしたちに了解させる。この小説に出てきたすべての人物がわたしたちにとってとても近しい者になりえたように、身近にいるこの人あの人から世界のあちらこちらでかけがえのない生を生き、それぞれの死を死ぬ人たちもまた、心親しい誰かになりうるのだということを。
感動とはこういう作品に対して、静かな声で発せられるべき特別な言葉であるはずだとわたしは思う。
【この書評が収録されている書籍】
一九七六年生まれの作家ジョン・マグレガーのデビュー作『奇跡も語る者がいなければ』は、イギリスの地方都市の平凡な住宅街のある一日の出来事を描いている。一九九七年八月三十一日。ダイアナ妃がパパラッチの追跡を振り切ろうとして自動車事故に遭い、死亡した日だ。おそらくその日、イギリスではどのチャンネルを回しても、この報道ばかりが流れていたことだろう。まるでその日死亡したのが世界でダイアナ妃ただ一人であるかのように。事故の原因を探り、状況を語り、死の直前の様子を想像し、皇太子妃にまつわる過去のゴシップを洗い直し、共に死んだ大富豪の恋人の情報を集め、やがてその興奮は世界中に伝染していったのである。
そんな一日を背景に、しかし、マグレガーはイングランド北部のある通りで起こった出来事について丁寧に語り起こしていく。報道記者も、テレビ局のカメラクルーも、野次馬も、事件現場に花束を投げ涙にくれる人もないまま、ひっそりと密やかに誰に知られることもなく起こった、ひとつの奇跡のことを。
ドラッグと酒で千鳥足になって朝帰りした十七番地の騒々しい若者たち。肺に重大な疾患を抱えていることを妻に打ち明けることができないでいる二十番地の二階の老人。その一階に住み、自分の家の裏庭に粗大ゴミが捨てられ放置されている苦境を留守番電話に向かって訴えかける、よく手入れされた口ひげの男。二十二番地に住む四角い小さな眼鏡の女の子のことを考えている十八番地のドライアイの男の子。十三番地の赤い三輪車をこぐのに夢中な男の子。十九番地の元気があり余っている双子の兄弟。その妹でフラミンゴみたいに一本足で立ってばかりいる無口な女の子。十二番地の年中洗車ばかりしている父親と、ようやく貯めた千ポンドで車を買う今日という日に胸ときめかしている若者。口汚くののしりあう喧嘩をしてはセックスで仲直りする二十一番地の三十代カップル。二十四番地のスニーカーを洗う男の子。窓枠を青いペンキで塗っている二十五番地のおじいさん。この通りの建物をスケッチしている十一番地の建築学の学生。火事で妻を救えなかった手に重度の火傷を負っている十六番地の男とその幼い娘。
そうした大勢の名もなき人々の生活を、朝からある悲劇的な出来事が起こる夕刻まで描く三人称語りによる現在時制のパートに、作者はもうひとつの物語をよりあわせる。その語り手は、二十二番地に住んでいた四角い小さな眼鏡の女の子。あの八月三十一日から三年後、彼女は別の街で一人暮らしをしていて、予定外の妊娠に動揺している。けれど、そのことを両親や友人になかなか打ち明けることができない。三年前にあの通りで目の当たりにした出来事をなぜかよく思い出す彼女が、彼女にとって、そして読者にとっても意外な人物と出会いを果たすあたりから、交互に語られるふたつの物語は互いの結びつきをより緊密にしていくのだ。この仕掛けといい、物語全体にとっての大きな意味を持つ三組の双子の存在といい、新人作家らしからぬ巧みな語り口でマグレガーは敬虔な驚きを伴う三四五ページ以降のある出来事へと読者を導いてくれるのである。
気持ちに余裕がない時、わたしたちはいつだって小さなものから犠牲にしていく。ダイアナ妃の死に涙しながら、理不尽な戦争によって毎日失われていく名もなき人々の命に心を留めない。自分以外のあらゆる人にもかけがえのない生活があり、思いがあり、感情があり、主義主張があり、大事にしている何かや誰かがあり、生があり、死があることを、つい忘れてしまう。美術館に展示されている「十五センチほどの赤い素焼きの人形が、何千体も何万体も並んで」いるインスタレーションを見て「どれもこれもほとんど同じで、どれもこれもみんな特別」と思う「わたし」や、「何もかもが無視され、失われ、捨て去られるのが嫌」で通りで見かけたいろんなものを集めてしまう十八番地のドライアイの男の子のような気持ちを見失った時、人は奇跡と無縁の存在になってしまうことを、奇跡というものが小さなものをおろそかにしない共感と愛情に満ちた心によってしか見つけられないことを、この小説は強く、しかし、とても穏やかな口調で伝えてくれるのだ。
作中、火事で妻を救えなかった十六番地の男は幼い娘にこう語りかける。
娘よ、ものはいつもそのふたつの目で見るように、ものはいつもそのふたつの耳で聴くようにしなければいけない(中略)この世界はとても大きくて、気をつけていないと気づかずに終わってしまうものが、たくさん、たくさんある(中略)奇跡のように素晴らしいことはいつでもあって、でも人間の目には、太陽を隠す雲みたいなものがかかっていて、その素晴らしいものを素晴らしいものとして見なければ、人間の生活は、そのぶん色が薄くなって、貧しいものになってしまう(中略)奇跡も語る者がいなければ、どうしてそれを奇跡と呼ぶことができるだろう。
マグレガーは、この小説の最後に読者だけが知りうる奇跡を用意している。あの通りの住民の誰も知りえなかった奇跡を、だ。その奇跡はわたしたちの胸のもっとも奥深いところへと届き、そしてわたしたちに了解させる。この小説に出てきたすべての人物がわたしたちにとってとても近しい者になりえたように、身近にいるこの人あの人から世界のあちらこちらでかけがえのない生を生き、それぞれの死を死ぬ人たちもまた、心親しい誰かになりうるのだということを。
感動とはこういう作品に対して、静かな声で発せられるべき特別な言葉であるはずだとわたしは思う。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする