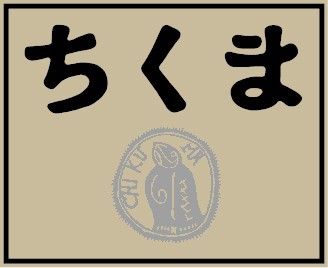作家論/作家紹介
『ちくま日本文学 037 岡本かの子』(筑摩書房)、『岡本かの子全集 』(筑摩書房)
年々のかの子
私は単純平凡な小説の読者である。好みの文章に身をひたす快楽か、世の矛盾や悲惨を知るためか、あるいは生きることを支えるために読む。岡本かの子はいわゆる社会性のある作家ではない。でも生きていくのが苦しくなると、ふっと立ち現われて、柔らかい手を差しのべてくれる。高校に入ったころ、瀬戸内晴美「かの子撩乱」の芝居を伯母につれられて見に行った。
「いよよ華やぐ命なりけり。『老妓抄』は昭和文学の白眉よ」
と帰りがけに浮き浮きと伯母はいい、私は帰って「ハクビ」という言葉をさっそく辞書で調べ、『金魚撩乱』と『老妓抄』から読みはじめた。が、高校一年生にはこの、愛について爆発的に考えたような小説群は分りにくかった。その果ての悲しみも伝わらなかった。近代結婚の倫理にもとらわれていたから、夫がいるのに恋愛をくり返し、その恋人を同居させるようなこの作家を断罪する目もはたらいていた。
友だちに聞いても、宮本百合子、野上弥生子、佐多稲子などはきっちり読んでいても、かの子は素通りしてしまった人が多い。色っぽすぎる、生々しい、気味悪いなどという。が、成長するにしたがって、年々にかの子は大事な作家になってきた。素通りするのは惜しい。
たとえば二十歳前後、私は知りあった男のひとに次々、去られる体験をした。みな、僕は君ほど強くない、というのだ。このとき、『花は勁し』を読んで、画家の小布施が主人公の桂子にいう科白(セリフ)にアッと思い当った。
「君には何か生れない前から予約されたとでもいう、一筋徹っている川の本流のようなものがあって、来るものを何でも流し込んで、その一筋をだんだん太らして行く。それに引き代え、僕は僅かに持って生れた池の水ほどの生命を、一生かかって撒き散らしてしまった」
「逞しい生命は弱い生命を小づき廻すものだ」「生命量の違うものの間に起こる愛は悲惨だ」ともある。私は男性との位置の決め方における失敗にもめげていたし、そして自分の生命量のすべてを引き受けてくれる男が現われないことも理不尽だと泣いたが、かの子の作品のナルシシズムにはずいぶん救われた。
「なんだなんだ。大きな体をして、三十八にもなって。美人の癖に。ちょっとの間は辛かろうが、君の弾力性が承知しないよ。君はまたじきにむくむくと起き上るだろう」
強いばかりの女じゃないのに、と泣きくずれる桂子に、別れ際に男はいう。強い女の孤独とはそういうものか、覚悟しなくちゃと思った。同じ三十八になってみると、この科白は岡本一平のものか、どの恋人のものか、あるいはかの子の自問自答だったのか、考えめぐらす。おそらく最後だろう。
岡本かの子は「よく育った女性」といわれる。「多摩の旧家の無口で憂愁の乙女」、二十一歳で画家岡本一平と結婚してからは「不如意で逼塞した新妻」、一平が漫画家として名をなすと「良人を仕立てた良妻」、太郎を産んで「息子に気魄を打込んだ賢母」、それから歌人となり、仏教学者として立ち、ついに念願の小説に転身した。四十七歳の『鶴は病みき』が本格的デビューで、三、四年めざましく活躍してパタリと逝く。元手がかかった文学だな、と思う。どんな作家もピークは十年くらいだろう。十八や二十五でしか書けない作品ももちろんあるが、やはりこれだけ生き切ったあと、かの子が爆発してくれてよかった。
読み始めてから長らく、かの子は「川」だ、その原風景は、育った多摩川べりに違いないと気づいてもいたのだが、そんなことは、彼女を「水の妖精」と呼ぶ亀井勝一郎氏ら多くの評者に、とうにいい尽くされていると知った。
たしかに水っぽい、みずみずしい、水太り、生々流転、かの子は水のイメジに満ちている。断じて脂粉は感じない。セーター姿のやや猫背の鈍くさい写真が残っている。その素顔のあどけないこと、にこにこと柔らかいこと。歌壇、文壇を相手にまなじり決したような厚化粧のポートレイトもカッコ良いが、この普段の顔も好きだ。
私は殊にもこの頃は水を憶っているのであった。私は差しあたりどうしても水のほとりに行き度いのであった。
と「河明り」にある。「川」という作品もある。私はいま、東京の川や池を復活する運動にかかわり、原稿も書くのだが、水の情景がうまく描けないのが悩みである。
河には無限の乳房のような水源があり、末にはまた無限に包容する大海がある。この首尾を持ちつつ、その中間に於ての河なのである。そこには無限性を蔵さなくてはならぬはずである。(「河明り」)
「水のリサイクル」などといわないで、その輪廻性をこのように描けるかと思うとうらやましい。わが愛する藍染川についても、
むかし石神井川といったその川は、今のように荒川平野へ流れて、荒川へ落ちずに、飛鳥山、道灌山、上野台の丘陵の西側を通って、海の入江に入った。その時には茫洋とした大河であった。やがて石神井川が飛鳥山と王子台との間に活路を拓いて落ちるようになって、不忍池の上は藍染川の細い流れとなり、不忍池の下は暗渠にされてしまって、永遠に河身を人の目に触れることは出来なくなった。(同前)
と簡にして要を得ている。背景の勉強もしのばれる。
原風景であった多摩川よりも、大川こと隅田川の方がよく描かれるのはなぜか。「田舎の女学生」の逆転した都会趣味だろうか。そういえば「家霊」や「鮨」に山の手と下町に通ずる坂の町を描いている。もっとも、実家の大貫家は市中に別邸も持ち、跡見女子校の寄宿舎でも暮らした。一高から東大へ進んだ兄大貫晶川が根津権現辺の下宿にいて、かの子もよくそこに居たから、市中のことも土地勘はあるのである。
いや、やはり多摩川の原風景は抽象化されてかの子の体内に生ききっていたのだろう。「落城後の女」の前書きに「この小説の題をまた「女の河」ともいう。女の生命の脈絡は摩訶不思議である。地の中の河のように人知れず流れている。そこに意志ありとも思えない。しかし卒爾(そつじ)ではない」とつけている。
芥川にしろ荷風にしろ、男性作家が川を「情景」として描くのと全く異なるスタンスだと思う。それが一番現われているのが「渾沌未分(こんとんみぶん)」である。江東砂村の岸で水練場を経営する父を持つ小初というピチピチした少女、日本橋小網町育ちの下町娘が荒川放水路で水泳の先生をやっている、というのは時代だなアと思う。町の八十くらいのお年寄りに、確かに小台橋や荒木田辺に、夏稼ぎの板張りの水練場が川にせりだしていたと聞く。
生ぬるい水中へぎゅーんと五体がただ一つの勢力となって突入し、全皮膚の全感覚が、重くて自由で、柔軟で、緻密な液体に愛撫され始めると何もかも忘れ去って、小初は「海豚の歓び」を歓び始める。
エクスタシーに近い生理的な快感がある。私自身、運動神経は鈍いのに水泳だけは得意で、水の抵抗感ですべての嫌なことを忘れてきたから、なんだか自分のための小説なのだ。
小初が幼ななじみの薫を思い切り、宮大工あがりの五十男貝原の妾になる筋は、どこか『たけくらべ』を思わせるが、運命ではあっても小初は不思議に性根が据わっている。
こせこせしたものは一切抛げ捨ててしまえ、生れたてのほやほやの人間になってしまえ。向うものが運命なら運命のぎりぎりの根元のところへ、向うものが事情なら、これ以上割り切れない種子のところに詰め寄って、掛値なしの一騎打の勝負をしよう。……渾沌未分……渾沌未分……。
これまた、諸々の外発的事情に流されることの多い女の一生で、呪文のように思い返される一節である。
私が妻であったころに励まされたのは、「青鞜」の復刻版でちらっと目に止まった歌。
人妻をうばはむほどの強さをば持てる男のあらば奪られむ
「かろきねたみ」の一首である。
結婚は予定調和ではなく、日常化した関係が愛も共感すらも磨滅させやすいこと、夫以外の男、妻以外の女に心を移すこともじつに自然なのだと知った。男と女も、男と男も、女と女も、人間関係はいろいろあらあナなので、かの子の結婚後の恋愛が面白くなった。次々と妻の愛人を同居させた岡本一平にもつくづく興味を抱いた。一人の女への愛で、息子の太郎も含め、男たちが友情や共感を成り立たせていたのかもしれない。
私には一平はいない。そしてもはや出会えないだろう。二十代初期で結婚し、葛藤し、男が放蕩し、改心したからあんな面白いことになったのだろうから。
東京の古い町を見つづけてきた私には、「家霊」や「老妓抄」「鮨」は前にも増してうならされる。とくに「家霊」の徳永老人が、やっとどじょう汁をつくってもらうとこ。
老人は見栄も外聞もない悦び方で、コールテンの足袋の裏を弾ね上げて受取り、仕出しの岡持ちを借りて大事に中へ入れると、潜り戸を開けて盗人のように姿を消した。
この描写は憎らしいほどだ。
さて、子ども三人、独り親の今の私のたしかに「切実な修業」であるような暮しを支えるかの子のおまじない。
丹花を口に銜(ふく)みて巷を行けば畢竟、惧れはあらじ。
「花は勁し」の作中ではジョルジュ・サンドがイメジされているが、私は椿の花をくわえ闊歩する男伊達の遊女、丹前勝山を心に描いて、自分の背をぐいとそらす。
【この作家論/作家紹介が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする
ちくま 1993年~1996年
筑摩書房のPR誌です。注目の新刊の書評に加え、豪華執筆陣によるエッセイ、小説、漫画などを掲載。
最新号の目次ならびに定期購読のご案内はこちら。