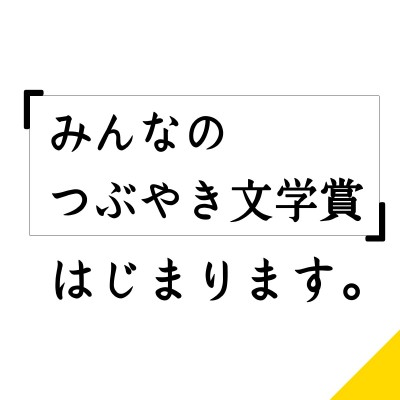映画監督・深田晃司と行く台湾書店ツアー!いま世界が注目する台湾の魅力とは?
2020年は世界的に台湾が注目された1年だった。コロナ禍においてマスクマップを作成、IQ180の天才オードリー・タン(デジタル担当大臣)の活躍は記憶に新しい。ひまわり運動への参加は彼女にとっても大きな経験だったと語っている。
台湾の民主化が前進するきっかけとなった、2014年ひまわり運動を記録した映画『私たちの青春、台湾』が10月31日よりポレポレ東中野にて公開される。最新作『本気のしるし』が第73回カンヌ国際映画祭の「オフィシャルセレクション2020」に選出された、映画監督の深田晃司が台湾の魅力、民主化の足跡を探るべく、台湾発のカルチャー書店、誠品生活日本橋を訪ねた。

傅楡(フー・ユー)監督の『私たちの青春、台湾』は、ひまわり運動のリーダー的存在だった陳為廷(チェン・ウェイティン)と大陸からの留学生、蔡博芸(ツァイ・ボーイ―)の2人を中心に、内部から運動を記録したドキュメンタリー。2018年、台湾アカデミー賞こと金馬奨の「最優秀ドキュメンタリー賞」を受賞した。
映画の公開に合わせ、傅楡監督の人生と台湾の民主化の歩みを書いた『わたしの青春、台湾(五月書房新社)』も刊行。今回は映画公開と出版を記念して、「映画監督と行く書店ツアーin誠品生活日本橋 Produce by “ALL REVIES” が実現。ナビゲーターはフランスを始め、海外との合作も多く、読書家でもある深田晃司監督。まず、参加者全員がかごを持ち、監督からの挨拶でツアーがスタートした。

深田:書店で大きな声で話すことに、まず背徳感を感じますね(笑)。自分は台湾に詳しくないのに、こうした機会をいただいて嬉しいです。今回『私たちの青春、台湾』を見て、私たちは政治はプロフェッショナルな人たちに任せるものだと思いがち。けれど、この映画の学生たちの姿は誰もが自分から関わることができるし、勝ち取ろうというエネルギーが大事であると思い出させてくれます。
映画では挫折も描かれますが、それで終わりではないんです。社会や政治は本来、いつまでたっても不完全であるし、それをいくら年を重ねたところで完成されない私たちが担うしかないもの。そして政治運動からさらにその奥の、個人の葛藤や孤独を描いたことが、この映画をさらに普遍的なテーマを持つ作品にしています。
映画監督をしていると、映画がいろんな国へ連れて行ってくれます。3、4年前、上海映画祭へ行った足で、台北の映画祭へ行きました。上海では当たり前のように皆が台湾は中国であるという前提で話をしていたので、台湾へ行って早々、ついうっかり台湾のことを中国とひとくくりにするような発言をしてしまい微妙な空気にさせてしまった事がありました。即座に訂正しましたが、そういう台湾と中国との微妙な関係が、この映画を見るとよく分かります。
店内の一角に設けられた「私たちの青春、台湾 ブックフェア」には小説、エッセイ、ガイドブック、料理書まで、台湾関連の書籍が幅広く集められている。専門家による丁寧なポップが多く添えられているのも嬉しい。また、映画の中で香港の雨傘運動の学生リーダーだった黄之鋒(ジョシュア・ウォン)や周庭(アグネス・チョウ)との交流が描かれているように、多くの香港関係の書籍も並ぶ。ツアー一同はまず、フェアのコーナーへ。


深田監督(以下、深田):今日は『私たちの青春、台湾』の字幕を担当された吉川龍生さん、『わたしの青春、台湾』で翻訳協力をされた劉怡臻(リュウ・イシン)さん、台湾LGBTQ文学の研究者である劉靈均(リュウ・レイキン)さんがいらしているので、助けてもらおうと思います。吉川さん、おすすめがあったら教えて下さい。
吉川龍生(以下、吉川):映画に関係のある文学でいえば、余華(ユイ・ホア)『活きる』(中央公論新社)は張芸謀(チャン・イーモウ)の『活きる』の原作です。『台北ストーリー』(国書刊行会)の白先勇(はくせんゆう)もアン・リーが映像化している作家で、読みやすいと思いますよ。
劉怡臻:徐嘉澤(じょ・かたく)の『次の夜明けに (現代台湾文学選1) 』(書肆侃侃房)は出版されたばかりで、台湾の近現代史を背景にし、民主化運動で傷つき、それまでの生き方を変えざるを得ない三代にわたる家族の物語です。ぜひ皆さんに読んでいただきたい作品です。
深田:じゃあ、買っちゃおう(笑)。
吉川:この『落日-とかく家族は』(勉誠出版)の方方(ファンファン)は、武漢をベースに活躍する有名作家ですが、最近は『武漢日記』(河出書房新社)が話題になりました。
深田:文学の世界では台湾と中国の交流は盛んでしょうか?
吉川:文学は映像ほど規制も厳しくないので、交流しやすいかも知れません。ただ、台湾の若い作家の言語はもう、大陸の言語とはかなり違ってきていると思いますね。中国の作品ではなく、英語や他の言語からの影響を感じます。
劉怡臻:今の台湾には、中国の作家も小さい頃から読んでいるし、外国の作家の作品も同じように読んでいて、それぞれから影響を受けて出来た、台湾の文学というものがあると思います。
深田:なるほど。映画に関する中国の検閲はとても厳しいと聞きます。性的なもの、反体制的な政治的なものは一切ダメ。しかも実際のところは検閲で落ちても理由を教えてくれない。そこが一番の抑圧で、みんな忖度して、ダメだと言われそうなものは自己検閲で排除してしまう。だから世界で評価されるような中国のリアルを描いた映画は本国では上映もできないものも少なくない。中国の実情を知りたいなら、映画よりも文学の方が良いかも知れませんね。この『郁達夫と大正文学―“自己表現”から“自己実現”の時代へ』(東京大学出版)は?
吉川:郁達夫(いく・たっぷ)は日本留学をし、第二次大戦中はシンガポールで仕事をした小説家。戦争が終わってから、避難先のスマトラで日本軍に殺されとも言われています。中国文学の中では自我の目覚めを書いた人として有名です。
深田:戦争を描いた本は単純に読みたいですね。5、6年前、映画の上映会のためにインドネシアへ行きまして。その時、交流会で大学生の女性に、まっすぐ目を見ながら「日本では戦争犯罪について教えているんですか?」と聞かれたことがあります。「すいません、あんまり教わっていません」と答えるしかなかったのですが、インドネシアは親日国というイメージがあるけれど、それは日本側から言うことではない。インドネシアの方が言ってくれるのはありがたいですけど。近隣の国から日本がどう見ているかは知らないといけない。
吉川:阿壠(アーロン)の『南京 抵抗と尊厳』(五月書房新社)は中国側から南京事件を扱った最初の小説。阿壠はのちに弾圧の対象となり獄中で亡くなった作家で、いろんな意味で衝撃的な内容です。

深田:この『父なる中国、母(クィア)なる台湾?』(作品社)の帯に「なぜ、現代の台湾において、性的マイノリティ文学が隆盛を誇るのか?」とありますが、そうなんですか?
劉靈均:はい。87年の戒厳令解除後、フェミニズム、ゲイリブ、クィアカルチャーなどが台湾で紹介されるようになったといわれています。『次の夜明けに』では日本のゲイカルチャーの影響も感じることができますよ。台湾のLGBTQの作品は30冊くらい翻訳されているので、ぜひ読んで欲しいです。胡淑雯(フーシューウェン)の『太陽の血は黒い 台湾文学セレクション2』(あるむ)は二・二八事件とLGBTQの関係についても描いていて、おすすめしたい一冊です。
説明を聞きながら、フェアのコーナーをゆっくり見て回った後、監督が少し足早に向かったのは美術書のコーナーだ。
自分は小さい頃から絵を描くのが好きで、家にも山ほど画集があります。最近、NetflixやU-NEXTのような配信が増えている状況を、映画監督としてどう思いますか? という質問を受けることがあります。映画館で見る人が減り、劇場が衰退するのではないかという危惧はありますか、という問いかけです。
でも、美術に例えるなら、画集で見ているから本物は見なくていい、美術館はいらないとはならないですよね。画集の印刷で見るものと美術館で見る実物はだいぶ違いますし。映画も同じだと思っていて。多くの映画監督は映画館で見てもらうことを前提に作品を作ります。DVDやストリーミングには過去の膨大な名作がありますし手軽ですし、それを見て映画が好きになってくれたら、ぜひ映画館にも足を運んで欲しい。スクリーンで見られる機会をきちんと残しておくことが大事だと思っています。
ちなみに深田監督が一番好きな画家はドガだそうです。次は映画関係のコーナーに移動。

自分の歴史の中では、映画を見ることと映画の本を読むことはほぼ重なっています。淀川長治さんと蓮實重彦さん、山田宏一さんの鼎談集『映画千夜一夜』(中央公論新社)を読み、出てくる映画を片っ端から見ていったのが、本格的に映画にのめり込んだきっかけでした。
山田宏一さんは「カイエ・デュ・シネマ」の同人だった人。ジャン・リュック・ゴダールやフランソワ・トリュフォーといった、ヌーヴェル・ヴァーグの監督たちとの交流を『友よ映画よ わがヌーヴェル・ヴァーグ誌』(平凡社)という本に書いています。この本の読後感と、『私たちの青春、台湾』を見た後の感覚には共通点があります。何をやってもうまくいき、すべてが新しい経験という青春の高揚感、多幸感と同時に、青春は永遠に続かない、いつか終わってしまうという寂寥感がどちらにもある。
今年の東京国際映画祭Japan now部門では、深田監督特集 が組まれている。上映予定のアニメ作品「ざくろ屋敷 バルザック『人間喜劇』より」(2006)の原作者、オノレ・ド・バルザックも映画をきっかけに興味を持った作家という。
短編「知られざる傑作」が原作のジャック・リヴェットの『美しき諍い女』(1991)を見てから、バルザックに興味を持ち読むようになりました。トリフォーの『大人は判ってくれない』の中にもバルザックの写真が出てくるし、エリック・ロメールも「映画を撮りたければバルザックを読め」と言っています。こんな風に映画と文学は、自分の中で繋がっているんです。
とはいえただの読者に過ぎませんから、『ざくろ屋敷』の時は、フランス文学者の鹿島茂さんに監修をお願いし、鹿島さんにもお話を伺い自分もだいぶ勉強しました。バルザックの魅力はダイナミックな物語展開やアクの強いキャラクター。まず読むなら『ゴリオ爺さん』がおすすめです。地方からパリに出てきた青年が主人公で、最後は熱血少年漫画のラストシーンみたいですよ(笑)。
書店ツアーの後半、監督が足を止めたのは人文書のコーナーだった。

大学時代に読んだE.H. カー『歴史とは何か』(岩波新書)は、今だに影響を受けている本です。カーは、歴史とは客観的な事実を積み重ねたものとは言い切れない、歴史家の主観で書かれたものである。なぜなら私たちは常に無意識に影響されていてそこから逃れることはできない、と。彼はユングやフロイトが発見した無意識という概念をふまえて、歴史を考えなければならないと言っていて、その考え方は演技について考える時に役立っています。
俳優が役の感情や性格をきちんと把握し、計算して、身体で表現する演技は分かりやすいけれど、どこか嘘くさく感じる。人間というのはすべての動きをコントロールしているわけではない。それは無意識が「発見」される前の19世紀的演技なんじゃないかということをフロイトやE.H. カーから学びました。

現在公開中の最新作『本気のしるし 劇場版』。女性の主体性を描いたこの作品は、映画にもなった韓国のチョ・ナムジュ『82年生まれ、キム・ジヨン』と比較されることも多いという。
自分がフェミニズムやジェンダーを考える時に、とても影響を受けているのが、6、70年代のフェミニズムを語るうえで欠かせない富岡多恵子です。『波うつ土地』(講談社)という長編小説が一番好きで、当時から女性が男性社会の中でいかに傷つきながら生きているか、男性社会の抑圧をきちんと描いている。一方で、母性に対する疑いといったことにも切り込んだ人で、ぜひ読んでもらいたい作家です。
各自が持つカゴの重さが、ツアーもそろそろ終わりに近づいていることを知らせてくれる。参加者も「楽しかった! あっという間の1時間でした」「監督の個人的な話も聞けて嬉しかった」と感想を話しつつ、深田監督と行く書店ツアーは充実のうちに幕を閉じた。誠品生活日本橋の『私たちの青春、台湾』公開&書籍「わたしの青春、台湾」発売記念ブックフェアは11月19日(木)まで。
なお本イベントの様子は YouTube ALL REVIEWS公式チャンネル にて全編無料配信中。(野村麻里)
[ライタープロフィール]野村麻里(のむら まり)ライター、時々編集も。著作は『香港風味』等。編集の仕事は『南方熊楠 人魚の話』『Sisterhood-Little Thunder Art Book-』等。最新の仕事はリトルサンダー『わかめとなみとむげんのものがたり』(リイド社)。
台湾の民主化が前進するきっかけとなった、2014年ひまわり運動を記録した映画『私たちの青春、台湾』が10月31日よりポレポレ東中野にて公開される。最新作『本気のしるし』が第73回カンヌ国際映画祭の「オフィシャルセレクション2020」に選出された、映画監督の深田晃司が台湾の魅力、民主化の足跡を探るべく、台湾発のカルチャー書店、誠品生活日本橋を訪ねた。
深田晃司監督との書店ツアーが実現

傅楡(フー・ユー)監督の『私たちの青春、台湾』は、ひまわり運動のリーダー的存在だった陳為廷(チェン・ウェイティン)と大陸からの留学生、蔡博芸(ツァイ・ボーイ―)の2人を中心に、内部から運動を記録したドキュメンタリー。2018年、台湾アカデミー賞こと金馬奨の「最優秀ドキュメンタリー賞」を受賞した。
映画の公開に合わせ、傅楡監督の人生と台湾の民主化の歩みを書いた『わたしの青春、台湾(五月書房新社)』も刊行。今回は映画公開と出版を記念して、「映画監督と行く書店ツアーin誠品生活日本橋 Produce by “ALL REVIES” が実現。ナビゲーターはフランスを始め、海外との合作も多く、読書家でもある深田晃司監督。まず、参加者全員がかごを持ち、監督からの挨拶でツアーがスタートした。

深田:書店で大きな声で話すことに、まず背徳感を感じますね(笑)。自分は台湾に詳しくないのに、こうした機会をいただいて嬉しいです。今回『私たちの青春、台湾』を見て、私たちは政治はプロフェッショナルな人たちに任せるものだと思いがち。けれど、この映画の学生たちの姿は誰もが自分から関わることができるし、勝ち取ろうというエネルギーが大事であると思い出させてくれます。
映画では挫折も描かれますが、それで終わりではないんです。社会や政治は本来、いつまでたっても不完全であるし、それをいくら年を重ねたところで完成されない私たちが担うしかないもの。そして政治運動からさらにその奥の、個人の葛藤や孤独を描いたことが、この映画をさらに普遍的なテーマを持つ作品にしています。
映画監督をしていると、映画がいろんな国へ連れて行ってくれます。3、4年前、上海映画祭へ行った足で、台北の映画祭へ行きました。上海では当たり前のように皆が台湾は中国であるという前提で話をしていたので、台湾へ行って早々、ついうっかり台湾のことを中国とひとくくりにするような発言をしてしまい微妙な空気にさせてしまった事がありました。即座に訂正しましたが、そういう台湾と中国との微妙な関係が、この映画を見るとよく分かります。
店内の一角に設けられた「私たちの青春、台湾 ブックフェア」には小説、エッセイ、ガイドブック、料理書まで、台湾関連の書籍が幅広く集められている。専門家による丁寧なポップが多く添えられているのも嬉しい。また、映画の中で香港の雨傘運動の学生リーダーだった黄之鋒(ジョシュア・ウォン)や周庭(アグネス・チョウ)との交流が描かれているように、多くの香港関係の書籍も並ぶ。ツアー一同はまず、フェアのコーナーへ。


専門家の熱いおススメ
深田監督(以下、深田):今日は『私たちの青春、台湾』の字幕を担当された吉川龍生さん、『わたしの青春、台湾』で翻訳協力をされた劉怡臻(リュウ・イシン)さん、台湾LGBTQ文学の研究者である劉靈均(リュウ・レイキン)さんがいらしているので、助けてもらおうと思います。吉川さん、おすすめがあったら教えて下さい。
吉川龍生(以下、吉川):映画に関係のある文学でいえば、余華(ユイ・ホア)『活きる』(中央公論新社)は張芸謀(チャン・イーモウ)の『活きる』の原作です。『台北ストーリー』(国書刊行会)の白先勇(はくせんゆう)もアン・リーが映像化している作家で、読みやすいと思いますよ。
劉怡臻:徐嘉澤(じょ・かたく)の『次の夜明けに (現代台湾文学選1) 』(書肆侃侃房)は出版されたばかりで、台湾の近現代史を背景にし、民主化運動で傷つき、それまでの生き方を変えざるを得ない三代にわたる家族の物語です。ぜひ皆さんに読んでいただきたい作品です。
深田:じゃあ、買っちゃおう(笑)。
吉川:この『落日-とかく家族は』(勉誠出版)の方方(ファンファン)は、武漢をベースに活躍する有名作家ですが、最近は『武漢日記』(河出書房新社)が話題になりました。
深田:文学の世界では台湾と中国の交流は盛んでしょうか?
吉川:文学は映像ほど規制も厳しくないので、交流しやすいかも知れません。ただ、台湾の若い作家の言語はもう、大陸の言語とはかなり違ってきていると思いますね。中国の作品ではなく、英語や他の言語からの影響を感じます。
劉怡臻:今の台湾には、中国の作家も小さい頃から読んでいるし、外国の作家の作品も同じように読んでいて、それぞれから影響を受けて出来た、台湾の文学というものがあると思います。
深田:なるほど。映画に関する中国の検閲はとても厳しいと聞きます。性的なもの、反体制的な政治的なものは一切ダメ。しかも実際のところは検閲で落ちても理由を教えてくれない。そこが一番の抑圧で、みんな忖度して、ダメだと言われそうなものは自己検閲で排除してしまう。だから世界で評価されるような中国のリアルを描いた映画は本国では上映もできないものも少なくない。中国の実情を知りたいなら、映画よりも文学の方が良いかも知れませんね。この『郁達夫と大正文学―“自己表現”から“自己実現”の時代へ』(東京大学出版)は?
吉川:郁達夫(いく・たっぷ)は日本留学をし、第二次大戦中はシンガポールで仕事をした小説家。戦争が終わってから、避難先のスマトラで日本軍に殺されとも言われています。中国文学の中では自我の目覚めを書いた人として有名です。
深田:戦争を描いた本は単純に読みたいですね。5、6年前、映画の上映会のためにインドネシアへ行きまして。その時、交流会で大学生の女性に、まっすぐ目を見ながら「日本では戦争犯罪について教えているんですか?」と聞かれたことがあります。「すいません、あんまり教わっていません」と答えるしかなかったのですが、インドネシアは親日国というイメージがあるけれど、それは日本側から言うことではない。インドネシアの方が言ってくれるのはありがたいですけど。近隣の国から日本がどう見ているかは知らないといけない。
吉川:阿壠(アーロン)の『南京 抵抗と尊厳』(五月書房新社)は中国側から南京事件を扱った最初の小説。阿壠はのちに弾圧の対象となり獄中で亡くなった作家で、いろんな意味で衝撃的な内容です。

深田:この『父なる中国、母(クィア)なる台湾?』(作品社)の帯に「なぜ、現代の台湾において、性的マイノリティ文学が隆盛を誇るのか?」とありますが、そうなんですか?
劉靈均:はい。87年の戒厳令解除後、フェミニズム、ゲイリブ、クィアカルチャーなどが台湾で紹介されるようになったといわれています。『次の夜明けに』では日本のゲイカルチャーの影響も感じることができますよ。台湾のLGBTQの作品は30冊くらい翻訳されているので、ぜひ読んで欲しいです。胡淑雯(フーシューウェン)の『太陽の血は黒い 台湾文学セレクション2』(あるむ)は二・二八事件とLGBTQの関係についても描いていて、おすすめしたい一冊です。
画集とストリーミングは似ている?
説明を聞きながら、フェアのコーナーをゆっくり見て回った後、監督が少し足早に向かったのは美術書のコーナーだ。
自分は小さい頃から絵を描くのが好きで、家にも山ほど画集があります。最近、NetflixやU-NEXTのような配信が増えている状況を、映画監督としてどう思いますか? という質問を受けることがあります。映画館で見る人が減り、劇場が衰退するのではないかという危惧はありますか、という問いかけです。
でも、美術に例えるなら、画集で見ているから本物は見なくていい、美術館はいらないとはならないですよね。画集の印刷で見るものと美術館で見る実物はだいぶ違いますし。映画も同じだと思っていて。多くの映画監督は映画館で見てもらうことを前提に作品を作ります。DVDやストリーミングには過去の膨大な名作がありますし手軽ですし、それを見て映画が好きになってくれたら、ぜひ映画館にも足を運んで欲しい。スクリーンで見られる機会をきちんと残しておくことが大事だと思っています。
ちなみに深田監督が一番好きな画家はドガだそうです。次は映画関係のコーナーに移動。

『私たちの青春、台湾』とヌーヴェル・ヴァーグの共通性
自分の歴史の中では、映画を見ることと映画の本を読むことはほぼ重なっています。淀川長治さんと蓮實重彦さん、山田宏一さんの鼎談集『映画千夜一夜』(中央公論新社)を読み、出てくる映画を片っ端から見ていったのが、本格的に映画にのめり込んだきっかけでした。
山田宏一さんは「カイエ・デュ・シネマ」の同人だった人。ジャン・リュック・ゴダールやフランソワ・トリュフォーといった、ヌーヴェル・ヴァーグの監督たちとの交流を『友よ映画よ わがヌーヴェル・ヴァーグ誌』(平凡社)という本に書いています。この本の読後感と、『私たちの青春、台湾』を見た後の感覚には共通点があります。何をやってもうまくいき、すべてが新しい経験という青春の高揚感、多幸感と同時に、青春は永遠に続かない、いつか終わってしまうという寂寥感がどちらにもある。
今年の東京国際映画祭Japan now部門では、深田監督特集 が組まれている。上映予定のアニメ作品「ざくろ屋敷 バルザック『人間喜劇』より」(2006)の原作者、オノレ・ド・バルザックも映画をきっかけに興味を持った作家という。
短編「知られざる傑作」が原作のジャック・リヴェットの『美しき諍い女』(1991)を見てから、バルザックに興味を持ち読むようになりました。トリフォーの『大人は判ってくれない』の中にもバルザックの写真が出てくるし、エリック・ロメールも「映画を撮りたければバルザックを読め」と言っています。こんな風に映画と文学は、自分の中で繋がっているんです。
とはいえただの読者に過ぎませんから、『ざくろ屋敷』の時は、フランス文学者の鹿島茂さんに監修をお願いし、鹿島さんにもお話を伺い自分もだいぶ勉強しました。バルザックの魅力はダイナミックな物語展開やアクの強いキャラクター。まず読むなら『ゴリオ爺さん』がおすすめです。地方からパリに出てきた青年が主人公で、最後は熱血少年漫画のラストシーンみたいですよ(笑)。
書店ツアーの後半、監督が足を止めたのは人文書のコーナーだった。

人間はすべてをコントロールできない
大学時代に読んだE.H. カー『歴史とは何か』(岩波新書)は、今だに影響を受けている本です。カーは、歴史とは客観的な事実を積み重ねたものとは言い切れない、歴史家の主観で書かれたものである。なぜなら私たちは常に無意識に影響されていてそこから逃れることはできない、と。彼はユングやフロイトが発見した無意識という概念をふまえて、歴史を考えなければならないと言っていて、その考え方は演技について考える時に役立っています。
俳優が役の感情や性格をきちんと把握し、計算して、身体で表現する演技は分かりやすいけれど、どこか嘘くさく感じる。人間というのはすべての動きをコントロールしているわけではない。それは無意識が「発見」される前の19世紀的演技なんじゃないかということをフロイトやE.H. カーから学びました。
富岡多恵子の先見性の凄さ

現在公開中の最新作『本気のしるし 劇場版』。女性の主体性を描いたこの作品は、映画にもなった韓国のチョ・ナムジュ『82年生まれ、キム・ジヨン』と比較されることも多いという。
自分がフェミニズムやジェンダーを考える時に、とても影響を受けているのが、6、70年代のフェミニズムを語るうえで欠かせない富岡多恵子です。『波うつ土地』(講談社)という長編小説が一番好きで、当時から女性が男性社会の中でいかに傷つきながら生きているか、男性社会の抑圧をきちんと描いている。一方で、母性に対する疑いといったことにも切り込んだ人で、ぜひ読んでもらいたい作家です。
各自が持つカゴの重さが、ツアーもそろそろ終わりに近づいていることを知らせてくれる。参加者も「楽しかった! あっという間の1時間でした」「監督の個人的な話も聞けて嬉しかった」と感想を話しつつ、深田監督と行く書店ツアーは充実のうちに幕を閉じた。誠品生活日本橋の『私たちの青春、台湾』公開&書籍「わたしの青春、台湾」発売記念ブックフェアは11月19日(木)まで。
なお本イベントの様子は YouTube ALL REVIEWS公式チャンネル にて全編無料配信中。(野村麻里)
[ライタープロフィール]野村麻里(のむら まり)ライター、時々編集も。著作は『香港風味』等。編集の仕事は『南方熊楠 人魚の話』『Sisterhood-Little Thunder Art Book-』等。最新の仕事はリトルサンダー『わかめとなみとむげんのものがたり』(リイド社)。
ALL REVIEWSをフォローする