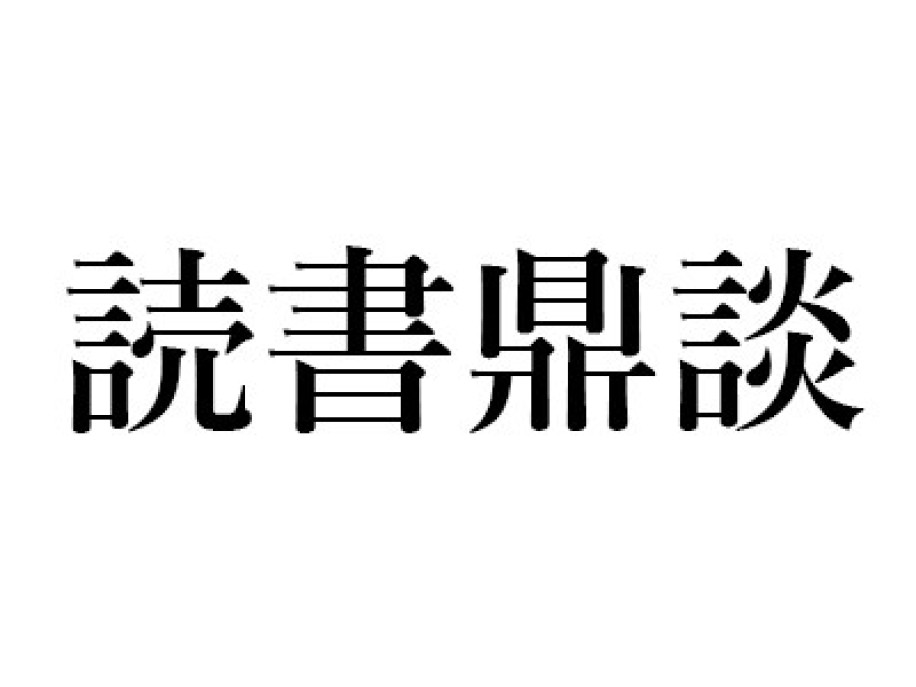書評
『PERSONA最終章』(筑摩書房)
〈観る者〉が観られているような視線の交わりを写しとる
「銀ヤンマのような娘」カバー写真の作品につけられたキャプションである。光るサングラス、長く白い両腕、細い太もも、そうか銀ヤンマ嬢……写真と言葉と実像が交錯し、意識の深層が揺れる、ちくちく揺さぶられる。
写真集『PERSONA最終章 2005―2018』は、人間が蠢(うごめ)く深い森のなかへ誘う一冊だ。写し出されるひとりひとり、たしかに人間の形はしているが、魑魅魍魎(ちみもうりょう)の化身にも見えてくる。
「病気で、板前を辞めざるをえなかったという人」
「猫(16歳)に英単語で話しかける税理士」
「表情を変えない男」
「右肩だけが凝るとわらう人」
「『減るものではないので、撮れば……』という人」
「『むろん、本物よ』という女性」
「護国神社の宮司」
「前髪を気にする青年」
「いつの間にか、80歳になっていると語る婦人」
……芝居の役柄を語るかのようなキャプションが、虚構と現実のあわいをきわどく攻めてくる。大判写真集の一ページ、一作品、一人物。カメラに向かって立つ姿を浮かび上がらせるのは、鬼海(きかい)トーンというべきグレイの色彩の階調だ。
すべて、浅草・浅草寺の境内、朱銅色の壁の前で撮られている。写真家、鬼海弘雄が浅草に通い始めたのは1973年。以来45年、同じ場所を路上の“特設スタジオ”として市井の人々を撮り続けてきた。前作『PERSONA』(草思社)は、2004年に土門拳賞を受けている。
いわゆるポートレート写真とは一線を画する。というか、表す世界が違う。『PERSONA』に写し出された人物たちは、国境も時空間も突き破り、イメージの領域に至ろうとする。〈カメラに視線を注ぐ者〉〈写真を観る者〉、両者の視線がするどく交わるとき、ここに写し出された人々は触媒なのだと気づく。触媒が何を連れてくるのか、何を見せるのか。それは〈写真を観る者〉に手渡された特権であり、物語の始まりでもあるだろう。
写真を撮り始める以前、大学を卒業した鬼海弘雄は、種々雑多な職業を経験している。トラック運転手、工事現場の作業員、遠洋マグロ漁船の見習漁師……明滅のはげしい時間の手触りや匂いや音や映像が、浅草を行き来する無名の人物と一瞬の苛烈な引き合いを生じさせるのか。ただし、浅草寺に数時間いても、一日に撮影するのはわずかひとりかふたりだったという。
長い間続けているのに、人物を選ぶ基準はいまでも自分でもよく分らない。あえて言葉にすれば、ポートレートを観る人たちが、普段持っている人間に対しての堅くなりがちな情とイメージを揉(も)み解(ほぐ)し、豊かなひろがりをもたらしてくれる人物と思っている。こだまのような波動が、生きることを少しだけ楽しくしてくれるからだ。(「あとがきにかえて」より)
若い日、ダイアン・アーバスの作品に触発されて写真家になったという鬼海弘雄がレンズを向ける被写体の人物たちは、観る者の前で、素顔と虚構を巧みにシャッフルする。「こだまのような波動」が怖い。ここには人の真実がたしかに写っているが、真実の行方はわからなくさせる。
ALL REVIEWSをフォローする