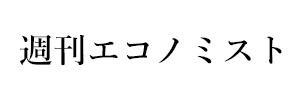書評
『明治期のポルノグラフィ』(新潮社)
裸の女たちが語る時代
「フォト・ミュゼ」(新潮社)というシリーズが好きだ。写真集というと重厚長大、これでもかの大きさと紙の質で扱いにくくて弱るが、これはA5判という軽やかさ。適度な紙質とシャープな編集がいい。荒木経惟『さっちん』、影山光洋『芋っ子ヨッチャンの一生』、桑原甲子雄『東京1934〜1993』など、手元において疲れたら眺めている。本書『明治期のポルノグラフィ』(石黒敬章編、新潮社)も日本のヌードの夜明けを示す貴重な本だ。「とんちン館」名誉会長、骨董ブームの仕掛け人の著者を、珍品ゲテモノ趣味と見込んで、誰かが六枚の明治のヌードを届けてくれた。これをきっかけに百枚もあればコレクションになるのでは、と集めはじめる。
文久三(一八六三)年来日し、愛宕山を写したことで有名なフェリクス・ベアトがヌード写真を撮ってたとは驚いた。桐タンスの上に盆栽、着物姿の女性の手前に、胸をはだけて横たわる女。不思議な構図だが、これがベアトの考えた「日本」なのだ。明治八年ころのスチルフリードの撮影もほとんど同じ構図である。
いわゆる横浜写真といわれる土産物写真にも、入浴や化粧する裸体の女が多出する。たいてい腰巻はつけて片肌あるいは双肌脱ぎのぎごちない、静的なポーズ。裸体のまま三味線を弾き、花傘をさし、本を読んだりと、写真師のいいつけでポーズをとる。その写真師のまなざし、その向こうに写真を買う外国人の日本へのまなざしが見てとれる。
旦那衆が妾を無理矢理脱がせたらしい素人写真のようなポルノもある。あどけない少女の裸体、どうとも写せと大股開きのおばさんポルノ。秘すべき所を見せながら扇子で顔を隠したり、足袋をはいてなおさらエッチな写真。写される側の表情の一つ一つが興味深く、写す側の小細工がどことなく幼くてほのぼのしている。それにしても平らな胸、垂れた乳、ぽこんと出た腹、太い足の五頭身を、女たちは惜し気もなく写されたものだ。
二枚だけ日本人離れしたプロポーションの写真があるが、案の定、これは外国人の体に日本人の顔だけすげかえた合成写真らしい。いやそもそも「日本人離れした」という言葉の裏に日本人の顔も体も偏平で貧しいという固定観念、コンプレックスが潜む。それがいまだに美の基準として女たちを縛り、エステ、ダイエット食品、整形手術、化粧品など美容産業を肥え太らせている。
たかが足、たかが手、なんぼのもんじゃ、と明治期の裸体は問いかけてくる。これはこれで十分美しい。もしかして貧しい娘が金のために、あるいはそれ以外の強制力で撮られたものかもしれないが、微笑すら浮かべている。そしてここに肌をさらした女性の一人としていま生きていない、と思うと、ふいに鼻のつまるような切なさを覚える。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする