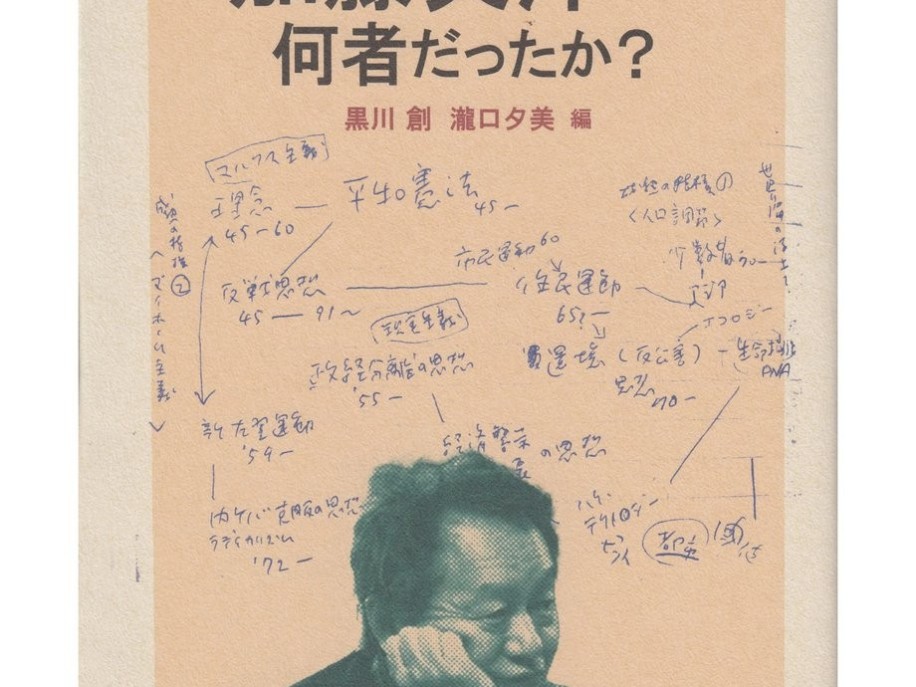書評
『小沼丹 小さな手袋/珈琲挽き 大人の本棚』(みすず書房)
「玄関で風呂をたいている」と聞き、風呂桶を置いているだけのことなのに「君とこの玄関は随分たてつけがいいんだね」、たたきに水を張って湯を沸かすと勘違いした――尾崎一雄の短編で茶化されている井伏鱒二も可愛いけれど、小沼丹のエッセイ集に顔を出す井伏先生も相当にお茶目だ。原稿の締切が迫っているのに、「もう一番」と勝つまで将棋を指しつづけたり、小沼さんの庭にある地蔵を見て、「何だ、君は地蔵迄……」と絶句、盗んできたと勘違いし、最後までその誤解を解かないとか(とはいえ、小沼さんには若い頃、飲み屋の徳利や、道路標識、工事現場の点滅灯などを失敬してきた“前科”があるから、井伏先生の思い込みも仕方ないといえば仕方ない?)。
大作家だけじゃない。この本に出てくるすべての人が、動物が、物が、小沼丹という類いまれなる品格とユーモアと優しさを備えたレンズを通し、柔らかな輪郭と親しみをまとって立ち上がってくるのだ。お尻をかきたいのに、もんぺをはかされているため思うようにかけず、その隔靴掻痒(かっかそうよう)感を不満げな横眼で伝える猿。一見弱そうなのに、見事ガキ大将を退散させてしまう男の子。庭にやってくる鳥たち。近況をさらりと書いたハガキを送ってくれる親友の庄野潤三。いつの間にか一〇〇〇枚ほども集まってしまったコースター。
そうした身近なものを描いた小沼さんのエッセイは、読み出すと止まらないほど面白い。筆趣に飽きるということがない。それはやはり小沼丹その人の魅力に端を発しているのではないか。もの忘れが激しく(このエピソードの数々も実に可笑しい)、おおらかで、穏やかで、知的で、ユーモリストで。大人のエッセイだなあ、と思う。大人ならこういうエッセイを読まなきゃなあ、と思う。
【文庫版】
【この書評が収録されている書籍】
大作家だけじゃない。この本に出てくるすべての人が、動物が、物が、小沼丹という類いまれなる品格とユーモアと優しさを備えたレンズを通し、柔らかな輪郭と親しみをまとって立ち上がってくるのだ。お尻をかきたいのに、もんぺをはかされているため思うようにかけず、その隔靴掻痒(かっかそうよう)感を不満げな横眼で伝える猿。一見弱そうなのに、見事ガキ大将を退散させてしまう男の子。庭にやってくる鳥たち。近況をさらりと書いたハガキを送ってくれる親友の庄野潤三。いつの間にか一〇〇〇枚ほども集まってしまったコースター。
そうした身近なものを描いた小沼さんのエッセイは、読み出すと止まらないほど面白い。筆趣に飽きるということがない。それはやはり小沼丹その人の魅力に端を発しているのではないか。もの忘れが激しく(このエピソードの数々も実に可笑しい)、おおらかで、穏やかで、知的で、ユーモリストで。大人のエッセイだなあ、と思う。大人ならこういうエッセイを読まなきゃなあ、と思う。
【文庫版】
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする