書評
『エリザベス・コステロ』(早川書房)
デイヴィッド・ロッジ『小説の技巧』(白水社)、イタロ・カルヴィーノ『カルヴィーノの文学講義』(朝日新聞社)、バルガス=リョサ『若い小説家に宛てた手紙』(新潮社)、池澤夏樹『世界文学を読みほどく』(新潮選書)、倉橋由美子『あたりまえのこと』(朝日文庫)などなど、作家が書いた小説論や文学論を読むのが好きだ。そこには一介の読者にはわからない、実作者ならではの創作の秘訣や苦労、小説の読み方が明かされており、その一端に触れるだけで読書の愉しみはより大きくも、より深くもなるからだ。
クッツェーのノーベル文学賞受賞第一作にあたる本書にも、小説という芸術に対する理解を深めるのに絶好の文学論が多々披露されている。ただし、ちょっとひねった形で。これは、実作と批評が一冊の本の中に同居するというスタイルを取った小説なのだ。主人公はオーストラリア生まれの六十六歳、ジョイスの『ユリシーズ』(集英社文庫)に想を得た作品によって世界的に知られるエリザベス・コステロという架空の作家。そんな〈老境にある辛辣な女性作家が、世界を股にかけて文学論議をふっかけてまわる話〉(「訳者あとがき」より)になっているのだ。エリザベスはクッツェーの代弁者であると同時に、批評者でもある。同業者を主人公にすることで、クッツェーは現在流通している文学に実作者としてのメスを入れるばかりか、自分がこれまで書いてきた作品や、そこで開陳してきた世界観なり小説観まで批評のターゲットにしているのだ。そのフェア&スクエアな精神に、まずは感服つかまつり候。
エリザベスは小説におけるリアリズムについての疑念を隠さない。アフリカの文学は同胞に向けてではなく、外国人のために書かれてきたのではないかと問う。人文主義では飢えや病で苦しむ人を救えないと断ずる尼僧の実姉と論争をする。現実にある小説を俎上にのせることで、“文学と悪”の問題にヒューマニズムの視点から、返す刀で自らも傷つけてしまうかもしれない諸刃の剣を向ける。エロスとタナトスという古典的なテーマをユーモラスに語る。作家とは自分の信条について語る者ではなく、〈意見やら偏見やらを寄せつけずに、ことばを伝える導管のような役目をはたし、ことばが中を通り抜けていくだけの〉存在だと言い放つ。深い教養と思慮に支えられた鮮やかにして深い文学観を、実践的レッスンとでも呼ぶべき六つの短篇で提出。そのスタイルのおかげで、難しい理論もするするっと頭の中に入ってくる。作家による小説論として、出色の面白さを約束してくれる一冊なのだ。
【この書評が収録されている書籍】
クッツェーのノーベル文学賞受賞第一作にあたる本書にも、小説という芸術に対する理解を深めるのに絶好の文学論が多々披露されている。ただし、ちょっとひねった形で。これは、実作と批評が一冊の本の中に同居するというスタイルを取った小説なのだ。主人公はオーストラリア生まれの六十六歳、ジョイスの『ユリシーズ』(集英社文庫)に想を得た作品によって世界的に知られるエリザベス・コステロという架空の作家。そんな〈老境にある辛辣な女性作家が、世界を股にかけて文学論議をふっかけてまわる話〉(「訳者あとがき」より)になっているのだ。エリザベスはクッツェーの代弁者であると同時に、批評者でもある。同業者を主人公にすることで、クッツェーは現在流通している文学に実作者としてのメスを入れるばかりか、自分がこれまで書いてきた作品や、そこで開陳してきた世界観なり小説観まで批評のターゲットにしているのだ。そのフェア&スクエアな精神に、まずは感服つかまつり候。
エリザベスは小説におけるリアリズムについての疑念を隠さない。アフリカの文学は同胞に向けてではなく、外国人のために書かれてきたのではないかと問う。人文主義では飢えや病で苦しむ人を救えないと断ずる尼僧の実姉と論争をする。現実にある小説を俎上にのせることで、“文学と悪”の問題にヒューマニズムの視点から、返す刀で自らも傷つけてしまうかもしれない諸刃の剣を向ける。エロスとタナトスという古典的なテーマをユーモラスに語る。作家とは自分の信条について語る者ではなく、〈意見やら偏見やらを寄せつけずに、ことばを伝える導管のような役目をはたし、ことばが中を通り抜けていくだけの〉存在だと言い放つ。深い教養と思慮に支えられた鮮やかにして深い文学観を、実践的レッスンとでも呼ぶべき六つの短篇で提出。そのスタイルのおかげで、難しい理論もするするっと頭の中に入ってくる。作家による小説論として、出色の面白さを約束してくれる一冊なのだ。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
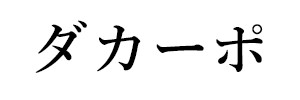
ダカーポ(終刊) 2005年4月20日号
ALL REVIEWSをフォローする
































