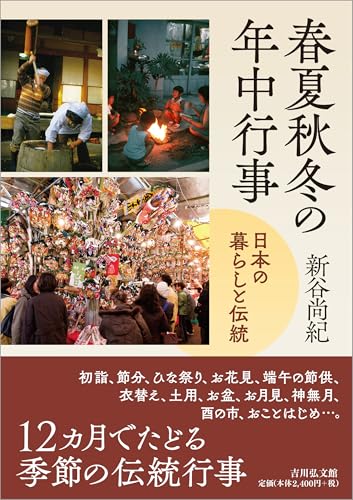本文抜粋
『生き延びるための女性史: 遊廓に響く〈声〉をたどって』(青土社)
遊廓に生きた女性たちの〈声〉を描きだす歴史家であり、また戦時下の厦門を舞台に小説を展開した著者の最新作。本書の刊行を記念して「はじめに 〈声〉をたどる」より一部抜粋してお届けいたします!
亜熱帯の焼けつくような日差しの下、車は軽快に厦門(アモイ)の東海岸を走り抜ける。真っ青な海のむこうに緑の木々におおわれた島影が見えた。金門島ですよ、と運転している友人がいう。大陸にもっとも近い台湾領の島だ。中国と台湾の緊張が高まった時期には、お互いに巨大なスピーカーで、プロパガンダ放送から歌謡曲まで流していたとも教えてくれた。
車は更に海岸線を北上し、広大な工事現場のような一帯を走り抜ける。大きなマンションを建てているのか何台もクレーンが見えた。友人は、またていねいに事情を説明してくれる。戦争の危機が近かったころ、この海岸には建物が建てられなかったらしい。それから、クレーンを横目で見て言葉を続ける。――日本軍がきたときに、住民がたくさん殺されたので、厦門のひとは心情的にこっちを避けるんですよ。泉州出身のその友人が「厦門のひと」と少し距離をおいて語るのが印象に残った。主語を明確にしない語り口は、かつての侵略者の国からやってきたわたしへの気遣いなのかもしれない。その言葉をきいたときに、たくさんのひとが殺されるというリアリティをうまくイメージできたとはいえない。死者たちは、はるかに彼方にあって、わたしは亜熱帯のむせかえるような熱気と、豊かな自然にすっかり目を奪われていた。海岸沿いのブーゲンビリアは美しい薄紫の花を咲かせ、大学の教員宿舎の窓からは背の高い木綿花の木に咲き乱れる真っ赤な花が見えた。風が吹くたびに、潮のにおいとどこか果実のくさったような甘い香りが漂う都市。それでも、榕樹の地上根が風に揺れる細い街路を歩き抜けて、ひとたび街にでるとコロニアル様式の建物群や鐘楼が、この街がたどってきた歴史を物語っているようにも感じた。生活するなかで、意識は自然と過去にむいていった。
占領下の厦門で発行された『全閩新日報』を見ると、八〇年前の街やひとが目に飛び込んでくる。一九四〇年九月七日の紙面は、「あたしたちも新体制」という見出しで、厦門の繁華街で働く女給たちによる厦門神社の雑草抜きを報じている。
当時、日本人むけのカフェーや食堂が建ち並んでいたという大中路の「カフェー喜楽」で働く女給たちは、白や花柄の旗袍(チーパオ)という、およそ草むしりには適さない格好をしている。まだあどけない顔立ちをした女性たちは二〇代前半くらいだろうか。その記事は、総力戦体制のために近衛内閣が掲げた新体制運動に、中国に飛び地のように広がる占領地で働く女給たちもまた組み入れられていたことを示している。わたしは、観光客で賑わう大中路を歩きながら、その女性たちのことを想像する。戦災にあわなかった厦門の中心部には当時の建物がほぼそのまま残っていて、おそらく「カフェー喜楽」も大中路に立ち並ぶ、強い日差しに退色したビルディングのどこかに入っていたのだろう。女性たちが写っている厦門神社の跡地には、いまは一対の狛犬と石段だけが残っていた。帝国の「辺境」の占領地で日本人相手に働く女給たちという、二重にも三重にも周縁化された、記事では名前も書かれていない女性たちは、日本の敗戦後、どこにいったのだろう。
(中略)
厦門という、いまや遠くなってしまった土地の話から書きはじめたのは、そこでの生活がわたしにとって、女性史を研究するということと、自分自身が生きるということがはじめてしっかりと交差する経験としてあったからである。「生き延びるための女性史―遊廓に響く〈声〉をたどって」と名付けられたこの本には、ひとことでいうとわたしが肌感覚とでもいうべきものをとおしてききとった無数の〈声〉が文章という形になって収録されている。〈声〉はいま見たように生活の現場であった厦門できいたものもあれば、はるか昔の史料のなかに響く、比喩的な意味での〈声〉もある。
厦門を訪れる前から現在にいたるまで、わたしがかかわっている女性史とは、いわゆる歴史学が公的領域の男性についての歴史叙述になっているという批判意識から、過去の女性たちの活動や経験に焦点をあてた歴史研究のことである。そのなかでもわたしは、日本の近代公娼制度下の遊廓で生きた女性たちの研究をしている。近世をとおして形作られた遊廓は、人身売買禁止を建前とする明治政府によって近代公娼制度、いわば国家公認の管理売春制度として再編された。
「自由意志」で働きたい女性については「救貧」のために許容する、という欺瞞的な説明のもとで、遊廓は貸座敷という名称に変わったが、そこで働く女性たちのほとんどは前借金による拘束と楼主や警察による監視で自由な外出すら難しい状況に置かれていた。
従来、女性史研究では、遊廓の搾取や過酷さに光があてられ、そこに生きる女性たちは「犠牲者」として一面的に表象される傾向が強かった。しかし、わたしが遊廓のなかの女性たちを中心にして研究をすすめるなかで見えてきたのは「犠牲者」というイメージには収まらない、複数のアイデンティティを生きる女性たちの姿だった。遊廓のなかには、底辺女性労働者の仕事を転々とするなかで娼妓になった女性や、幼少期に片親を失い弟や妹を養うために芸娼妓紹介業者を訪れた女性、半ば騙されるように親元から売られた女性、植民地出身の女性、いったん廃業したものの世間の差別のために舞い戻った女性など、さまざまな女性たちがいた。それらのいくつものアイデンティティが交差する地点に女性たちの生はあり、その経験を語る〈声〉をききとるためにはインターセクショナルな視点が不可欠だった。
女性たちの多様な生に目をむけると、それまで歴史研究で描かれたことのない〈声〉が響いてくるように感じた。博士過程の日々に見たマイクロフィルムの古い新聞記事には、困難な状況にあってもストライキや新聞への告発によって状況改善を求めた遊廓のなかの女性たちの言葉が断片的であっても残っていた。それは遊廓の不条理を訴える、怒りや苦しみの声であり、生き延びるためのエネルギーに満ちた声でもあった。それと同時に、遊廓での日常を語る当事者の言葉からは、張見世で本を読んだり、朋輩とかるたをしたり、冗談をいいあったり、廃業後の仕事について考える、生活者としての女性たちの姿が浮かび上がってきた。その発見は、初の著書である『遊廓のストライキ―女性たちの二十世紀・序説』(共和国、二〇一五年)にまとめられている。
本書に収録されているのは、それ以降の二〇一五年から二〇二三年にかけて書かれた文章である。
この本は三部構成である。
第一部「生活を形作るさまざまな〈声〉」には、雑誌『現代思想』に掲載された文章が集められている。第一章の論考「たったひとりにさせない/ならないために―危機の時代の分断をこえて」は、二〇二〇年に寄稿したものである。コロナパンデミックについて、女性史や中国滞在経験なども含めて書いてほしい、という相当にアクロバティックな原稿依頼を受けたときは、どうして感染症をめぐる社会史の専門家でもないわたしなのだろう、と思ったが、書き上げてみれば自分自身の研究とも生活のリアリティとも重なるテーマであると気がついた。
この文章では、パンデミックがはじまった当初の入口の危機感が鮮明に表現されている。わたし自身が大学非正規労働者としてかかえてきた生きがたさや、女性史でふれてきた証言は、「ステイ・ホーム」という一見だれにとっても疑義を呈しにくい標語の裏側にある、無数の分断やマジョリティの傲慢さに目をむける手がかりになった。仕事を休むと生活もままならない非正規労働者や、家に居場所がなく街に逃れた子どもが、ウイルスの媒介者とみなされるような社会は絶対にまちがっている、そんな確信のなかで書いた。いまやあっというまに歴史になりつつあるパンデミックという時代の、手ざわりをまず確認しておきたくて、実際の発表順とは異なるが本書の冒頭に置くことにした。
イタリアの作家パオロ・ジョルダーノは、二〇二〇年三月にコロナの時代の入口に立って、「数々の真実が浮かび上がりつつあるが、そのいずれも流行の終焉とともに消えてなくなることだろう。もしも、僕らが今すぐそれを記憶に留めぬ限りは」(*2)と書いた。わたしもそう思う。ここに書かれているのは、わたしたちが圧倒的な分断の時代を生きているという認識である。それは危機の時代をへて改善されることもなく、より一層破滅的な様相を見せている。第一部には、わたしたちが常に立ち戻り問い続けなければいけないこの社会をめぐる問題が通奏低音のように響いている。
第二部「遊廓のなかに響く〈声〉」には、遊廓のなかで〈読む〉ということと、遊廓の生活を〈描く〉ことをめぐる論考を集めた。一般的にはほとんど知られていないことだが、内藤新宿遊廓で働く和田芳子が『遊女物語―苦海四年の実験告白』(文明堂、一九一三年)を書いて以降、遊廓のなかを生きた当事者による本が断続的に発行されている。労働運動の高揚期である一九二六(大正一五)年には遊廓のなかからの告発が相次ぎ、同年に労働運動家の支援のもとで廃業した森光子や松村喬子はのちに遊廓での体験を手記や小説という形で発表した。この本は、これまで女性史研究でも文学研究でも取り上げられてこなかった、それらの当事者の自己表現についてのはじめてのまとまった研究でもある。
第三部「響きあう〈声〉」には、女性たちの〈声〉がどのように響きあい、つながっていた(いく)のかを描きだす文章を集めた。女性史とは、史料のなかに断片的に響いている〈声〉をつないでいく実践でもある。そこでは〈声〉をきくことは受動的な行為ではなく、その場に参加して、その語りが生み出す変化を感じ取ることである。ここでは、わたし自身が女性史叙述の方法をみつけていった過程と、研究のなかで出会った無数の〈声〉が、どのようにして小説という新たな表現にむすびついたのかということについてはじめて書いた。
いつのまにか女性史研究者や小説家と名乗るようになっていたわたしが、歴史や物語を書くことにどうして関心を持ったのかあまりはっきりとは思いだせない。バージニア・リー・バートンの『生命のれきし』を繰り返し読んでいた幼少期かもしれないし、あるいはアーシュラ・K・ル=グウィンの『ゲド戦記』に描かれた多島海(アーキペラゴ)をめぐる壮大なクロニクルにひかれた一〇代のはじめかもしれない。
ただ、ひとつはっきりといえるのは、大学でジュディス・バトラーの『ジェンダー・トラブル――フェミニズムとアイデンティティの攪乱』(竹村和子訳、青土社、一九九八年)と出会ったことが、その後の女性史研究とも、ジェンダーやセクシュアリティをテーマにした小説の執筆ともつながっているということである。同書は歴史をめぐる本ではないが、そこで提示された、二元論的な身体という概念自体が文化装置としてのジェンダーによって作り上げられたものであり、つねに変容の可能性のなかにあるという視点は、自分自身の生活も含めて現在という時間を批判的にとらえかえしていく大きなきっかけになった。
繰り返しページをめくるなかですっかりぼろぼろになってしまった『ジェンダー・トラブル』をいま開きながら、この本を世のなかに送りだしてくれた出版社から、自分の本が出版されるということに静かな喜びを感じている。
この本に響く多様な〈声〉が、生活のなかの小さな疑問をときほぐしたり、いま困難のなかで表現の言葉を探しているひとにしっかりと届くことを心から祈っている。
註
*1 ロクサーヌ・ゲイ『飢える私―ままならない心と体』野中モモ訳、亜紀書房、二〇一九年、六頁。
*2 パオロ・ジョルダーノ『コロナの時代の僕ら』飯田亮介訳、早川書房、二〇二〇年、一〇八頁。
〔書き手〕山家悠平(やんべ・ゆうへい)
女性史がひらくフェミニズムのかたち
ひとりひとりの体にそれぞれの物語と歴史がある。――ロクサーヌ・ゲイ(*1)亜熱帯の焼けつくような日差しの下、車は軽快に厦門(アモイ)の東海岸を走り抜ける。真っ青な海のむこうに緑の木々におおわれた島影が見えた。金門島ですよ、と運転している友人がいう。大陸にもっとも近い台湾領の島だ。中国と台湾の緊張が高まった時期には、お互いに巨大なスピーカーで、プロパガンダ放送から歌謡曲まで流していたとも教えてくれた。
車は更に海岸線を北上し、広大な工事現場のような一帯を走り抜ける。大きなマンションを建てているのか何台もクレーンが見えた。友人は、またていねいに事情を説明してくれる。戦争の危機が近かったころ、この海岸には建物が建てられなかったらしい。それから、クレーンを横目で見て言葉を続ける。――日本軍がきたときに、住民がたくさん殺されたので、厦門のひとは心情的にこっちを避けるんですよ。泉州出身のその友人が「厦門のひと」と少し距離をおいて語るのが印象に残った。主語を明確にしない語り口は、かつての侵略者の国からやってきたわたしへの気遣いなのかもしれない。その言葉をきいたときに、たくさんのひとが殺されるというリアリティをうまくイメージできたとはいえない。死者たちは、はるかに彼方にあって、わたしは亜熱帯のむせかえるような熱気と、豊かな自然にすっかり目を奪われていた。海岸沿いのブーゲンビリアは美しい薄紫の花を咲かせ、大学の教員宿舎の窓からは背の高い木綿花の木に咲き乱れる真っ赤な花が見えた。風が吹くたびに、潮のにおいとどこか果実のくさったような甘い香りが漂う都市。それでも、榕樹の地上根が風に揺れる細い街路を歩き抜けて、ひとたび街にでるとコロニアル様式の建物群や鐘楼が、この街がたどってきた歴史を物語っているようにも感じた。生活するなかで、意識は自然と過去にむいていった。
占領下の厦門で発行された『全閩新日報』を見ると、八〇年前の街やひとが目に飛び込んでくる。一九四〇年九月七日の紙面は、「あたしたちも新体制」という見出しで、厦門の繁華街で働く女給たちによる厦門神社の雑草抜きを報じている。
当時、日本人むけのカフェーや食堂が建ち並んでいたという大中路の「カフェー喜楽」で働く女給たちは、白や花柄の旗袍(チーパオ)という、およそ草むしりには適さない格好をしている。まだあどけない顔立ちをした女性たちは二〇代前半くらいだろうか。その記事は、総力戦体制のために近衛内閣が掲げた新体制運動に、中国に飛び地のように広がる占領地で働く女給たちもまた組み入れられていたことを示している。わたしは、観光客で賑わう大中路を歩きながら、その女性たちのことを想像する。戦災にあわなかった厦門の中心部には当時の建物がほぼそのまま残っていて、おそらく「カフェー喜楽」も大中路に立ち並ぶ、強い日差しに退色したビルディングのどこかに入っていたのだろう。女性たちが写っている厦門神社の跡地には、いまは一対の狛犬と石段だけが残っていた。帝国の「辺境」の占領地で日本人相手に働く女給たちという、二重にも三重にも周縁化された、記事では名前も書かれていない女性たちは、日本の敗戦後、どこにいったのだろう。
(中略)
厦門という、いまや遠くなってしまった土地の話から書きはじめたのは、そこでの生活がわたしにとって、女性史を研究するということと、自分自身が生きるということがはじめてしっかりと交差する経験としてあったからである。「生き延びるための女性史―遊廓に響く〈声〉をたどって」と名付けられたこの本には、ひとことでいうとわたしが肌感覚とでもいうべきものをとおしてききとった無数の〈声〉が文章という形になって収録されている。〈声〉はいま見たように生活の現場であった厦門できいたものもあれば、はるか昔の史料のなかに響く、比喩的な意味での〈声〉もある。
厦門を訪れる前から現在にいたるまで、わたしがかかわっている女性史とは、いわゆる歴史学が公的領域の男性についての歴史叙述になっているという批判意識から、過去の女性たちの活動や経験に焦点をあてた歴史研究のことである。そのなかでもわたしは、日本の近代公娼制度下の遊廓で生きた女性たちの研究をしている。近世をとおして形作られた遊廓は、人身売買禁止を建前とする明治政府によって近代公娼制度、いわば国家公認の管理売春制度として再編された。
「自由意志」で働きたい女性については「救貧」のために許容する、という欺瞞的な説明のもとで、遊廓は貸座敷という名称に変わったが、そこで働く女性たちのほとんどは前借金による拘束と楼主や警察による監視で自由な外出すら難しい状況に置かれていた。
従来、女性史研究では、遊廓の搾取や過酷さに光があてられ、そこに生きる女性たちは「犠牲者」として一面的に表象される傾向が強かった。しかし、わたしが遊廓のなかの女性たちを中心にして研究をすすめるなかで見えてきたのは「犠牲者」というイメージには収まらない、複数のアイデンティティを生きる女性たちの姿だった。遊廓のなかには、底辺女性労働者の仕事を転々とするなかで娼妓になった女性や、幼少期に片親を失い弟や妹を養うために芸娼妓紹介業者を訪れた女性、半ば騙されるように親元から売られた女性、植民地出身の女性、いったん廃業したものの世間の差別のために舞い戻った女性など、さまざまな女性たちがいた。それらのいくつものアイデンティティが交差する地点に女性たちの生はあり、その経験を語る〈声〉をききとるためにはインターセクショナルな視点が不可欠だった。
女性たちの多様な生に目をむけると、それまで歴史研究で描かれたことのない〈声〉が響いてくるように感じた。博士過程の日々に見たマイクロフィルムの古い新聞記事には、困難な状況にあってもストライキや新聞への告発によって状況改善を求めた遊廓のなかの女性たちの言葉が断片的であっても残っていた。それは遊廓の不条理を訴える、怒りや苦しみの声であり、生き延びるためのエネルギーに満ちた声でもあった。それと同時に、遊廓での日常を語る当事者の言葉からは、張見世で本を読んだり、朋輩とかるたをしたり、冗談をいいあったり、廃業後の仕事について考える、生活者としての女性たちの姿が浮かび上がってきた。その発見は、初の著書である『遊廓のストライキ―女性たちの二十世紀・序説』(共和国、二〇一五年)にまとめられている。
本書に収録されているのは、それ以降の二〇一五年から二〇二三年にかけて書かれた文章である。
この本は三部構成である。
第一部「生活を形作るさまざまな〈声〉」には、雑誌『現代思想』に掲載された文章が集められている。第一章の論考「たったひとりにさせない/ならないために―危機の時代の分断をこえて」は、二〇二〇年に寄稿したものである。コロナパンデミックについて、女性史や中国滞在経験なども含めて書いてほしい、という相当にアクロバティックな原稿依頼を受けたときは、どうして感染症をめぐる社会史の専門家でもないわたしなのだろう、と思ったが、書き上げてみれば自分自身の研究とも生活のリアリティとも重なるテーマであると気がついた。
この文章では、パンデミックがはじまった当初の入口の危機感が鮮明に表現されている。わたし自身が大学非正規労働者としてかかえてきた生きがたさや、女性史でふれてきた証言は、「ステイ・ホーム」という一見だれにとっても疑義を呈しにくい標語の裏側にある、無数の分断やマジョリティの傲慢さに目をむける手がかりになった。仕事を休むと生活もままならない非正規労働者や、家に居場所がなく街に逃れた子どもが、ウイルスの媒介者とみなされるような社会は絶対にまちがっている、そんな確信のなかで書いた。いまやあっというまに歴史になりつつあるパンデミックという時代の、手ざわりをまず確認しておきたくて、実際の発表順とは異なるが本書の冒頭に置くことにした。
イタリアの作家パオロ・ジョルダーノは、二〇二〇年三月にコロナの時代の入口に立って、「数々の真実が浮かび上がりつつあるが、そのいずれも流行の終焉とともに消えてなくなることだろう。もしも、僕らが今すぐそれを記憶に留めぬ限りは」(*2)と書いた。わたしもそう思う。ここに書かれているのは、わたしたちが圧倒的な分断の時代を生きているという認識である。それは危機の時代をへて改善されることもなく、より一層破滅的な様相を見せている。第一部には、わたしたちが常に立ち戻り問い続けなければいけないこの社会をめぐる問題が通奏低音のように響いている。
第二部「遊廓のなかに響く〈声〉」には、遊廓のなかで〈読む〉ということと、遊廓の生活を〈描く〉ことをめぐる論考を集めた。一般的にはほとんど知られていないことだが、内藤新宿遊廓で働く和田芳子が『遊女物語―苦海四年の実験告白』(文明堂、一九一三年)を書いて以降、遊廓のなかを生きた当事者による本が断続的に発行されている。労働運動の高揚期である一九二六(大正一五)年には遊廓のなかからの告発が相次ぎ、同年に労働運動家の支援のもとで廃業した森光子や松村喬子はのちに遊廓での体験を手記や小説という形で発表した。この本は、これまで女性史研究でも文学研究でも取り上げられてこなかった、それらの当事者の自己表現についてのはじめてのまとまった研究でもある。
第三部「響きあう〈声〉」には、女性たちの〈声〉がどのように響きあい、つながっていた(いく)のかを描きだす文章を集めた。女性史とは、史料のなかに断片的に響いている〈声〉をつないでいく実践でもある。そこでは〈声〉をきくことは受動的な行為ではなく、その場に参加して、その語りが生み出す変化を感じ取ることである。ここでは、わたし自身が女性史叙述の方法をみつけていった過程と、研究のなかで出会った無数の〈声〉が、どのようにして小説という新たな表現にむすびついたのかということについてはじめて書いた。
いつのまにか女性史研究者や小説家と名乗るようになっていたわたしが、歴史や物語を書くことにどうして関心を持ったのかあまりはっきりとは思いだせない。バージニア・リー・バートンの『生命のれきし』を繰り返し読んでいた幼少期かもしれないし、あるいはアーシュラ・K・ル=グウィンの『ゲド戦記』に描かれた多島海(アーキペラゴ)をめぐる壮大なクロニクルにひかれた一〇代のはじめかもしれない。
ただ、ひとつはっきりといえるのは、大学でジュディス・バトラーの『ジェンダー・トラブル――フェミニズムとアイデンティティの攪乱』(竹村和子訳、青土社、一九九八年)と出会ったことが、その後の女性史研究とも、ジェンダーやセクシュアリティをテーマにした小説の執筆ともつながっているということである。同書は歴史をめぐる本ではないが、そこで提示された、二元論的な身体という概念自体が文化装置としてのジェンダーによって作り上げられたものであり、つねに変容の可能性のなかにあるという視点は、自分自身の生活も含めて現在という時間を批判的にとらえかえしていく大きなきっかけになった。
繰り返しページをめくるなかですっかりぼろぼろになってしまった『ジェンダー・トラブル』をいま開きながら、この本を世のなかに送りだしてくれた出版社から、自分の本が出版されるということに静かな喜びを感じている。
この本に響く多様な〈声〉が、生活のなかの小さな疑問をときほぐしたり、いま困難のなかで表現の言葉を探しているひとにしっかりと届くことを心から祈っている。
註
*1 ロクサーヌ・ゲイ『飢える私―ままならない心と体』野中モモ訳、亜紀書房、二〇一九年、六頁。
*2 パオロ・ジョルダーノ『コロナの時代の僕ら』飯田亮介訳、早川書房、二〇二〇年、一〇八頁。
〔書き手〕山家悠平(やんべ・ゆうへい)
ALL REVIEWSをフォローする