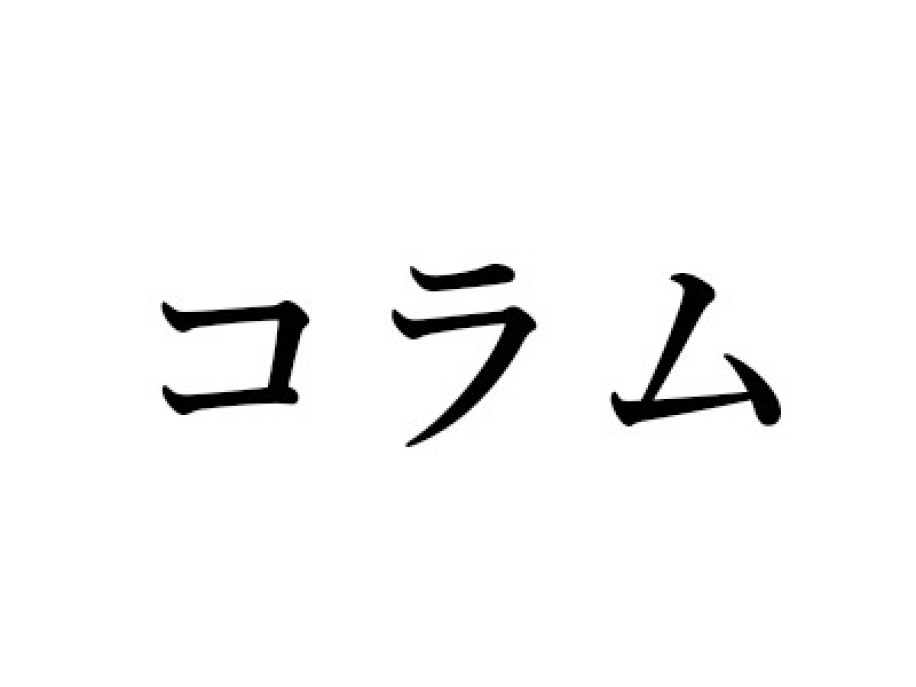解説
『修理する権利: 使いつづける自由へ』(青土社)
いま、欧米を中心に「修理する権利」を求める立法や運動がひろがっています。「壊れたら買い替え」へ消費者を促す資本主義社会に一石を投じるこの概念/運動は、日本においても重要な契機となるでしょう。このたび刊行された『修理する権利——使いつづける自由へ』は、「修理する権利」をめぐる議論の最前線である米国から届いた、本邦初の決定的入門書です。
そもそも、なぜ修理を「権利」として求める必要があるのか、修理を阻んでいるものはなにか——。当たり前なようでいて、しかし気づけば遠ざかってしまった「修理」という営みを問い直すために、本書に寄せられた吉田健彦氏による解題「修理する権利、あるいは私たちの生を取り戻すための抵抗運動」の一部を限定公開いたします。
それは少しばかりトラブルの多い、けれどありきたりの日常の光景のように思えるかもしれない。だが本当にそうだろうか? 私たちは私たちが持っている物が壊れたとき、修理できるのであれば修理しようとする。私たちの腕前がどれだけあるかどうかはさておき、少なくとも修理しようと試みたり検討したりすること自体に疑問を抱くことはない。ほつれてしまったTシャツを繕ったり、木製のテーブルについた傷をパテで埋めたりする。そういったささやかな修理の経験は誰にでもあるだろうし、それを殊更に「権利」として考えることもない。きみがフライパンの持ち手を締めなおそうとした途端、フライパンの製造業者がどこからか走りよってきてそれを妨害してくることなどあり得ない。
だけれども、いま、私たちは現実としてそれに近い状況を生きている。私がある物を所有しているとはどういうことか、そしてそれが壊れたときにどのような選択肢があるのかについて私たちが漠然と抱いているイメージは、既におとぎ話のようなものになってしまっている。私たちは私たち自身の生に──生活だけではなく生命にまで──大きな影響を与えている様ざまな製品に対して、それを購入したにもかかわらず、壊れても修理できる可能性は極めて低い。このような時代状況に対して、それ故カウンターとしての「修理する権利」が重要になってくる。
本書は現代社会において極めて重要な概念/運動である修理する権利についての優れた概説書であり、初の包括的な邦訳書となる。著者のアーロン・パーザナウスキーはミシガン大学ロー・スクールで教鞭をとる法学の研究者で、特にデジタル社会における所有権や知的財産権などを専門にしている。そのため本書においても修理する権利を分析する上で知的財産法、反トラスト法、消費者法などの枠組みが重要な位置を占めているが、パーザナウスキーの丁寧で軽快な筆致は法学の知識がなくとも十分理解できる。
同時に、パーザナウスキーが本書で生き生きと描写しているように、修理は私たちの生に直結する根源的で不可欠の要素でもある。彼がいうように「人類は誕生以来、ずっと修理をしてきた」(本書七五頁)のだ。だから修理する権利は法的枠組の問題にのみ収まるようなものではなく、後に見るように環境破壊や奴隷労働への抵抗であり、健全なコミュニティ再生のための運動であり、何より、私が私として生きるために必須の営為でもある。
人類の歴史とともにあったはずの修理に大きな転換点をもたらしたのが工業化であることは確かだろう。大量生産された製品が市場に飽和するまでは、当初フォードがそうしていたようにより長く使える製品を生産することが消費者に対する効果的なアピールとなり得る(本書八二頁)。しかし一たび飽和してしまえば定期的に新製品を購入するよう消費者を誘導するほうが利益を上げやすい。
よく知られている経済学的/工学的手法として「計画的陳腐化」があるが、この用語が初めて明確に登場するのはバーナード・ロンドンによる一九三二年の小論文「計画的陳腐化による不況の終焉」に遡る。ここでロンドンは、国がすべての製品に使用期限を割り当て、それを超えて使用する人びとには「課税して、その行為を思いとどまらせる」(本書八五頁)ことを提案した。
あるいは設計上の単純な方法でも修理を妨害することができる。例えば製造時にネジではなく接着剤を使用すれば分解はより困難になるし、ネジ止めであってもペンタローブなど特殊な形状であれば専用ドライバが必要になる。安全性やセキュリティを確保するために仕方がない場合もあるが、修理は困難になるだろう。あるいはAppleがかつてしたように、自己修理によってサードパーティ製の部品を用いたり独立系の修理業者が修理したことを検知すると動作を制限するようなソフトウェア上のロックをかけることもできる(本書一二五頁)。
表面的に修理の選択肢が与えられているように見えても、現実的には選択しようがない場合もある。パーザナウスキーはAirPodsのバッテリー交換サービスを例に挙げている。AirPodsはデザインからも明らかなように、寿命に達したバッテリーの交換は実質的に不可能であり、結局このサービスは新品と取り換えるだけのものでしかない。当然それには新品購入とほぼ同じ費用がかかる。そうであるのなら私たちは多少の差額は受け入れて、より新型のAirPodsを購入するのではないだろうか。
また、世界規模の農業機器メーカーであるディア社のトラクターは新製品で八〇万ドルと高価であり、その修理にはソフトウェアロックの解除が必須となる。そのため正規の修理業者でなければ修理はできないが、それにもまた途轍もないコストがかかる。このような修理の独占の根拠はソフトウェアに対する著作権にあるというディア社の戦略は、長い法的闘争を経た後に棚上げされたが、修理はあいかわらず困難なままになっている。
パーザナウスキーが挙げる豊富な事例から見えてくるのは、要するに企業はこれまでずっと「修理市場を妨害するか獲得するために、製品設計、経済学、法律を活用した戦略を考え出してきた」(本書二三頁)ということだ。
[書き手]吉田健彦
そもそも、なぜ修理を「権利」として求める必要があるのか、修理を阻んでいるものはなにか——。当たり前なようでいて、しかし気づけば遠ざかってしまった「修理」という営みを問い直すために、本書に寄せられた吉田健彦氏による解題「修理する権利、あるいは私たちの生を取り戻すための抵抗運動」の一部を限定公開いたします。
修理するということ
朝食を作っているとき、きみはフライパンの持ち手が緩んでいることに気づく。もうだいぶ長く使っているフライパンで、持ち手を止めているねじのひとつが錆びて外れかけている。朝食後、きみは近くのホームセンターでねじを買おうと思い、自転車を出す。けれども後輪がパンクしており、ため息をつきながらバケツに水を張り、穴を見つけて修理キットで塞ぐ。ホームセンターでは必要のないものまでつい眺めてしまう。きみはふと、鉢植を置いている木製の棚が壊れていたことを思い出し、適当な木材も買うことにする。やることは増えたが、修理が好きなきみにとってそれは少しも苦ではない……。それは少しばかりトラブルの多い、けれどありきたりの日常の光景のように思えるかもしれない。だが本当にそうだろうか? 私たちは私たちが持っている物が壊れたとき、修理できるのであれば修理しようとする。私たちの腕前がどれだけあるかどうかはさておき、少なくとも修理しようと試みたり検討したりすること自体に疑問を抱くことはない。ほつれてしまったTシャツを繕ったり、木製のテーブルについた傷をパテで埋めたりする。そういったささやかな修理の経験は誰にでもあるだろうし、それを殊更に「権利」として考えることもない。きみがフライパンの持ち手を締めなおそうとした途端、フライパンの製造業者がどこからか走りよってきてそれを妨害してくることなどあり得ない。
だけれども、いま、私たちは現実としてそれに近い状況を生きている。私がある物を所有しているとはどういうことか、そしてそれが壊れたときにどのような選択肢があるのかについて私たちが漠然と抱いているイメージは、既におとぎ話のようなものになってしまっている。私たちは私たち自身の生に──生活だけではなく生命にまで──大きな影響を与えている様ざまな製品に対して、それを購入したにもかかわらず、壊れても修理できる可能性は極めて低い。このような時代状況に対して、それ故カウンターとしての「修理する権利」が重要になってくる。
本書は現代社会において極めて重要な概念/運動である修理する権利についての優れた概説書であり、初の包括的な邦訳書となる。著者のアーロン・パーザナウスキーはミシガン大学ロー・スクールで教鞭をとる法学の研究者で、特にデジタル社会における所有権や知的財産権などを専門にしている。そのため本書においても修理する権利を分析する上で知的財産法、反トラスト法、消費者法などの枠組みが重要な位置を占めているが、パーザナウスキーの丁寧で軽快な筆致は法学の知識がなくとも十分理解できる。
同時に、パーザナウスキーが本書で生き生きと描写しているように、修理は私たちの生に直結する根源的で不可欠の要素でもある。彼がいうように「人類は誕生以来、ずっと修理をしてきた」(本書七五頁)のだ。だから修理する権利は法的枠組の問題にのみ収まるようなものではなく、後に見るように環境破壊や奴隷労働への抵抗であり、健全なコミュニティ再生のための運動であり、何より、私が私として生きるために必須の営為でもある。
修理の妨害
けれども、まずは私たちの生活からいかに修理が奪われているかを確認しよう。人類の歴史とともにあったはずの修理に大きな転換点をもたらしたのが工業化であることは確かだろう。大量生産された製品が市場に飽和するまでは、当初フォードがそうしていたようにより長く使える製品を生産することが消費者に対する効果的なアピールとなり得る(本書八二頁)。しかし一たび飽和してしまえば定期的に新製品を購入するよう消費者を誘導するほうが利益を上げやすい。
よく知られている経済学的/工学的手法として「計画的陳腐化」があるが、この用語が初めて明確に登場するのはバーナード・ロンドンによる一九三二年の小論文「計画的陳腐化による不況の終焉」に遡る。ここでロンドンは、国がすべての製品に使用期限を割り当て、それを超えて使用する人びとには「課税して、その行為を思いとどまらせる」(本書八五頁)ことを提案した。
あるいは設計上の単純な方法でも修理を妨害することができる。例えば製造時にネジではなく接着剤を使用すれば分解はより困難になるし、ネジ止めであってもペンタローブなど特殊な形状であれば専用ドライバが必要になる。安全性やセキュリティを確保するために仕方がない場合もあるが、修理は困難になるだろう。あるいはAppleがかつてしたように、自己修理によってサードパーティ製の部品を用いたり独立系の修理業者が修理したことを検知すると動作を制限するようなソフトウェア上のロックをかけることもできる(本書一二五頁)。
表面的に修理の選択肢が与えられているように見えても、現実的には選択しようがない場合もある。パーザナウスキーはAirPodsのバッテリー交換サービスを例に挙げている。AirPodsはデザインからも明らかなように、寿命に達したバッテリーの交換は実質的に不可能であり、結局このサービスは新品と取り換えるだけのものでしかない。当然それには新品購入とほぼ同じ費用がかかる。そうであるのなら私たちは多少の差額は受け入れて、より新型のAirPodsを購入するのではないだろうか。
また、世界規模の農業機器メーカーであるディア社のトラクターは新製品で八〇万ドルと高価であり、その修理にはソフトウェアロックの解除が必須となる。そのため正規の修理業者でなければ修理はできないが、それにもまた途轍もないコストがかかる。このような修理の独占の根拠はソフトウェアに対する著作権にあるというディア社の戦略は、長い法的闘争を経た後に棚上げされたが、修理はあいかわらず困難なままになっている。
パーザナウスキーが挙げる豊富な事例から見えてくるのは、要するに企業はこれまでずっと「修理市場を妨害するか獲得するために、製品設計、経済学、法律を活用した戦略を考え出してきた」(本書二三頁)ということだ。
[書き手]吉田健彦
ALL REVIEWSをフォローする