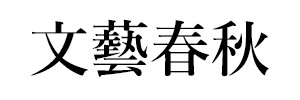対談・鼎談
『ルーツ』アレックス・ヘイリー|丸谷才一+木村尚三郎+山崎正和の読書鼎談
丸谷 十年くらい前になるかな、オーストラリアに旅行したことがあるんですが、オーストラリア側でつくった予定表の中に、刑務所の見学というのがあるんですよ。ぼくはくたびれているから、刑務所なんか見たくないのに、ぜひ見てくれ、何しろ古い建物だから、というんですね。「十九世紀の半ばにできた」っていうわけです(笑)。それで、われわれにとっては、十九世紀のものなんかは、まったく新しいものなんであって、およそ意味がないんだ、といって断わった。
そのとき思ったんですけれども、ああいう歴史の新しい国は、むやみに歴史に憧れるものなんですね。
山崎 そうですね。
丸谷 アメリカ人はまずアメリカ史自体に憧れた。エドマンド・ウィルソンの『愛国の血』という南北戦争の話とかその他いろいろ、とにかくずうっとこの数十年やってみた。そしてこの本では、それのもっと徹底したものとして黒人の歴史をさかのぼることをやった。そうすると、白人の歴史をさかのぼるのよりも、自然と密着しているために、人類の歴史のもっと古い要素にさかのぼることができるわけですね。わずか二百年前ではあるけれども、その二百年前のアフリカの黒人の住み方というものは、じつは数千年前の人間の生き方と同じだという感じがあって、人類史の根源にさかのぼるという感じになる。そこのところが第一のポイントだと思うんです。
もう一つは、これは文学的小説ではないと思いますけど、しかし、まあ小説ですよね。
山崎 歴史ではなくてね。歴史ならぬ歴史を書いたという意味において小説ですね(笑)。
丸谷 その小説論を少し強引に当てはめてみましょうよ。
そうすると、二十世紀の小説のいちばん大きな発見というものは、どんな身分の低い、どんなに職業的に賤しい、社会的にいって無に等しい人間の内部にすらもたいへんな宇宙がある、ということですね。それをいちばん極端にやったのがジェイムス・ジョイスという男で、その方法が、二十世紀の小説全体をものすごく席捲したんですね。フォークナーの小説もそうだし、サルトルの小説もそうだし、みんなその手でやった。それを第二次大戦後は、アメリカの黒人作家たちが大々的にやってみたわけですね。その典型がボールドウィンの小説で、その結果わかったことは、ジョイスやフォークナーがやったほどすごい世界は出てこなかった。
すると、いまの黒人の内部を探ってうまくゆかないとすれば、現在でなく、もっと過去まで行ったら別のものが出てきやしないか、という考え方を、小説家だったらすると思うんです。アレックス・ヘイリーの手は、意識的であったか無意識であったかはともかくとして、ボールドウィンをひとひねりした手だといえるんじゃなかろうか。
山崎 わたくしは、ちょっとそれ、賞めすぎのような気がするんですがね(笑)。
丸谷 もちろん、純粋に方法論的に小説の問題を考えるから、非常に甘い評価が出てるわけです。
山崎 わたくしがこれを読んで真先に連想したのはパール・バックの『大地』です。ジャーナリズムのレポートと紙ひと重のところで、人物の内面とか細かい心理とかにこだわらずに、異質の風俗、その運命を描いてみようという姿勢が、アメリカ文学の一つの伝統としてあるような気がするんです。
丸谷 そうですね。アメリカ人がテレビを発明したというのは非常にうなずけますね。
山崎 大賛成。この作品は、もともと非常にテレビになり易いお話なんですね。
木村 そうですね。でも、テレビにならないところもあるんですよ。普通、白人が黒人のことを臭い臭いというでしょう。ところが、この本では逆に、黒人が白人の体臭を臭い、息が詰まりそうになると書いているんですよ。何度も出てきます。濡れた鶏の匂いがする、というんですね。
これはテレビでは出ないわけです。われわれも白人を獣臭いと思いますが、こういった非常に感覚的なところがたいへんおもしろかったですね。
丸谷 あれはよかったね。とっても感心した。
木村 このクンタという人は、つねに自由を求めて何べんも何べんもトライするわけですね。同時に、自分の民族的な意識をいつも失わない。自分の民族に対する誇りをもっていますね。しかし、ああいった意識は、本当のアフリカ人のものだろうか、むしろアメリカ人の精神ではないかという疑問があります。
山崎 アフリカ人という概念は、彼らがアメリカにくるまでなかった概念なんですからね。
丸谷 ジョン・ハーシーの『ヒロシマ』という小説を読んでみると、広島という街が、ものすごく立体的に社会学的に捉えられている。それは非常に立派なことなんだけれども、われわれ日本人があれを読むと、まるでアメリカの街みたいに見えるんですね。
それとまったく同じことが、このクンタ・キンテが住んでいる部落を描写するときのアレックス・ヘイリーの筆致にあると思う。
木村 まったく同感です。奴隷船の場面に「われわれは部族は違うけれども、一つの村をここに作ろう、コミュニティーを作ろう」という主張が二度ばかり出てくるんですよ。それは、いまのアメリカにいる黒人の意識なんですね。アレックス・ヘイリーが『ルーツ』を書き、それがたいへん評判になったということにおいて、黒人は、いままさに本格的にアメリカ人になったという意味でもあると思うんです。
丸谷 こういう笑い話があるんです。あるイギリス人がニューヨークへ行った。どこのパーティに出ても、トルーマン・カポーティの『冷血』の噂でもちきりである。みんながあまりすごいすごいというので、どこに行けば売っているかと訊いたら、まだ出ていないという。書いてる最中なんですね。「どうしてあなたは出ていない本を賞めるのか」と、あるパーティで『冷血』の話をしている女の子にいったら、「あなたはどうして読んでもいない小説の悪口をいうのか」といわれた(笑)。
つまり、そういう種類の、出版以前に噂を流して盛り立ててベストセラーを作るには、この小説はもってこいの小説だという気がしました。
【この対談・鼎談が収録されている書籍】
そのとき思ったんですけれども、ああいう歴史の新しい国は、むやみに歴史に憧れるものなんですね。
山崎 そうですね。
丸谷 アメリカ人はまずアメリカ史自体に憧れた。エドマンド・ウィルソンの『愛国の血』という南北戦争の話とかその他いろいろ、とにかくずうっとこの数十年やってみた。そしてこの本では、それのもっと徹底したものとして黒人の歴史をさかのぼることをやった。そうすると、白人の歴史をさかのぼるのよりも、自然と密着しているために、人類の歴史のもっと古い要素にさかのぼることができるわけですね。わずか二百年前ではあるけれども、その二百年前のアフリカの黒人の住み方というものは、じつは数千年前の人間の生き方と同じだという感じがあって、人類史の根源にさかのぼるという感じになる。そこのところが第一のポイントだと思うんです。
もう一つは、これは文学的小説ではないと思いますけど、しかし、まあ小説ですよね。
山崎 歴史ではなくてね。歴史ならぬ歴史を書いたという意味において小説ですね(笑)。
丸谷 その小説論を少し強引に当てはめてみましょうよ。
そうすると、二十世紀の小説のいちばん大きな発見というものは、どんな身分の低い、どんなに職業的に賤しい、社会的にいって無に等しい人間の内部にすらもたいへんな宇宙がある、ということですね。それをいちばん極端にやったのがジェイムス・ジョイスという男で、その方法が、二十世紀の小説全体をものすごく席捲したんですね。フォークナーの小説もそうだし、サルトルの小説もそうだし、みんなその手でやった。それを第二次大戦後は、アメリカの黒人作家たちが大々的にやってみたわけですね。その典型がボールドウィンの小説で、その結果わかったことは、ジョイスやフォークナーがやったほどすごい世界は出てこなかった。
すると、いまの黒人の内部を探ってうまくゆかないとすれば、現在でなく、もっと過去まで行ったら別のものが出てきやしないか、という考え方を、小説家だったらすると思うんです。アレックス・ヘイリーの手は、意識的であったか無意識であったかはともかくとして、ボールドウィンをひとひねりした手だといえるんじゃなかろうか。
山崎 わたくしは、ちょっとそれ、賞めすぎのような気がするんですがね(笑)。
丸谷 もちろん、純粋に方法論的に小説の問題を考えるから、非常に甘い評価が出てるわけです。
山崎 わたくしがこれを読んで真先に連想したのはパール・バックの『大地』です。ジャーナリズムのレポートと紙ひと重のところで、人物の内面とか細かい心理とかにこだわらずに、異質の風俗、その運命を描いてみようという姿勢が、アメリカ文学の一つの伝統としてあるような気がするんです。
丸谷 そうですね。アメリカ人がテレビを発明したというのは非常にうなずけますね。
山崎 大賛成。この作品は、もともと非常にテレビになり易いお話なんですね。
木村 そうですね。でも、テレビにならないところもあるんですよ。普通、白人が黒人のことを臭い臭いというでしょう。ところが、この本では逆に、黒人が白人の体臭を臭い、息が詰まりそうになると書いているんですよ。何度も出てきます。濡れた鶏の匂いがする、というんですね。
これはテレビでは出ないわけです。われわれも白人を獣臭いと思いますが、こういった非常に感覚的なところがたいへんおもしろかったですね。
丸谷 あれはよかったね。とっても感心した。
木村 このクンタという人は、つねに自由を求めて何べんも何べんもトライするわけですね。同時に、自分の民族的な意識をいつも失わない。自分の民族に対する誇りをもっていますね。しかし、ああいった意識は、本当のアフリカ人のものだろうか、むしろアメリカ人の精神ではないかという疑問があります。
山崎 アフリカ人という概念は、彼らがアメリカにくるまでなかった概念なんですからね。
丸谷 ジョン・ハーシーの『ヒロシマ』という小説を読んでみると、広島という街が、ものすごく立体的に社会学的に捉えられている。それは非常に立派なことなんだけれども、われわれ日本人があれを読むと、まるでアメリカの街みたいに見えるんですね。
それとまったく同じことが、このクンタ・キンテが住んでいる部落を描写するときのアレックス・ヘイリーの筆致にあると思う。
木村 まったく同感です。奴隷船の場面に「われわれは部族は違うけれども、一つの村をここに作ろう、コミュニティーを作ろう」という主張が二度ばかり出てくるんですよ。それは、いまのアメリカにいる黒人の意識なんですね。アレックス・ヘイリーが『ルーツ』を書き、それがたいへん評判になったということにおいて、黒人は、いままさに本格的にアメリカ人になったという意味でもあると思うんです。
丸谷 こういう笑い話があるんです。あるイギリス人がニューヨークへ行った。どこのパーティに出ても、トルーマン・カポーティの『冷血』の噂でもちきりである。みんながあまりすごいすごいというので、どこに行けば売っているかと訊いたら、まだ出ていないという。書いてる最中なんですね。「どうしてあなたは出ていない本を賞めるのか」と、あるパーティで『冷血』の話をしている女の子にいったら、「あなたはどうして読んでもいない小説の悪口をいうのか」といわれた(笑)。
つまり、そういう種類の、出版以前に噂を流して盛り立ててベストセラーを作るには、この小説はもってこいの小説だという気がしました。
【この対談・鼎談が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする