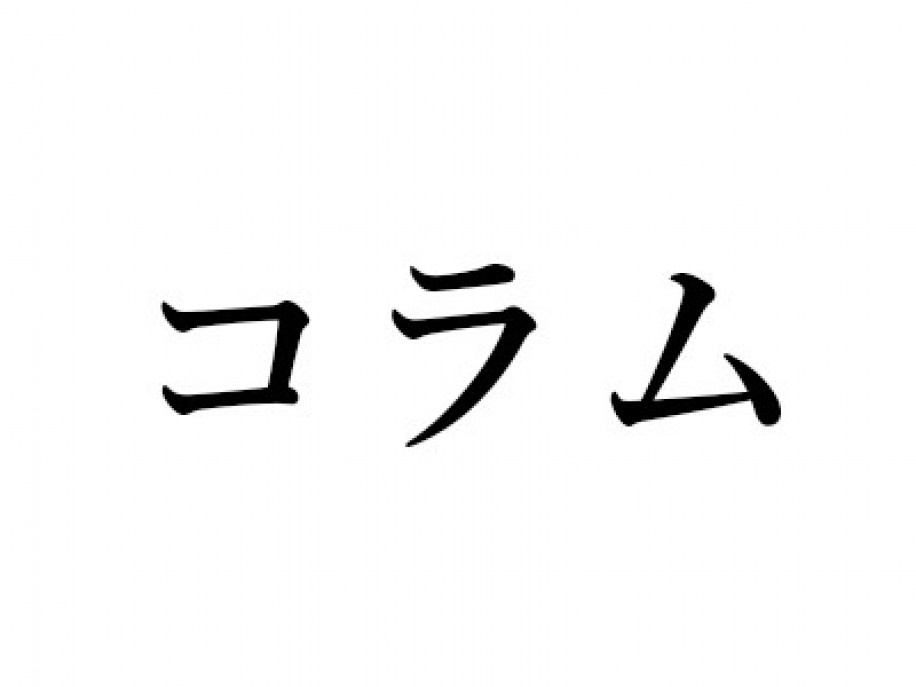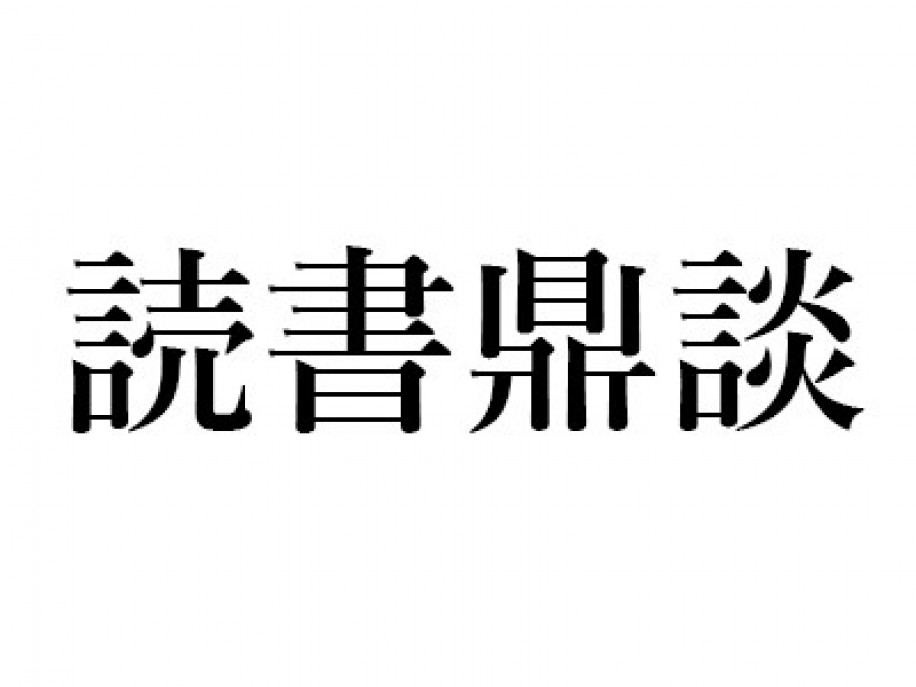書評
『ミドルセックス』(早川書房)
今からちょうど十年前だったのだ、『ヘビトンボの季節に自殺した五人姉妹』(ハヤカワepi文庫)というジェフリー・ユージェニデスのデビュー作が日本で紹介されたのは。それは、十三歳から十七歳まで年子の美人五姉妹がたて続けに自殺する出来事を綴った物語で、語り手はハイスクール時代に彼女たちに怖れと憧れを抱き、今や中年と化した〈ぼくら〉だった。
さて、しかし、一人称複数語りというテクニック自体はそれほど斬新なものではない。浅学な身でも、バルガス=リョサの中篇『子犬たち』(集英社文庫『ラテンアメリカ五人集』所収)、T・R・ピアソンの長篇『甘美なる来世へ』(みすず書房)、アンソニー・ドーアの短篇「長いあいだ、これはグリセルダの物語だった」(新潮社『シェル・コレクター』所収)なんかがパッと思い浮かぶくらいだし。共同体の無意識を露わにしたり、読者に共犯者的な目配せを示すという効果を生むこの語り口は、ギリシャ演劇におけるコロスのようなもので、だから、作品全体に神話的なムードをまとわせるという役割も果たしている。
ユージェニデスの長篇二作目にあたる『ミドルセックス』もまた、神話との親和性に秀でた物語だ。非常に人間臭いエピソードに満ちたギリシャ神話の魅力を下敷きに、あるギリシャ系一族が紡いできたドラマを、二十世紀アメリカの歩みとシンクロさせながら描いているがゆえに。語り手は、カル/カリオペ。〈わたし〉という一人称になってはいても、これは一種の複数の語り手と見なすべきだ。第五染色体に起きた劣性突然変異遺伝子の持ち主である彼/彼女は、女児(カリオペ)としてこの世に生を受けたのに、第二次性徴が現れる十四歳の時、男(カル)として生まれ直した半陰陽者なのだから。そのカル/カリオペが四十一歳になって自らのルーツを語り起こすというのが、このとても長い、そしてその長大さを支えるだけの面白さを十二分に備えた大河ファミリー・サーガなんである。
時は一九二二年。貧しい寒村に生まれ、両親とも失っているデズデモーナ・ステファニデスは養蚕で生計を立てるかたわら、可愛い弟レフティーの嫁探しに奔走している。ところが、ある日、二人は気づいてしまうのだ。自分たちが互いを深く愛していることを。やがて、ギリシャとトルコの戦争で村が壊滅。大火の中、逃げまどう姉弟は艱難辛苦の末、いとこのスーメリナ夫婦を頼りにアメリカはデトロイトへ、夫婦として渡っていく。やがて男児ミルトンが誕生。成長したミルトンはスーメリナの娘テッシーと結婚する。そして――。十八世紀半ば、〈わたし〉から九代遡ったペネロペ・エヴァンゲラトスの第五染色体に出現した突然変異遺伝子は、数々の“船”に運ばれ、一九六〇年、〈わたし〉へと伝えられる。
自動車産業が隆盛を誇る地デトロイトに渡り、レフティーが始めた食堂を息子ミルトンが繁盛させ、しかし、街の斜陽化と共に店も落ち目に。追い打ちをかけるように黒人による暴動が起こり、食堂は焼け落ちてしまう。ところが、かつてレフティーがかけていた保険のおかげで、災い転じて福となし、大金持ちとなったレフティーはホットドッグの屋台を始め、そのチェーン店化に大成功。という一家の波瀾万丈の歴史の中に、〈わたし〉の成長記が巧みに織り込まれていく。
とっても可愛い女の子として生まれたはずなのに、だんだん顔つきが男っぽくなっていき、背ばかりにょきにょき伸びていくのに胸はぺちゃんこのままで生理も来ない。女子高に通うようになった〈わたし〉は、自分と他の娘との違いに悩み、ある同級生への熱い想いに苦しむ。このあたりの思春期ならではの苦悩や歓びは、すべての読者にとって多少は覚えのあることばかりなのではないだろうか。“普通”ではないキャラクターを主人公にしながら、その感情の起伏を誰にでも共感できる普遍の域で語ることのできるユージェニデスの語り部としての巧みさには感心させられるばかりなんである。
さて、この物語の中ではすべての人物と事象がカル/カリオペ同様、二重性を帯びている。タイトルになっているミドルセックスも、男と女の中間という意味を持つと同時に、主人公一家が住む町にある通りの名を指している。一族に目を転じれば、スーメリナは〈わたし〉の祖父母のいとこというだけではなく、〈わたし〉の祖母でもある。〈わたし〉の父は自身の母(あるいは父)の甥でもある。デズデモーナとレフティーは〈わたし〉の祖父母であるのみならず、大おじ大おばでもある。〈わたし〉の父母は夫婦であると同時に、またいとこ同士でもある。そしてこの物語全体がギリシャ系移民一家のサーガであると共に、移民の国アメリカの戦後史にもなっているのだ。
巻末におかれた柴田元幸氏の素晴らしい解説でも触れられているように、カル/カリオペの一人称視点にもかかわらず全登場人物の内面が語られるとか、同一エピソードのしつこいくらいの繰り返しとか、語りにも(確信犯的な)反則ぎりぎりのテクニックが駆使されている。その饒舌さがもたらす喚起力豊かな“声”と、巧みなキャラクタライゼーション、先述した二重性の仕掛けによって、コミカルでありながら深みを伴う奥行きある物語性を獲得。すべての登場人物の心中に分け入り、共感し、その運命に寄り添う。これはそんな書き方をされた小説なのだし、そんな読み方を求められる小説なのだ。そして、わたしはそんな小説がとても好きなのだ。
【この書評が収録されている書籍】
さて、しかし、一人称複数語りというテクニック自体はそれほど斬新なものではない。浅学な身でも、バルガス=リョサの中篇『子犬たち』(集英社文庫『ラテンアメリカ五人集』所収)、T・R・ピアソンの長篇『甘美なる来世へ』(みすず書房)、アンソニー・ドーアの短篇「長いあいだ、これはグリセルダの物語だった」(新潮社『シェル・コレクター』所収)なんかがパッと思い浮かぶくらいだし。共同体の無意識を露わにしたり、読者に共犯者的な目配せを示すという効果を生むこの語り口は、ギリシャ演劇におけるコロスのようなもので、だから、作品全体に神話的なムードをまとわせるという役割も果たしている。
ユージェニデスの長篇二作目にあたる『ミドルセックス』もまた、神話との親和性に秀でた物語だ。非常に人間臭いエピソードに満ちたギリシャ神話の魅力を下敷きに、あるギリシャ系一族が紡いできたドラマを、二十世紀アメリカの歩みとシンクロさせながら描いているがゆえに。語り手は、カル/カリオペ。〈わたし〉という一人称になってはいても、これは一種の複数の語り手と見なすべきだ。第五染色体に起きた劣性突然変異遺伝子の持ち主である彼/彼女は、女児(カリオペ)としてこの世に生を受けたのに、第二次性徴が現れる十四歳の時、男(カル)として生まれ直した半陰陽者なのだから。そのカル/カリオペが四十一歳になって自らのルーツを語り起こすというのが、このとても長い、そしてその長大さを支えるだけの面白さを十二分に備えた大河ファミリー・サーガなんである。
時は一九二二年。貧しい寒村に生まれ、両親とも失っているデズデモーナ・ステファニデスは養蚕で生計を立てるかたわら、可愛い弟レフティーの嫁探しに奔走している。ところが、ある日、二人は気づいてしまうのだ。自分たちが互いを深く愛していることを。やがて、ギリシャとトルコの戦争で村が壊滅。大火の中、逃げまどう姉弟は艱難辛苦の末、いとこのスーメリナ夫婦を頼りにアメリカはデトロイトへ、夫婦として渡っていく。やがて男児ミルトンが誕生。成長したミルトンはスーメリナの娘テッシーと結婚する。そして――。十八世紀半ば、〈わたし〉から九代遡ったペネロペ・エヴァンゲラトスの第五染色体に出現した突然変異遺伝子は、数々の“船”に運ばれ、一九六〇年、〈わたし〉へと伝えられる。
自動車産業が隆盛を誇る地デトロイトに渡り、レフティーが始めた食堂を息子ミルトンが繁盛させ、しかし、街の斜陽化と共に店も落ち目に。追い打ちをかけるように黒人による暴動が起こり、食堂は焼け落ちてしまう。ところが、かつてレフティーがかけていた保険のおかげで、災い転じて福となし、大金持ちとなったレフティーはホットドッグの屋台を始め、そのチェーン店化に大成功。という一家の波瀾万丈の歴史の中に、〈わたし〉の成長記が巧みに織り込まれていく。
とっても可愛い女の子として生まれたはずなのに、だんだん顔つきが男っぽくなっていき、背ばかりにょきにょき伸びていくのに胸はぺちゃんこのままで生理も来ない。女子高に通うようになった〈わたし〉は、自分と他の娘との違いに悩み、ある同級生への熱い想いに苦しむ。このあたりの思春期ならではの苦悩や歓びは、すべての読者にとって多少は覚えのあることばかりなのではないだろうか。“普通”ではないキャラクターを主人公にしながら、その感情の起伏を誰にでも共感できる普遍の域で語ることのできるユージェニデスの語り部としての巧みさには感心させられるばかりなんである。
さて、この物語の中ではすべての人物と事象がカル/カリオペ同様、二重性を帯びている。タイトルになっているミドルセックスも、男と女の中間という意味を持つと同時に、主人公一家が住む町にある通りの名を指している。一族に目を転じれば、スーメリナは〈わたし〉の祖父母のいとこというだけではなく、〈わたし〉の祖母でもある。〈わたし〉の父は自身の母(あるいは父)の甥でもある。デズデモーナとレフティーは〈わたし〉の祖父母であるのみならず、大おじ大おばでもある。〈わたし〉の父母は夫婦であると同時に、またいとこ同士でもある。そしてこの物語全体がギリシャ系移民一家のサーガであると共に、移民の国アメリカの戦後史にもなっているのだ。
巻末におかれた柴田元幸氏の素晴らしい解説でも触れられているように、カル/カリオペの一人称視点にもかかわらず全登場人物の内面が語られるとか、同一エピソードのしつこいくらいの繰り返しとか、語りにも(確信犯的な)反則ぎりぎりのテクニックが駆使されている。その饒舌さがもたらす喚起力豊かな“声”と、巧みなキャラクタライゼーション、先述した二重性の仕掛けによって、コミカルでありながら深みを伴う奥行きある物語性を獲得。すべての登場人物の心中に分け入り、共感し、その運命に寄り添う。これはそんな書き方をされた小説なのだし、そんな読み方を求められる小説なのだ。そして、わたしはそんな小説がとても好きなのだ。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア

Invitation(終刊) 2004年6月号
ALL REVIEWSをフォローする