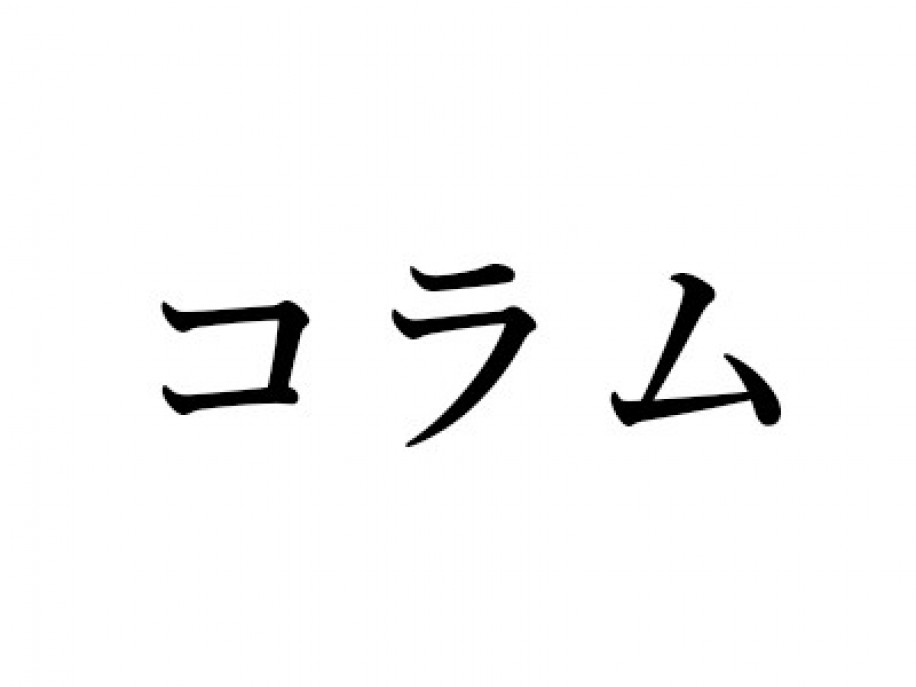コラム
スペインを読む『フラメンコ狂日記』ほか
月並みな表現になるが、まさに雨後のたけのこのような勢いで、ここ一、二年の間に数多くのスペイン本が出版された(事務局注:初出1992年5月3日)。単行本、観光案内書、ムック、さらに雑誌の特集のたぐいまで入れると、ゆうに百冊を超える。その中から、最近興味深く読んだものを選んで、何冊か紹介してみたい。
*
まずスペイン全体を取り上げた本から。
手ごろな入門書として、イベロアメリカ文化史の専門家、増田義郎が監修した『スペイン』(新潮社)と、浜田滋郎らスペイン通の複数執筆者による『現代のスペイン』(角川書店)の二冊があげられる。どちらも分担執筆のため、少々まとまりに欠けるきらいはあるが、スペイン全般にわたる情報が、まんべんなく盛り込まれている。ともに細かい索引つきなので、事典的な使い方もできる。
事典といえば、中丸明の『スペインを読む事典』(宝島社)がおもしろい。これはスペインびいき、というよりスペインぐるいの著者による、《スペインなんでも事典》である。ここには著者の、多年にわたるスペイン研究の成果がぎっしりと詰まっており、その分量と密度に圧倒される。
野々山真輝帆の『スペイン辛口案内』(晶文社)は、女性の立場から書かれたルポルタージュで、類書にないユニークな視点をもっている。ことに女性問題、高齢者問題に対する切り込みは、現代スペインを考えるうえで貴重な情報を含む。
元スペイン駐在の銀行マン、中西省三の『スペインの素顔』(山手書房新社)は、生活体験に根差したスペイン観察が興味深い。また高士宗明、ヘスス・ラカラ共著の『とっておきのスペイン』には、よほどのスペイン通でも知らないような、小さな町がたくさん出てくる。
*
つぎに、オリンピックを目前に控えた、バルセロナに関する本。
森枝雄司の『ガウディになれなかった男』(徳間書店)は、ガウディの陰に隠れたカタルーニャ・モデルニスモの建築家、リュイス・ドメネクに光を当てた、刺激的な本である。
また岡村多佳夫の『バルセロナ』(講談社現代新書)は、この町を巡る多彩な芸術、文化活動を紹介した好著で、これら二冊を読めば歴史的、政治的な特質も含めて、バルセロナという町がよく理解できる。
バルセロナをより多面的、総合的にとらえた本としては、神吉敬三の『バルセローナ』(文藝春秋)がある。著者はスペイン美術史、文化史の専門家であるが、現代史の側面もきちんとおさえており、バルセロナを紹介する本としては、もっともバランスの取れたものの一つといえよう。
最新のバルセロナ情報を知りたい向きには、伊藤千尋の『バルセロナ賛歌』(朝日新聞社)をおすすめしたい。著者は、昨年開設された朝日新聞バルセロナ支局の支局長で、本紙面にもしばしば署名原稿を寄せている。ジャーナリストの目から見たバルセロナには、一味違った新鮮な魅力があり、オリンピックを控えたこの町の鼓動が、生なましく伝わってくる。
バルセロナ在住の建築家、丹下敏明の『わが街バルセローナ』(TOTO出版)は、建築と美術を中心にした本ではあるが、グルメ情報やショッピング、ナイトライフ情報まで盛り込まれており、ガイドブックとしても役に立つ。
*
かわって内戦、現代史を扱ったものを、二冊紹介する。
バーネット・ボロテンの『スペイン革命-全歴史』(晶文社)は、スペイン内戦の研究者にとってバイブルともいうべき、古典的な名著である。翻訳が出るのが遅すぎたほどで、昨今の東欧、ソ連の激変はこの本によって予言されていた、といってもよい。ともかくこの翻訳によって、わが国におけるスペイン内戦研究が、飛躍的に進むことは間違いない。若松隆の『スペイン現代史』(岩波新書)は、内戦前後からフランコ体制下、そしてフランコ以後のスペインの状況を手際よく描いた、気鋭の学者による概説書である。岩波書店が初めて出版した、スペイン現代史の本という点にも、注目したい。
*
最後に、ユニークな随筆を一つ。マドリード在住の画家、堀越千秋の『フラメンコ狂日記』(主婦の友社)は、著者のフラメンコ生活(!)を描いた破天荒な本である。リズム感に満ちたシニカルな文章は、フラメンコを知らない人も、十分楽しめるはずだ。
ところで、このスペインブームは、セビリャ万博の終了をもって、静かに去るだろう。したがって、ここに挙げた本くらいは、絶版にならぬうちに購入しておくよう、おすすめするしだいである。
【このコラムが収録されている書籍】
*
まずスペイン全体を取り上げた本から。
手ごろな入門書として、イベロアメリカ文化史の専門家、増田義郎が監修した『スペイン』(新潮社)と、浜田滋郎らスペイン通の複数執筆者による『現代のスペイン』(角川書店)の二冊があげられる。どちらも分担執筆のため、少々まとまりに欠けるきらいはあるが、スペイン全般にわたる情報が、まんべんなく盛り込まれている。ともに細かい索引つきなので、事典的な使い方もできる。
事典といえば、中丸明の『スペインを読む事典』(宝島社)がおもしろい。これはスペインびいき、というよりスペインぐるいの著者による、《スペインなんでも事典》である。ここには著者の、多年にわたるスペイン研究の成果がぎっしりと詰まっており、その分量と密度に圧倒される。
野々山真輝帆の『スペイン辛口案内』(晶文社)は、女性の立場から書かれたルポルタージュで、類書にないユニークな視点をもっている。ことに女性問題、高齢者問題に対する切り込みは、現代スペインを考えるうえで貴重な情報を含む。
元スペイン駐在の銀行マン、中西省三の『スペインの素顔』(山手書房新社)は、生活体験に根差したスペイン観察が興味深い。また高士宗明、ヘスス・ラカラ共著の『とっておきのスペイン』には、よほどのスペイン通でも知らないような、小さな町がたくさん出てくる。
*
つぎに、オリンピックを目前に控えた、バルセロナに関する本。
森枝雄司の『ガウディになれなかった男』(徳間書店)は、ガウディの陰に隠れたカタルーニャ・モデルニスモの建築家、リュイス・ドメネクに光を当てた、刺激的な本である。
また岡村多佳夫の『バルセロナ』(講談社現代新書)は、この町を巡る多彩な芸術、文化活動を紹介した好著で、これら二冊を読めば歴史的、政治的な特質も含めて、バルセロナという町がよく理解できる。
バルセロナをより多面的、総合的にとらえた本としては、神吉敬三の『バルセローナ』(文藝春秋)がある。著者はスペイン美術史、文化史の専門家であるが、現代史の側面もきちんとおさえており、バルセロナを紹介する本としては、もっともバランスの取れたものの一つといえよう。
最新のバルセロナ情報を知りたい向きには、伊藤千尋の『バルセロナ賛歌』(朝日新聞社)をおすすめしたい。著者は、昨年開設された朝日新聞バルセロナ支局の支局長で、本紙面にもしばしば署名原稿を寄せている。ジャーナリストの目から見たバルセロナには、一味違った新鮮な魅力があり、オリンピックを控えたこの町の鼓動が、生なましく伝わってくる。
バルセロナ在住の建築家、丹下敏明の『わが街バルセローナ』(TOTO出版)は、建築と美術を中心にした本ではあるが、グルメ情報やショッピング、ナイトライフ情報まで盛り込まれており、ガイドブックとしても役に立つ。
*
かわって内戦、現代史を扱ったものを、二冊紹介する。
バーネット・ボロテンの『スペイン革命-全歴史』(晶文社)は、スペイン内戦の研究者にとってバイブルともいうべき、古典的な名著である。翻訳が出るのが遅すぎたほどで、昨今の東欧、ソ連の激変はこの本によって予言されていた、といってもよい。ともかくこの翻訳によって、わが国におけるスペイン内戦研究が、飛躍的に進むことは間違いない。若松隆の『スペイン現代史』(岩波新書)は、内戦前後からフランコ体制下、そしてフランコ以後のスペインの状況を手際よく描いた、気鋭の学者による概説書である。岩波書店が初めて出版した、スペイン現代史の本という点にも、注目したい。
*
最後に、ユニークな随筆を一つ。マドリード在住の画家、堀越千秋の『フラメンコ狂日記』(主婦の友社)は、著者のフラメンコ生活(!)を描いた破天荒な本である。リズム感に満ちたシニカルな文章は、フラメンコを知らない人も、十分楽しめるはずだ。
ところで、このスペインブームは、セビリャ万博の終了をもって、静かに去るだろう。したがって、ここに挙げた本くらいは、絶版にならぬうちに購入しておくよう、おすすめするしだいである。
【このコラムが収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする