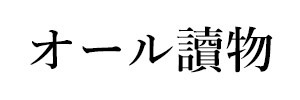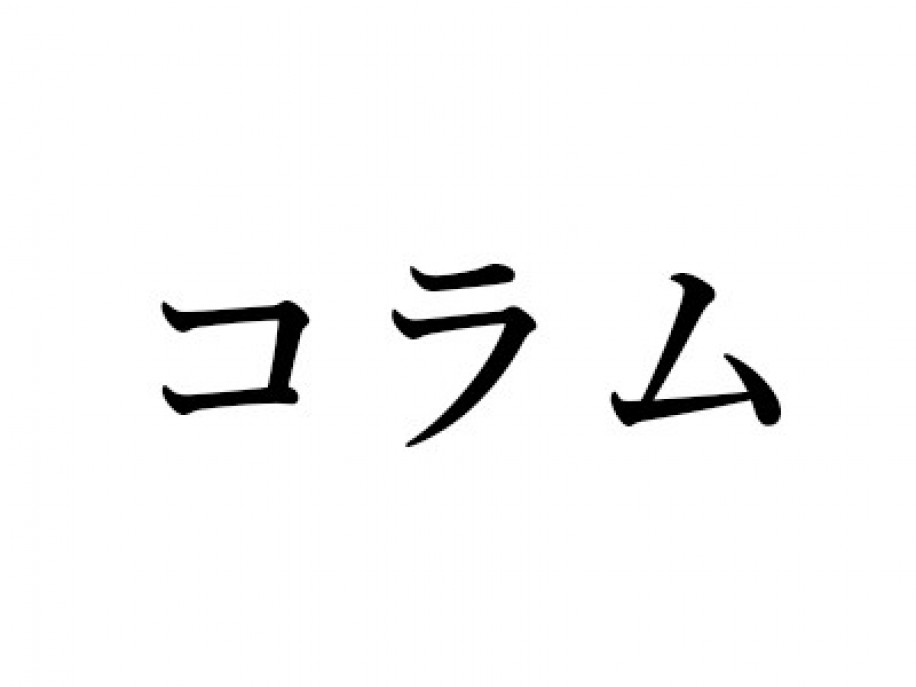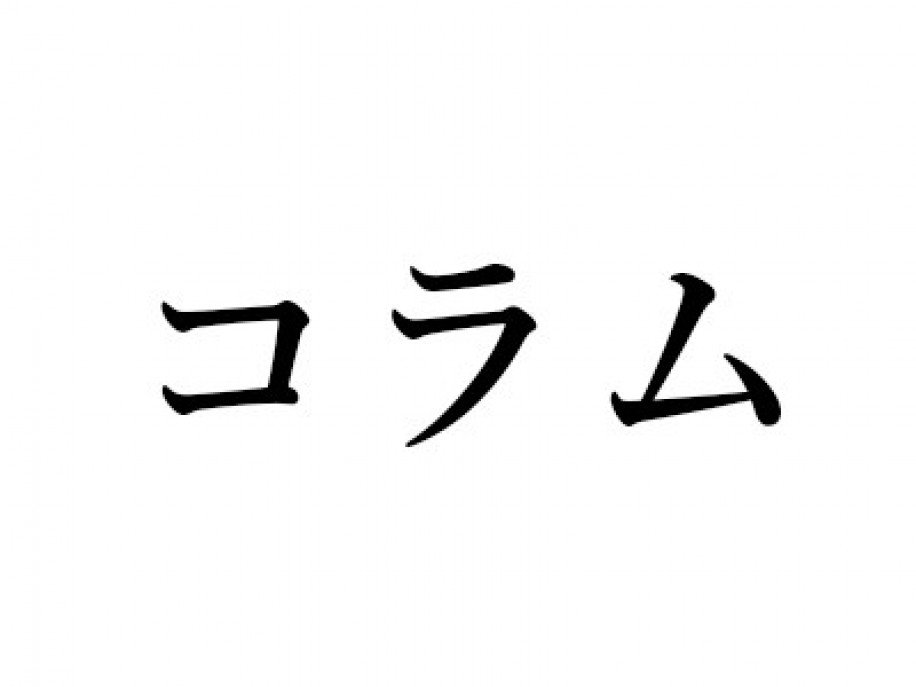選評
『鷺と雪』(文藝春秋)
直木三十五賞(第一四一回)
受賞作=北村薫「鷺と雪」/他の候補作=西川美和「きのうの神さま」、貫井徳郎「乱反射」、葉室麟「秋月記」、万城目学「プリンセス・トヨトミ」、道尾秀介「鬼の跫音」/他の選考委員=浅田次郎、阿刀田高、五木寛之、北方謙三、林真理子、平岩弓枝、宮城谷昌光、宮部みゆき、渡辺淳一/主催=日本文学振興会/発表=「オール讀物」二〇〇九年九月号一つの達成
「この国には大阪国という、豊臣家の末裔を守るための独立国が以前より、別個存在する。このことは慶応四年四月六日の、太政官政府と大阪国の間で取り交わされた十カ条の条約からも明らか……」というのが『プリンセス・トヨトミ』(万城目学)の拵(こしら)えである。独立国家の中にもう一つ小国家があるという発想は魅力的だが、しかしこの壮大なホラを成立させるためには、あらゆる細部をいちいち、もっともらしいものに作り上げなければならない。本作ではその工夫が足りなかった。たとえば、太政官政府との間で取り交わされたという十カ条の条約、作者はどんなことをしてでも、その条文のすべてを読者の前に明示しなければならなかった。それなのに、〈太政官政府は大阪国を承認する、という項目から始まる“条約”の中身をすべて確認し、〉(二六〇頁)とあるだけで、それ以上のことは書かれていない。作者と登場人物がわかっていればそれでいいのだろうか。これでは読者はこのホラとはつきあえない。くどいがもう一つ、豊臣家末裔の危機を聞きつけて〈大阪城に参集した男たちの総計は実に百二十万人を超えた。〉(四〇六頁)。それにもかかわらずこの大事件は大阪市以外に伝わらなかったという。作者は伝わらなかった理由をいろいろ並べ立てるが、みんな言い訳にすぎない。むしろ全国に伝わった方がいいのだ。いっそ、あの阪神タイガースさえもじつは大阪国の国立野球チームだったとでも大ホラを吹いて、その大ホラを無数の、まことしやかでもっともらしい細部で支えるぐらいの気組みと手練が必要だ。
語りで騙(かた)る――これが、六つの短篇を収めた『鬼の跫音』(道尾秀介)で、ほぼ一貫して採られている手法である。日記における時間の流れを逆行させたら読者を騙(だま)せるのではないか、決定的な事実を最後の最後に語るようにすれば読者を騙せるのではないかなど、才気あふれる語りが本作の魅力である。また、語りの工夫で巧みに時間を繋ぎ合わせる離れ業もみごとだが、しかし長所は短所と隣り合っていて、その語りによって明らかにされて行く物語の中身が、血糊(ちのり)一色で、いささか月並みである。語りの凄さ巧みさが中身を均一にしてしまったきらいがある。おしまいの一篇、人間を吸い取るキャンバスという奇抜なアイデアで展開する「悪意の顔」は、疑いもなく一個の佳品だが、この一篇では語りが読者を騙(かた)ろうとしていない。それで愛の哀しさがよく出たのかもしれない……とはいうものの、絢爛たる語りはこの作者の最強の武器、もっと柄(がら)の大きな物語で得意の武器を駆使していただきたいと願うばかりである。
歩道に倒れた一本の街路樹をめぐる悲喜劇の中から、普通の人々の無責任さや小狡(こずる)さをうまく抉(えぐ)り出したのが『乱反射』(貫井徳郎)である。自分勝手を押し通すが、それがひとたび波紋を引き起こすと、とたんに知らぬふりを決め込む人たち、自分さえよければと市民モラルを踏みにじっておいて、一向に責任を取ろうとしない人たちなど、普通に生活する人間の「罪と罰」を鋭く摘出する作者の力量にはたしかなものがある。けれども、作品のどの部分も均質、同じ密度で書いてあって、小説的なふくらみに欠け、通読すると少しばかり、のっぺらぼうの感があった。
事あるたびに口を出してきては支藩の秋月藩を支配しようと悪く企(たくら)む本藩の福岡藩――『秋月記』(葉室麟)は、この両藩の凄惨な軋轢(あつれき)の中で、秋月藩の命運を担って苦心する一藩士の生涯を、綿密な資料考証を経(へ)ながらくっきりと浮かび上がらせた。とりわけこの藩士の、「逃げない男になりたい」と志してから藩政改革を成し遂げるまでの前半生は、文章は清潔、展開の速度も快(こころよ)く、たいへんな名作である。しかし藩政の黒幕となってからの彼には、その黒幕度が不足、記述もいったいに早足になって失速、おもしろさにも乏しくなった。清濁併せ呑むのが行政官の定めであるとすれば、「清」だけで終わってしまった感があって、前半が傑作だっただけに、惜しいとしかいいようがない。
『きのうの神さま』(西川美和)に収められた五篇には、際立った特色が二つある。一つは、五篇とも、病気を通して人間の心の底を覗き込むことを生業(なりわい)にしている医師を登場させたこと。もう一つは、これまでの小説の約束をかすかに脱関節化していること――脱関節化が熟さない言い方とするなら、定法ずらしとでも言えばよいか。たとえば最初の短篇「1983年のほたる」の劈頭の一行、〈今、何か言った気がする。〉で、だれが何を言ったのかがはっきりするのは十五頁もあとの〈「りつ子さん」/今度ははっきりと、そう聞こえた。〉まで、待たねばならない。読者はお約束通りに情報が入ってこないのでイライラするが、その分だけなにか清新なものにふれた感じを受けるからふしぎだ。主人公に名前のないこともあれば、過去と現在とが勝手に入り交じったりもして、たしかにつんのめりながら読まねばならないが、それが魅力にもなっているところは、作者に物語を語る才能があるからだろう。その才能を十分に買った上で言えば、せっかく医師を登場させながら、人間の生命や魂の奥底に「ねじ込む力」が少し弱い。そこがやはり惜しい。すてきなスケッチやエピソードをうんと撚(よ)り上げて、芯のある物語を創ることができれば、優れた書き手になるはずだ。
局番ちがいの間違い電話――こんな安易な手はほかにないが、『鷺と雪』(北村薫)では、この手が、二度と逢うことがないはずの反乱軍の青年将校と良家令嬢の、この世で一度の魂の通い道になる。人間の日常生活に一瞬、立ちあらわれる厳しい歴史の断面を、一本の間違い電話が読者の前にありありと示すのだ。見えないものを見えるようにするのが、詩や劇や絵や小説など芸術本来の働きであるとすれば、周到に書かれたこの場面こそは、まさにその芸術の達成そのものと言ってよいだろう。
【この選評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする