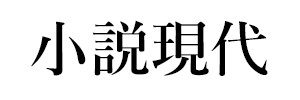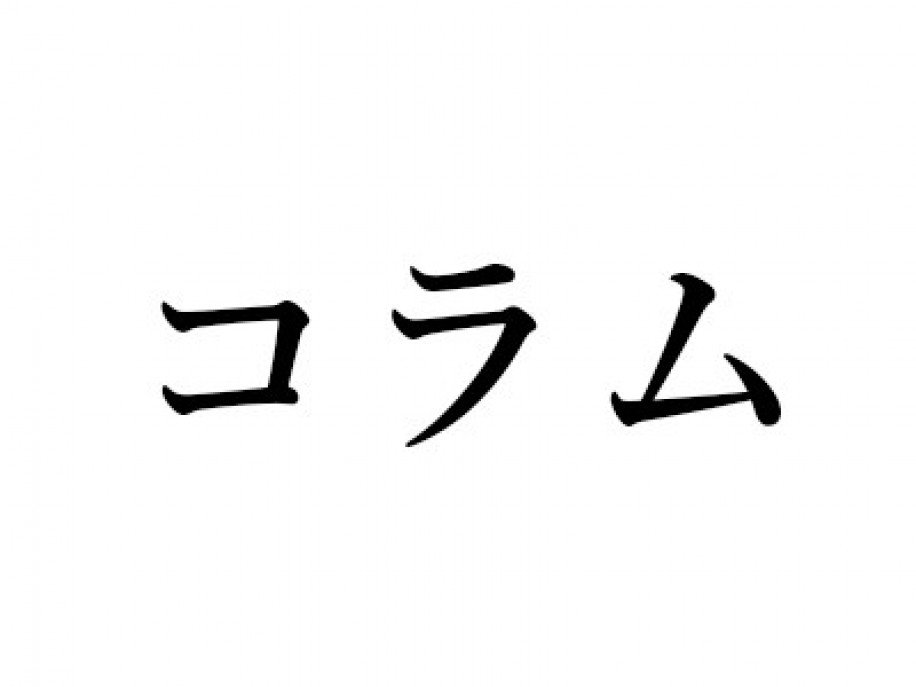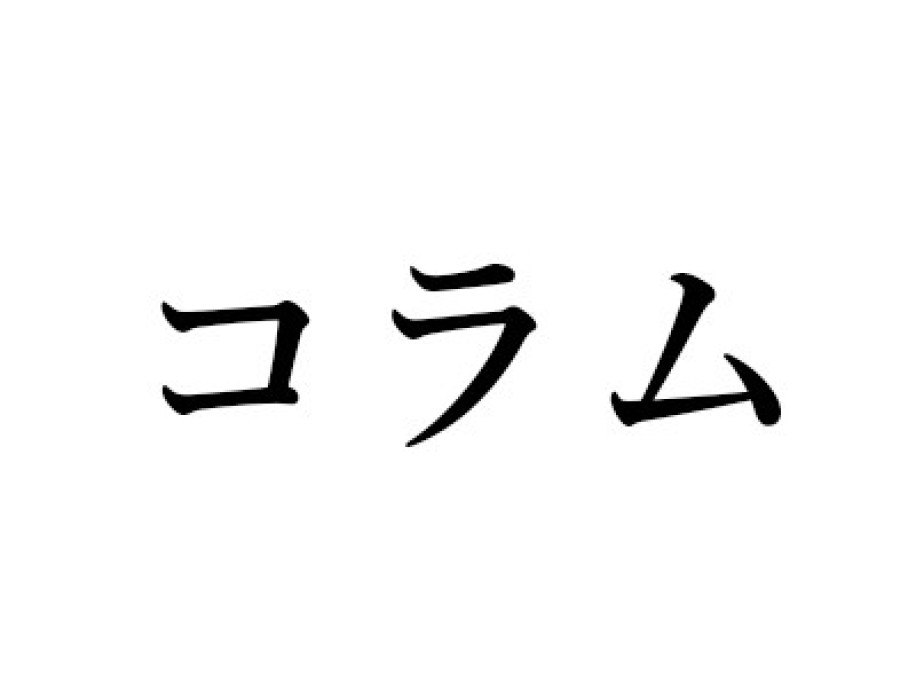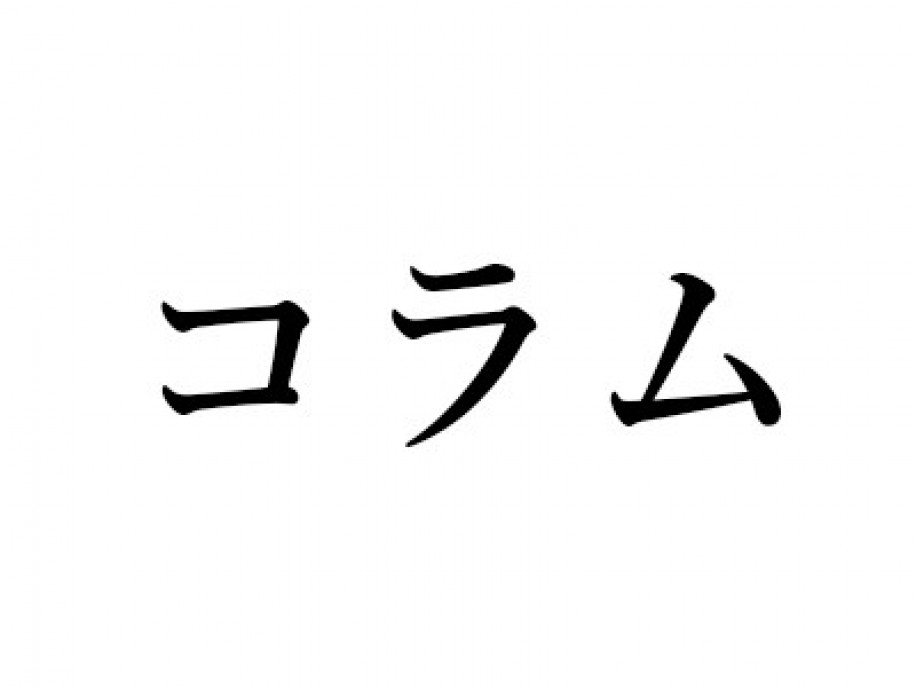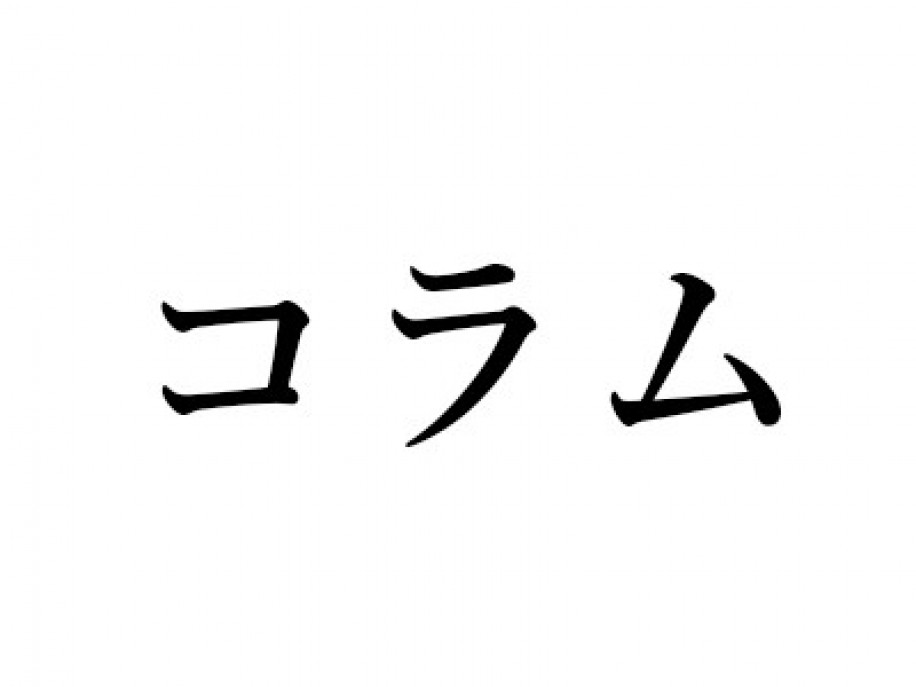コラム
恋すれば少年―ゲーテ『若きウェルテルの悩み』、木原武一『天才の勉強術』、フィッシェ兄弟「エステル」
「うちの夫はどうも恋をしているらしい」
知り合いの女性が言う。携帯電話の着信メモや、メールを見たわけではない。が、状況証拠が多過ぎる。
まず、平日の出がけの機嫌がよくなった。洗面所で、身じたくにいやに時間がかかるなと思って覗いてみると、なんと、ネクタイを締めながら鼻唄を歌っている。ついぞ聞いたことのないものだ。
鏡の前で、首を斜めに伸ばし剃りあとなんぞをチェックしたり、正面を向き、ぐっと顎を引いて「男らしい」表情を作ってみたりと、あまりにもマンガチック。「今晩は、彼女とデートです」と顔に書いてあるようなものである。
それと、行く先をやたらくだくだしく告げるようになった。
「何々君の送別会がある」
「会議の後、部長に呼ばれているから、話が長くなるかも知れない。外で飲みながらということになると思う」
帰りが遅くなることの、正当にして非の打ちどころのない理由を、聞きもしないのに述べるのだ。
「もともとうち、そんなコミュニケーションが密な夫婦じゃなかったのに、かえって疑わしいじゃないの、ねえ」
妻は私に同意を求める。
その代わり、週末は人が変わったようにうちしおれている。妻が話しかけても、反応がうつろで、心ここにあらずのようす。
そして「これが決定的」と妻は言うのだが、日曜の夜十時頃になると、決まって、
「タバコ切らした。ちょっと買ってくる」
と、しばし家をあける。おそらく、週末をともに過ごせない彼女のことを慮って、外から慰めの電話をかけているのではないか、という。みえすいた口実に、
「なんで毎週、同じ曜日の同じ時間帯に切らすんだ。学習ということをしないのか、お前は」
と突っ込みたくなるそうだ。
妻にとって憎らしいのは、他の女性に熱をあげているそのことよりも、恋に夢中になってまわりが見えなくなっている無邪気さというか、バカさかげんというか。
「十九や二十歳の坊やじゃあるまいし、もう少しでんと構えていればいいものを。男って、どうしてああわかりやすいのかね」
が、気づかぬふりして放ってある。自分ががたがた騒がなくとも、この恋は早晩終わるだろうと。妻のみたてでは、夫は年をとることに抗して、一時的に青春に戻ろうとしているだけ。そして、青春の「純愛」ほど、長続きしないものはないのだから、と。その予測は、たぶん正しい。
若者が恋に苦しむお話には、ゲーテの『若きウェルテルの悩み』(岩波文庫)がある。
この本が「自分のために書かれたと感じる時期がないなら、その人は不幸だ」とゲーテは言いきっている。婚約者のいるロッテを熱烈に愛し、彼女の結婚後、ピストル自殺を遂げるストーリーは、十八世紀後半ドイツの「シュトルム・ウント・ドラング」の代表作とされるにふさわしく、まさに疾風怒濤。ときの社会にセンセーションを巻き起こし、ウェルテルと同じ服装で自殺する者が続出したという。
しかし、あらためて読み返すと、このウェルテル、はっきり言ってすごいジコチュー(自己中心的)である。人妻となったロッテは、彼が家に訪ねてくるのを迷惑がっているのはあきらかで、旅に出てふさわしい相手をみつけてほしい、皆で友情を楽しもう、とまで言っている。女が「友情」を口に出すときは、拒絶と同義語だ。
それに対しウェルテルは、「歯ぎしりをして、ロッテをじっと陰鬱に見つめ」たりする。
これはもう、未成熟な子どもの反応と同じ。しかも、ただ自殺するならまだしも、こともあろうにロッテの夫からピストルを借り、ロッテに宛て長い長い手紙をしたためるのだから、あてつけとしか言いようがない。
「愛しているなら、なぜロッテの幸せを祝福できないのだ、これではまるで、呪いをかけるようなものではないか。それが純愛か?」
と、疑義を唱えたくなる。
でも、そんなものなのか。愛がエゴイズムの変形であるならば。
この小説は、ゲーテの実体験をもとにしているが、本人は、熱しやすい割りに立ち直りの早い性格らしく、木原武一著『天才の勉強術』(新潮選書)によれば、ロッテのモデルである女性のもとから去る帰路に、もう別の女性のとりこになっている。ゲーテに何人の恋人がいたかは、いまだ謎で、作品を通し名をあきらかにしているだけで、少なくとも十二、三人を数えるという。
が、タダでは終わらず、恋するたびに必ず何編かの詩や小説を生み出しているところが、ゲーテのゲーテたるゆえん。「天才は、普通の人びとがただ一度しか持たぬ青春を何度もくりかえし経験する」との言葉を残している。
『天才の勉強術』は、さまざまなジャンルで偉業を成し遂げた人々を、人生のどんな出来事から学んできたかという観点でとらえていて面白いのだが、ゲーテについては、創作の原動力は、ずばり女性。何たって、七十六歳で十九の娘にプロポーズしているのだ。
天才ならぬ凡人にも、「青春」が再びめぐり来ることがある。フィッシェ兄弟作「エステル」(堀口大學訳のアンソロジー『詩人のナプキン』ちくま文庫に収録)は、サブタイトルが「あるいはポオル・フェルドスパ氏の一世一代の恋物語」。
主人公フェルドスパ氏は「アブウキル街二十八番地」で卸小売商を営む小市民。「一世一代の」という形容が、それとの対比で生きてくる。
この作品が変わっているのは、地の文も台詞(せりふ)もいっさいなく、全編これ支出メモであるところ。「九月」の項では、妻、妻の母、子どもひとりという家族構成や、彼らを動物園に連れていき料理店で食事をしたりする、よき父、よき夫ぶりが、まず示される。
エステル嬢なる女子職員を、事務所に雇い入れてから、費目はにわかに変わる。理容代、香水代など、身づくろいに要するものが増え、ある晩、エテスル嬢を家まで送り、そこでわりない仲となったことが、「帰りの辻馬車代、(ただし夜半過の増料金共)」なる記述から、わかる。
お金のかけ方は急激に、エステルへと傾斜して、家族関係の記述は、冷淡になる。が、それも二か月間だけのこと。「十二月」には、妻子に服やおもちゃを買ってやる、マイホームパパに戻っている。つかの間の「青春」だったのだ。
費目と金額だけで、恋のはじまりから終わりまでを描いた、この手法、すごいアイディアだと思う。これもまた、ゲーテの詩とは別な意味で、じゅうぶんに詩的である。
【このコラムが収録されている書籍】
知り合いの女性が言う。携帯電話の着信メモや、メールを見たわけではない。が、状況証拠が多過ぎる。
まず、平日の出がけの機嫌がよくなった。洗面所で、身じたくにいやに時間がかかるなと思って覗いてみると、なんと、ネクタイを締めながら鼻唄を歌っている。ついぞ聞いたことのないものだ。
鏡の前で、首を斜めに伸ばし剃りあとなんぞをチェックしたり、正面を向き、ぐっと顎を引いて「男らしい」表情を作ってみたりと、あまりにもマンガチック。「今晩は、彼女とデートです」と顔に書いてあるようなものである。
それと、行く先をやたらくだくだしく告げるようになった。
「何々君の送別会がある」
「会議の後、部長に呼ばれているから、話が長くなるかも知れない。外で飲みながらということになると思う」
帰りが遅くなることの、正当にして非の打ちどころのない理由を、聞きもしないのに述べるのだ。
「もともとうち、そんなコミュニケーションが密な夫婦じゃなかったのに、かえって疑わしいじゃないの、ねえ」
妻は私に同意を求める。
その代わり、週末は人が変わったようにうちしおれている。妻が話しかけても、反応がうつろで、心ここにあらずのようす。
そして「これが決定的」と妻は言うのだが、日曜の夜十時頃になると、決まって、
「タバコ切らした。ちょっと買ってくる」
と、しばし家をあける。おそらく、週末をともに過ごせない彼女のことを慮って、外から慰めの電話をかけているのではないか、という。みえすいた口実に、
「なんで毎週、同じ曜日の同じ時間帯に切らすんだ。学習ということをしないのか、お前は」
と突っ込みたくなるそうだ。
妻にとって憎らしいのは、他の女性に熱をあげているそのことよりも、恋に夢中になってまわりが見えなくなっている無邪気さというか、バカさかげんというか。
「十九や二十歳の坊やじゃあるまいし、もう少しでんと構えていればいいものを。男って、どうしてああわかりやすいのかね」
が、気づかぬふりして放ってある。自分ががたがた騒がなくとも、この恋は早晩終わるだろうと。妻のみたてでは、夫は年をとることに抗して、一時的に青春に戻ろうとしているだけ。そして、青春の「純愛」ほど、長続きしないものはないのだから、と。その予測は、たぶん正しい。
若者が恋に苦しむお話には、ゲーテの『若きウェルテルの悩み』(岩波文庫)がある。
この本が「自分のために書かれたと感じる時期がないなら、その人は不幸だ」とゲーテは言いきっている。婚約者のいるロッテを熱烈に愛し、彼女の結婚後、ピストル自殺を遂げるストーリーは、十八世紀後半ドイツの「シュトルム・ウント・ドラング」の代表作とされるにふさわしく、まさに疾風怒濤。ときの社会にセンセーションを巻き起こし、ウェルテルと同じ服装で自殺する者が続出したという。
しかし、あらためて読み返すと、このウェルテル、はっきり言ってすごいジコチュー(自己中心的)である。人妻となったロッテは、彼が家に訪ねてくるのを迷惑がっているのはあきらかで、旅に出てふさわしい相手をみつけてほしい、皆で友情を楽しもう、とまで言っている。女が「友情」を口に出すときは、拒絶と同義語だ。
それに対しウェルテルは、「歯ぎしりをして、ロッテをじっと陰鬱に見つめ」たりする。
これはもう、未成熟な子どもの反応と同じ。しかも、ただ自殺するならまだしも、こともあろうにロッテの夫からピストルを借り、ロッテに宛て長い長い手紙をしたためるのだから、あてつけとしか言いようがない。
「愛しているなら、なぜロッテの幸せを祝福できないのだ、これではまるで、呪いをかけるようなものではないか。それが純愛か?」
と、疑義を唱えたくなる。
でも、そんなものなのか。愛がエゴイズムの変形であるならば。
この小説は、ゲーテの実体験をもとにしているが、本人は、熱しやすい割りに立ち直りの早い性格らしく、木原武一著『天才の勉強術』(新潮選書)によれば、ロッテのモデルである女性のもとから去る帰路に、もう別の女性のとりこになっている。ゲーテに何人の恋人がいたかは、いまだ謎で、作品を通し名をあきらかにしているだけで、少なくとも十二、三人を数えるという。
が、タダでは終わらず、恋するたびに必ず何編かの詩や小説を生み出しているところが、ゲーテのゲーテたるゆえん。「天才は、普通の人びとがただ一度しか持たぬ青春を何度もくりかえし経験する」との言葉を残している。
『天才の勉強術』は、さまざまなジャンルで偉業を成し遂げた人々を、人生のどんな出来事から学んできたかという観点でとらえていて面白いのだが、ゲーテについては、創作の原動力は、ずばり女性。何たって、七十六歳で十九の娘にプロポーズしているのだ。
天才ならぬ凡人にも、「青春」が再びめぐり来ることがある。フィッシェ兄弟作「エステル」(堀口大學訳のアンソロジー『詩人のナプキン』ちくま文庫に収録)は、サブタイトルが「あるいはポオル・フェルドスパ氏の一世一代の恋物語」。
主人公フェルドスパ氏は「アブウキル街二十八番地」で卸小売商を営む小市民。「一世一代の」という形容が、それとの対比で生きてくる。
この作品が変わっているのは、地の文も台詞(せりふ)もいっさいなく、全編これ支出メモであるところ。「九月」の項では、妻、妻の母、子どもひとりという家族構成や、彼らを動物園に連れていき料理店で食事をしたりする、よき父、よき夫ぶりが、まず示される。
エステル嬢なる女子職員を、事務所に雇い入れてから、費目はにわかに変わる。理容代、香水代など、身づくろいに要するものが増え、ある晩、エテスル嬢を家まで送り、そこでわりない仲となったことが、「帰りの辻馬車代、(ただし夜半過の増料金共)」なる記述から、わかる。
お金のかけ方は急激に、エステルへと傾斜して、家族関係の記述は、冷淡になる。が、それも二か月間だけのこと。「十二月」には、妻子に服やおもちゃを買ってやる、マイホームパパに戻っている。つかの間の「青春」だったのだ。
費目と金額だけで、恋のはじまりから終わりまでを描いた、この手法、すごいアイディアだと思う。これもまた、ゲーテの詩とは別な意味で、じゅうぶんに詩的である。
【このコラムが収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする