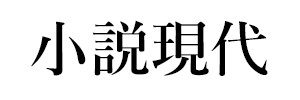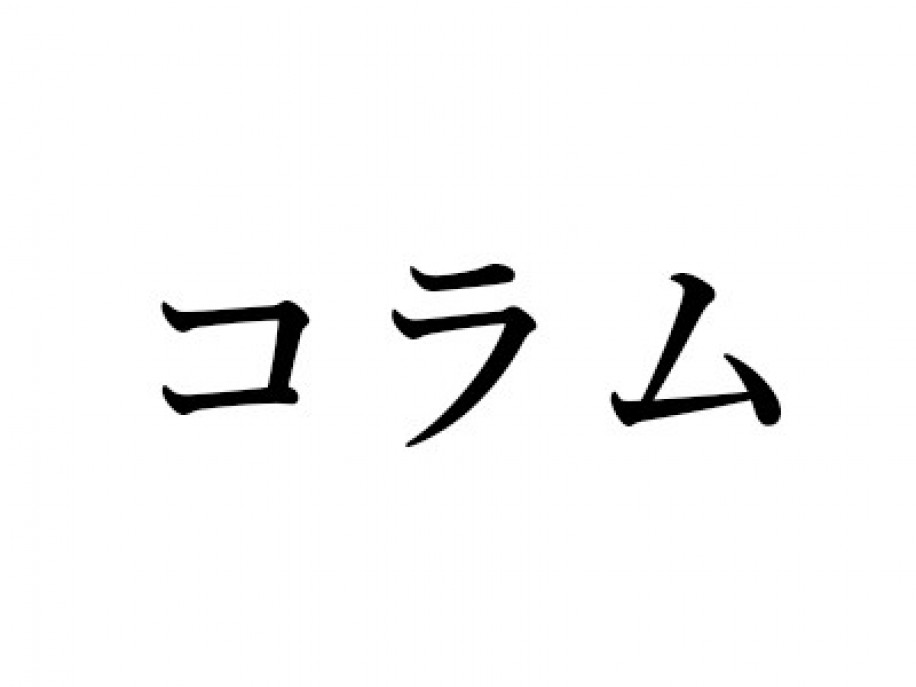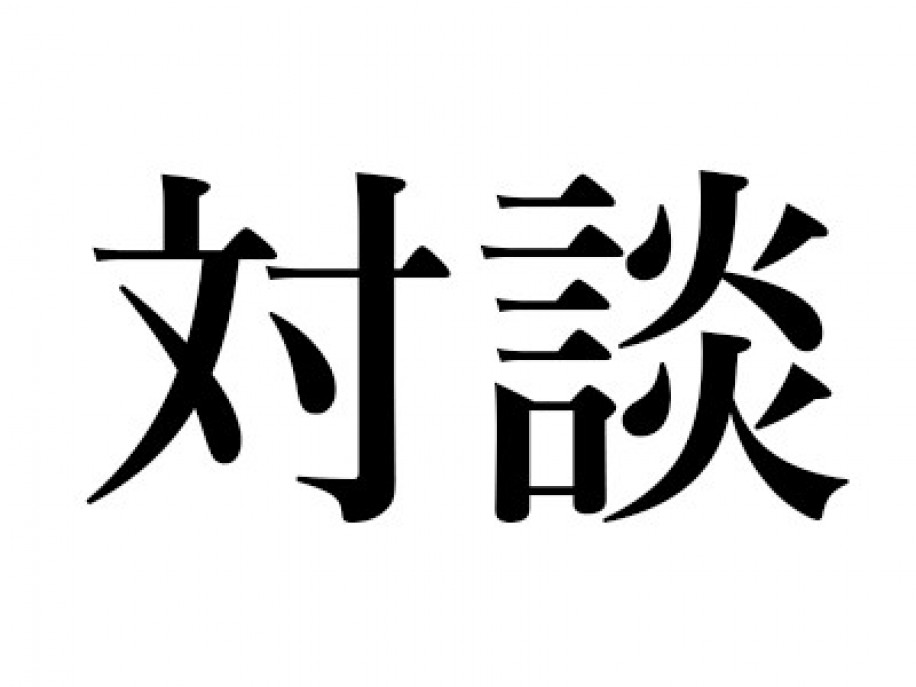コラム
石崎秀夫『機長のかばん』(講談社)、杉山隆男『兵士に聞け』(新潮社)、鍬本實敏『警視庁刑事』(講談社文庫)、上野正彦『死体は生きている』(角川書店)
仕事あれこれ
関西空港から日本の航空会社によるデリーへの初のフライトに乗ったときのこと。ロビーでは、デリー線就航を祝うセレモニーが行われた。地元のテレビ局のカメラが何台も回る中、司会の女性の張りのある声が響き、ネクタイのお歴々が挨拶を述べて、くす玉が割られ、紙吹雪が華やかに舞った。乗客には、記念品のアラーム時計とボールペンとが配られた。シートベルトを確認し、スチュワーデスも席につくと、飛行機は徐々に加速し、滑走路がどんどん後ろへ。そろそろ離陸か、と思ったとき、車なら「キキーッ!」とハデな音を上げそうな急ブレーキがかかり、前につんのめった。シートベルトが腹にくい込み、やがて元に。飛行機が止まったのだ。
「何、何?」
「これって、もしかして事故?」
「のはずないわよね、だって、アタシたちぴんしゃんしてるんだもの」
乗客の間にどよめきが起こる。
「ただ今、機体に不調がみつかりましたので、離陸を中止いたしました」
キャプテンからのアナウンス。点検が長引きそうなので、いったん降り、大阪市内のホテルに入ることになる。ロビーに出てきた客の中には、テレビクルーから、
「どうしたんですか?」
とマイクを向けられ、取材されている人もいた。そりゃ、聞きたくもなるだろう。今さっき見送ったばかりの客が、ぞろぞろと戻ってきたのだから。
あてがわれたホテルの部屋で、ぼうっとニュースを見ていたら、「初のデリー線、離陸中止」の文字が。滑走路で停止するところが映り、ロビーで私のとなりにいたおじさんが、
「いやー、急に、ブレーキがかかって」
などと答えている。こうなると、テレビクルーが来ていたのも、航空会社としてはアダになったな。空に飛び立つ、雄々しい映像になるはずが、とんだ恥さらしである。
結局、原因がわからず、成田から代替の飛行機を取ってきて、十時間遅れの出発となった。予定はくるったが、私としては、ぎりぎりのところで思いとどまった機長に、敬意を表したい。一秒でもよけいに迷ったら、それこそ「オーバーラン、炎上」のニュースになったかも知れないのだ。会社のおえらがたや来賓が注目する中、どれほどのプレッシャーのもとで決断したことか。
(孤独な職業だわ)
とあらためて思うのだった。
石崎秀夫著『機長のかばん』(講談社+α文庫)はタイトルがうまい。かばん→中身→覗いてみたい、と連想がはたらく。
著者は二万五千回余の飛行経験を持つ元機長。人からもっとも多く受ける質問は、離陸と着陸はどちらが難しいか、だそうだ。
答は「離陸は気を使い、着陸は難しい」。刻々と下がる高度を測りつつ、降下速度を限りなくゼロに近づけていくのは、十分の一秒間隔の判断の連続だそうだ。トライスターの場合、接地時の機長の目の高さは、マンションの四階から地面を見るほどもある。進入速度は二百五十キロと、新幹線なみ。それでタイヤを滑走路にぴたりと着けるのだから、熟練とはすごい。
横風のある場合はさらに、流される角度を計算に入れつつ、接地の瞬間、機首を風下に振ると同時に機体を風上側に傾ける。「一本脚着陸」はへまではなく、キャプテンの腕の見せどころなのである。
他にも、食中毒によるリスクを回避するため副操縦士とは違う機内食をとるとか、よそで披露すれば、
「へー、そうなんだ」
と受けること間違いなしの知識がたくさん詰まっている。短命職業の一位とされるたいへんな仕事だが、それでも人があこがれるわけは、「空から見る景色はとにかく美しい」「地上とは全く別の世界がここにはある」との、あとがきの言葉に尽きるのではないか。
杉山隆男著『兵士に聞け』(新潮文庫)は、自衛隊の基地を訪ね歩いた労作。救難ヘリからワイヤーで吊され、護衛艦で船酔いに苦しみ、レンジャー訓練ではほとんどへたばりそうになりながら、インタビューを重ねた。フェンスの向こう側には「僕らが忘れてきた、忘れようとしてきた戦後の日本がいまも生き続けている」。制服の彼らに聞く旅は、「自衛隊という鏡が映し出すもうひとりの自分を見に行く旅なのである」。
聞き書きにとどまらず、著者が身を置いた風景と、そこで感じたことを描写しつつ綴る。
五百ページ以上の本だが、文章のうまさで、読み通すことができた。
鍬本實敏著『警視庁刑事』(講談社文庫)は、四十年間の刑事生活を語ったもの。警察手帳の中はどうなっている、タクシーに乗って犯人を追ったらお金は払うか、といった素朴な疑問にも答える。
終戦後間もない頃の、有楽町交番勤務。終電過ぎると、駅員が燃えさしのタドンをさし入れにきて、客にあぶれた商売女があたりにきた。担ぎ屋を見て見ぬふりをしたこともある。取り調べ中盲腸で倒れ、入院先から逃げ出したスリが、こっそりと治療費を払いにきたことも。貧しいけれど、仁義や情のあった時代の匂いがたちのぼる。
話の合間にぽろりぽろり人生訓がこぼれる。「耳というのは、人の話を聞くためにあるんです」「後ろから声をかけられる人間になりたいですな。前から見て横道に逃げられる人間じゃ、ね」。
かっこいい。ドラマにしたい。
高村薫が帯に寄せた「職人であり、個人であった、刑事という半生の滋味がする」との言に、深くうなずける。
上野正彦著『死体は生きている』(角川文庫)は監察医によるノンフィクション。三十四年間、現場に赴き、突然死か自殺か他殺か不明の変死体を、二万体以上扱った。
よく出るという、「解剖した後、ご飯が食べられますか」の問いには、
「検死や解剖をしないと私は、ご飯が食べられないのですよ」
そう、それが仕事というもの。
失火にみせかけるため、絞め殺してから火を放つのは、よくある手だが、死体は焼けても、頭蓋骨の中に証拠が残る。完全犯罪を遂げる方法は、「証拠を残さないことだろうが、証拠を残さずに人の命を奪うことはできない」ときっぱり。
日本の全死亡者のうち、十五パーセントは変死体という。にもかかわらず、監察医制度は五大都市にしかない。突然死した人々の、生前の人権を擁護し、社会秩序を守るため、全国に普及させたく、本を書いた。すみずみまで職業倫理に貫かれている。
【このコラムが収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする