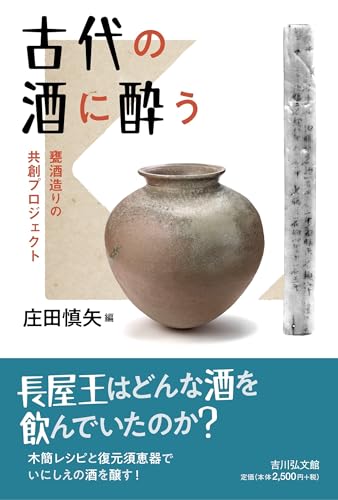対談・鼎談
『猪瀬直樹電子著作集「日本の近代」第1巻 構造改革とはなにか 新篇 日本国の研究』(小学館)
『猪瀬直樹電子著作集』の刊行を記念し、『日本の近代 猪瀬直樹著作集』刊行当時(2001年)に行われた対談を掲載いたします。
猪瀬 単行本としては『天皇の影法師』ですね。この著作集では第十巻目になります。朝日新聞社から出したのは一九八三年(昭和五八年)でした。実際には八〇年ごろに構想し、八一年にフィールドワークをつづけながら執筆し、八二年に入ったころには完成していました。『天皇の影法師』には八瀬童子をあつかった民俗学的なもの、「昭和」の元号のスクープ合戦を見つめたメディア論的なもの、『かのやうに』を著した森鷗外が晩年に『元号考』を執筆することになるのですがその心境を分析した評伝的なものなど、さまざまな要素がこの作品に現れており、全体としてはミステリー小説として読める構成になっています。『天皇の影法師』自体が、日本の近代の諸問題を内包していたのです。
鹿島 処女作には、その作家のすべてが含まれるという定石通りですね。歴史研究であり、評伝であり、ミステリーであったわけですから。
猪瀬 そもそも、書店が『天皇の影法師』をどのコーナーに置いたらよいのか迷ってしまった。文学なのかアカデミズムなのか、既成のジャンルに入らない。たまたまノンフィクションという場所に置いてもらえた。それからノンフィクションということになったのだけれど、さてノンフィクションとはなにか、というとこれがわかったようでわからない。結局、そこにもあてはまらない、ということになってきた。
鹿島 猪瀬さんの作品はたんに幅が広いというよりも、広義での「歴史学」のような気がします。たとえば『ペルソナ 三島由紀夫伝』『マガジン青春譜 川端康成と大宅壮一』『ピカレスク 太宰治伝』の三部作ですが、これは一般の分類では文学評論になるけれども、文学評論という従来の概念ではとうてい切り取れないものを多く含んでいる。案の定、文芸評論家はとまどってしまって何も言えなかった。当然なんですね。彼らの領域に踏み込んでいながら、彼らが全然気づかなかったことをやっているわけだから。
それで思い出すのはビクトル・ユゴーの『レ・ミゼラブル』のことです。『レ・ミゼラブル』は歴史研究に全く役立たないと言われていた。なぜかというと、書いてある歴史事項は不正確だし、かなり物語的なものだから、史実としては役立たない。反対にバルザックはかなり史料的に正確だから役立つと言われてきた。ところが、ルイ・シュヴァリエという人が、そうじゃないんだと唱えた。文学作品というのは、その作家の時代に対する怯えだとか、恐怖だとかを反映していて、広い意味での無意識というものが出てくる。たとえば作家がある一人のマージナルな人間を取り上げたときに、描かれている点が多少不正確であっても、そのときに描いている作家の心理なり何なりというのは、れっきとした歴史的な事実なんだ、と。いってみれば神話と神話学の関係ですね。ビクトル・ユゴーが書いたのは、これはいわば近代の神話。これに対して近代の神話学は、荒唐無稽な神話をつくり出す人間の心理を研究する。猪瀬さんがやっているのはこの近代の神話学ですね。
猪瀬 なるほど。置き場所というふうに外側から規定されてしまったというだけで、自分は、そうだと思っていない。僕はしっかりとした基盤を描き、その基盤のうえに人物を歩かせてみたい。いわば大人のミステリーだよね。ミステリーという言葉はちょっと誤解を招く可能性があるんだけれども、構造的にはそういう大人のミステリーのようなものを考えていた。いま、ふと思ったけれども、ウンベルト・エーコの『薔薇の名前』ってありますね。あれは大人のミステリーだよね。
鹿島 猪瀬さんの作品がミステリーの形を取るのは猪瀬さんが、作中の探偵でありながら、同時に探偵を描く作家でもあるからなんですね。猪瀬さんという探偵があって、それを描く書き手の猪瀬直樹というものがある。その二重構造があるからおもしろいんですね。ある時代を描いても、凡庸なタイプの書き手だと、非常に通俗的な物語を想定してしまってその物語に現実のほうを合わせてしまう。一方、猪瀬さんはというと、想定するのは通俗的な物語ではなく、あくまで「謎」なんですね。そこから、日本近代の数世代を貫く、大河小説的な物語が流れ出てくる。『ペルソナ 三島由紀夫伝』は、ただの評伝ではなく、この著作集のタイトルにした『日本の近代』というくくりで、官僚制と文学がひとつの視界に入ってくる。
猪瀬 日本の近代という土壌がどんな花を咲かせたか。僕は、土壌と花の両方を見たい。そうすると大河小説的な要素が出てくると思うんだけれどもね。
鹿島 猪瀬さんは、あえてミステリー小説だと言いましたね。例えば天皇制とか、まあ天皇制というと近代の言葉で、いろいろ手垢がついているから、あえてミカドと置き換えて、クエスチョンマークをかける。そのクエスチョンマークをかけるところから、もう仮説が、つまりミステリーがはじまっている。猪瀬さんは、同じテキストを読んでも、文芸評論家とは気づくところが違う。そこに情動なり何なりの謎があるんじゃないか。一見、気づかないようなことなんだけれども、心の動きがかなり生の状態であらわれている箇所があって、そこから読み込んでいけば、同じテキストでもまったく違うように見えてくる。このクエスチョンの発見がいちばん大切なんですね。
『ピカレスク 太宰治伝』に出てくる太宰の遺書の一行、「井伏さんは悪人です」だって、ああ、そうかと。ふつうはただそれだけなんです。だけれども、直感で、これは少し変だぞ、と感じとる。そして、この「何か変だ」をたんなる謎に終わらせずに、作家の本質と彼を生んだ時代へと至る道であることを見抜く。その本質的な細部を取り出す猪瀬さんの手つきは鮮やかですね。
宿命というのは、これはしょうがないんだよ。自分が恣意的に選択して、自由に何かを選んで進んできたようでもその実、追い詰められながら何かを選んでいくというところがある。主人公たちは、みんな、そうだと思うんですが、自分もそうだなと思っているわけで、そういう宿命性みたいなものの自覚があるかないか、これですね。このごろは日本人は増長していてね、何でも選べると思っているけれど、何も選んでいない。選ぶということは、どこか宿命性の影がないと選んでないと思うんだよね。
日本の近代というのは、世界史のなかで強いられた宿命性の意味です。ヨーロッパ近代という世界があって、世界史を勝手につくり上げてしまったときに、自分たちはそこに組み込まれた国民の一人である、そういう自覚がどこかにあるはずですね。
鹿島 そうですね。無意識を探ろうとする自分自身も無意識に規定されているわけですね。だから、自分だけ探ってもダメで、歴史だけを探ってもダメ。両方がリンクする部分を見つけなきゃいけない。猪瀬さんの場合は、いろいろ突き詰めていったら、そのリンクする部分というのがミカドだったんだということですね。自分がどこか非常に深いところで何かに規定されている部分、そこのところを求めていった。一方、自分とは一見全然関係ないところで、地球の表面に、ちょっとずつ浮かんでいるものがある。そういうものを拾い集めていくとやがて底の部分が、大きなところが見えてくる。
猪瀬 ミカドという規定であえて集約してみたんです。“空気”と言い換えればそれで終わってしまうかもしれないものを。アメリカとの戦争も、一握りの軍国主義者が勝手にやったのではない。そこを突き詰めないで逃げていたら現代にはつながりません。日本の近代がどんなかたちで追い詰められていったのか、その宿命性のようなものを含めてみないと。
いまも日本は経済戦争をやっていますが、GDP(国内総生産)が五百兆円もあるなんて、これは戦艦大和をつくったときよりも、もっとすごいことですね。アメリカが一千兆円強で、ヨーロッパ全部を集めてEU加盟国で八百数十兆円だから。一国で五百兆円になってしまい、これを維持するしかない。五百兆円の維持へと追い詰められちゃって、どうしてよいのかわからないんです、日本人は。失われた十年といったって、五百兆円は維持しながらの十年だからね。『日本国の研究』も、そのあたりの処方箋がないから、日本人がどこにいて何に躓(つまず)いているか、示してみたんです。日本の近代というものへの理解がベースにあって、そして百五十年の近代化の課程でいまどこにいるか、そんな遠近法があってこれをやれるんだと思う。
鹿島 僕はいま渋沢栄一を調べていますけれど、渋沢が苦労したのは自由競争という概念を、どうやって民衆に植えつけるかということだった。お上が「はい、おまえら、銀行をつくれ」というんじゃなくて、民間に自ら起業させる。これが、ほんとうに死ぬほどたいへんだったみたいですね。
猪瀬 いまの特殊法人の民営化みたいなものだろうね。民営化をわからせるのは、それぐらいむずかしい。
鹿島 その通りで、渋沢も結局、半ば失敗し半ば成功しているんですよ。彼は奉加帳方式という感じで株式会社を立ちあげて、最終的には、それでやるしかなかった。
猪瀬 日本的なソフィスティケイトされた世界は、ある種の自己完結した空間性にまもられている社会なんです。
鹿島 さきほど猪瀬さんの方法論は、広い意味での近代の神話学と言ったんですけれども、その神話学は決して堅苦しくなくて、語り口は、すごく小説的。小説としてもうまくできている。抜群のストーリーテリングですね。
猪瀬 この著作集の入り口は自由なんです。編集委員には鹿島茂さん、関川夏央さん、大岡玲さん、船曳建夫さん、とみな幅の広い人にお願いしたんです。それぞれが僕の分野と重なってきますから。どんな方に編集委員になっていただくか、その組み合わせ自体も僕の企画のうち、ということになります。勝手なことですみません(笑)。僕の書いたものがそれぞれの分野でばらばらに分類されていってしまう。そうじゃない。ひとつのテーマを多面的に追跡しているんだと言いたいし、そう理解していただきたいからです。
鹿島 ビジネスマンだと『日本国の研究』で、『ピカレスク 太宰治伝』は文学青年で、と別々のところへ入ってしまう。だけれども全部読んでみればみなつながっているということがよくわかる。そこが猪瀬直樹のすごいところなんだけれどね。
猪瀬 『日本凡人伝』は一種のインタヴューのゲームです。対話です。日本には対話のおもしろい作品がなかったんです。真剣勝負でかつユーモラスな対話がなかった。プロ同士でやるとお互いわかりあっちゃっているから、知らない人をつかまえてきてやってみた。初対面の人と話をすると、おもしろい。
じつは『日本国の研究』も対話なんです、もとは。いろいろと各省庁を回って官僚のキャリアと対話してみた。そうすると、ソクラテスの無知の知じゃないけれども、そのキャリアはその部署においては、よく知っている。けれど全体のなかで、あなたは何をやっているんだ? ということになるとうまく答えられない。全体をつかんでないから。全体がなければ、あなたはいられないでしょう、と対話をするんです。全体を見ようとしても、全体が見えにくくなるほど、複雑怪奇になっている世界、カフカの『城』じゃないけれども、そこで自分は部分ではない、と主張するのにはかなり知的な攪拌作業が必要になるんですよ。
鹿島 だれが全体の責任者だというと、だれもわからない。
猪瀬 あなたはどれだけ知らないの? ということをわからせていくための対話です。自分は何でも知っていると錯覚していますから。そうすると自分はこれぐらい知っている、と主張します。たしかによく知っているんです。ところが対話を重ねていくうちに、知らないということがわかってくる。そういう対話の繰り返しなんです。その過程でいろいろな話が出てきて、しだいに全体の構造がどうなっているかという自己認識に辿り着く。だから対話とは何かということなんです。そのプロセスがおもしろい。
鹿島 『十二人の怒れる男』という映画があったでしょう。議論を重ねていくと、最後にそれぞれの立場をとらせるに至った、十二人の陪審員自身の生涯が出てきちゃう。そんなところがあったわけですね。
猪瀬 それがおもしろい、と思うかどうかですね。僕はおもしろいんです、それが。
鹿島 そうすると、『日本国の研究』でも、建設省のキャリアと対話することは、ある意味では、『日本凡人伝』に登場する列車のダイヤをつくっているおじさんに、根掘り葉掘り訊ねているのと同じで……。
猪瀬 そうそう。インタヴューという言葉をやめちゃってもいい。対話です。対話っていうのは子供電話相談室みたいなことの繰り返しなんです。どうしてこうなの? なんで丸いの? なんで四角いの? と訊かれたら、かんたんに答えられないでしょう。児童や少年の気持ちを、どこかに持っていれば、相手が裸の王様に見えるときがある。無垢でいると。
霞が関のキャリアのところに行って、あなた何でここにいるの? と子供相談室みたいな質問ができるかどうかですね。相手は全精力を投入して答えるしかない。表層の意識だけじゃ、答えにならないから。それから、体系性を必死で維持しようとするよね。そういうところから出てくるものを逆にとりいれていけばいい。柔道でも、空手でも、最終的には、カウンターを取れるかどうかですからね。子供電話相談室でいきながら、カウンターを取るという感じで力を抜いていればいいんです。
鹿島 だけれども、それは専門的な予備知識をいろいろ仕込んでおいたうえでの子供相談室ですから。その辺のよくあるようなインタヴューは、ほんとうに何もしていない。そこのところは違うから、念を押しておかないと(笑)。
猪瀬 日本語というのは概念が非常にあいまいです。キャッチボールはできるだけストライクの球を出していかないと、ボールばっかり投げていたら相手から返ってこない。受けて、きちんと包んであげて、また戻して。情況に応じた正確な日本語を、遠近法がとれた言葉を、どれだけ拾って、返していくかということですね。
鹿島 それは、猪瀬さんの作品全体に言えることで、グッド・クエスチョンじゃないと、グッド・アンサーは出ない。
猪瀬 遠近法とは、距離の取り方ですね。詩人の谷川俊太郎さんが言葉を選ぶような気持ちでしょう。なかなかその域には届かないとしても。言葉を選ぶときに、もう距離の取り方は決まっているところがありますから。
鹿島 それと、これはあまり言われていないことだけれど、猪瀬さんの文体はきわめて明晰ですね。実は、明晰に見えて、そうじゃない文章というのが案外多い。外国語に訳そうと思うと全然訳せないというケースがある。たとえば、英語にしろフランス語にしろ、名詞と形容詞の結びつきってすごく厳密なんですよ。そこへいくと日本語というのはかなりあいまいに結びつけてしまう。猪瀬さんの文章はそういうあいまいさがない。だから外国語に翻訳しやすいと思いますよ。
最後に、猪瀬さん、これからの狙いは?
猪瀬 いえいえ。いまはこの著作集の完成だけを考えています。二十年間、ほとんど仕事場で過ごしてきましたから。
鹿島 そりゃ、そうというしかない。この仕事場を見たら、まるでこれは自主バリケードだ(笑)。
猪瀬 野茂選手みたいに球を投げていたら肩をこわします。なんでこんなに一所懸命やったんだろうと思うぐらい、仕事をしました。「子供より、親が大事と思いたい」と太宰治が言っているけれども、僕も家庭の幸福を犠牲にして、迷惑をかけながら二十年やってきたんです。そういえば鹿島さんも『子供より古書が大事と思いたい』という本を出しましたね(笑)。
鹿島 この十二冊がひとつのかたまりになって、猪瀬的ユニバースができあがったという感じですね。お話を伺って、非常によくわかりました。
猪瀬 ヨーロッパから借りてきた枠組みはいっぱいあったと思うんだけれども。文学は、純文学、中間小説、娯楽小説、ノンフィクション、と細かく分けながらパワーを失いつつ解体しはじめています。そろそろ日本独自のパラダイムをつくらないといけない。ただそのためにはやはり認識が先でしたね。日本の近代を、どれだけ自己認識として明晰になれるか、とりあえず課題としてやったような感じがあります。
鹿島 なるほどね。フーコーが『知の考古学』という言葉を使ったけど、なぜ考古学かといえば、書かれたものからでなく書かれてないもののなかからいかに言葉を拾ってくるかという問題意識があったからです。いま猪瀬さんがやっていることは、まさにそれで、言葉のない人間から、言葉を拾ってきて、そして語られざるものに語らせるということでしょう。まさに考古学ですね。では、その考古学から何を導き出したかというと、これまたフーコーなんだけれども、エピステーメというものだと思います。要するに認識要素ということ。その時代時代の一つの認識素と言ったらいいのかな。ギリシャ語だから、日本語にならないんだけれども。その時代の認識素みたいなものを拾い出してくるということでしょうね。
というわけで、猪瀬さんがやっていることは、僕の印象で言うと、十種競技だと思う。昔は十種競技の選手こそが英雄だったけれど、いまのスポーツだと、十種競技というのは、カス扱いになっている。でも本来はそうじゃないはずだ。つまり、百メートルなり棒高跳びしかできないやつは、スポーツ選手としてはよくても、本来のアスリート(戦う人)としては失格なんです。同じことはものを考えることでも言える。思想の百メートル選手や棒高跳び選手は総合的な認識力が全然ない。それではいまの時代は困るんだ。必要なのは、十種競技的な思想人なんですね。このごろは、トライアスロンかな。
猪瀬さんの功績は、近代というものを総合的認識力の十種競技選手として捉えたことですね。官僚にしろ、政治家にしろ、学者にしろ、物書きにしろ、みんな、十種競技にエントリーできる人がいなくなっちゃった。これからは十種競技の復活ですよ。
2001年6月26日 西麻布の事務所にて
知の“十種競技”選手として
猪瀬式新ジャンルの開拓
鹿島 猪瀬さんの著作集に『日本の近代』というタイトルがつけられました。このタイトルから、発刊の意図について話していきたいと思います。まずはデビュー作からいきましょう。猪瀬 単行本としては『天皇の影法師』ですね。この著作集では第十巻目になります。朝日新聞社から出したのは一九八三年(昭和五八年)でした。実際には八〇年ごろに構想し、八一年にフィールドワークをつづけながら執筆し、八二年に入ったころには完成していました。『天皇の影法師』には八瀬童子をあつかった民俗学的なもの、「昭和」の元号のスクープ合戦を見つめたメディア論的なもの、『かのやうに』を著した森鷗外が晩年に『元号考』を執筆することになるのですがその心境を分析した評伝的なものなど、さまざまな要素がこの作品に現れており、全体としてはミステリー小説として読める構成になっています。『天皇の影法師』自体が、日本の近代の諸問題を内包していたのです。
鹿島 処女作には、その作家のすべてが含まれるという定石通りですね。歴史研究であり、評伝であり、ミステリーであったわけですから。
猪瀬 そもそも、書店が『天皇の影法師』をどのコーナーに置いたらよいのか迷ってしまった。文学なのかアカデミズムなのか、既成のジャンルに入らない。たまたまノンフィクションという場所に置いてもらえた。それからノンフィクションということになったのだけれど、さてノンフィクションとはなにか、というとこれがわかったようでわからない。結局、そこにもあてはまらない、ということになってきた。
鹿島 猪瀬さんの作品はたんに幅が広いというよりも、広義での「歴史学」のような気がします。たとえば『ペルソナ 三島由紀夫伝』『マガジン青春譜 川端康成と大宅壮一』『ピカレスク 太宰治伝』の三部作ですが、これは一般の分類では文学評論になるけれども、文学評論という従来の概念ではとうてい切り取れないものを多く含んでいる。案の定、文芸評論家はとまどってしまって何も言えなかった。当然なんですね。彼らの領域に踏み込んでいながら、彼らが全然気づかなかったことをやっているわけだから。
それで思い出すのはビクトル・ユゴーの『レ・ミゼラブル』のことです。『レ・ミゼラブル』は歴史研究に全く役立たないと言われていた。なぜかというと、書いてある歴史事項は不正確だし、かなり物語的なものだから、史実としては役立たない。反対にバルザックはかなり史料的に正確だから役立つと言われてきた。ところが、ルイ・シュヴァリエという人が、そうじゃないんだと唱えた。文学作品というのは、その作家の時代に対する怯えだとか、恐怖だとかを反映していて、広い意味での無意識というものが出てくる。たとえば作家がある一人のマージナルな人間を取り上げたときに、描かれている点が多少不正確であっても、そのときに描いている作家の心理なり何なりというのは、れっきとした歴史的な事実なんだ、と。いってみれば神話と神話学の関係ですね。ビクトル・ユゴーが書いたのは、これはいわば近代の神話。これに対して近代の神話学は、荒唐無稽な神話をつくり出す人間の心理を研究する。猪瀬さんがやっているのはこの近代の神話学ですね。
猪瀬 なるほど。置き場所というふうに外側から規定されてしまったというだけで、自分は、そうだと思っていない。僕はしっかりとした基盤を描き、その基盤のうえに人物を歩かせてみたい。いわば大人のミステリーだよね。ミステリーという言葉はちょっと誤解を招く可能性があるんだけれども、構造的にはそういう大人のミステリーのようなものを考えていた。いま、ふと思ったけれども、ウンベルト・エーコの『薔薇の名前』ってありますね。あれは大人のミステリーだよね。
鹿島 猪瀬さんの作品がミステリーの形を取るのは猪瀬さんが、作中の探偵でありながら、同時に探偵を描く作家でもあるからなんですね。猪瀬さんという探偵があって、それを描く書き手の猪瀬直樹というものがある。その二重構造があるからおもしろいんですね。ある時代を描いても、凡庸なタイプの書き手だと、非常に通俗的な物語を想定してしまってその物語に現実のほうを合わせてしまう。一方、猪瀬さんはというと、想定するのは通俗的な物語ではなく、あくまで「謎」なんですね。そこから、日本近代の数世代を貫く、大河小説的な物語が流れ出てくる。『ペルソナ 三島由紀夫伝』は、ただの評伝ではなく、この著作集のタイトルにした『日本の近代』というくくりで、官僚制と文学がひとつの視界に入ってくる。
猪瀬 日本の近代という土壌がどんな花を咲かせたか。僕は、土壌と花の両方を見たい。そうすると大河小説的な要素が出てくると思うんだけれどもね。
鹿島 猪瀬さんは、あえてミステリー小説だと言いましたね。例えば天皇制とか、まあ天皇制というと近代の言葉で、いろいろ手垢がついているから、あえてミカドと置き換えて、クエスチョンマークをかける。そのクエスチョンマークをかけるところから、もう仮説が、つまりミステリーがはじまっている。猪瀬さんは、同じテキストを読んでも、文芸評論家とは気づくところが違う。そこに情動なり何なりの謎があるんじゃないか。一見、気づかないようなことなんだけれども、心の動きがかなり生の状態であらわれている箇所があって、そこから読み込んでいけば、同じテキストでもまったく違うように見えてくる。このクエスチョンの発見がいちばん大切なんですね。
『ピカレスク 太宰治伝』に出てくる太宰の遺書の一行、「井伏さんは悪人です」だって、ああ、そうかと。ふつうはただそれだけなんです。だけれども、直感で、これは少し変だぞ、と感じとる。そして、この「何か変だ」をたんなる謎に終わらせずに、作家の本質と彼を生んだ時代へと至る道であることを見抜く。その本質的な細部を取り出す猪瀬さんの手つきは鮮やかですね。
作家・猪瀬直樹の“原動力”とは?
猪瀬 『日本の近代』編集委員のひとりである関川夏央さんが、この著作集のパンフレットに「自分への興味と疑い」が僕の原動力だ、と書いてくれていますが、すべては自分に対する問いの結果でもあるんです。確かにね。好奇心というのは自分に最終的に向かっていくわけだけれども、それへ向かっているものと同じものを対象にぶつけないといけない。自分を置いておいて、対象だけ分析したってだめだから、自分だったらどうするんだろうとか、自分はどうしてこうなっているんだろうと思いながら、対象を見ていかないといけないというのがあって。でもそれだけならば人間中心、かつ相対主義に陥りやすい。もうひとつは全体に対する畏れみたいなものなんだろうね。すべて宿命のせいにしては無責任だから、日本の近代の宿命的なものにフォーカスさせるぐらいがいい。なんとか手が届く。分析はできるから。宿命というのは、これはしょうがないんだよ。自分が恣意的に選択して、自由に何かを選んで進んできたようでもその実、追い詰められながら何かを選んでいくというところがある。主人公たちは、みんな、そうだと思うんですが、自分もそうだなと思っているわけで、そういう宿命性みたいなものの自覚があるかないか、これですね。このごろは日本人は増長していてね、何でも選べると思っているけれど、何も選んでいない。選ぶということは、どこか宿命性の影がないと選んでないと思うんだよね。
日本の近代というのは、世界史のなかで強いられた宿命性の意味です。ヨーロッパ近代という世界があって、世界史を勝手につくり上げてしまったときに、自分たちはそこに組み込まれた国民の一人である、そういう自覚がどこかにあるはずですね。
鹿島 そうですね。無意識を探ろうとする自分自身も無意識に規定されているわけですね。だから、自分だけ探ってもダメで、歴史だけを探ってもダメ。両方がリンクする部分を見つけなきゃいけない。猪瀬さんの場合は、いろいろ突き詰めていったら、そのリンクする部分というのがミカドだったんだということですね。自分がどこか非常に深いところで何かに規定されている部分、そこのところを求めていった。一方、自分とは一見全然関係ないところで、地球の表面に、ちょっとずつ浮かんでいるものがある。そういうものを拾い集めていくとやがて底の部分が、大きなところが見えてくる。
猪瀬 ミカドという規定であえて集約してみたんです。“空気”と言い換えればそれで終わってしまうかもしれないものを。アメリカとの戦争も、一握りの軍国主義者が勝手にやったのではない。そこを突き詰めないで逃げていたら現代にはつながりません。日本の近代がどんなかたちで追い詰められていったのか、その宿命性のようなものを含めてみないと。
いまも日本は経済戦争をやっていますが、GDP(国内総生産)が五百兆円もあるなんて、これは戦艦大和をつくったときよりも、もっとすごいことですね。アメリカが一千兆円強で、ヨーロッパ全部を集めてEU加盟国で八百数十兆円だから。一国で五百兆円になってしまい、これを維持するしかない。五百兆円の維持へと追い詰められちゃって、どうしてよいのかわからないんです、日本人は。失われた十年といったって、五百兆円は維持しながらの十年だからね。『日本国の研究』も、そのあたりの処方箋がないから、日本人がどこにいて何に躓(つまず)いているか、示してみたんです。日本の近代というものへの理解がベースにあって、そして百五十年の近代化の課程でいまどこにいるか、そんな遠近法があってこれをやれるんだと思う。
鹿島 僕はいま渋沢栄一を調べていますけれど、渋沢が苦労したのは自由競争という概念を、どうやって民衆に植えつけるかということだった。お上が「はい、おまえら、銀行をつくれ」というんじゃなくて、民間に自ら起業させる。これが、ほんとうに死ぬほどたいへんだったみたいですね。
猪瀬 いまの特殊法人の民営化みたいなものだろうね。民営化をわからせるのは、それぐらいむずかしい。
鹿島 その通りで、渋沢も結局、半ば失敗し半ば成功しているんですよ。彼は奉加帳方式という感じで株式会社を立ちあげて、最終的には、それでやるしかなかった。
猪瀬 日本的なソフィスティケイトされた世界は、ある種の自己完結した空間性にまもられている社会なんです。
鹿島 さきほど猪瀬さんの方法論は、広い意味での近代の神話学と言ったんですけれども、その神話学は決して堅苦しくなくて、語り口は、すごく小説的。小説としてもうまくできている。抜群のストーリーテリングですね。
猪瀬 この著作集の入り口は自由なんです。編集委員には鹿島茂さん、関川夏央さん、大岡玲さん、船曳建夫さん、とみな幅の広い人にお願いしたんです。それぞれが僕の分野と重なってきますから。どんな方に編集委員になっていただくか、その組み合わせ自体も僕の企画のうち、ということになります。勝手なことですみません(笑)。僕の書いたものがそれぞれの分野でばらばらに分類されていってしまう。そうじゃない。ひとつのテーマを多面的に追跡しているんだと言いたいし、そう理解していただきたいからです。
鹿島 ビジネスマンだと『日本国の研究』で、『ピカレスク 太宰治伝』は文学青年で、と別々のところへ入ってしまう。だけれども全部読んでみればみなつながっているということがよくわかる。そこが猪瀬直樹のすごいところなんだけれどね。
対話を通じて全体の構造に迫る
鹿島 猪瀬さん、ちょっと古い話になりますが、『天皇の影法師』をお書きになったころに同時並行で『日本凡人伝』を連載していましたね。猪瀬 『日本凡人伝』は一種のインタヴューのゲームです。対話です。日本には対話のおもしろい作品がなかったんです。真剣勝負でかつユーモラスな対話がなかった。プロ同士でやるとお互いわかりあっちゃっているから、知らない人をつかまえてきてやってみた。初対面の人と話をすると、おもしろい。
じつは『日本国の研究』も対話なんです、もとは。いろいろと各省庁を回って官僚のキャリアと対話してみた。そうすると、ソクラテスの無知の知じゃないけれども、そのキャリアはその部署においては、よく知っている。けれど全体のなかで、あなたは何をやっているんだ? ということになるとうまく答えられない。全体をつかんでないから。全体がなければ、あなたはいられないでしょう、と対話をするんです。全体を見ようとしても、全体が見えにくくなるほど、複雑怪奇になっている世界、カフカの『城』じゃないけれども、そこで自分は部分ではない、と主張するのにはかなり知的な攪拌作業が必要になるんですよ。
鹿島 だれが全体の責任者だというと、だれもわからない。
猪瀬 あなたはどれだけ知らないの? ということをわからせていくための対話です。自分は何でも知っていると錯覚していますから。そうすると自分はこれぐらい知っている、と主張します。たしかによく知っているんです。ところが対話を重ねていくうちに、知らないということがわかってくる。そういう対話の繰り返しなんです。その過程でいろいろな話が出てきて、しだいに全体の構造がどうなっているかという自己認識に辿り着く。だから対話とは何かということなんです。そのプロセスがおもしろい。
鹿島 『十二人の怒れる男』という映画があったでしょう。議論を重ねていくと、最後にそれぞれの立場をとらせるに至った、十二人の陪審員自身の生涯が出てきちゃう。そんなところがあったわけですね。
猪瀬 それがおもしろい、と思うかどうかですね。僕はおもしろいんです、それが。
鹿島 そうすると、『日本国の研究』でも、建設省のキャリアと対話することは、ある意味では、『日本凡人伝』に登場する列車のダイヤをつくっているおじさんに、根掘り葉掘り訊ねているのと同じで……。
猪瀬 そうそう。インタヴューという言葉をやめちゃってもいい。対話です。対話っていうのは子供電話相談室みたいなことの繰り返しなんです。どうしてこうなの? なんで丸いの? なんで四角いの? と訊かれたら、かんたんに答えられないでしょう。児童や少年の気持ちを、どこかに持っていれば、相手が裸の王様に見えるときがある。無垢でいると。
霞が関のキャリアのところに行って、あなた何でここにいるの? と子供相談室みたいな質問ができるかどうかですね。相手は全精力を投入して答えるしかない。表層の意識だけじゃ、答えにならないから。それから、体系性を必死で維持しようとするよね。そういうところから出てくるものを逆にとりいれていけばいい。柔道でも、空手でも、最終的には、カウンターを取れるかどうかですからね。子供電話相談室でいきながら、カウンターを取るという感じで力を抜いていればいいんです。
鹿島 だけれども、それは専門的な予備知識をいろいろ仕込んでおいたうえでの子供相談室ですから。その辺のよくあるようなインタヴューは、ほんとうに何もしていない。そこのところは違うから、念を押しておかないと(笑)。
猪瀬 日本語というのは概念が非常にあいまいです。キャッチボールはできるだけストライクの球を出していかないと、ボールばっかり投げていたら相手から返ってこない。受けて、きちんと包んであげて、また戻して。情況に応じた正確な日本語を、遠近法がとれた言葉を、どれだけ拾って、返していくかということですね。
鹿島 それは、猪瀬さんの作品全体に言えることで、グッド・クエスチョンじゃないと、グッド・アンサーは出ない。
猪瀬 遠近法とは、距離の取り方ですね。詩人の谷川俊太郎さんが言葉を選ぶような気持ちでしょう。なかなかその域には届かないとしても。言葉を選ぶときに、もう距離の取り方は決まっているところがありますから。
鹿島 それと、これはあまり言われていないことだけれど、猪瀬さんの文体はきわめて明晰ですね。実は、明晰に見えて、そうじゃない文章というのが案外多い。外国語に訳そうと思うと全然訳せないというケースがある。たとえば、英語にしろフランス語にしろ、名詞と形容詞の結びつきってすごく厳密なんですよ。そこへいくと日本語というのはかなりあいまいに結びつけてしまう。猪瀬さんの文章はそういうあいまいさがない。だから外国語に翻訳しやすいと思いますよ。
最後に、猪瀬さん、これからの狙いは?
猪瀬 いえいえ。いまはこの著作集の完成だけを考えています。二十年間、ほとんど仕事場で過ごしてきましたから。
鹿島 そりゃ、そうというしかない。この仕事場を見たら、まるでこれは自主バリケードだ(笑)。
猪瀬 野茂選手みたいに球を投げていたら肩をこわします。なんでこんなに一所懸命やったんだろうと思うぐらい、仕事をしました。「子供より、親が大事と思いたい」と太宰治が言っているけれども、僕も家庭の幸福を犠牲にして、迷惑をかけながら二十年やってきたんです。そういえば鹿島さんも『子供より古書が大事と思いたい』という本を出しましたね(笑)。
鹿島 この十二冊がひとつのかたまりになって、猪瀬的ユニバースができあがったという感じですね。お話を伺って、非常によくわかりました。
猪瀬 ヨーロッパから借りてきた枠組みはいっぱいあったと思うんだけれども。文学は、純文学、中間小説、娯楽小説、ノンフィクション、と細かく分けながらパワーを失いつつ解体しはじめています。そろそろ日本独自のパラダイムをつくらないといけない。ただそのためにはやはり認識が先でしたね。日本の近代を、どれだけ自己認識として明晰になれるか、とりあえず課題としてやったような感じがあります。
鹿島 なるほどね。フーコーが『知の考古学』という言葉を使ったけど、なぜ考古学かといえば、書かれたものからでなく書かれてないもののなかからいかに言葉を拾ってくるかという問題意識があったからです。いま猪瀬さんがやっていることは、まさにそれで、言葉のない人間から、言葉を拾ってきて、そして語られざるものに語らせるということでしょう。まさに考古学ですね。では、その考古学から何を導き出したかというと、これまたフーコーなんだけれども、エピステーメというものだと思います。要するに認識要素ということ。その時代時代の一つの認識素と言ったらいいのかな。ギリシャ語だから、日本語にならないんだけれども。その時代の認識素みたいなものを拾い出してくるということでしょうね。
というわけで、猪瀬さんがやっていることは、僕の印象で言うと、十種競技だと思う。昔は十種競技の選手こそが英雄だったけれど、いまのスポーツだと、十種競技というのは、カス扱いになっている。でも本来はそうじゃないはずだ。つまり、百メートルなり棒高跳びしかできないやつは、スポーツ選手としてはよくても、本来のアスリート(戦う人)としては失格なんです。同じことはものを考えることでも言える。思想の百メートル選手や棒高跳び選手は総合的な認識力が全然ない。それではいまの時代は困るんだ。必要なのは、十種競技的な思想人なんですね。このごろは、トライアスロンかな。
猪瀬さんの功績は、近代というものを総合的認識力の十種競技選手として捉えたことですね。官僚にしろ、政治家にしろ、学者にしろ、物書きにしろ、みんな、十種競技にエントリーできる人がいなくなっちゃった。これからは十種競技の復活ですよ。
2001年6月26日 西麻布の事務所にて
ALL REVIEWSをフォローする