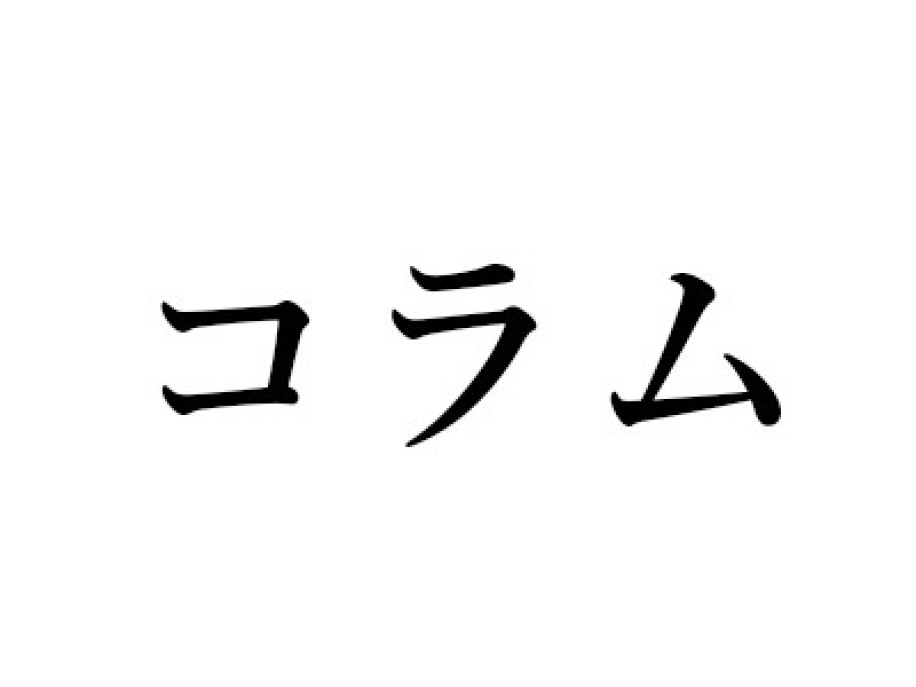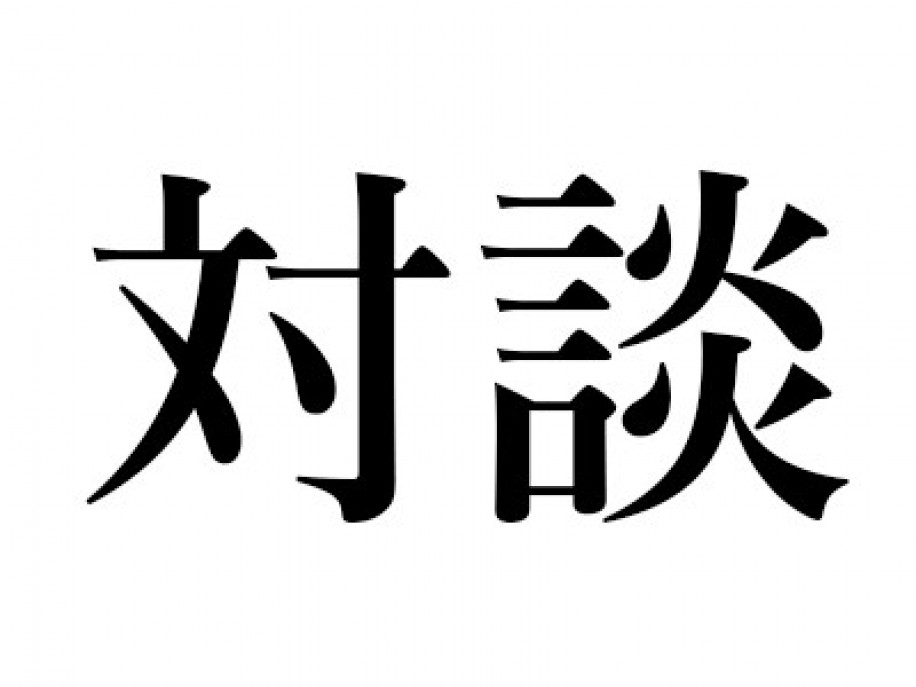書評
『猪瀬直樹電子著作集「日本の近代」第3巻 マガジン青春譜 川端康成と大宅壮一』(小学館)
川端と大宅軸に描く大正のメディア絵図
青春のガツガツ──。それが本書の一番の魅力だ。「濃い人」が続々登場する。若き日の川端康成と大宅壮一を主軸に据えた評伝的小説である。かたや純文学でかたやジャーナリズム。作品も人柄もまるで別世界という感じだが、この二人には接点が多かったのだという。そもそも二人は同世代で(川端のほうが一歳上)、同じ大阪の茨木中学に学んでいて、その後の人生もたびたび交錯しているというのだ。
著者がこの二人の関係に着目し、おそろしく綿密に調べあげ、これだけの長さの読みものにまとめあげた裏には、一つの大きなもくろみがあったに違いない。「一見対極的に見られるこの二人を中心に、大正メディア絵図を描き出したい。純文学も大衆文学もジャーナリズムもその境界をおぼろにし、巨大なマーケットとの争闘に直面せざるを得なくなって行った。今につながる大衆社会の姿を浮かびあがらせたい」──というような。
このもくろみは成功したと思う。川端康成と大宅壮一、この若者二人の背後に、年長世代の芥川龍之介と菊池寛を副主人公的コンビとして配したこと。島田清次郎『地上』と賀川豊彦『死線を越えて』という、二冊の異色のベストセラーに注目して詳述したこと。作家の作品分析に際して、金と女という下世話なアプローチを採用していることなどが勝因だと思う。
伊藤整『日本文壇史』の「その後」にあたる時代を描いているわけだが、文壇がサロンからマーケットに変わっていく状況をとらえようとしたら、おのずから生ぐさい話になってしまうのだろう。
全編にガツガツとした気分──超俗的部分も通俗的部分も混沌(こんとん)とした、若者らしい欲望のエネルギーがあふれていて青春劇画的な面白さがある(ひときわカラフルに劇画的なのが島田清次郎だ)。
最も好もしく、この本を読んでよかったと思わせたのは、大宅壮一の中学時代の師である「多門先生」だ。「読め、書くな教」を提案し、「早熟なるべからず」といましめた人。「紙にて造られたる人、インクにて塗られたる自然のみを観るなかれ」という言葉は、美しく正しい。
朝日新聞 1998年7月5日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする