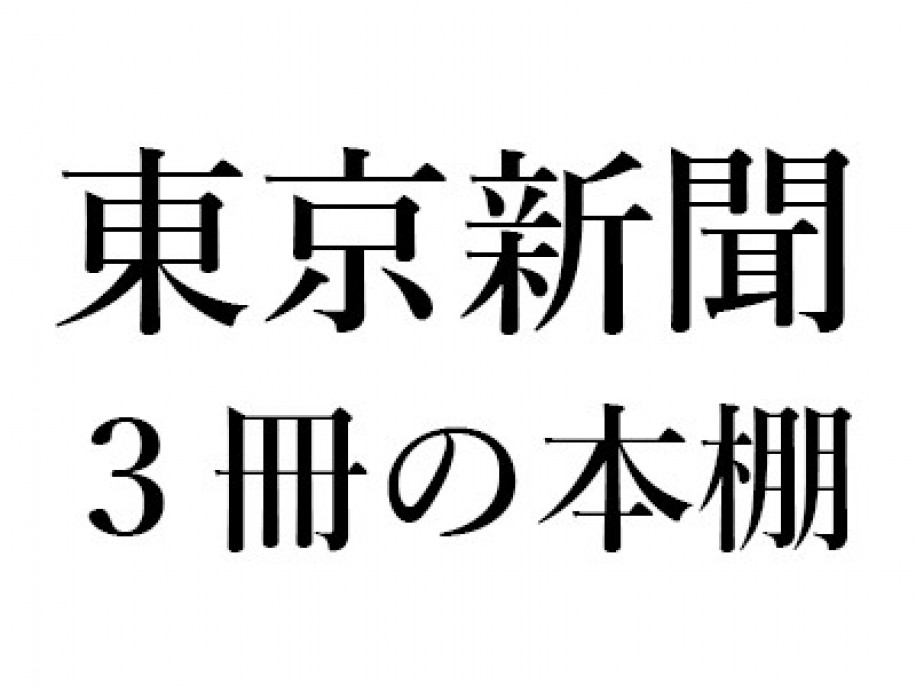読書日記
安野光雅『安野光雅 自分の眼で見て、考える』(平凡社)、とみさわ昭仁『レコード越しの戦後史』(Pヴァイン)、ティラー・J・マッツェオ『イレナの子供たち』ほか
◆『安野光雅 自分の眼で見て、考える』安野光雅・著(平凡社/1200円)税別
著名人が自身の人生を語り下ろす、この「のこす言葉」シリーズはいい。第3弾は『安野光雅 自分の眼で見て、考える』。絵本作家、エッセイストでも知られる画家は、今年93歳だという。
1926年、島根県津和野生まれ。小学生の頃「不登校児」というのが意外。ただ、「絵描きになりたい」とずっと思っていて、その「一本の線を、くねくねと軌道修正しながら辿ってきて今がある」と語り口はユニークでユーモアがある。戦後、玉川学園園長・小原と運命の出会いをして、道が開けた。
激動の時代を生きぬいた者としてのさまざまな提言もある。日本の教育は、何でも数字や順位で評価する。「自分の頭で考えることが大事です」と言う。『旅の絵本』シリーズが下描きなし、というのは驚いた。旅をして、実物を見た自信が独自の風景画を生んだ。
モットーにする言葉が「雲中一雁」。雁(がん)は群れて飛ぶが、離れて一羽でも飛ぶ。「しょせん一人」という覚悟が著者を支えた。
◆『レコード越しの戦後史 歌謡曲でたどる戦後日本の精神史』とみさわ昭仁・著(Pヴァイン/税別1800円)
改元でますます遠ざかる「昭和」の切り口は幾つもあるが、終戦後から変容する社会を映し出したのはレコードではないか。とみさわ昭仁『レコード越しの戦後史』は、それを証明して見せる。
戦後復興、高度成長、ヒーローや花粉症と、事件や流行の陰に、つねに歌謡曲が流れていた。戦後復興を象徴する「東京タワー」が完成した昭和33年、「東京333米」が出た。数字は高さ。歌うはミラクル・ヴォイス。
著者は珍レコードコレクターとしても知られるが、その強みが随所で生きている。昭和47年に帰還した日本兵・横井庄一さん。「お帰りなさい横井さん」というレコードが出ていた。中国残留孤児の歌も多数紹介され、著者は背景にある日中国交問題をちゃんと押さえている。戦後史と向き合う姿勢は真摯(しんし)で、貫く骨は太い。
歌謡曲の時代が終わって、この本で連打されるような歌と時代が添い寝する関係も消えた。そのことを寂しがる私は時代おくれか。
◆『イレナの子供たち』ティラー・J・マッツェオ/著(東京創元社/税別2800円)
ナチス占領下、多くのユダヤ人を救ったシンドラーは、映画にもなって有名。ティラー・J・マッツェオ『イレナの子供たち』(羽田詩津子訳)は、その女性版だ。福祉局勤務のポーランド人女性・イレナは、 ワルシャワのゲットーから、2500人ものユダヤ人の子供たちを救い出した。トラックの積み荷に隠し、あるいは下水道を使い、幼い命が生き延びた。彼女の勇気と行動力に感心するが、同時に、この計画に加わった多くの無名同志の存在も、本書では描かれる。瞠目(どうもく)のノンフィクション。
◆『鉄条網の世界史』石弘之・石紀美子/著(角川ソフィア文庫/税別960円)
石弘之・石紀美子『鉄条網の世界史』が面白い。居留地、収容所、戦地の前線と、外敵排除と暴力に加担する鉄条網。その歴史と使う人間の心理を、世界中を取材し明らかにした異色の世界史だ。フランスとアメリカでほぼ同時期に発明され、きわめてローテク、安価な商品として、またたくまに広がった。当初、開拓時代に家畜などを囲うため使われた。しかし、同時に先住民を締め出す暴力性を発揮し始める。分断が加速されていく世界の底に人類の冷酷さが潜むことを、鉄条網が教える。
◆『ある若き死刑囚の生涯』加賀乙彦・著(ちくまプリマー新書/税別840円)
加賀乙彦『ある若き死刑囚の生涯』は、1968年、横須賀線爆破事件で死刑囚となった青年の話。医師でもある著者は、東京拘置所医務技官を務め、犯人と接見している。彼の生い立ちから書き起こし、事件に至る過酷な人生を描き出す。彼は獄中で、純多摩(すみたま)良樹のペンネームで多数の短歌を詠み、日記をつづり、信仰を持った。死と向き合う穏やかな日々。「鉄扉ひらく音に心のさわだちぬ処刑の部屋につづく朝露」は彼の歌。75年12月死刑執行。懸命な短い人生は我々に何を教えるのか。
著名人が自身の人生を語り下ろす、この「のこす言葉」シリーズはいい。第3弾は『安野光雅 自分の眼で見て、考える』。絵本作家、エッセイストでも知られる画家は、今年93歳だという。
1926年、島根県津和野生まれ。小学生の頃「不登校児」というのが意外。ただ、「絵描きになりたい」とずっと思っていて、その「一本の線を、くねくねと軌道修正しながら辿ってきて今がある」と語り口はユニークでユーモアがある。戦後、玉川学園園長・小原と運命の出会いをして、道が開けた。
激動の時代を生きぬいた者としてのさまざまな提言もある。日本の教育は、何でも数字や順位で評価する。「自分の頭で考えることが大事です」と言う。『旅の絵本』シリーズが下描きなし、というのは驚いた。旅をして、実物を見た自信が独自の風景画を生んだ。
モットーにする言葉が「雲中一雁」。雁(がん)は群れて飛ぶが、離れて一羽でも飛ぶ。「しょせん一人」という覚悟が著者を支えた。
◆『レコード越しの戦後史 歌謡曲でたどる戦後日本の精神史』とみさわ昭仁・著(Pヴァイン/税別1800円)
改元でますます遠ざかる「昭和」の切り口は幾つもあるが、終戦後から変容する社会を映し出したのはレコードではないか。とみさわ昭仁『レコード越しの戦後史』は、それを証明して見せる。
戦後復興、高度成長、ヒーローや花粉症と、事件や流行の陰に、つねに歌謡曲が流れていた。戦後復興を象徴する「東京タワー」が完成した昭和33年、「東京333米」が出た。数字は高さ。歌うはミラクル・ヴォイス。
著者は珍レコードコレクターとしても知られるが、その強みが随所で生きている。昭和47年に帰還した日本兵・横井庄一さん。「お帰りなさい横井さん」というレコードが出ていた。中国残留孤児の歌も多数紹介され、著者は背景にある日中国交問題をちゃんと押さえている。戦後史と向き合う姿勢は真摯(しんし)で、貫く骨は太い。
歌謡曲の時代が終わって、この本で連打されるような歌と時代が添い寝する関係も消えた。そのことを寂しがる私は時代おくれか。
◆『イレナの子供たち』ティラー・J・マッツェオ/著(東京創元社/税別2800円)
ナチス占領下、多くのユダヤ人を救ったシンドラーは、映画にもなって有名。ティラー・J・マッツェオ『イレナの子供たち』(羽田詩津子訳)は、その女性版だ。福祉局勤務のポーランド人女性・イレナは、 ワルシャワのゲットーから、2500人ものユダヤ人の子供たちを救い出した。トラックの積み荷に隠し、あるいは下水道を使い、幼い命が生き延びた。彼女の勇気と行動力に感心するが、同時に、この計画に加わった多くの無名同志の存在も、本書では描かれる。瞠目(どうもく)のノンフィクション。
◆『鉄条網の世界史』石弘之・石紀美子/著(角川ソフィア文庫/税別960円)
石弘之・石紀美子『鉄条網の世界史』が面白い。居留地、収容所、戦地の前線と、外敵排除と暴力に加担する鉄条網。その歴史と使う人間の心理を、世界中を取材し明らかにした異色の世界史だ。フランスとアメリカでほぼ同時期に発明され、きわめてローテク、安価な商品として、またたくまに広がった。当初、開拓時代に家畜などを囲うため使われた。しかし、同時に先住民を締め出す暴力性を発揮し始める。分断が加速されていく世界の底に人類の冷酷さが潜むことを、鉄条網が教える。
◆『ある若き死刑囚の生涯』加賀乙彦・著(ちくまプリマー新書/税別840円)
加賀乙彦『ある若き死刑囚の生涯』は、1968年、横須賀線爆破事件で死刑囚となった青年の話。医師でもある著者は、東京拘置所医務技官を務め、犯人と接見している。彼の生い立ちから書き起こし、事件に至る過酷な人生を描き出す。彼は獄中で、純多摩(すみたま)良樹のペンネームで多数の短歌を詠み、日記をつづり、信仰を持った。死と向き合う穏やかな日々。「鉄扉ひらく音に心のさわだちぬ処刑の部屋につづく朝露」は彼の歌。75年12月死刑執行。懸命な短い人生は我々に何を教えるのか。
ALL REVIEWSをフォローする