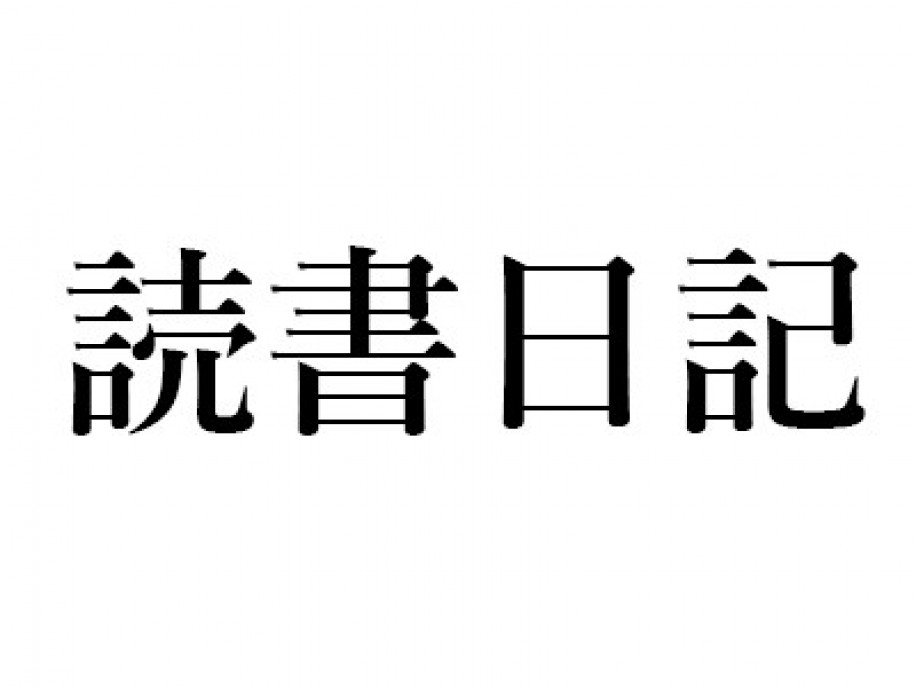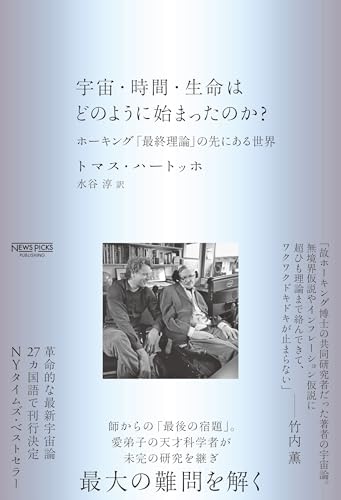書評
『砂戦争 知られざる資源争奪戦』(KADOKAWA)
身近で生活を支えるものの危機
子どもの頃の思い出には「お砂場」がつきものだ。水で少し湿らせてつくった山にトンネルを掘った仲間と両側から入れた手を握り合った時の嬉しかったこと。砂はいつも身近にあり、変わらないものとして存在していたのだ。天然資源の枯渇については多くが語られているが、ありふれたものの代表と思っていた砂が争奪戦の中にあり、「21世紀の最重要の資源のひとつとして注目を浴びている」ことは本書で初めて知った。
「砂がなければ私たちの日常が成り立たないところまで砂に頼りきった生活」の具体を見ていこう。最大の用途は砂をセメントで固めたコンクリートである。都会のビル群はまさに砂の固まりなのである。今日も世界の各地で建設されているであろうビルを思うと、砂の枯渇が現実味を帯びてくる。
次いで大きい用途が「埋め立て用土砂」と「工業用原料」であり、近年「オイルシェール掘削用」が急激に伸びているとのことだ。ガラス、鋳型などの他、パソコン、スマホ、デジタル家電製品に不可欠な半導体のシリコンも砂からとるのだ。
砂資源を巡る世界の動きを見よう。国連報告書によると、砂の使用は年に500億トンと、この20年間で5倍になっており、世界の川が運ぶ土砂の2倍にもなるとのことだ。500億トンは「高さ5メートル、幅1メートルの壁をつくると地球を125周する」量と聞くと恐ろしくなる。
21世紀は都市膨張の世紀と言える。とくに途上地域で著しく、人口1000万人以上のメガ都市が次々出現している。世界最大の都市は東京を中核とする首都圏で3700万人、次いでデリー2900万人、上海2600万人、サンパウロとメキシコシティの2200万人と続く。ここに高層ビルが建設されているのだ。ドバイに828メートル、上海に632メートルのビルが建ち、日本のあべのハルカス(300メートル)は169位というのだから、砂の消費の凄さがわかる。この急速な都市化は、交通渋滞、大気汚染に始まりスラム化や感染症の蔓延などの問題を生んでおり、決して好ましい生活に向かっているとはいえない。「砂上の楼閣」という言葉があるが、今や「砂の楼閣」が抱える大問題に向き合っているのだ。しかも世界はなお「砂の楼閣」をつくり続けている。主としてアジア、中東で起きている資源略奪の現場を訪れた著者の報告を見ていこう。
砂の消費量が最大なのは世界の6割となる中国だ。国内での採掘は長江沿岸で行われ、その結果1998年には被災者2億2000万人(全人口の5分の1)という大規模な洪水が発生した。2020年の大洪水では中流の鄱陽湖(はようこ)の堤防を人為的に壊すほかなく、6300万人が被災している。鄱陽湖は世界のソデグロヅルの9割が越冬するなど、東アジア最大の渡り鳥の越冬地である。国内での採掘が困難になり国連決議に反して北朝鮮から輸入を始めたとの情報もある。
同様に発展しているのがアラブ首長国連邦で、ドバイでは砂漠に莫大なコンクリートとエネルギーを使った虚構ともいえる空間をつくった。砂漠の砂は細かいうえに塩濃度が高くて骨材にはならず、砂はすべて輸入というのだから皮肉だ。アラビア湾には宇宙からも見える世界最大の人工島がある。アジアではジャカルタも同じ道を歩き、いずれの国でも砂マフィアが暗躍する。
日本では砂浜の砂はサンゴなどと同様「国有財産」で持ち帰り禁止ということをご存じだろうか。そのような国が増えているとのことで、気をつけなければいけない。そこで砂泥棒が横行している。毎年採掘される470億~590億トンの砂で合法取引は150億トンというのだから驚く。19年には「組織犯罪防止国際イニシアティブ」が「インドの砂マフィア」という報告書を出した。
それを支える労働者は日に200回以上潜りバケツですくった砂を小舟に積み込み、小舟1杯で5ドルの報酬という実態も辛い。しかもこれが平均賃金の4倍になるので、潜水病に苦しみながらも労働者が集まるのだ。この陰には「警察官や政治家など多くの公職者の汚職を生み出している。この問題を追及するジャーナリストは命の危険にさらされ」ているという実態がある。
ところで、白砂青松(はくしゃせいしょう)は日本人の原風景だが、実は砂浜は17~18世紀の新田開発による森林消失によって生み出されたものである。そこにススキやマツが勢力を伸ばして海岸の風景ができ上がった。しかし今や砂浜の典型とされた千葉県の九十九里浜でも海岸は突堤、波消しブロック、コンクリートで固めた駐車場という姿である。まず川砂が使われての高度成長だったが、70年代からは海砂も利用されたのである。
19年世界経済フォーラムは「地球は資源の収奪によって自然を危機的状況に追いやられ、持続不可能な状態に陥っている」と警告した。膨大なものと情報とに押し流されて息せき切って走り、水や空気や砂など身近で生活を支えているものまで危機に陥れ、私たちはどこへ行こうとしているのだろう。
ALL REVIEWSをフォローする