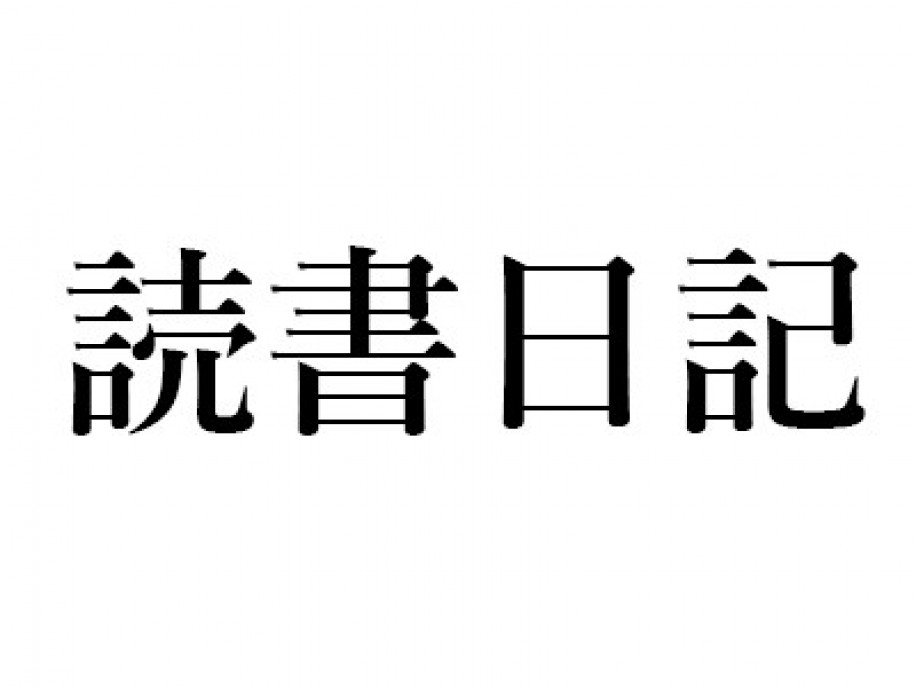書評
『三國志逍遙』(山川出版社)
鋭くえぐる歴史とゆったり描かれる風景
画家と中国文学者とのコラボ企画である。三国志といえば、関羽や張飛などの英雄、孔明などの軍師の活躍がよく知られ、その戦国ロマンを誘う物語は多くの人々に愛好されてきた。かくいう私もその一人であるのだが、画家の安野光雅もそこから出発し、彼らの足跡をたどって中国各地の風景を描いてきており、それらはすでに『繪本三國志』(朝日新聞出版)として出版されている。
中国文学の中村愿(すなお)は、中国の文学や歴史を探って『中国故景』(岩崎美術社)を著すなど、その文物・風物に多大の関心を示してきた。
この二人が連れ立って大陸を旅しながら、三国志の世界に思いを馳せて、成ったのが本書である。それぞれが独自に描き、記したものが合体して成っている。
その際、中村はこの逍遙(しょうよう)の旅を通じて、これまで親しまれてきた三国志の世界とは大きく違う歴史を考えてゆく。それは孔明の敵役ともいえる魏(ぎ)の曹操を高く評価し中心に据えることにあるが、折しも曹操の墓が発見されたというビッグニュースが飛び込んできたのも何かの縁であろう。
中村はその作業を三国志という歴史書の批判的考察に基づいて行う。三国志とはいうが、もともとその名がつけられていたのかも疑わしい。晋(しん)王朝の官僚であった陳寿が著したのは、『魏書』『蜀(しょく)書』『呉(ご)書』の三つであって、これが後に三国志として一括して捉(とら)えられるようになったのであり、やがて陳寿の考えとは全く違った形で享受されていった、という。
しかも約百五十年後に裴松之(はいしょうし)がこれに詳細な補注をつけ、それが本文と一緒に読まれるようになると、それ以来、曲解はさらに広がった。歴史家・陳寿の意図は全く変えられてしまい、誤りの多い史料をぶちこんだ、文体もなにもあったものではないものとなってしまった、と徹底的に批判する。
この影響を真っ向から受けたのが羅貫中(らかんちゅう)の『三国志演義』であって、今に我々が見るのは基本的に裴松之の補注が入っている本であるから、その補注を取り去って読まねばならない、という。
そこには曹操という詩人・政治家を復権させたいという狙いがある。陳寿は曹操を「非常の人、超世の傑」と評しており、革新的詩人としての評価はすこぶる高い。その曹操の動きを後世の無益な史料を入れた解釈ではなく、陳寿の記録文学としての記事をしっかりと追ってゆくならば、すぐれた政治家であったことがわかってくる。
こうして陳寿の『魏書』に沿って、漢王朝最後の皇帝であった献帝から曹操へ禅譲しようとした動きなどの政治の流れを追って、『魏書』の魅力をその著者の陳寿の文章からたっぷり描いてゆく。
そのためにユニークな工夫をこらした訳文を考えているのも興味深い。たとえば「晧は既に志に得と」という文章には、「そんこうはすでにねがいどおりにこうていのざにつくと」と読ませるようにルビを振るのである。慣れるまで若干とまどったが、おもしろい試みといえよう。
さてでは蜀の軍師で宰相の諸葛亮孔明への評価はどうなるか。当然のこと著しく低くなり、孔明が仕えた劉備(りゅうび)もまた小物とされてしまう。かの「出師(すいし)の表」などの内容もめためたに切られることになる。これまで我々が享受してきた三国志の世界はどこかにふっとんでしまった感がある。
このように政治家とは何か、歴史家とは何か、詩人とは何かと、鋭く迫る中村に対して、安野はその中村の主張とは別に独自の絵心から農村や都市、山や川など各地の風景をゆったりした筆致で描いている。
全七章のうち六章について、その章末に九十三枚もの絵が載せられており、まさに圧巻である。それぞれの絵には「黄河看戦」といった四字からなる標題が付され、それに「画家は絵の具の詩人だと思う。千変万化する母なる大河の表情を、安野さんは銀のひと刷(は)きで表わした」といった中村の解説がつく。
絵は三国志の世界に始まり、その世界の背景をなす悠久の大地を描くが、さらに「露天市場」といった都市の素顔なども描いて、見る者をとりこにしてしまう。中国に展開する安野ワールドといった感がある。
中村は安野の絵への解説に自らの主張を加えるのではなく、安野の気分をできるだけ理解しようと努めて書いており、相互の交流が窺(うかが)える工夫がなされている。
そこからは文学者の心と画家の心の違いと触れあいが浮かび上がってきて、実は三国志にはこの二つの世界が共存しているのである、と思えてきた。中村の熱く説く見方だけになると、儒教的世界一色になってしまう恐れもある。
絵を見、文章を読むうちに改めて三国志の世界の奥深さが見えてきた。もう一度、三国志を陳寿が書いたものに即して読んでみようかと思った。
ALL REVIEWSをフォローする