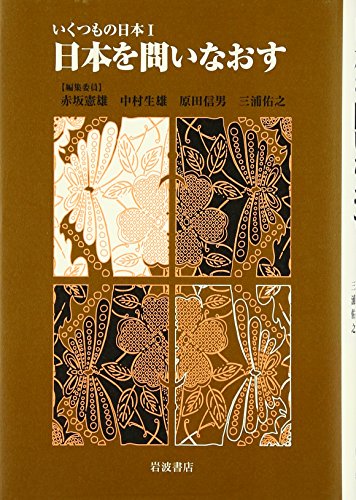書評
『シェバの女王: 伝説の変容と歴史との交錯』(山川出版社)
「魔女」から回心の原型、レゲエまで
人は伝説を求めて旅をし、作られた伝説は人を揺り動かす。シェバ(シバ)の女王の伝説は実にこのことをよく物語っている。『旧約聖書』に記されたシェバの女王は、南の国から多くの財宝や産品を積んで、智恵と富とで名高いイスラエルの王ソロモンを訪ねてきて、質問を浴びせた。それらにソロモンがことごとく答えたので、女王はそれを讃えて財宝を贈ったところ、ソロモンもそれに応え、女王の願うものは何でもあたえたので、それらを積んで女王は故国に帰っていったという。
このわずかな記事から伝説は様々に派生してゆくことになる。シェバの実在をめぐって、アラビア半島の南であるイエメン付近をあてる説が出され、アフリカのエチオピア辺をあてる説が出されるなど、史実性については疑問符がつくが、そのなかで伝説は様々な形で広がっていったのである。
その想像を超えた広がりに著者は関心を抱き、伝播(でんぱ)した先の文化的・歴史的状況に応じて、いかに独自の変容を遂げていったかを明らかにすることを目指したのである。
シェバの女王といえば、妖艶なジーナ・ロロブリジーダの演じる『ソロモンとシバの女王』という映画や、ミッシェル・ローランのシャンソン「サバの女王」程度の知識しかない私も、読んでゆくなかでその伝説の広がりと伝説が人を動かす力には驚かされた。
まずユダヤ教に持ち込まれたシェバの女王の話では、女王は毛深い女、人を試す行動的な女というイメージで捉えられ、アンチ・ヒロインの扱いを受け魔女として見られるようになったという。
ところがイスラム世界に持ち込まれると、違った形をとった。『コーラン』によれば、この話は女王が太陽神崇拝を捨てて万有の神アッラーにすべてを捧げるという回心の話とされ、マイナスイメージで語られてはいない。
さらにキリスト教世界になると、女王は悔い改めて回心する異教徒の原型とみなされ、ソロモンと女王の関係は、キリストと教会との関係を予(あらかじ)め示したものとして捉えられるようになった。その積極的な評価から、中世のヨーロッパでは女王像は広く描かれていった。
そしてエチオピアでは、さらに王朝の正統性や民族のアイデンティティのより所にまで女王の伝説がその地位を獲得した。
すなわち女王はイスラエルの神に帰依したのだが、ソロモンの奸計によって子を身ごもり、帰国して息子を出産した。その子はソロモンを訪ねてエチオピアに王国を建てるように命じられると、神殿に安置されているモーゼが神から授かったという十戒の石板を納める聖櫃(せいひつ)を盗み出し、エチオピアに正統なる王国を建設したという。
この話は十四世紀に成立したエチオピアのソロモン朝の正統性を物語る話として迎えられただけでなく、アフリカから連れてこられた奴隷の末裔としてのアメリカの黒人にも受容された。ラスタファリ(エチオピア最後の皇帝ハイレ・セラシェのこと)運動である。
これは奴隷からの解放とともに約束の地であるエチオピアに帰還することを望むもので、さらにその運動の進展とともに、ボブ・マーリィによるレゲエという音楽が生まれたという。
このような南の豊かな国の女王の魅惑的な話は、その内容からして、もっと面白く書けるようにも思えるが、著者は丹念に、かつ冷静に跡づけて、説得力あるものに仕上げている。
ALL REVIEWSをフォローする