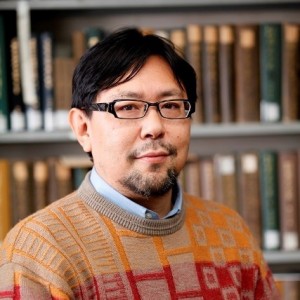書評
『古写真で見る幕末の城』(山川出版社)
武士の世の象徴である城の栄枯盛衰を思う
会津の白虎(びゃっこ)隊の悲劇はあまりにも有名である。飯盛山から鶴ヶ城が燃えるのを見た少年たちは、その場で次々と自害していった。実は城は落ちておらず、炎は城下町の火災により生じていた。だが、それが誤認であったにせよ、彼らの絶望感は紛れもなく本物だった。日ごろ行き来した門、頼もしく感じた堀に石垣、振り仰いだ天守閣。鶴ヶ城は彼らにとって、ふるさと会津そのものだったに相違ない。日本列島における東京一極集中の是非が論じられる昨今だが、地方に目を転じると、県庁所在地への一極集中という状況がある。県庁所在地は活力を保っているが、第二、第三の町は人口が減少し、繁華街はシャッター通りになった。そんな町を訪れたときにお城を見つけると、整備したら観光資源にできないかな、住民のみなさんの愛郷心のよりどころにならないかな、とよそ者の私は夢想する。
本書は江戸末・明治初めの城郭の様子を、多くの貴重な写真を丁寧に集めて、読者に伝えるものである。もちろん、掲載された建物の多くは、そののち失われて今はない。だからページをめくりながら、ああもったいない、とため息が出る。これらが残っていれば、と。だが、富国強兵という重い試練を課せられた先人たちは、乗り越えるべき「武士の世」の遺物を保存する余裕を持てなかったのだろう。あるいは、人々が競って寺院と仏教文化財を破壊した廃仏毀釈(きしゃく)を想起すると、特権的な武士を象徴する城郭の破壊に、新たに台頭した庶民は、積極的に関わったのかもしれない。
歴史への認識が成熟していなかったのか、現実の厳しさが優先したのか、武士への批判が作用したのか。そんなことも考えながら、「城のある町」に思いを馳せてみてはいかがだろう。
ALL REVIEWSをフォローする