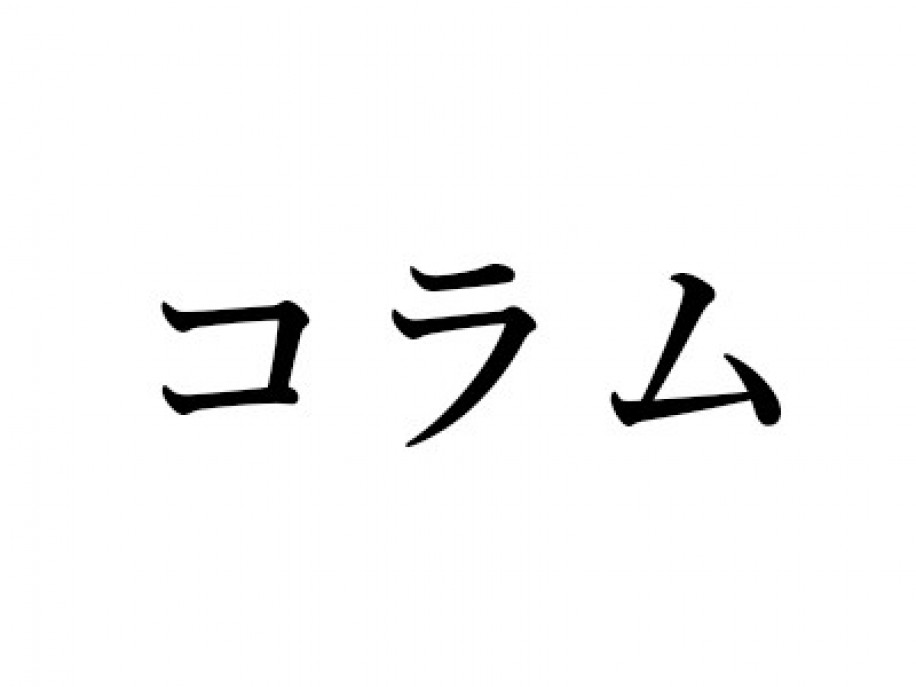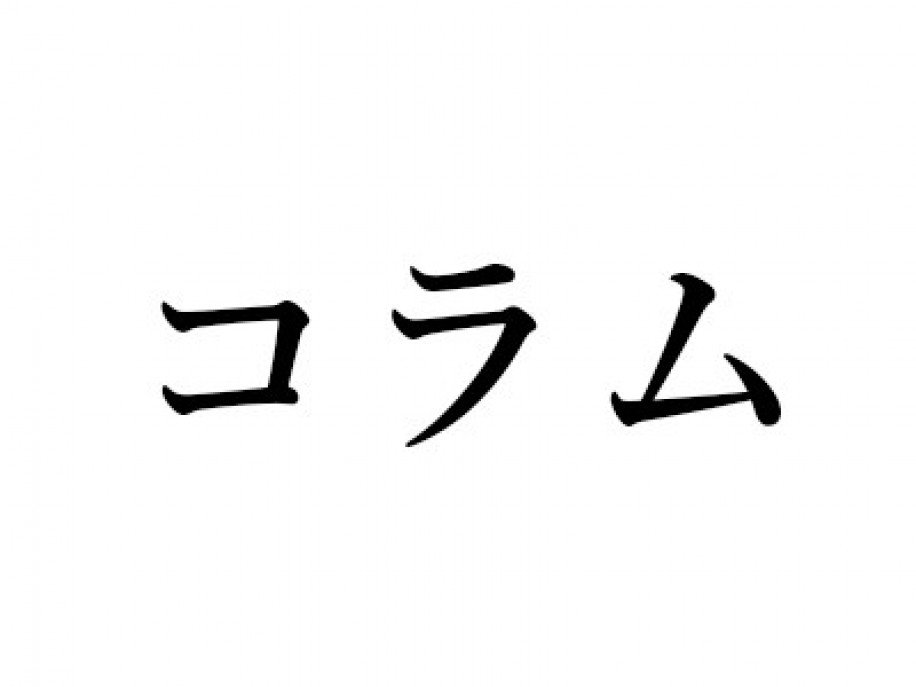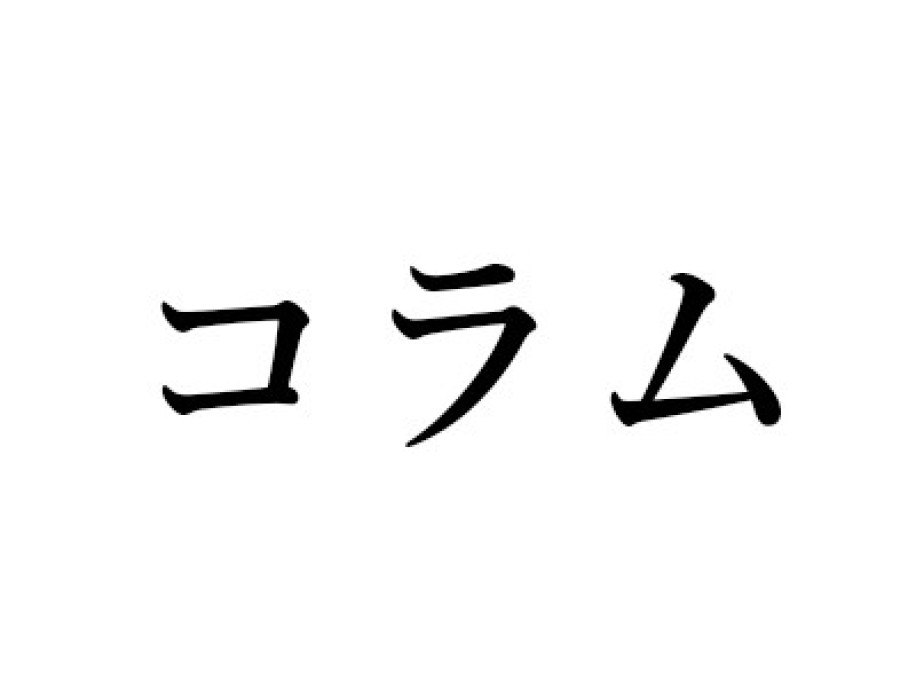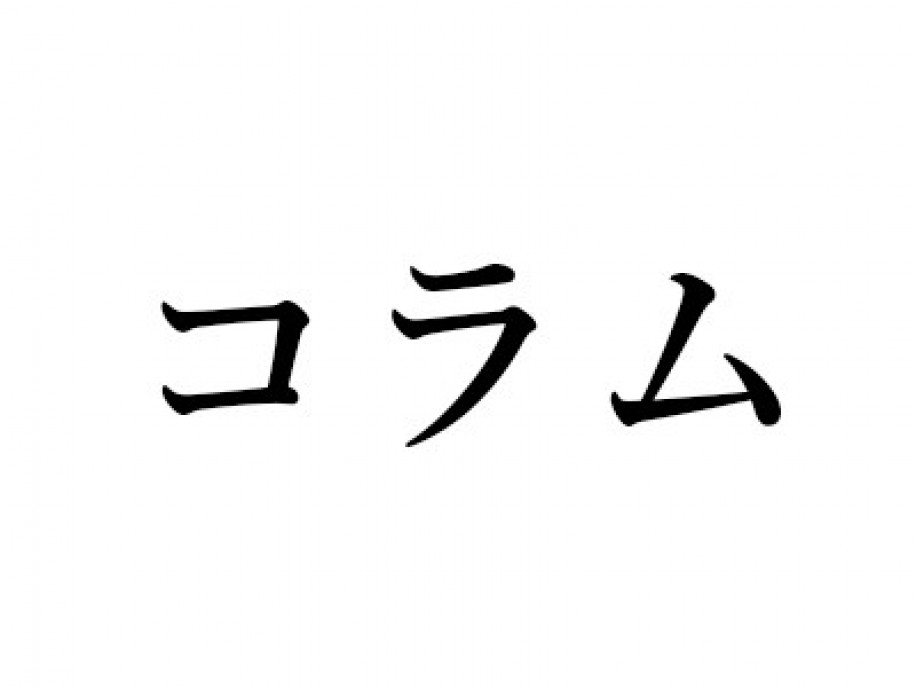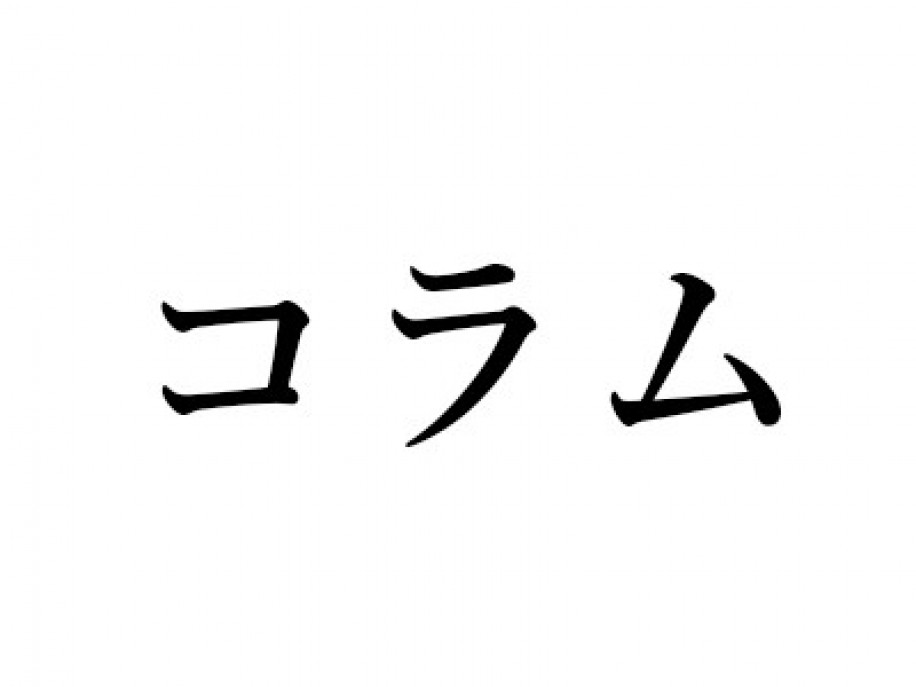コラム
筈見恒夫『映画五十年史』(鱒書房)、高橋健二訳『ゲーテ恋愛詩集』(郁文堂)ほか
なぜ本は一極集中するか
公民館に呼ばれて、北陸は能登半島の付け根の某市に出かけた。小松空港で降りて、とりあえず金沢に入る。久しぶりの金沢だ。大学時代に二回、この町に来た。一人で卯辰山のユースホステルに何泊もし、犀川のほとりで室生犀星を思った。泉鏡花や中野重治のことを考えてだらだらと時をすごした。今回は子どもをおいての一泊だから、町をあわただしくレンタサイクルで走ってみる。二十年ぶりというのに、よそ者の目には町はそう変わらないように映った。ふと「森八」本店の前に出た。種村季弘さんが、「森八」前に南洋堂という古本屋があり、どうしてもそちらに寄ってしまうため、「森八」にたどりつけずお菓子をお土産にできない、という話を思い出した。
あったあった、これが南洋堂だ。じつになんてことのない構えだ。それでもうれしくて両側からのしかかるような本棚の前をうろうろした。ゆっくり探せば戦前の落語や邦楽の雑誌のバックナンバーなどみつかりそうだった。北陸の地域史の本もけっこうある。そんなことをしているとすぐ二、三時間たつだろう。もう暗くなりかけている。私がつと棚から引いたのは筈見恒夫『映画五十年史』(鱒書房、昭和十七年)。これが二千四百円は安い。真珠湾急襲の直前に筆はとられ、憂鬱な世相の中で、映画という「永遠に色褪せぬ恋人」に心を踊らせている。福宝堂の日暮里撮影所の記述もあるし、もしかすると谷中辺の寺や庭園を借りてのロケではないかといった写真も多く入っているので即座に買った。
店の奥で、コタツにあたって店番をしていた若奥さんは、「最近、種村先生のご本を読んでたずねて見える方がたまにありますねえ」とりんごのように赤い頬をほころばせた。われながらミーハーだなあ、とあきれつつ、奥付に「南洋堂書林」の古い丸い印を押してもらった。
ここでは千円につき一枚文庫本の券をくれる。つまり二枚。「そこの棚のお好きなのをどうぞ」というので、興津要さんの落語の本を一冊、そしておやっと思って『ゲーテ恋愛詩集』を手にとった。高橋健二訳、郁文堂、昭和二十三年百二十円。これはめっけもの。旅の道連れになる。
昔、習い覚えたリートがきれいな言葉になっている。私は唯一ドイツ語で歌える曲を口ずさみながら金沢の町を走った。
野に咲くすみれ
うなだれて草かげに
やさしきすみれ
うら若き羊飼いの女
心も空に足かろく
歌を歌いつ
野を来れば(「すみれ」)
この本は一生恋ばかりして、七十四歳で十九のウルリーケに求婚してフラれたりしたゲーテの詩を、時代別、つまり女性別に配列しているのが面白い。ケーチヒェン時代、フリーデリケ時代、リリー時代、シュタイン夫人時代……という風に。訳者によると、ゲーテの主な作品はすべて恋の告白とざんげであり、恋の喜びと怯(ひる)みと反省と戦いと超克と諦念こそが、ナポレオンが会ったとき「これこそ人間だ」と叫ばざるをえないようなゲーテを形成したのだそうである。ふーむ。
「恋人から遠く離れていると幸福はいつもなお一層大きい」。響く言葉である。
どこに行っても、彼女を忘れることができない
だが、わたしは落ちついて食事をし
わたしの精神はほがらかに自由だ(「離れている幸福」)
「恋を尊敬にし、欲情を熱中にする」かくあらまほし。と私は自転車を捨て、文庫本をポケットに金沢の町をあてもなく歩いた。
目の前にいれば、意識しない
別れてみて、驚いて自覚する
離れれば、うしろ髪をひかれる
いなくなって始めて貴さがわかる
七十四の男が歌っている。しかし、だれが笑うことができよう。
わたしたちが愛しあっていることを人がとがめても
わたしたちは暗い気持になってはならない
とがめだてに力はない
ほかのことなら知らぬこと
否認やこごとは
愛を非難すべきものにはしない
一八二一年の話だ。百七十年たっても人間の感情は変わらない。いやになる。
「本の力」を信じて翌日、海沿いに車で走って某市へ向かった。講演前、公民館の館長さんが自室に案内して下さった。本だらけである。これほど本が積み上がった部屋をみたことがない。
「本がよほどお好きなんですねえ」と私は開口一番そういった。快活な館長さんはいう。
「そうじゃないんですよ。うちの市は人口五万もいませんが、まだ図書館が一つもないんです。市の図書購入予算が、年に二十万くらい。で、一家で一冊運動というのをしてましてね。各戸一冊ずつ寄付して頂いて図書館を作ろうというので、とりあえずここに集めて私が整理してるんですが、つい読んじゃってね、なかなか進みませんワ」
なるほど。そういえばバラバラな雑本の感はあったのだ。ここで私は二十万しか図書費をつけない市にあきれたのではない。反射的に頭に浮かんだのは、私の町の図書館の廃棄本の山である。私の住む区は十七万の人口に十館も図書館があり、新刊をどんどん入れる一方、大量に本を捨てざるを得ないのである。捨てる中から館員さんに見ないフリをしてもらって、M・トレーズ『人民の子』や渋谷定輔『農民哀史』をひき抜いてきた。利用度の低いことが廃棄の一つの条件なので、ベストセラーは残るが、手に入りにくい大事な本が捨てられやすい。絶版のアラゴン『レ・コミュニスト』も知らないうちに棚から消えていた。
反対に某市で家から寄贈で出てくる本は読みすてのベストセラーが大半だ。それは当り前のことだろう。うちの区の廃棄本をここに持ってきた方がいい図書館ができそうだ、と失礼なことをふと思った。その次の瞬間には、余り物の衣類を施設に送りつけて、自分はつぎつぎ新しい服に目移りする「有閑マダム」と同じようなことを考えつく自分に腹を立てた。
だいたい、二十万円というのは私の年間書籍代より少ない。本当かしら。私の区には書庫を持っている住民も多く、区内に眠ったり飾られている本全体を考えると気が遠くなると図書館員がいっていた。そんな区に十館もあるのになァ。
やっぱり、あの廃棄本でもいいから欲しいところだ。井上ひさし氏のように、どっと蔵書を寄贈してくれるこの市出身の作家や文化人はいないかな。仲間に声をかけて、本を集めて段ボール箱で送ろうか。出番を待っている間、くだらぬアイデアをいろいろ考えた。
一極集中、ということがさまざまな形で現われる。東京はゴミ処理場や老人ホームを地方に押しつけてくる。東京は経済が活発で、高所得者が多ければ税収も多いから図書館も建つ。本も買える。過密と過疎、中央と地方の構造的問題を解決しなければ、図書館一つ満足にできないのだ。
そんなことを考えて壇に昇ったせいか、その日の出来はさんざんだった。「中央」である東京から来て突然、町づくりについて語るなんて、おこがましくて、恥ずかしくて、白けてしまったからである。
【このコラムが収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする