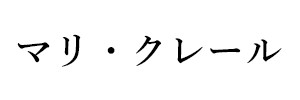コラム
ジャン=ポール・サルトル 『奇妙な戦争―戦中日記』(人文書院)、エーリッヒ・ケストナー『ケストナーの終戦日記』 (福武書店)
この二つのまったく異質な日記には、ひとつ共通点がある。もちろん第二次大戦下の生なましい局面を皮膚でじかに触れている場所から記述されていることだ。だがわたしがいいたいのはそういう記述の環境のことではない。戦争が頭上を通り過ぎようが、兵士として巻きこまれようが、要監視の人物として間近にさし迫ろうが、国家の戦争行為とは次元のちがったところに一個の私人として居るという記述の場所を、はっきりとした輪郭でもっている。これは日本のどんな文学者や哲学者ももつことができないことだ。たぶん日本人が(一般に東洋人が)全般的に貫けなかった場所だといって過言ではない。このことが印象深かったので、はじめに記しておきたい。
あとはこの二つの日記のちがいを強調すればよさそうだ。
サルトルの日記は「軍服を着ているにもかかわらず」顔には「一種ののどかさが漂っている」応召兵として、戦闘が一触即発で起こりかねない緊張した時期に、前線で書き記されている。じぶんの幼時を回顧したり、『嘔吐』や『壁』を書いたときの気分や、その作品の運命を語ってみたり、同僚の応召兵の性格を論じてみたり、哲学上の思考の演習(たとえば意志論)をメモしてみたりといった、平時と変らない壮年期の私的な形成が語られている。サルトルには、どうせ戦争の中に投げ入れられたのだから、最大限のペテンと策略の力を見とどけないうちに、終ったらつまらないといった余裕がただよっている。つまり戦争は、修道院のなかのおなじことが繰返される日常の精進の場だという意味を、一面でもっていたことがとてもわかる。その中でもとくにわたしを感心させたことは、少なくともふたつの点だ。ひとつは応召兵は、銃後の民間人に賛嘆と感謝を要求する権利があると思いこむか、さもなければ経験者の特権に化けて、いや戦争など大したもんでないですよ、怖ろしがるのは傍観者だからだといいたがるか、どちらかになるので、じぶんはその何れでもない態度を見つけ、そこに位置したいと述べているところだ。もうひとつは『分別ざかり』をタイプしてくれた愛人ボーヴォワールの妹が、サルトルの作品の主人公は、暗くてやりきれないといったと、間接的に聴かされてショックをうけ、紙の中に棲むロカンタンやマチューは「生の原則を抜き取られた私」なのだと弁解している個所だ。愛人の妹からあの人は暗い人相ばかり考えているひとだといわれて、私と私の小説の主人公とはちがう、だがひとはなぜ暗い人物を造型するかといったことを、サルトルは懸命にかんがえこんでいて、とても愉しくなる。人間の思想や感情のなかには「恐るべき悲哀をつくり出す力が、しかるべき場所におさまって」いて、統合的な全体性が保たれているあいだは顔を出さないが、全体のシステムが崩れると低次な諸構造が氾濫してくるのだと、サルトルは論理づけている。わたしが読むとこの個所が日記のなかで、いちばん印象深い個所のようにみえる。そしてサルトルがマジノラインの内側で、応召兵として任務についていた時期までのことでいえば、戦争はサルトルの思想形成と、文学的な成熟にとって、決定的な意義をもっていたことがわかる。日記では「私をこの道に置いてくれたのは戦争とハイデッガーだ」(四〇年三月十一日 月曜)と記している。これは滅多に手に入らない偶然の時間を、サルトルが手にしていたことを意味している。
ケストナーの日記は、まったくサルトルとちがっている。離ればなれに住んでいる母親や親戚や友人の消息についての個人的な心配は、いたるところにはめこまれているが、大部分は西からはアメリカ軍が、東からはソ連軍が刻々と迫ってくるのを、ナチスから要監視の人物として睨まれていながら、ドイツ人としては国家の敗北を悲しむ情念も呼びおこされるといった矛盾のなかで受けとめている記述の場所が、ケストナーの日記の主調音として聴こえてくる。そして痛ましい思いをさせるのは、つぎつぎとアメリカ軍とソ連軍の進撃にさらされた都市では、ナチスの大官とその部下の都市管理者のあいだに内紛と殺し合いが起って自壊してゆく有様が、描かれていることだ。日本でも沖縄でそんなことがあって、現在でも傷のあばき合いがあるが、もし本土全体で陸戦が行なわれていたら、きっと同じことが起っていたことが、ケストナーの記述からひしひしと伝わってくる。そしてその民族的な情動の類似性まで思い起される気がした。
「暴行が行なわれていること(ソ連侵攻軍による――註)、ベルリンでもごく近いうちに行なわれるだろうということを、女たちは疑ってなぞいない。だが、女たちは同時に、そういう報道によって行なわれる偽りの愛国的宣伝に気づいている。それが女たちを憤慨させる」(ベルリン、一九四五年二月十二日)という記述の場所が、ケストナーの日記の場所であり、同時にごくふつうのドイツの民衆の場所だったことが、この日記を読むととてもよくわかる。これもまた、ソ連軍が侵攻してきた中国東北区で局部的に日本人が体験したことだった。サルトルの日記にはないことだが、まだ侵攻をうけていない領土を次第に連合軍からせばめられて、呼吸する空間がベルリン郊外だけになってしまうようなひっ迫した息使いまでが、文体のあいだから伝わってくる。ナチス・ドイツの第一級の大官が第二級の大官を、戦わないで降伏する気配だと猜疑心を燃やして処刑する。そういう陰惨なドラマを、侵攻する連合軍を眼のまえにして、それぞれの都市が繰返しながら、ナチス・ドイツは破局にむかってゆく。ケストナーは、このドラマは「最後から一つ手まえの処置」で、最後の処置は第一級のものが誰かに首を絞められることだと、冷静に書き記している。
やがてアメリカ軍はライプチヒに迫り、ソ連軍はドレースデンに迫って、ベルリンは孤立する(四月二十一日)。そしてヒトラーは五十六回目の誕生日を迎えるが、ケストナーはそれがヒトラーの「最後の誕生日か、最後の誕生日だ」と悪意をこめて記している。
サルトルの戦中日記を西欧的なものの晴れた日々の極限とすると、ケストナー敗戦日記は西欧の陰陰とした日々の極限をさしているようにおもえる。いわば第二次大戦下の西欧の光と影の極限の振幅が、この二つの日記に象徴されている。わたしたちの第二次大戦の体験は、これにくらべるとあいまいな皮膜におおわれて、光も影もちいさく、犠牲だけが多かったようにおもえてならない。
【このコラムが収録されている書籍】
あとはこの二つの日記のちがいを強調すればよさそうだ。
サルトルの日記は「軍服を着ているにもかかわらず」顔には「一種ののどかさが漂っている」応召兵として、戦闘が一触即発で起こりかねない緊張した時期に、前線で書き記されている。じぶんの幼時を回顧したり、『嘔吐』や『壁』を書いたときの気分や、その作品の運命を語ってみたり、同僚の応召兵の性格を論じてみたり、哲学上の思考の演習(たとえば意志論)をメモしてみたりといった、平時と変らない壮年期の私的な形成が語られている。サルトルには、どうせ戦争の中に投げ入れられたのだから、最大限のペテンと策略の力を見とどけないうちに、終ったらつまらないといった余裕がただよっている。つまり戦争は、修道院のなかのおなじことが繰返される日常の精進の場だという意味を、一面でもっていたことがとてもわかる。その中でもとくにわたしを感心させたことは、少なくともふたつの点だ。ひとつは応召兵は、銃後の民間人に賛嘆と感謝を要求する権利があると思いこむか、さもなければ経験者の特権に化けて、いや戦争など大したもんでないですよ、怖ろしがるのは傍観者だからだといいたがるか、どちらかになるので、じぶんはその何れでもない態度を見つけ、そこに位置したいと述べているところだ。もうひとつは『分別ざかり』をタイプしてくれた愛人ボーヴォワールの妹が、サルトルの作品の主人公は、暗くてやりきれないといったと、間接的に聴かされてショックをうけ、紙の中に棲むロカンタンやマチューは「生の原則を抜き取られた私」なのだと弁解している個所だ。愛人の妹からあの人は暗い人相ばかり考えているひとだといわれて、私と私の小説の主人公とはちがう、だがひとはなぜ暗い人物を造型するかといったことを、サルトルは懸命にかんがえこんでいて、とても愉しくなる。人間の思想や感情のなかには「恐るべき悲哀をつくり出す力が、しかるべき場所におさまって」いて、統合的な全体性が保たれているあいだは顔を出さないが、全体のシステムが崩れると低次な諸構造が氾濫してくるのだと、サルトルは論理づけている。わたしが読むとこの個所が日記のなかで、いちばん印象深い個所のようにみえる。そしてサルトルがマジノラインの内側で、応召兵として任務についていた時期までのことでいえば、戦争はサルトルの思想形成と、文学的な成熟にとって、決定的な意義をもっていたことがわかる。日記では「私をこの道に置いてくれたのは戦争とハイデッガーだ」(四〇年三月十一日 月曜)と記している。これは滅多に手に入らない偶然の時間を、サルトルが手にしていたことを意味している。
ケストナーの日記は、まったくサルトルとちがっている。離ればなれに住んでいる母親や親戚や友人の消息についての個人的な心配は、いたるところにはめこまれているが、大部分は西からはアメリカ軍が、東からはソ連軍が刻々と迫ってくるのを、ナチスから要監視の人物として睨まれていながら、ドイツ人としては国家の敗北を悲しむ情念も呼びおこされるといった矛盾のなかで受けとめている記述の場所が、ケストナーの日記の主調音として聴こえてくる。そして痛ましい思いをさせるのは、つぎつぎとアメリカ軍とソ連軍の進撃にさらされた都市では、ナチスの大官とその部下の都市管理者のあいだに内紛と殺し合いが起って自壊してゆく有様が、描かれていることだ。日本でも沖縄でそんなことがあって、現在でも傷のあばき合いがあるが、もし本土全体で陸戦が行なわれていたら、きっと同じことが起っていたことが、ケストナーの記述からひしひしと伝わってくる。そしてその民族的な情動の類似性まで思い起される気がした。
「暴行が行なわれていること(ソ連侵攻軍による――註)、ベルリンでもごく近いうちに行なわれるだろうということを、女たちは疑ってなぞいない。だが、女たちは同時に、そういう報道によって行なわれる偽りの愛国的宣伝に気づいている。それが女たちを憤慨させる」(ベルリン、一九四五年二月十二日)という記述の場所が、ケストナーの日記の場所であり、同時にごくふつうのドイツの民衆の場所だったことが、この日記を読むととてもよくわかる。これもまた、ソ連軍が侵攻してきた中国東北区で局部的に日本人が体験したことだった。サルトルの日記にはないことだが、まだ侵攻をうけていない領土を次第に連合軍からせばめられて、呼吸する空間がベルリン郊外だけになってしまうようなひっ迫した息使いまでが、文体のあいだから伝わってくる。ナチス・ドイツの第一級の大官が第二級の大官を、戦わないで降伏する気配だと猜疑心を燃やして処刑する。そういう陰惨なドラマを、侵攻する連合軍を眼のまえにして、それぞれの都市が繰返しながら、ナチス・ドイツは破局にむかってゆく。ケストナーは、このドラマは「最後から一つ手まえの処置」で、最後の処置は第一級のものが誰かに首を絞められることだと、冷静に書き記している。
やがてアメリカ軍はライプチヒに迫り、ソ連軍はドレースデンに迫って、ベルリンは孤立する(四月二十一日)。そしてヒトラーは五十六回目の誕生日を迎えるが、ケストナーはそれがヒトラーの「最後の誕生日か、最後の誕生日だ」と悪意をこめて記している。
サルトルの戦中日記を西欧的なものの晴れた日々の極限とすると、ケストナー敗戦日記は西欧の陰陰とした日々の極限をさしているようにおもえる。いわば第二次大戦下の西欧の光と影の極限の振幅が、この二つの日記に象徴されている。わたしたちの第二次大戦の体験は、これにくらべるとあいまいな皮膜におおわれて、光も影もちいさく、犠牲だけが多かったようにおもえてならない。
【このコラムが収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする