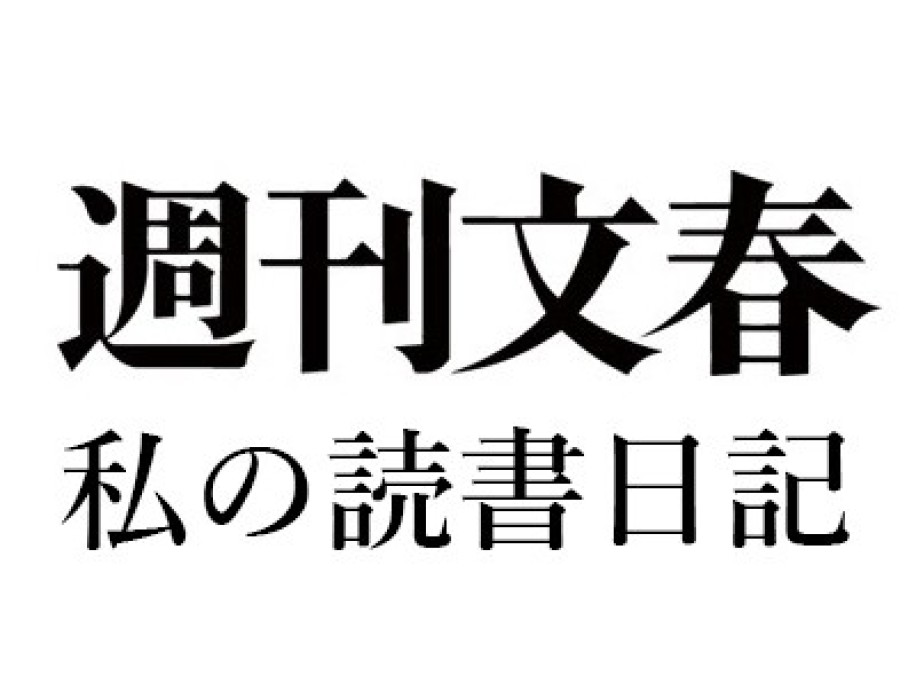書評
『サルトルの世紀』(藤原書店)
今年はサルトル生誕百年にあたる(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆年は2005年)。
パリの巨大な国立図書館では「サルトル展」が開かれている。大規模な展覧会だが、新しい知見を示すより、「最後の文化英雄サルトル」のイメージを盛りあげる演出が露骨で、逆に、文化英雄のいない現代の不安がすけて見える。かつての沢田研二の歌を借りるなら、「サルトル、あんたの時代は良かった」というわけである。
実際、二十世紀はサルトルの時代だった。B=H・レヴィによれば、「サルトルとは、世紀を縦断し、世紀の中に呑み込まれるあらゆるやり方が一堂に会する場」だったからだ。
一九〇五年に生まれたサルトルは、小説『嘔吐』で「実存」という観念をうちだし、西欧哲学の長い歴史にあと戻りのきかない亀裂を入れた。第二次世界大戦後のパリでは、実存主義のチャンピオンとして、あらゆる文化領域に君臨し、その講演は観客の失神や暴動の場と化した。のちのロックのコンサートのように。
サルトルの名声は世界的になり、彼は積極的にデモや政治活動に参加する。そう、参加(アンガージュマン)というフランス語が世界の若者の合言葉となった。そして、彼はマルクス主義を標榜し、革命の実現を信じて戦った。
しかし、社会主義が無残に崩壊したいま、サルトルの理想は失効し、挫折した英雄へのノスタルジーが回顧展を包んでいる。だが、そんな風潮に逆らって、レヴィと海老坂武はサルトルの再生を試みる。ただし、正反対の方向から。
レヴィは、二人のサルトルがいた、という。若いサルトルとその後のサルトル。若いサルトルは、『嘔吐』や『存在と無』で、物の実存を探求し、人間中心主義の哲学を破壊した。つまり、一九七〇年代以降の、構造主義と呼ばれる反人間主義的な哲学の潮流を創ったのは、サルトルなのだ。構造主義の流行の三十年も前に。
レヴィの論証は圧倒的で、確かにサルトルが二十世紀哲学の転回点なのだと思えてくる。「実存は本質に先立つ」という彼の言葉とともに、知はポストモダンの時代に入っていたのだ。
では、その後のサルトルは? 物(実存)を捨て、人間(本質)の立場に立った。人間をより良く変え、より良い社会の実現=革命が可能だと信じた。だが、そうしたより良い人間への信仰こそが、収容所列島、文化大革命、ポル・ポト派の虐殺につながるとレヴィはいう。サルトルもまた同じ道に踏み迷っていった。
一方、海老坂武は、そんな反人間主義の先駆としてサルトルを再評価されたのではたまらない、と叫ぶ。著書の副題にもあるとおり、サルトルの関心の中心は一貫して人間であり、彼は、「人間はどこまで人間でありうるか」という問いを極限まで生きた人間なのだ、と。
レヴィが思想史的に新たなサルトル像を築いたとすれば、海老坂武は個人的体験としてこそ生きるべきサルトルというドラマを熱く描いてみせる。この二冊を補完的に読むことで、サルトルの真実はいっそう厚みをますことだろう。
パリの巨大な国立図書館では「サルトル展」が開かれている。大規模な展覧会だが、新しい知見を示すより、「最後の文化英雄サルトル」のイメージを盛りあげる演出が露骨で、逆に、文化英雄のいない現代の不安がすけて見える。かつての沢田研二の歌を借りるなら、「サルトル、あんたの時代は良かった」というわけである。
実際、二十世紀はサルトルの時代だった。B=H・レヴィによれば、「サルトルとは、世紀を縦断し、世紀の中に呑み込まれるあらゆるやり方が一堂に会する場」だったからだ。
一九〇五年に生まれたサルトルは、小説『嘔吐』で「実存」という観念をうちだし、西欧哲学の長い歴史にあと戻りのきかない亀裂を入れた。第二次世界大戦後のパリでは、実存主義のチャンピオンとして、あらゆる文化領域に君臨し、その講演は観客の失神や暴動の場と化した。のちのロックのコンサートのように。
サルトルの名声は世界的になり、彼は積極的にデモや政治活動に参加する。そう、参加(アンガージュマン)というフランス語が世界の若者の合言葉となった。そして、彼はマルクス主義を標榜し、革命の実現を信じて戦った。
しかし、社会主義が無残に崩壊したいま、サルトルの理想は失効し、挫折した英雄へのノスタルジーが回顧展を包んでいる。だが、そんな風潮に逆らって、レヴィと海老坂武はサルトルの再生を試みる。ただし、正反対の方向から。
レヴィは、二人のサルトルがいた、という。若いサルトルとその後のサルトル。若いサルトルは、『嘔吐』や『存在と無』で、物の実存を探求し、人間中心主義の哲学を破壊した。つまり、一九七〇年代以降の、構造主義と呼ばれる反人間主義的な哲学の潮流を創ったのは、サルトルなのだ。構造主義の流行の三十年も前に。
レヴィの論証は圧倒的で、確かにサルトルが二十世紀哲学の転回点なのだと思えてくる。「実存は本質に先立つ」という彼の言葉とともに、知はポストモダンの時代に入っていたのだ。
では、その後のサルトルは? 物(実存)を捨て、人間(本質)の立場に立った。人間をより良く変え、より良い社会の実現=革命が可能だと信じた。だが、そうしたより良い人間への信仰こそが、収容所列島、文化大革命、ポル・ポト派の虐殺につながるとレヴィはいう。サルトルもまた同じ道に踏み迷っていった。
一方、海老坂武は、そんな反人間主義の先駆としてサルトルを再評価されたのではたまらない、と叫ぶ。著書の副題にもあるとおり、サルトルの関心の中心は一貫して人間であり、彼は、「人間はどこまで人間でありうるか」という問いを極限まで生きた人間なのだ、と。
レヴィが思想史的に新たなサルトル像を築いたとすれば、海老坂武は個人的体験としてこそ生きるべきサルトルというドラマを熱く描いてみせる。この二冊を補完的に読むことで、サルトルの真実はいっそう厚みをますことだろう。
朝日新聞 2005年07月24日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする