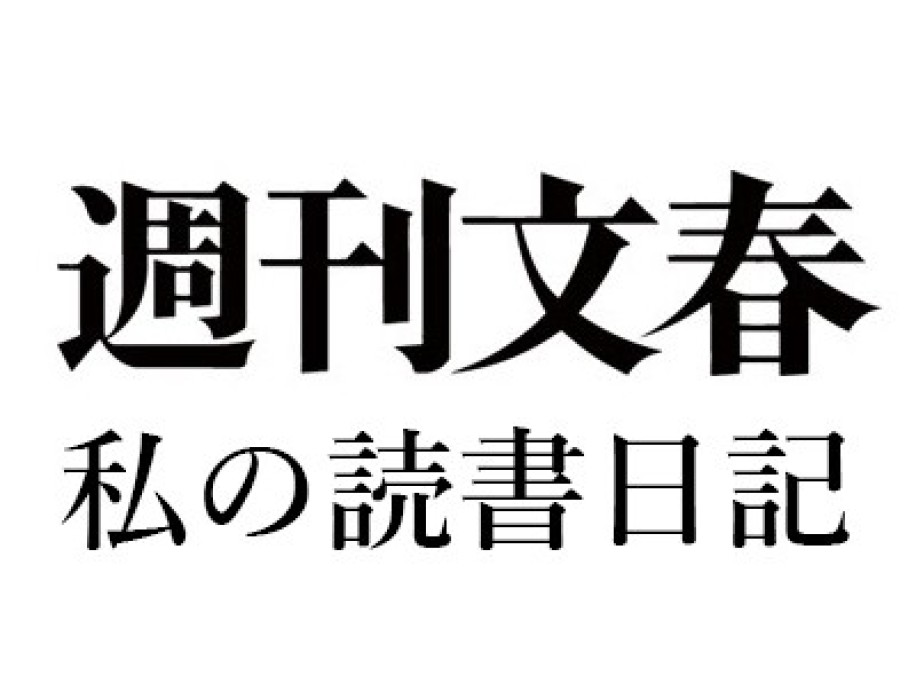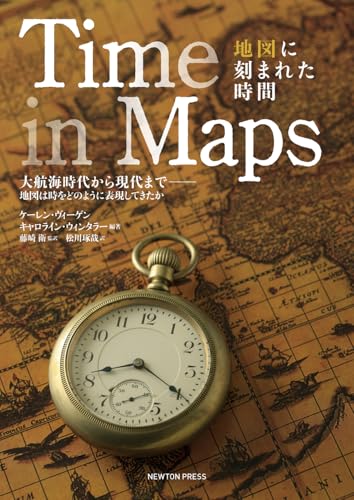書評
『エマニュエル・トッドの冒険』(藤原書店)
世界史左右 「家族システム」の発見
われわれ日本人は同調圧力に弱いというが、学究の徒も例外ではない。新しい物の観方(みかた)や説明の仕方をすることに慎重で、これまでのやり方を多少ズラすくらいで済ませがちである。だから、フランスのエマニュエル・トッドのような学者はなかなか出ないのではないか。なにしろ肩書だけでも、人類学者、経済学者、歴史学者、社会学者、人口統計学者、地政学者、政治アナリストなどと冠されるのだから、その多様な知的活動の創造力は半端ではない。それでも、トッドの学究の基礎となるものは、まずは家族システムの人類学であり、次に人口統計学であろう。本書は、彼の著作の大半を翻訳し、日本に紹介してきた比類ない研究者による最良の手引である。
現代最高の知性のひとりトッドは、評者と同じく団塊の世代に属する。われわれの青春時代には、ソ連を中心とする社会主義圏はどっしりと安定しており、やがて地球規模で席巻しかねないほどの勢いがあった。そのころ、留学先のケンブリッジ大学に博士論文を提出したばかりの25歳の青年が、『最後の転落』(原著1976年公刊)と題する気鋭のデビュー作で、来たるべきソ連の崩壊を予言したのは、とんでもなかった。
トッドの歴史人口学の要点は、なにはともあれ家族システムと心性に因果関係があることの発見であろう。すでに、産業革命以前から、イングランドでは核家族が存在しており、それに基づいて個人主義が生まれたと指摘されていた。これに対して、トッドは、家族システムは単一ではなく多様であるが、それらは類型化できると見通した。さらに、それらの家族システムの全世界規模での分布を確定し、それらと住民の心性との関係を見出すことがトッド理論の核心をなす。
そもそもソ連崩壊の予言が、人口統計学の資料の解読によるのだから、驚愕である。ソ連の70年代における乳児死亡率と自殺などの変死死亡率の上昇は、トッドの予言の発端だったという。全体主義体制が順調に運行されていれば、乳児死亡率は低下し、変死死亡率が上昇するものだが、それが同時に上昇していたため、その並行は強権国家社会の解体を示唆すると見なしたのである。そこには感傷的な道徳的批判などみじんもない冷静な推察があったのだ。
この背後には、各地域の家族システムは安定しており、その土台の上に、近代における宗教とイデオロギーが展開し変遷するという共時態がある。これを前提にして、やがてトッドは家族システムが変動し変遷することに注目し、近代のみならず世界史および現代世界を解明する作業にとりかかる。
この変動・変遷に目を向けると、これらの社会の原動力として大衆識字化があるという。経済発展に先行して識字化という文化発展がある。市民の大部分が読み書き能力を獲得することで国民=民族が成立し、これが民主主義の条件となる。それとともに、読める青少年と読めない高齢者との社会的分断がおこり、革命にいたることがある。女性の識字化は出生率の低下をもたらすことにもなる。
これらの冒険をふまえ、本書の最後には「『われわれは今どこにいるのか』を読む」とある。この最新作の紹介を本欄掲載の佐藤優氏の筆に委ねられるのは幸いだ!
ALL REVIEWSをフォローする