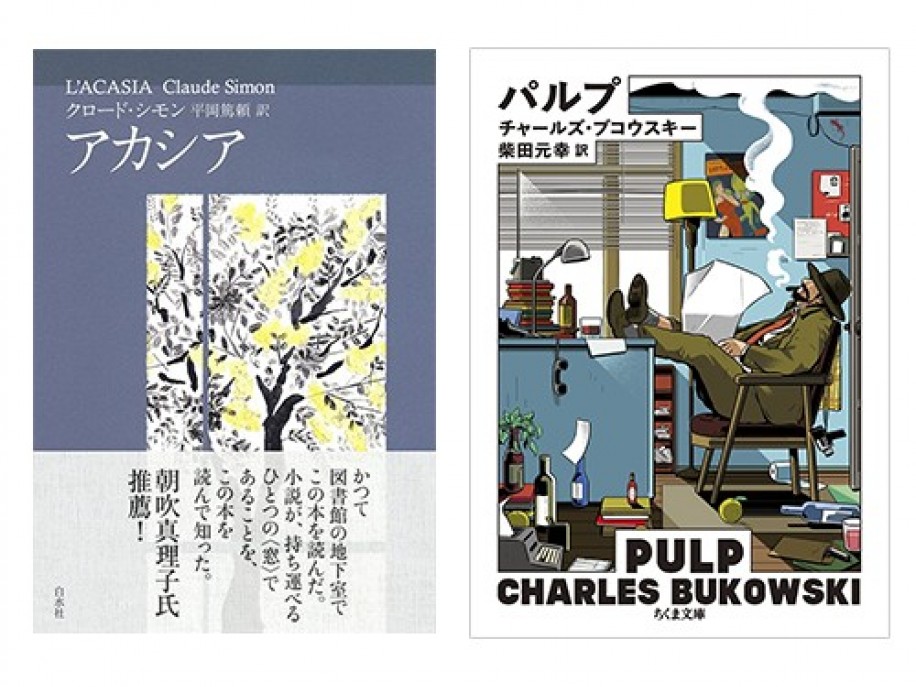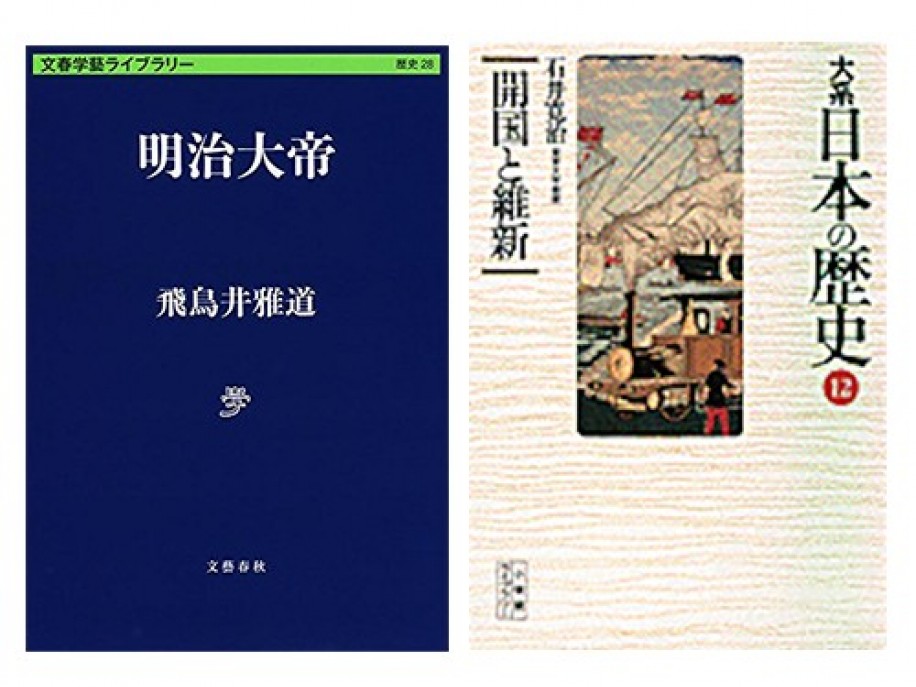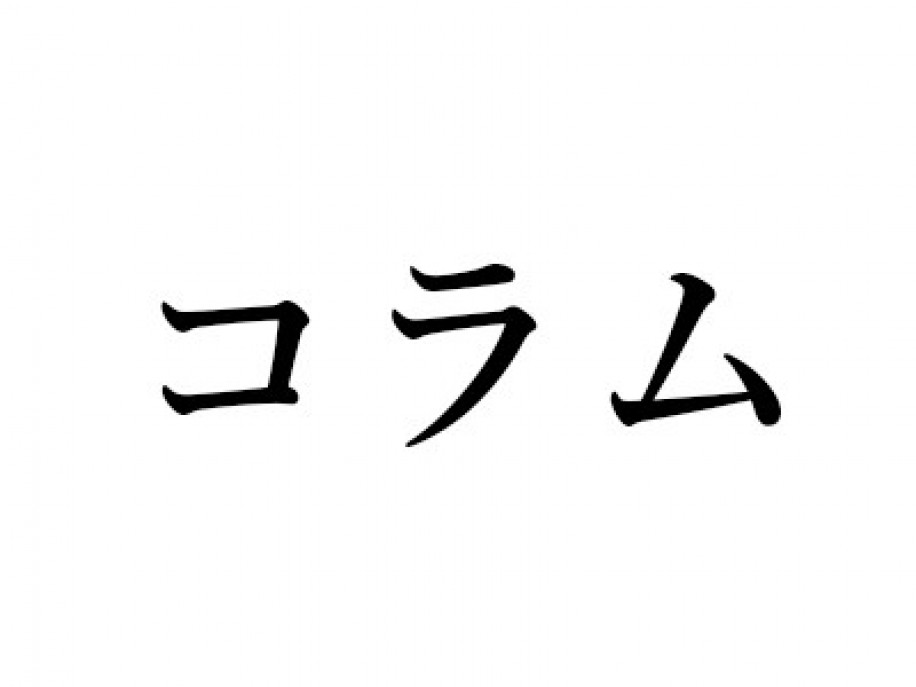コラム
バルザック『ゴリオ爺さん』(新潮社)、フロベール『感情教育』(岩波書店)、リルケ『マルテの手記』(新潮社) ほか
パリ憧憬の文学九選
●『ゴリオ爺さん』(バルザック著 平岡篤頼訳・新潮文庫)
フランスの大作家の中で、バルザックほど日本文学に何の痕跡も残さなかった小説家もいないのではなかろうか。スタンダール、モーパッサン、ロマン・ロランなど、日本文学に影響を与えてきた作家はすくなくないが、ことバルザックに関するかぎり、これを正しく読みこんで、そこに霊感の源泉を認めた小説家は、わずかに三島由紀夫ぐらいしかいない。その最大の原因は日本人好みの求道的な要素がバルザックには全くないからである。バルザックの小説は、いかに生くべきかを追い求める、旧制高校的な読書とはおよそ無縁である。というよりも、たいていは、成り上がることばかりを考えている俗物的な青年が主人公になっている。『ゴリオ爺さん』の場合も主人公はパリに上り、立身出世を望むラスチニャックという学生である。悩みといっても、社交界に出入りするための服が買えないとか靴を汚さずにすむように馬車がほしいなどといった類のはなはだ物欲的な悩みにすぎない。
だがひるがえって現在の日本の社会を見てみると、もはや小説を求道的に読むなどという若者は皆無で、その悩みは、まさにラスチニャックのそれと同じものになってきている。いいかえれば、ようやく日本の社会もバルザックを読むことのできるまで成熟してきたということになる。その証拠に、学生にこの『ゴリオ爺さん』を強制的に読ませてみると、こんな面白い小説は読んだことがないという返事が返ってくる。
どうやら、バブルの影響は、かならずしも悪いことばかりとは限らなかったようだ。
●『感情教育』(フロベール著 生島遼一訳・岩波文庫)
この小説の偉大なところは、およそ主体性というものがなく、時代の流れに惰性で引きずられていくダメな青年、フレデリック・モローを主人公にしたところにある。フレデリック・モローはタイトルに「教育」という言葉が入っているにも拘(かかわ)らず、いっこうに成長しない。人と出会ったり挫折を経験しても、精神的にたくましくなるわけでもなく、人間的に豊かになるわけでもない。ただ気分だけ青年のままで、ずるずると齢を重ねていく。
「感情」という言葉があるとおり、フレデリック・モローの人生の目的は素晴らしい恋を成就させることである。だがそれとても人妻アルヌー夫人に積極果敢にアタックするわけではなく、ただ成り行きに身をまかせているにすぎない。
そのわりには女性にはもてるが、積極的なのは女性のほうで主人公は受け身のままである。ストーリー展開も主人公の性格に見合ってスッキリしないことおびただしい。読者は主人公に同一化することができず、最後には「しっかりしろ!」と背中をどやしつけてやりたくなる。
だが小説が面白くないかといえば、事実はその逆で、これだけ再読に耐える小説もすくない。なぜかといえば、それは主人公の優柔不断こそが、じつは男性の本質の「優しさ」なのだということが、こちらが年をとるごとに理解できるようになってくるからだ。
フロベールは、教養小説風の初稿を全面的に書き改め、主人公をわざと成長しない万年青年にした。その結果、この小説は時代を越えた傑作となったのである。
●『マルテの手記』(リルケ著 大山定一訳・新潮文庫)
パリの安宿にたった一人で泊まり、真ん中が人間の形にへこんだベッドに身を横たえながら、窓で切り取られた鉛色の空を眺めていると、いかに陽性の私であろうともどうしようもなく鬱の気分にとらえられてくるが、そんなときには、あの『マルテの手記』の冒頭の文章が、いささかの感傷もなしに蘇(よみがえ)ってくる。「人々は生きるためにこの都会へ集まって来るらしい。しかし、僕はむしろ、ここではみんなが死んでゆくとしか思えないのだ」じっさい「大都会の孤独」という言葉は、メガロポリスが地球上に数多く出現しているにも拘らず、パリにのみふさわしい響きをもっている。そして、その「大都会の孤独」が生み出す「パリの憂鬱」を描いた『マルテの手記』ほど、心の琴線にふれる作品はない。たとえば、時差ぼけのせいでなかなか寝付かれず、窓の下を走り過ぎてゆく車の騒音にいらだっているうちに、夜明けが近づき、急に街が静かになる一瞬があるが、時に、その静寂が、なぜかたまらなく恐ろしいものに思えることがあるのだ。リルケは、その恐怖を火事のさなかに訪れる緊張の一瞬にたとえ「僕にはこの都会の静寂がそんな無言の恐怖と少しも変わらないのである」と言っている。
この「恐怖」を味わった人は、次の一句の持つ意味が、痛いほどよくわかるようになるのである。「すべてのものが僕の心の底に深く沈んでゆく。ふだんそこが行詰りになるところでけっして止まらぬのだ」。パリを訪れたのを機会に、作家になる人が多いのはこのためである。
●『パリ・ロンドン放浪記』(ジョージ・オーウェル著 小野寺健訳・岩波文庫)
バルザックの『ゴリオ爺さん』を読んだ読者は、下宿屋ヴォケー館は最底辺の吹き溜りだと思ってしまうが、じつはこれは間違いで、ヴォケー館は、プチ・ブル相手の「清潔で衛生的な」宿屋なのである。だが、百年後にオーウェルがヴォケー館とほぼ同じ一画にある、「オテル・デ・トロワ・モワノー」に宿をとったときには、すでにあたりは移民と浮浪者しかいない、完全なスラムになっていた。「天井のちかくには一日中、南京虫の長い行列が軍隊の隊列のように行進していて、これが夜になると猛烈に腹をすかせて下りてくる」というから、その凄(すさ)まじさたるや相当なものである。客もホテルに見合って「いま着ているものを四年間ぬいでいない」ような連中ばかりである。だが、客たちは奇妙に明るい。「金が労働から解放してくれるように、貧乏は人間を常識的な行動から解放してくれる」からである。オーウェルはやがて食いつめて、高級ホテルの皿洗いとなる。ここでオーウェルが行う人間観察がまた素晴らしい。たとえば、ウェイターは金持ちのそばにばかりいるので上流志向のスノッブとなり、組合も作れない。コックは芸術家だが、その芸術は清潔さとは関係なく、料理を恐ろしく不潔に取り扱う。皿洗いは長時間重労働を強いられ、貯金もできないので極貧生活から逃れるすべはない。
しかし、奴隷のような皿洗い生活を続けながらも、パリに注ぐオーウェルの視線はなぜか穏やかで、後半のロンドンの陰鬱なトーンとはあまりに対照的である。もしかするとパリには貧困そのものまでを人間的にする不思議な魅力があるのかもしれない。
●『北回帰線』(ヘンリー・ミラー著 大久保康雄訳・新潮文庫)
「世間の書物では省かれているすべてのものを記録すること」ヘンリー・ミラーが、全著作を通じてみずからの作家的モラルとしていたのはこのことだった。ミラーはこのモラルに忠実に従い、卑猥(ひわい)で騒々しく、俗物的で意地汚いが、同時に瞑想的(めいそうてき)で誠実でもある自己の生活と思想を、赤裸々な性生活や排泄(はいせつ)行為まで含めて、一切の美化を避けて書きとめようと努める。彼はもはや、何のために書くのかというようなインテリ風の弱々しい問いを発しはしない。
いまではぼくは、自分の背後にあるもの、自分の前方にあるものに、一顧も与えない。ぼくは健康だ。癒(いや)しがたいほど健康だ。悲しみもなく、悔恨もない。過去もなく、未来もない。現在だけで、ぼくには十分だ。その日、その日。今日、美しき今日。
だがミラーがこの境地に辿(たど)りつくには、一つの決定的経験、パリ体験が必要だった。
パリに春がくるとき、この世の最も卑賤(ひせん)な生きものですら天国に住んでいるような気がする。このようにパリを感じるためには、金持ちである必要はない。市民である必要すらもない(……)ニューヨークのことを考えると、非常にちがった感じをいだく。ニューヨークは金持ちにさえ自分がつまらぬものだという感じをもたせる。
ミラーはパリはカフェ・セレクトとドームとアメリカン・エキスプレスしか知らず、常に一文なしで、友達の懐を当てにするほかはなかったが、断固として「ヨーロッパの貧民」となる道を選んだ。ただ、巡りくるパリの春の空気を呼吸するために。
●『ふらんす物語』(永井荷風著・新潮文庫)
二十年ほど前までの日本には確かにありながら、いまでは完全に失われてしまった精神作用の一つに、本で読んで長いあいだ憧れていた異国の都市を訪れるという経験がある。現在では、文学作品など一つも読んだことのない若者たちが大挙して外国を訪れ、土産物だけを買いあさって、何の感慨もなく帰ってくるが、そんな若者たちにとって、次のような荷風の感激ぶりは理解できるのだろうか。ああ巴里よ(……)、自分は見る処到る処に、つくづくこれまで読んだ仏蘭西(ふらんす)写実派の小説と、パルナッス派の詩篇とが、如何(いか)に忠実に如何に精細にこの大都の生活を写しているか、と云う事を感じ入るのであった。
パリばかりではない。すでにル・アーヴルの港に着いたときから、荷風はモーパッサンの小説の細部を思い出し、汽車に乗っては窓外の風景をゾラの『獣人』の描写と重ね合わせる。ようするに、荷風にとって、フランスとパリのすべては、「既視」の光景だったのである。だが、ままあるように、現実が想像力に及ばないことはなかったのか?
現実に見たフランスは見ざる時のフランスよりも更に美しく更に優しかった。鳴呼(ああ)わが仏蘭西。自分はどうかして仏蘭西の地を踏みたいばかりにこれまで生きてきたのである。
確かにこの頃のフランスはベル・エポックの残映の中にあり、最後の光芒(こうぼう)を放っていたということも事実だ。だが、それにしても、これほどまでに純粋に異国に憧れるということはもはや今日の日本人にとっては不可能である。我々は未だ見ぬ異国の都に憧れるという、精神の貴重な働きを失ってしまっているのだ。
●『東京の三十年』(田山花袋著・岩波文庫)
父親を西南戦争でなくし、幼いときから丁稚(でっち)奉公にだされた田山花袋は、フランス自然主義小説を英訳で読んで同時代の誰よりも強くパリに憧れながら、遂にフランスの地を踏むことはできなかった。あるとき洋書店でモーパッサンの『ピエールとジャン』を見つけた花袋は胸をときめかした。「恋人に世界の果で逢ったような気がした」。が、高すぎて買えない。
「Maupassantの字が寝ても覚めても、Tの頭を離れなかった。何ぞと言うと、それをかれは口にした。その本を買って、喜んで帰って来る夢から覚めた」。原稿料が入るとその足で洋書店に駆けつけた。「それを本当の恋人か何かのようにして、その身の傍から離さなかった」
花袋にとって、唯一の慰めは麻布のフランス料理店「龍土軒」で友と語り合うことだけだった。「『我々龍土会からも、フランスあたりに行くものがありそうなもんだな。その時は、うんと盛んに送別会をしようじゃないか。』こんなことを国木田君は言った。それほど我々は外国の文学にあこがれていた」
だから島崎藤村がフランスに行くことが決まると花袋はいてもたってもいられない気持ちになった。「私の心の動揺はなお長く続いた。落付いて家にもいられなかった。私は旅から旅へと出かけた」
憧憬(しょうけい)はついに実現しなかった。だが、花袋がパリへの憧れを胸に抱いて歩き回った明治の東京は、ドーデの『パリの三十年』に名を借りた、このみずみずしい青春の回想の中で、パリ以上の輝きをはなっている。
●『自叙伝・日本脱出記』(大杉栄著・岩波文庫)
大杉栄というと一般には女癖の悪い甘ったれのアナーキストというイメージが強いが、実際には左翼の人間には珍しい豊かな人間性と柔軟な現実感覚をもったナイス・ガイで、これなら女にもてるのは当たり前、男だって好きにならざるを得ない。なかでも、国際無政府主義大会に参加するために一九二三年にパリに赴いたときの『日本脱出記』は、安宿の細部に始まって、娼婦の客引きの手口、知り合った女工の家計簿、さらには、ぶち込まれたサンテ刑務所の実態まで、実に貴重な証言がつまっていて、出色のパリ滞在記となっている。たとえば、安ホテルについては、こんな記述がある。「トレ・コンフォルタブル(極上)とあって、便所付きとか電燈付きとかいう文句のついたのがある。便所が室についていないのはまだ分かる。しかし電燈のないホテルが、今時、このパリにあるんだろうか。僕は少々驚いてつれの女に聞いた。『ええ、ありますとも、いくらでもありますよ』」
これに比べるとサンテ刑務所の独房ははるかにましでシーツは清潔、便所もちゃんとある。おまけに、外部のレストランから出前も頼める。「僕はその中から四品だけ選んで、なお白葡萄酒のごく上等な奴をと贅沢をいった。ボオイはかしこまって引き下がった。僕はすっかりいい気持ちになってしまった。この分だと、月に四、五〇円もあれば、呑気にこうして暮らして行けそうだ」。だが「期待」も空しく判決は案外早く出て、大杉は国外退去となる。もう少し未決が長引けば、甘粕大尉に虐殺されるという悲劇的な運命を避けえたかも知れないのに。残念である。
●『新版 放浪記』(林芙美子著・新潮文庫)
最近では十万円の「ホテル付きパリ一週間」のパック・ツアーさえあるので、若い女性でも少し倹約すればパリに旅行することは十分可能である。だが大正十一年に林芙美子が十八歳で東京に出てきたときには、パリ旅行など夢のまた夢だった。セルロイド女工、株屋の女店員、牛屋の女中などを転々とし、いまでいうフリーターのような、その日暮らしを続けながら、のちに『放浪記』として結晶する日記を書きつけてゆく。小説家の家に子守として入ったときには、赤ん坊をあやしながら本棚からチェーホフを引っ張りだして読むことがせめてもの慰めだった。
「チェーホフは心の古里だ。チェーホフの吐息は、姿は、みんな生きて、黄昏の私の心に、何かブツブツものを言いかけてくる」。二週間後、暇を出され、文化住宅の空き家に無断で入りこんで休む。「はばかりから出て来ると、荒れ果てた縁側のそばへ狐のような目をした犬がじっと見ていた」
イタリア大使館の女中に応募してみる。「綺麗な砂利が遠い玄関までつづいている。私のような女の来るところではないように思えた」。結局、職は見つからない。結婚と離婚を何度か繰り返したあげく、最後は、おきまりのカフェーの女給に。親友の時ちゃんは男に騙(だま)されて待合に売り飛ばされる。「あんなに、貧乏はけっして恥じゃないと言ってあるのに」
やがて、この頑張りが報われるときがやってきた。『放浪記』が大ベストセラーとなって、林芙美子はパリで暮らすという夢を実現することができたのである。パリ版の放浪記『パリ日記』も、なかなか味わい深い旅行記である。
【このコラムが収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする