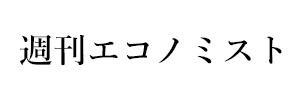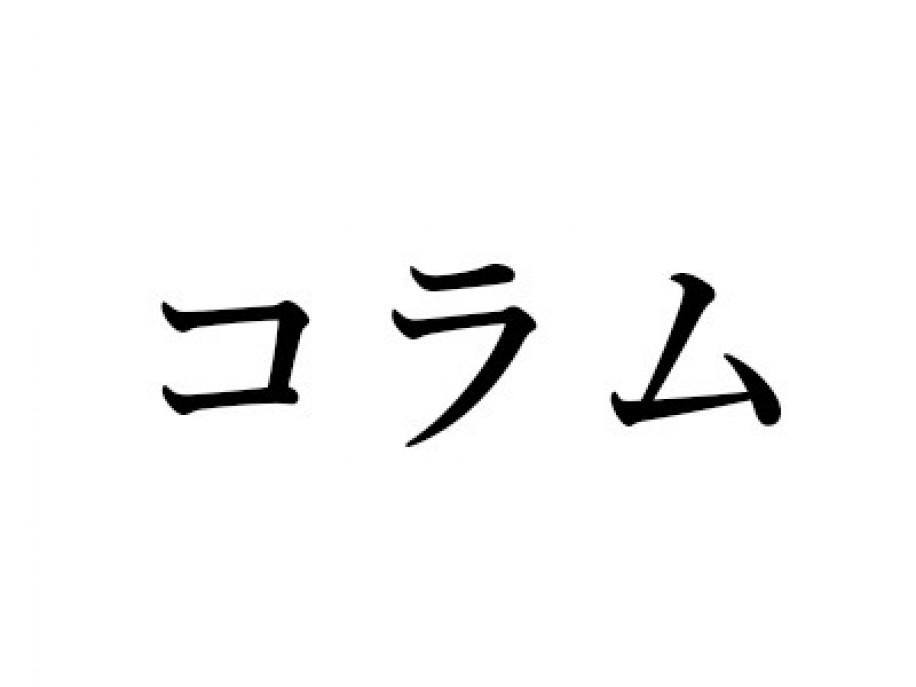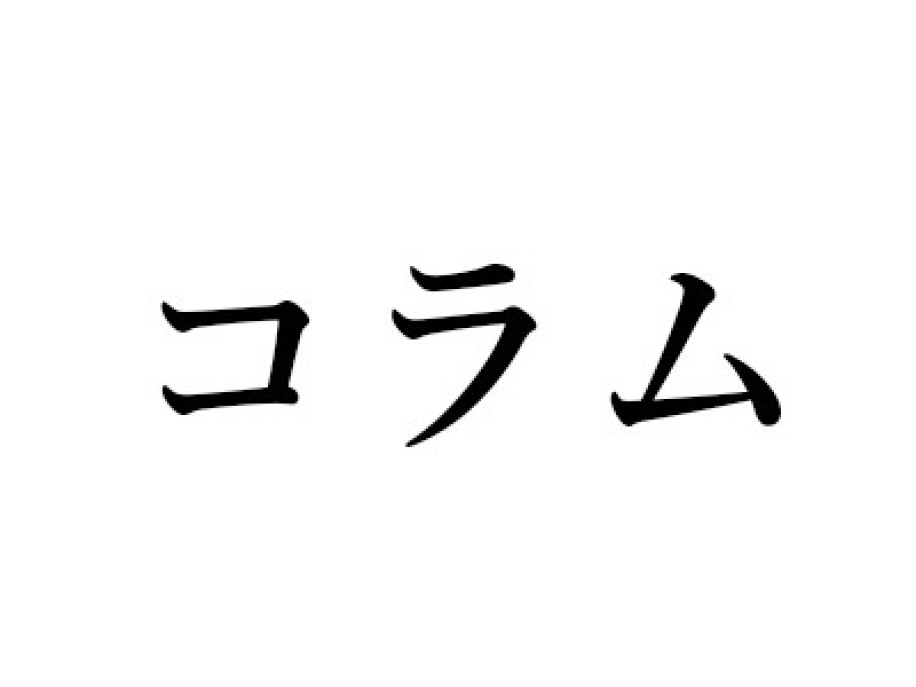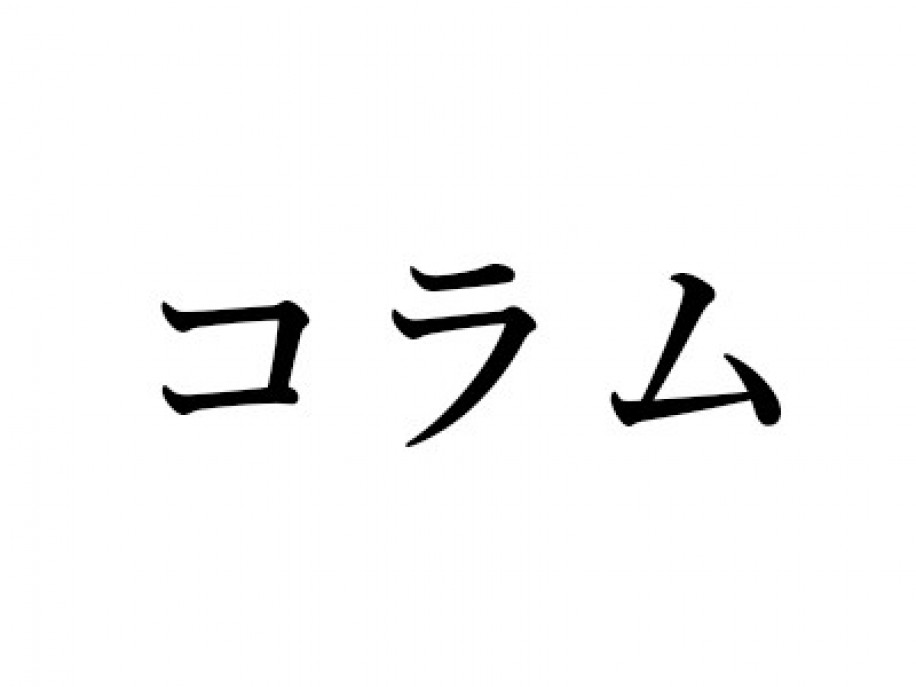書評
『明治深刻悲惨小説集』(講談社)
3行読んでは悶絶昏倒 悲惨描く明治文学の凄み
先日。神奈川県の鵠沼(くげぬま)というところを通行していたところ突然、恰(あたか)もひだる神に取りつかれたごとくに腹が減り、このままでは旅を続けられない、と思ったのでたまたまあったコンビニエンスストアに飛び込んでヤキソバパンなるものを購(もと)めて食したら悲惨なことになった。どのように悲惨だったかは……、言わぬが花でしょう。
いや、別に言わなかったからといって花ということはなく、せいぜい、草、程度のことで、正確に言うと、言わぬが草でしょう、ということになるのだが、兎(と)にも角にもいやはや悲惨な味であった。食べている間中ずっと苦しみしかなかった。
といってそれは私にとって確かに惨事で、私は、この苦しみの体験を元に短編小説を書くことができるのではないか、とさえ考え、構想を練ったら、驚いたことにまるで馬鹿のような構想しか浮かばず、これも悲惨事といえば悲惨事だった。
しかしこの世にはもっと深刻で、もっと悲惨な目に遭っている人が数多くいるはずで、そういう人からみればヤキソバパンが不味(ふみ)で閉口した、などというのは惨事のうちに入らず、なめとったらあかんど、ということになるに違いない。
そういう風に考えれば俺は、堅気嫌ってパンクになって太く短く生きるんでえ、などと意気がってはいるものの所詮は甘ちゃん、こんなときは自分ばかりが可哀想と思うのではなく、悲惨というものが元来、どういうものかを見つめ直す必要がある。
そう思って読んだのが、『明治深刻悲惨小説集』(講談社文芸文庫編、1800円)という小説集で、前田曙山(しょざん)、北田薄氷(うすらい)、小栗風葉、江見水蔭といった私やなんか、名前も知らなかった作家や、川上眉山、泉鏡花、田山花袋、広津柳浪、徳田秋声、樋口一葉といった名前は知っていて少しばかりは読んだけれども、この集を読まなかったら読み返すこともなかっただろうなあ、という作家の作品が収められている。
で、どうだったかというと、えげつなかった。えげつなく悲惨だった。あまりにも悲惨で、例えば、前田曙山の「蝗(いなご)うり」など、2行読んでは鳴咽(おえつ)号泣、3行読んでは悶絶昏倒(もんぜつこんとう)してしまうので、短いものであるのにもかかわらず、何日もかかってようやっと読み終えたような体たらくだった。
離さぬ真正面の力
と言うと、「なんでそんな悲惨なことを書くのだ。お蔭でこっちはすっかり嫌な気持ちになってメンタルを病んで仕事ができなくなってしまった。どうしてくれる」と苦情を仰(おっしゃ)る方、「自分はもっとポジティブな話が読みたかった」とレビューを書かれる方がでてくるのカナー、なんて語尾カタカナで思うが、しかし、これらの作家はおそらく、いまの小説家やクリエーターと称する方々のように、「読者を勇気づけるような、元気づけるような作品を作りたーい。等身大のままの自分を肯定とかしたーい。そして多額のギャラをもらいたーい」と考えていたわけではなく、文学というものが人間の、社会のなにをどう書くべきかということを真剣に考え、精神や言葉やとつかみ合い・殴り合いをした結果、こうしたものができてきたのだろう。なのでそこには訳のわからぬ迫力と圧倒的な悲哀が充(み)ちて、私やなんかはなんとかしてギャグに、笑いに逃げようとするのだけれども、そこをとらえて離さぬ真正面の力があって死ぬ。
ここで悲惨な目に遭うのは主に若い女や子供で、現代の感覚から考えれば信じられないような不条理が普通にあり、これをたとえるならば、若い女や子供はペットのような感覚でとらえられ、貴顕紳士が気に入った女を我が物にするのは現今、家族連れがペットショップで犬や猫を購入するのと同じような感覚である。
ということは時代が進んだいまは格差社会とは言い条、民権意識も徹底、人権条約も締結せられたるよりは斯(か)かる辛酸(しんさん)を嘗(な)める者も次第に減じ、よかったことだ。向後(こうご)も時代がさらに進めば人気(じんき)もさらによくなって斯(こ)うしたことはゆっくりではあるが減少していくだろう、と思いたいのだけれども、そうは思わせない人間の胸の底の底を書いた樋口一葉の「にごりえ」はすげかった。やはりすげかった。
ALL REVIEWSをフォローする