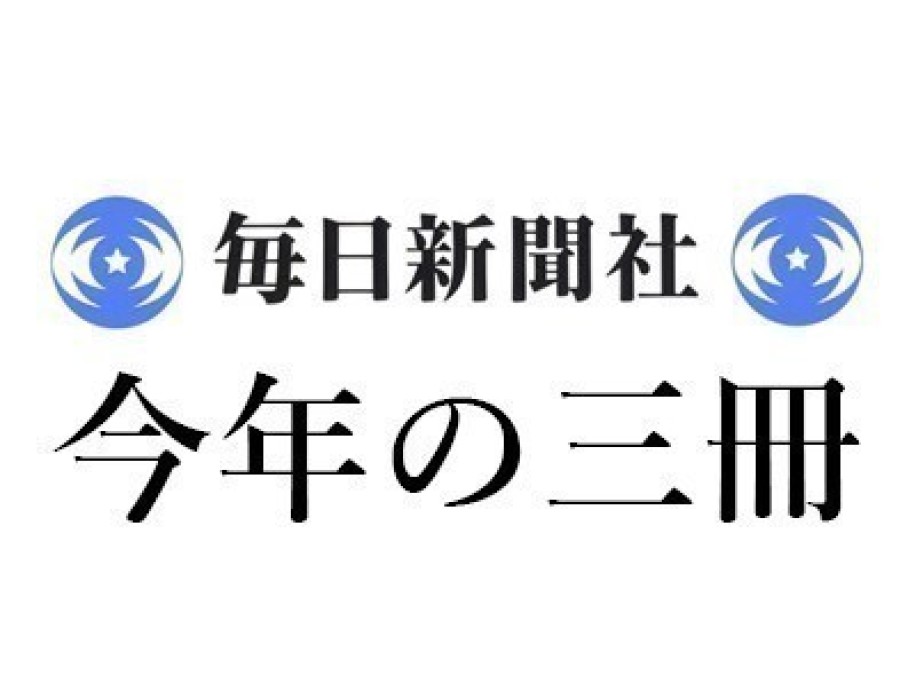読書日記
監修・スミソニアン協会『ビジュアルマップ大図鑑 世界史』(東京書籍)、佐藤猛『百年戦争』(中央公論社)、マイク・ラポート『ナポレオン戦争』(白水社)
大図鑑世界史、百年戦争とナポレオン戦争
×月×日
一〇〇年前のスペイン風邪蔓延の過程を自分なりに分析した結果、新型コロナ・ウィルスも人の免疫力が上がる夏には一時的に下火になるだろうと予測したのだが、甘かった。東京だけで新規感染者が一日二〇〇人を超えた。政府の無策もあいまって、この調子では欧米並みの感染拡大になりそうだ。緊急事態宣言が再発令されるかもしれないので、その前にと、リアル書店に出向いた。ヴァーチャル書店だと思いがけない出会いがない。やはり、書店はリアルでなければ。そんな思いを強くしたのが、編著・DK社、監修・スミソニアン協会、日本語版監修・本村凌二『ビジュアルマップ大図鑑 世界史』(東京書籍 六五〇〇円+税)。これは凄い本だ。さすがはスミソニアン協会監修だけのことはある。
正直言って、世界史を地図で見せる類いの本は少なくないが、本書は地図の中に時間をはめ込む編集技術が圧倒的に優れている。たとえば「ヴァイキング」のページを開けると、見開きページの左端に簡にして要を得た解説がある。右に眼を転じると、スカンジナヴィア半島を中心に北米、ヨーロッパ、地中海、黒海といったヴァイキングの征服地域全図があるが、その上には矢印と年号でヴァイキングの移動と時間的経過が示され、当該地点に「793年 ヴァイキングが初めて海を越えて、ノーサンバーランド王国のリンディスファーンにある富裕な修道院を襲撃する」というテクストがかぶる。この工夫は他の歴史地図と変わらないかもしれないが、優れた編集的レイアウトだと感じるのは、英仏を襲ったヴァイキングの進出経路を示す矢印と同じ色で、地図の上下辺に囲み記事が掲げられていること。「2 ブリテン諸島 793〜1103年 初めてブリテンでヴァイキングが略奪を行ったのは790年代である。初期の標的は非武装の修道院で、彼らはそこが宝の山だと知っていた。略奪行為の規模は拡大し、865年にはデンマークの『大異教徒軍』がイングランドのアングロ・サクソン諸国の大半を征服した」
その一方で、ページ下では、それぞれの移動期間が色別年表で視覚化されている。テーマによっては、人の移住した先で食されていた食料(主に穀物と家畜)も記号化されて地図に描かれている。
人類の誕生からオーストラリア移住までを図示した「先史時代」の「現生人類のアフリカからの出発」は最新のDNA歴史学の成果が生かされていて、興味が尽きない。同「農耕牧畜の起源」には農耕の開始で集団生活を強いられた結果、「人々は往々にして劣悪な健康状態におちいった。なぜなら、過密化した集落では、人々や家畜の間に感染症が蔓延しやすかったからである」と書かれている。感染症との戦いは農耕牧畜の開始と同時に始まったのである。
歴史好きの中・高校生、あるいは世界史マニアの恋人、夫・妻へのプレゼントに最適。
×月×日
毎年、夏休み前の忙しいこの時期になると、入試問題作成の命令が届き、天を呪ったものだが、晴れて年金生活者となり、その憂鬱からも解放され、自分の興味の赴くままに歴史書を繙くことができるのはうれしい限りだ。佐藤猛『百年戦争』(中公新書 九二〇円+税)はありそうでなかった専門研究者による一般向けの百年戦争通史。私にとって、百年戦争の関心の第一は、戦争を仕掛けたイングランド王エドワード三世が女系(母はカペー朝フランス王フィリップ四世の娘イザベル)での王位継承権を主張したことの真の理由である。プランタジネット朝初代のヘンリー二世がフランスの一諸侯(最初はアンジュー伯。後にノルマンディー公とアキテーヌ公)からイングランド王に即位できたのは、女系での王位相続(母はノルマン王朝三代のヘンリー一世の娘マティルダ)が認められていたことを根拠にしていたようだが、しかしそれはイングランド・ルールであり、これをフランスの王位継承にまで適用せよというのは無理筋ではないか? そのことはエドワード三世自身も判っていたのではないか? ならば、なにゆえに、王位継承を開戦理由にしたのか、その真意は?著者の答えは以下の通り。
イングランド王はアキテーヌ公でもあったヘンリー二世以来、慣例としてフランス王に優先的臣従礼をすることになっており、エドワード三世もこれに従わざるを得なかったが、このことが彼にとってはなによりの屈辱だったと著者は考える。では、優先的臣従礼をしないで済ませるにはどうしたらいいか? イングランド王ではなくフランス王になってしまえばいい。「エドワードがメンツを重んじたという人物評を信じるならば、彼がアキテーヌ公というフランス王の家臣としてよりも、対等な権利を要求する『対立国王』としての戦いを選んだ可能性は高い。(中略)なぜ戦争はこうも長期化したのか。それは、主従関係の清算という難題が、仏王位継承問題を交渉カードとして争われたからである」
なるほどこれはよくわかる。納得。
私の第二の関心は、休戦状態にあった百年戦争再開の遠因となったフランス王ジャン二世による親王領(アパナージュ)新設の理由である。ジャン二世は王太子シャルル以外の三人の王子に親王領を与え、さらに加増措置までしたが、その動機は何だったのかということ。なぜなら、国土分割を恐れて長らく回避されていた親王領が新設されたことにより、ブルゴーニュ公国が台頭し、イングランドと結んで百年戦争後半戦を用意することになったからだ。
第二の疑問への著者の答えはこうである。すなわち、ジャン二世はエドワード三世が大陸に侵攻したとき各地の諸侯がこれに合流したことを強く反省し、王と家臣の主従関係を引き締める目的で親王領を新設したというのである。「王への揺るぎない愛と奉仕に燃える白ユリ諸侯の姿を通して、王の家臣としてのあるべき姿を示すことができると考えられたのではないだろうか」
ふーむ。だとすれば、ジャン二世は「善良王 Jean le Bon」だとしても、やはりフランス的な意味での「善良」、つまり愚かな王だったのではないだろうか? 徴税権と軍隊をもつ親王家ほど王家にとって危険なものはないのだから。
×月×日
『ビジュアルマップ大図鑑世界史』で最も素晴らしいのはナポレオンがヨーロッパで繰り広げた戦いの数々を地図上で一望のもとに見せたことだが、これに刺激されてもう一度ナポレオン戦争を総括してみたくなった。マイク・ラポート『ナポレオン戦争 十八世紀の危機から世界大戦へ』(楠田悠貴訳 白水社 二三〇〇円+税)はナポレオン戦争を旧体制からの継続として再検討する試みである。たとえば多くの歴史好きが抱く疑問にナポレオンの軍隊はなぜあれほど強かったのかというのがあるが、これに対し著者は、旧体制下の軍制改革で歩兵・騎兵・砲兵を組み合わせた「師団」ができあがり、「扇状」展開が可能となったことを挙げる。「革命期にこの構想が採用され、ナポレオンは師団を軍団へと拡大し、各々が元帥によって指揮され、効率的な参謀体制によって統合できるようにした」
しかし、より重要だったのは大革命により官僚統治機構が完全に中央集権化していたことである。
「革命は、一七八九年以前に改革が難航していた免税特権、官職売買、徴税請負の難問に決定的に切り込んでいった。(中略)したがって、ナポレオンは効率的な財務システムによって開発された、再興するフランス経済の成長を継承したのである」
ナポレオン戦争を民間セクターが総動員された総力戦という観点から眺めるという視点が斬新。
英米系の歴史家ならではの一冊である。
ALL REVIEWSをフォローする