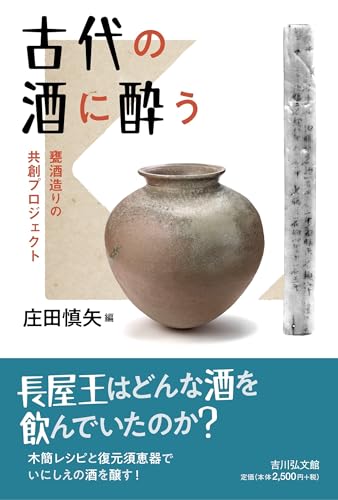コラム
名前と肩書の研究
その夜は、御徒町のガード下近くのさる朝鮮料理店で、甥の立大生を相手にマツカリを飲んでいた。ここは敗戦後の闇市時代からゆきつけの店である。当時は非合法だったマツカリを人間の背丈ほどもある大瓶から肥柄杓のようなものですくって飲ませてくれた。警察(サツ)の手入れと見るや、この大瓶をハンマーで叩き割るのである。すると白い液体はごぼごぼと床下の暗渠を流れて、みるみるうちに便所の壼のなかへと姿を消してゆく。
そんな壮烈な見世場こそなくなったが、プルコギを焼く煙とマツカリの酸味からさえ、私にとっては当時をしのぶよすがとなるある種の雰囲気を残しているもはや数少い場所なのである。パン助と浮浪児、GIと復員兵、露天商と運び屋。暴力と血と空腹とがエネルギッシュなゴッタ煮となって濛々たる湯煙を上げていた、一九四〇年代末期の界隈の面影が何となく追想されてくる。どうやら得体の知れない豚の臓物をつつきながらマツカリを飲むことは、私の場合、マルセル・プルーストの主人公が紅茶に浸したマドレーヌというお菓子を食べながら少年時を追想するのと、同じ効果を持っているらしいのである。
まあそんなわけで、年少の甥を相手に根拠薄弱なオダを上げていた、とご想像願いたい。するとそこへ、魔法を掛けて呼び出したように、出口裕弘教授が突如として姿を現したのである。顔見知りの美術雑誌の編集者を同伴しているが、両者ともすでにかなりきこしめしていて、羽化登仙の境にましますらしい。
「タッ、タネ公ッ、てッ、てめえ!こんなとこへ助平たらしくシケ込みやがって!」
出口教授の巻舌のお叱りを蒙るまでもなく、私は一種の恐慌状態に陥っていた。肩書誤記事件といい、知るはずもない立回り先への知人の突然の登場といい、これはどうやら私の行動が逐一何者かに監視されていて、私は得体の知れぬ大陰謀に巻き込まれているのではあるまいか。
仕掛けが割れてみると、どうということはなかった。出口さんは神田の古本屋見物の帰路、連れの編集者とゆきずりのおでん屋に入ったのである。酔うほどに照れ屋の露悪趣味が嵩じて、女性性器の俗名をナマで連発(ご当人の証言によれば「たった三回」)した。するといやにもったいぶったおでん屋の女将が、突然、「お客さん、出ていって下さい」と狐面(きつねづら)になった。
虚を衝かれたのであった。ふだんの出口さんなら、ここでべらんめえになってとっさに切り返すところを、まさかたった三回、「オ○ンコ」と唱えたばっかりにムキになる正直者が、箱根のこちら側に生息していようとは思いも寄らなかったのだ。
口惜しいから表へ出て立小便してやった。それをまた格子戸を開けて説教がましくジロジロ覗いてやがるじゃねえか。こうなったらもうタネ公を襲う以外にねえよなあ。
こういう観念連合は高尚なるボードレール研究においては通用しない。論理の運びがはなはだ学問的ではないからだ。おでん屋で啖呵を切り損ねた鬱憤をタネ公襲撃において晴らす、という端倪すべからぬ想像力の働き方は、これはもう純粋に小説家のものである。彼は研究されるべき側の人物なのだ。
どうやら拙宅に電話して行先を突きとめたのである。不意打ちを掛けると、そこにマツカリでうっとりと回顧的感傷に耽っている私がいた。一方私の側にしても、もしも悪魔がその場にもっともふさわしい人間を呼び出してくれると申し出たら、まっさきに指名するであろう人物は出口裕弘さんを措いて外にはなかったと思う。なにしろ彼はこんな文章を書く作家である。
「二階の喫茶店を出たのは三時ごろだったろう。出たとたん、階段を冷たい風がどっと駆けあがってきた。その風に押しあげられるようにして、私と高杉は街路の方へではなく、逆に焼ビルの三階へ向った。すぐに階段を下りようとする私に、ちょっとこのビルを探険してみないかと高杉は誘ったのである。ことわればすかさず小心を笑われるにきまっている。私は一も二もなく賛成した。」
敗戦後の焼土のなかでの出来事である。これだけでは何のことやらわかるまいが、このあと高杉という男は、いきなり焼ビルの四階と五階の間から身を躍らせて、あの世までさっさと駈け抜けてしまうのである。
戦後も三十余年、平和にうつけたこの晩はさすがにそんな物騒なことは起こらなかった。「上海帰りのリル」を歌い、「こんな女に誰がした」を歌い、ナツメロに太平楽に呆け、河岸を変えて拙宅で飲み直しているうちに、こちらの方が悪酔いしてきたからである。
「出口さんは、出ロヒロビロなんていい名前してるくせに、入ロセマゼマみたいな高踏的な小説ばっかり書いてますねえ」
性(たち)の悪いからみ方であった。深更近く、出口さんは出現したときと同様、風のごとく消え失せた。見ればあとには、主を失った刑事コロンボ風のレインコートがわが書斎脇の掛釘に夢のなかの物体のようにぐんにゃりと吊る下っている。正体をつかまえたと錯覚させておいて、脱殻だけ残して、本体はどこかへ突っ走ってしまっているその呼吸が、彼の作中人物と瓜ふたつであった。
(次ページに続く)
ALL REVIEWSをフォローする
初出メディア