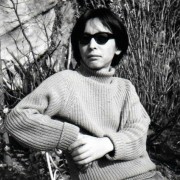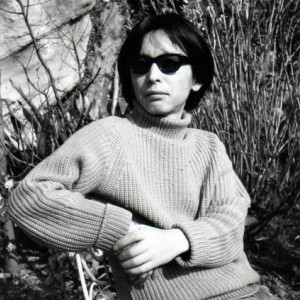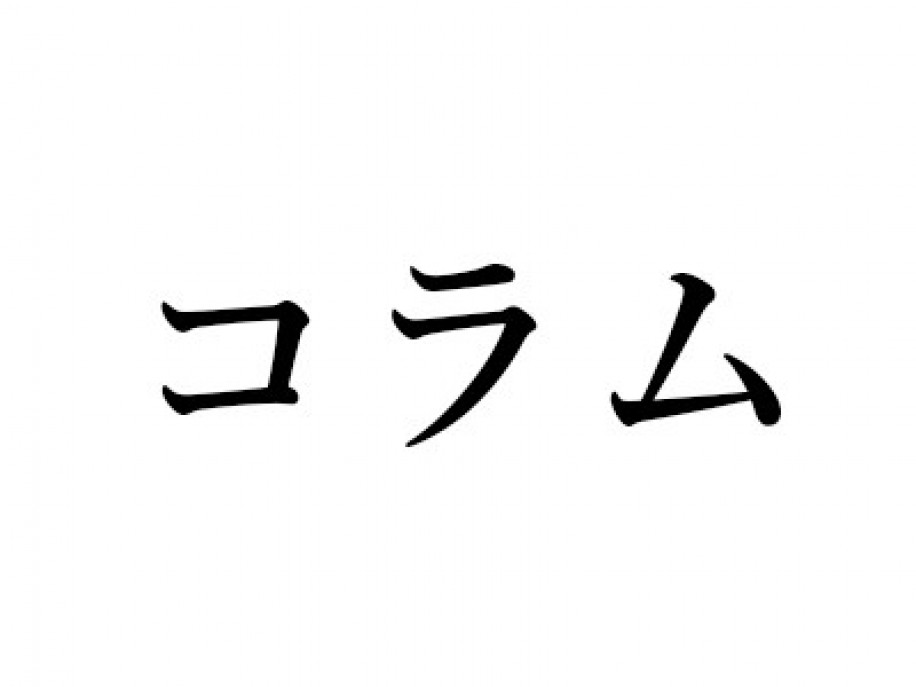書評
『有罪者―無神学大全』(現代思潮新社)
この本を要約することなどは到底不可能であるし、解説することもさらに無意味であろうと思う。バタイユの哲学を神秘主義と言っていいかどうかは疑問であるが、ともかく彼の哲学には、たとえばサルトルのような進歩的、合理主義的哲学者の著作を読む場合とは全く異った、圧倒的な重量感があって、私たちをくたくたに疲れさせてしまう。
その多分に主観主義的な語り口から言っても、苦悩のなかにどっぷり身を浸したかのごとき、その告知者的な風貌から言っても、バタイユは紛れもない二ーチェの系統を継ぐ者であるが、二ーチェの病的な性的差恥心は、ここには影すらもない。それどころか、ここにはあらゆる卑猥なもの、おぞましいものの寄せ集めがあって、肉体の酩酊と論理の冷静とが、手をつないで極限をめざすのである。したがってバタイユの哲学は、たしかに哲学を否定する哲学であろう。
この『有罪者』は、無神学大全三部作の一部をなすものであるが、一九三九年、第二次大戦勃発と同時に書きはじめられたものだという。著作の背後に作者の生活をのぞき見るといった本の読み方は、明らかに日本的な弊風で、不必要と思われるが、この頃、どうやらバタイユは、酒と女に浸りながら、ひたすらエクスタシスを求めるデカダン生活を送っていたらしい。「日ごと、捕捉しえぬものを捕捉しようとし、放蕩から放蕩へとわたり歩き……」と巻末の『ハレルヤ』にある通りだ。
バタイユは一時期、超現実主義に接近したが、シュルレアリスム特有の、あの一種のアンジェリスム(天使崇拝)ともいうべき楽天主義とは、およそ無縁な人だったと思われる。ときに詩的散文を書いても、バタイユは本質的に詩人ではないのだろう。
『有罪者』のなかに、「詩の神秘主義に反感を持つという点では私はへーゲルにひけを取らない。美学だの文学だのは、私の気を挫く」という文章があって、私の注意を惹いたのである。「曖昧な、観念論の、高尚な精神、卑俗さや屈辱的真理を無視するような精神から、私は顔をそむける」とあるが、これは暗にブルトン一派の超現実主義者を諷しているのではあるまいか。
バタイユが死んでから、今年はすでに六年目であるが(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1967年ごろ)、フランスでも、また日本でも、彼の声価は日ましに高くなって行く一方である。本書は邦訳されたバタイユの作品の六冊目(私はそのうちの四冊の書評を書いている)で、その内容が、難解をきわめた哲学的独白ともいうべきものであるだけに、訳者の苦労を多とすべきは、申すまでもあるまい。ともかくも、バタイユをこれだけ明晰な日本語に移し得るということが分っただけでも、本書には画期的な意義があろう。
【新版】
【この書評が収録されている書籍】
その多分に主観主義的な語り口から言っても、苦悩のなかにどっぷり身を浸したかのごとき、その告知者的な風貌から言っても、バタイユは紛れもない二ーチェの系統を継ぐ者であるが、二ーチェの病的な性的差恥心は、ここには影すらもない。それどころか、ここにはあらゆる卑猥なもの、おぞましいものの寄せ集めがあって、肉体の酩酊と論理の冷静とが、手をつないで極限をめざすのである。したがってバタイユの哲学は、たしかに哲学を否定する哲学であろう。
この『有罪者』は、無神学大全三部作の一部をなすものであるが、一九三九年、第二次大戦勃発と同時に書きはじめられたものだという。著作の背後に作者の生活をのぞき見るといった本の読み方は、明らかに日本的な弊風で、不必要と思われるが、この頃、どうやらバタイユは、酒と女に浸りながら、ひたすらエクスタシスを求めるデカダン生活を送っていたらしい。「日ごと、捕捉しえぬものを捕捉しようとし、放蕩から放蕩へとわたり歩き……」と巻末の『ハレルヤ』にある通りだ。
バタイユは一時期、超現実主義に接近したが、シュルレアリスム特有の、あの一種のアンジェリスム(天使崇拝)ともいうべき楽天主義とは、およそ無縁な人だったと思われる。ときに詩的散文を書いても、バタイユは本質的に詩人ではないのだろう。
『有罪者』のなかに、「詩の神秘主義に反感を持つという点では私はへーゲルにひけを取らない。美学だの文学だのは、私の気を挫く」という文章があって、私の注意を惹いたのである。「曖昧な、観念論の、高尚な精神、卑俗さや屈辱的真理を無視するような精神から、私は顔をそむける」とあるが、これは暗にブルトン一派の超現実主義者を諷しているのではあるまいか。
バタイユが死んでから、今年はすでに六年目であるが(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1967年ごろ)、フランスでも、また日本でも、彼の声価は日ましに高くなって行く一方である。本書は邦訳されたバタイユの作品の六冊目(私はそのうちの四冊の書評を書いている)で、その内容が、難解をきわめた哲学的独白ともいうべきものであるだけに、訳者の苦労を多とすべきは、申すまでもあるまい。ともかくも、バタイユをこれだけ明晰な日本語に移し得るということが分っただけでも、本書には画期的な意義があろう。
【新版】
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする