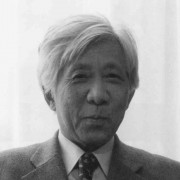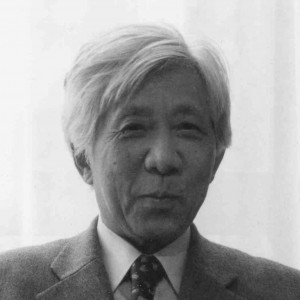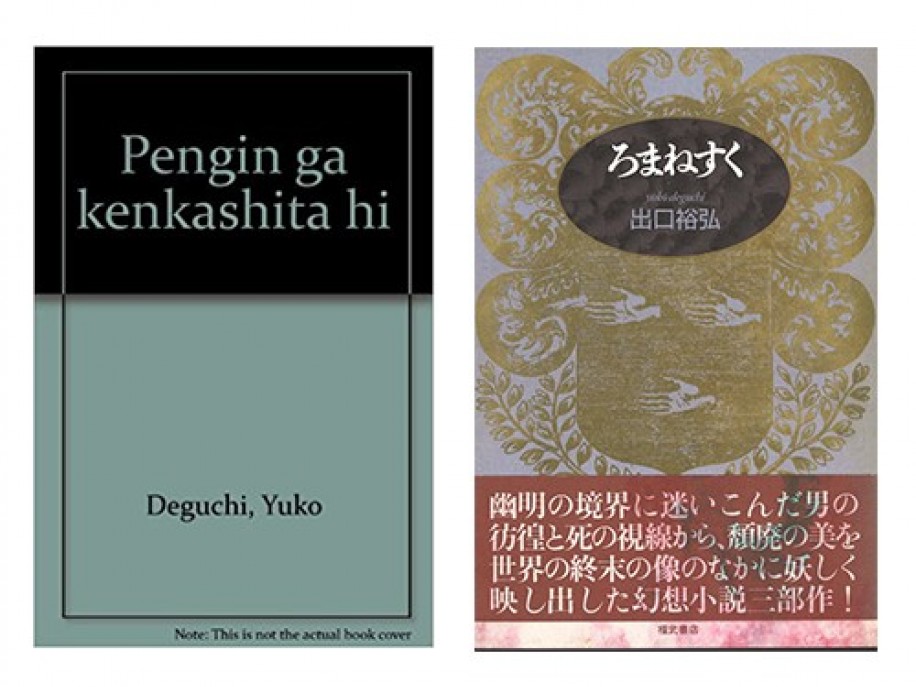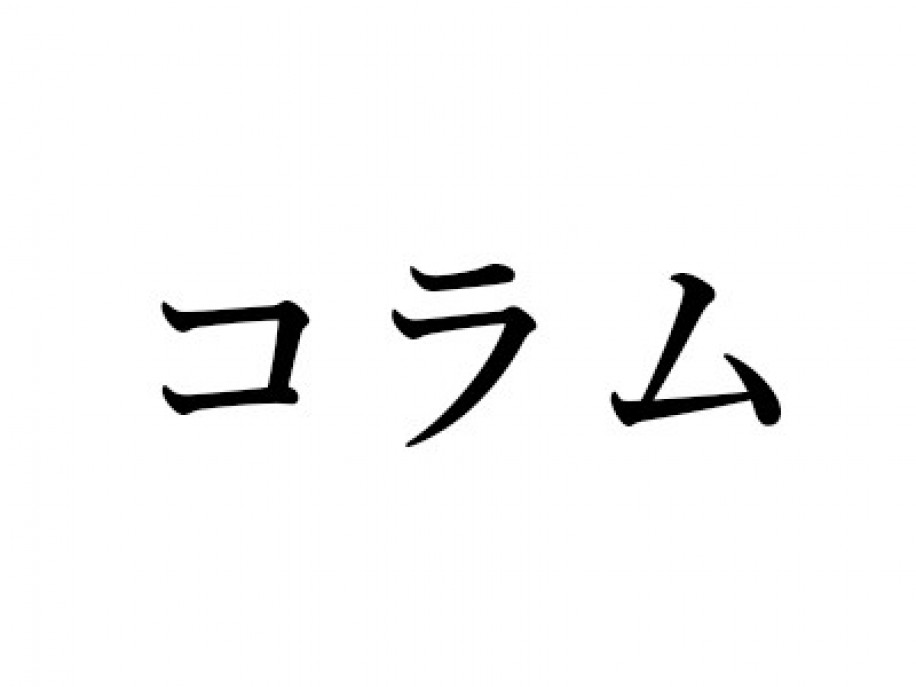自著解説
『坂口安吾 百歳の異端児』(新潮社)
安吾生誕百年 迷妄の霧晴らす「現役作家」
坂口安吾は1906年の生まれ、今年で生誕百年になる。戦後すぐこの人のものを読み始めた世代の人間として、私はこの夏、安吾私論を上梓(じょうし)した。「百歳の異端児」というタイトルはむろん生誕百年に焦点を合わせたものだが、安吾は百歳の現役作家という含みもたしかにあった(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2006年)。安吾といえば「堕落論」「白痴」、一歩踏み込んで戦中の作「日本文化私観」。彼を立論家、あるいは生の指南役として敬愛する人ほど、そこどまりになってしまう。私とて例外ではなかった。まず、この、久しく固定したままの安吾像を壊さなければ何ごとも始まらない。そう思って最新版全集を手がかりに安吾の読み直しを試みたわけだが、今は別のことを書こう。
安吾は“無頼派”と呼ばれてきた。アドルム中毒で神経科に入院し、暴力沙汰(ざた)のあげく留置所入りまでしたのだから、このレッテルもあながち的外れとはいえない。
しかしこの人、病床で幻聴、幻覚に苦しめられながら、なお「抑圧の除去」一点張りのフロイト式療法を痛烈に批判し、院内の患者、医師、看護人の生態を冷め切った目で記述した。まったく油断のならぬ人物だ。
出来、不出来の差の激しい小説のことはさておいても、得手だったエッセーの領域ですら、安吾全集には放言、言い過ぎ、自己矛盾が渦を巻いている。しかし、韜晦(とうかい)はなく、シニシズムもない。すべてが直球だ。読み進むうち、私たちは「明晰(めいせき)の人・坂口安吾」に目を開かれる。
実例を挙げよう。まず、昭和24年発表の「インテリの感傷」から。資源小国、人口大国の日本の経済を安定させる道は貿易しかない。「搾取階級がなくなろうと、なくなるまいと、貿易に依存せずに、日本がどうなるものでもない。外貨を獲得することだ」。戦後まだ日の浅いころの一小説家の発言として、類例のない明察に輝いている。
昭和22年発表の小説「暗い青春」の一節なども、現在ただ今の私たちに、目からうろこの落ちる思いをさせてくれる貴重な証言である。安吾の言い分はこうだ。
政治や社会制度は常に一時的なもの、ほかより良きものに置き換えられるべき進化の一段階にすぎない。「政治はただ現実の欠陥を修繕訂正する実際の施策で足りる。政治は無限の訂正だ」。何か判断に迷うことがあると、私はこの安吾の言葉に返る。すると必ず、迷妄の霧が晴れる。
もし安吾が今、生きていたら――。久しい以前、私は架空インタビューの形でその種のエッセーを書いたことがある。安吾なら、この今の日本について、何をどう書くか。
戦後的価値の全否定などというのは、安吾からすれば「狂信の一種」であり、問題にもならないだろう。狂信と密告ほど、安吾が嫌ったものはない。緻密(ちみつ)な頭脳と、的確な判断力を持った実務家。安吾が好きなのは、そうした人たちだ。
一本、貫徹したもののある国論。それは現在の日本にはない。安吾がそのことをとがめるだろうか。心はいくらでも熱く燃やしていい。だが頭は冷やせ、徹底して冷やせ、それが安吾の進言だと思う。頭を冷やせば、“一億一心”にはならない。
最後に――。自殺者年間3万人を知ったら、安吾はこう言うのではないか。私の全集を読んでくれ。死なずにすむ、と。
朝日新聞 2006年8月19日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする