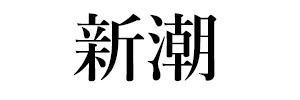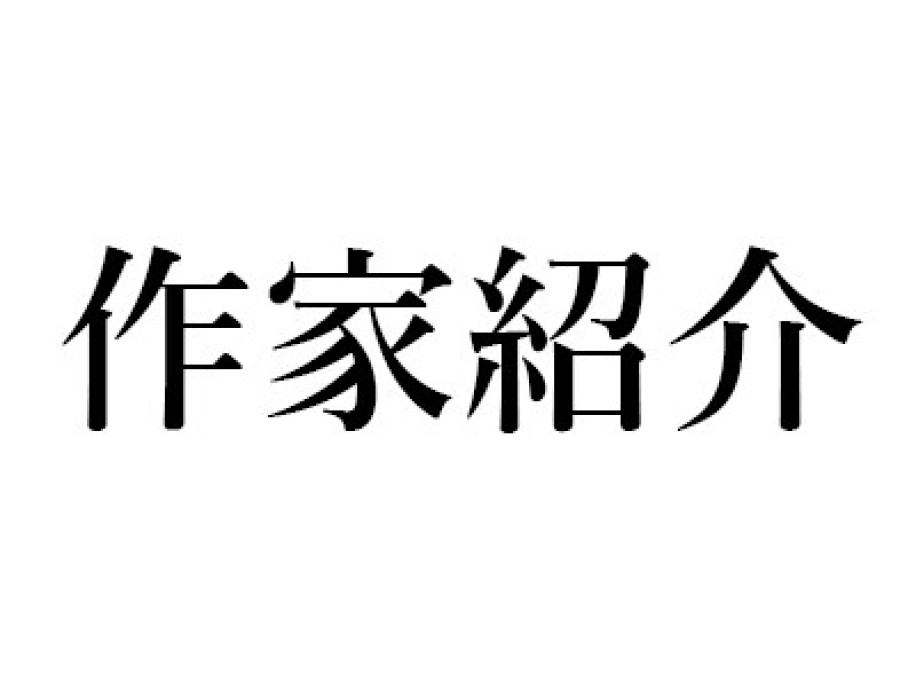対談・鼎談
星野 智幸『目覚めよと人魚は歌う』(新潮社)|星野 智幸×野谷 文昭による対談
ラテンアメリカとの混血へ! (第13回三島由紀夫賞受賞記念対談:星野智幸×野谷文昭)
中上・マルケスからの出発
野谷 星野君、受賞おめでとうございます。ここしばらく僕はメキシコに行っていたので、帰ってきたとたん何事が起きたんだと、ちょっとばかり面食っているというのが正直な感想です。受賞作の『目覚めよと人魚は歌う』(5月31日、新潮社刊)が「新潮」に掲載されたのも向こうにいて知らなかったくらいで、帰ってきて初めて気づきました。それから、三島由紀夫賞の候補になったことを新聞で知り、この間ブラジル映画祭で久し振りに会ったときに話題にしたら、2日後に受賞の報を受けたような次第で、まあ、僕の帰国が幸運の呼び水になったのかな(笑)。
星野 ありがとうございます。
野谷 少々過去を遡れば、僕は文藝賞を受賞したあなたの最初の作品「最後の吐息」を草稿の段階で読まされているんですね。あの段階で読んだ人は限られているでしょう。
星野 ええ、そうです。
野谷 我が家に若手のラテンアメリカ文学者を集めて研究会をやっていたときに、その連中と目を通したんですが、その段階ではみんなで言いたいことを言ってボロクソに叩きました(笑)。星野君はあれで自信をなくしかけたくらいでしたね。
星野 あれを生き延びて体力がつきました。
野谷 打たれ強くなった。
星野 研究会で僕の発表の番が来たので、小説でもいいですか、と断って提出し、読んでもらったんです。しかし、言っていることはみんな違うとはいえ、とにかく酷評の嵐。結果を見ておれ(笑)と内心思いながら聞いていました。でも本当に、彼らが真摯に意見を述べてくれたから、自分で気づかない欠点を知ることができたんです。今でも、彼らに受け入れられるかどうかは、書く際の基準の一つになっています。
野谷 あのときのメンバーはみんなラテンアメリカ体験があり、小説の舞台も知っているから、リアリズム的に読んだんでしょう。こんなことは現実にはありえないという批評が多かったですね。ただ、僕はラテンアメリカ文学を読んだり翻訳したりしながら、その手法や文体に興味を持ってきた者として、こういうタイプの小説は少なくとも日本には今までなかった、と感じました。
たしかにラテンアメリカ文学は一時期日本でもブームになって、作家たちにもずいぶん語られました。しかし、日本文学に本格的に移植されたかどうかは疑問です。ガルシア=マルケスやカルペンティエールなど一部の作家への批評的な言及の段階で終わっていたような気がします。しかし、星野君の作品を読むと、ラテンアメリカ文学を読んだことが、単なる知識に留まらずに文体のレヴェルにまで現れていて、それが面白いと思ったんです。
星野 それは僕が意識したことのーつです。
野谷 一方で、よく指摘されることだけれど、中上健次への思慕(笑)と言っていいような感情が、特に「最後の吐息」には明らかに出ている。これは、本人も承知してやっていることですね。星野君はおそらく、その二つの要素を合わせているんでしょう。中上健次はラテンアメリカ的だ、特にマルケスに近いなどとよく言われましたが、彼には星野君のような作品は書けない。中上健次は中上健次としてあるわけですから。それに対し、星野君はラテンアメリカ文学も読み、かつ中上も読むというスタンスからはじめて生まれてきた人だと思いました。
星野 今、中上・マルケスを読んで書き始めた人として、たとえば目取真俊さんがいます。しかし、僕とあの方々と決定的に違うのは場所の問題です。マルケスと中上は、マコンドや熊野といった場所との抜き差しならない関係の上に自分の文学を作り上げましたし、目取真さんもその関係のあり方を学んだと思われます。しかし僕の場合は、もはやそうした場所との関係は不可能だという認識から出発しています。
それは文学の問題だけではなく、生きてゆく上で拠りどころは何なのかという問題にも繋がる。80年代のポストモダン的言説が盛んだった時期には、拠りどころなんてなくていいんだという無邪気な明るさが世相を風靡した。それで目を開かれたようなところは僕にもあるし、間違いなく旧時代のくびきを断ち切る力とはなっていました。しかし、現実には拠りどころのない状態を耐えられる人は少ない。ポストモダンの言説は多くの人にとって何も考えないための口実となったし、そもそも80年代の明るい気分は何か別のものに支えられていたわけですが、その正体を見極めようとはせずにただ依存していた。90年代を通じてこの拠りどころの問題は反動的に処理される一方であり、今改めて直面せざるをえなくなっています。
野谷 目取真さんについて言えば、『水滴』とそれ以前の短編では大きな違いがありますね。『水滴』ではフォークロアの要素を取り入れ、語り手が個人から集団へと変っている。そこにフォークナーやマルケス、中上を読んだことが生かされていると思います。つまり共同体の力を取り込めるようになったんですね。そういうことが可能な場所を持っていることがうらやましい。でももちろん星野君にはそれはできません。星野君の作品の中に、時おり自分の願望を漏らすところがあるでしょう。映画のセルロイドそのものになりたい、と書いていた。その意識は、今度の受賞作にもありますね。登場人物が、「一本の木になったかのよう」とか「わたしが水であるかのように、魚のあなたはわたしにまみれた」というような言葉が繰り返し出てくるんです。その意識は、大きく言えば、同一性の問題に関わってきます。
今日、一般的には、同一性が崩れていると言われる。しかしその一方で、冷戦後の世界を見ると宗教戦争や民族主義など、過激な同一性の主張がその反動として出てきています。ポストモダン的な認識では捉えきれない状況でしょう。同一性幻想の崩壊とその反動という反復は、永遠に繰り返される課題です。星野君の作品には、私とは誰か、という問いが常にありますが、そこからいかに抜け出るか、そこからの脱出の難しさを含めて、新しい世紀に向けて、どう抜けて行くのかな、という期待がありますね。
星野 疑いえない決定的な同一性の幻想はもう持てないけれども、仮の、あるいはとりあえずの同一性、アイデンティティは必要なわけです。それを、今の日本で生きている場合どうするのか。マルケスや中上の持っていた“土地”は僕のような人間には最初から不可能ですから、それに頼らず相対的なアイデンティティと絶対的なアイデンティティの折りあいをどうつけるのか、それが一番のテーマです。これは近代以降、性懲りもなく論じられ続けてきた問題ですが、解決できていない以上、陳腐だといって切り捨てるわけにはいかない。
野谷 60年代のラテンアメリカ文学の実験性も、星野君に大きな刺激を与えていますね。たとえば、コルタサル。かれは極めてヨーロッパ的な作家で、人称や語りの問題に関して尖鋭な文体の実験を行いましたが、その成果が星野君の作品に生かされていると思います。
星野 先ほど、何かに成り代わることについてご指摘がありましたが、僕自身、相手に染まりやすいところがあるんです。こうして話していても、どうも相手に同化してしまう危険を感じる。だから、この対談の行方もどうなることやら(笑)。こちら側に揺るぎない確固たるアイデンティティがあるわけではないですから、常に他人のアイデンティティに侵食される危険がある。でも、侵食されることと、他人のアイデンティティに全部依存して自分のものにしてしまうこととは、別のことだと思っているんです。侵食されて自分の中で融合することを、僕は、“混血”と呼びたいのですが、それが僕の拠りどころの可能性だと考えたい。
文体の問題もそうですね。相手の文章に侵食されるということは、相手の頭脳を使って考えることになります。僕が文体を一番学んだのは、ラテンアメリカ文学をスペイン語で読み日本語に翻訳してみた時でした。翻訳する場合、原作者の頭脳を借りながら原語を日本語に変換してゆくわけですから、そこに相手と私のある種の融合が起こってくる。もちろん激しい軋轢もある。翻訳することで生まれた言葉はもう“混血”の日本語でしょう。翻訳に限りませんが、それが僕の小説の文体だと思っています。
トポスのないところでどう書くか
野谷 星野君にとっては、島田雅彦との出会いも大きかったと思います。島田雅彦自身も、ポスト中上という意識を強く持った作家ですね。今、トポスがないところでどう書いてゆくかということを最も考えている人でしょう。その結果、いろいろ実験するわけで、たとえば「郊外」をトポスに見たてることをやった。それはそれで面白かったけれども、あくまで「郊外」は架空のトポスであり、継続的にやってゆくことはできません。その事態をすでに自分自身で見せてしまいました。だから、あの実験を真似しようという作家は現れないでしょうね(笑)。星野君の場合も、多少年齢は違うけれども、共通の意識を持って出てきているわけです。マルケスや中上のやったようなことを自分はやりたいけれどもできない。星野君の場合は、先行する作家や作品への愛が、初期作品には、対象そのものになってしまいたいという情熱として出ていました。しかしなれない。なれないからこそ批評性が生まれるわけです。逆に、トポスを持つ作家は、極端に言えば場所を書いていればいいわけで、批評がいらなかったりする。ラテンアメリカにはそういう作家もいます。星野君の場合は、トポスを持たずにどうやって書き続けるか、という問題をプラスに転化して、ラテンアメリカを見つけた。
星野 おっしゃるとおり、「対象になれない」という経験が自分の限界をはっきりさせ、その外側へ踏み出すことを強いるのだと思います。島田さんの「郊外」は、場所というより、土地や地縁血縁から切り離された者たちが仮に集まるどっちつかずの状態を指していると僕は読みました。仮のアイデンティティとして積極的に打ちだそうという試みは僕には理解できますが、現実には仮のアイデンティティを持てない空洞として郊外はある気がする。
ラテンアメリカも、僕にとっては具体的な場所であると同時に、ある概念を表してもいます。言葉、意識が先ほど述べたような意味での混血を起こす時空を、ラテンアメリカとして想定しているわけです。
野谷 中上健次は、現実の「路地」がなくなってから、作品に「路地」というトポスを作り、しかもそれすら後に解体してしまいました。最終的には『異族』の方向に行って完成させずに死にましたが、その中間に、“路地の増殖”などさまざまなことを試みましたね。週刊誌の連載で新宿を舞台に、怪しげでやや劇画的な外国系の人物を色々登場させる。僕はあれも実験の一種だったと考えていますが、星野君の実験も、それにオーヴァーラップする。“混血”というのは境界を越える戦略のーつですね。ジェンダーなども含めて、二項対立を無化してゆく。トポスを作っても、そこに排他的に閉じ籠っている限り、その周囲は外部であり敵であって、永遠に解決できない対立が残ってしまいます。それを無化する戦略として、混血という方法は大きい。中上も同じようなことを考えていたと思います。
星野 これからのアイデンティティのことを考えると、僕の中では二分法という発想は吹っ飛んでしまいます。クローンやインターネットというコピーと増殖のことを思うだけでも、アイデンティティは無数に細分化され、どこが外でどこが内か、どれが敵でどれが味方か、何が本物で何がニセか、まったく判別不能な状態をもたらす気がする。現にジェンダーの問題とは、男か女かの旧来の二分法を超えるというより、どちらともつかない性の領域をどのように肯定していくかに移っていると思います。
そのように一見無秩序と思えるような、相対化の嵐が吹き荒れるような世界で、それを分類するのでなく肯定できるかという点でも、混血という概念は有効なんじゃないでしょうか。
ALL REVIEWSをフォローする