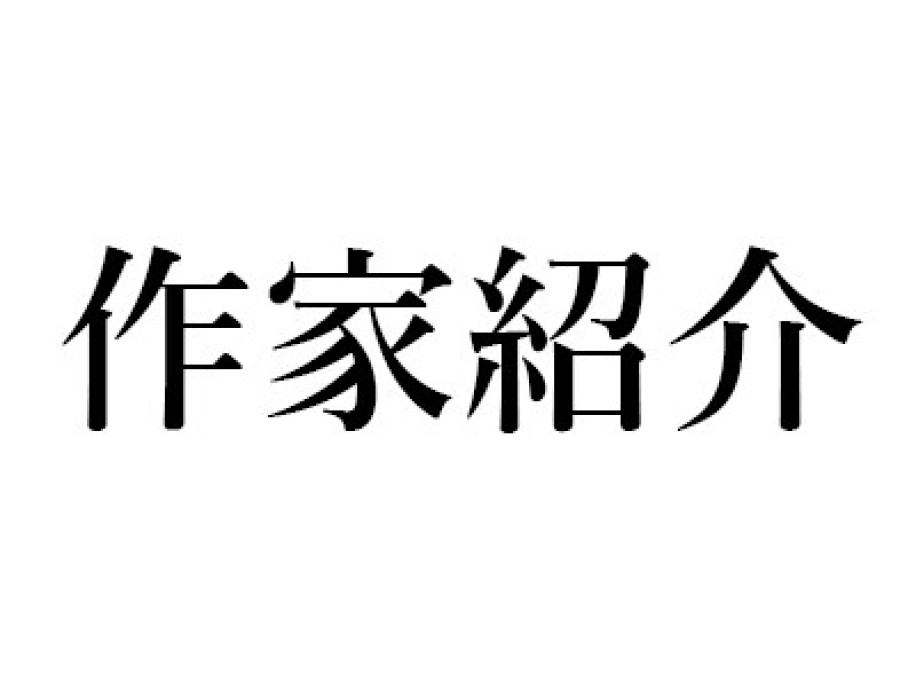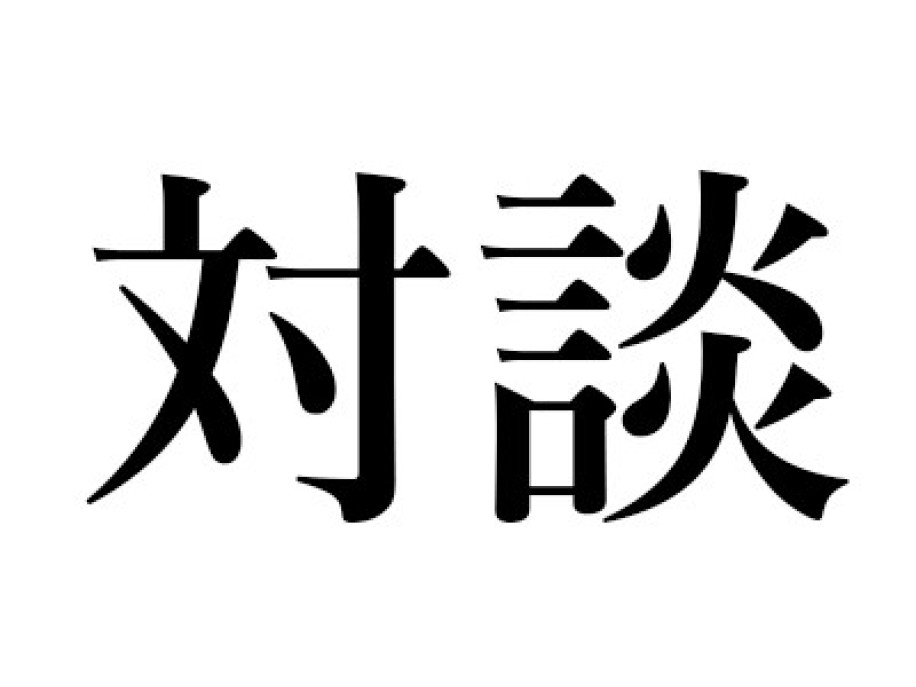書評
『緑色の濁ったお茶あるいは幸福の散歩道』(河出書房新社)
山本昌代の三島賞受賞作と少女マンガ
今回の三島由紀夫賞の受賞作は山本昌代さんの『緑色の濁ったお茶あるいは幸福の散歩道』(河出書房新社)に決まった。山本昌代さんの小説というと、いままでは江戸物が多く、そういう作品に慣れている読者にとっては、今度の作品はちょっととっつきにくいかもしれない。とにかく、紛れもない現代物で、事件らしいこともなにも起きないのだ。では、「なにごとも起きない、静かな日常生活を描いた現代文学」なのかというと、それもちょっと違う。ぼくはこの小説をはじめて開いた時、読みながら、「ああ、これはやはり少女マンガに似ている。それでいて、しかも少女マンガを超えてるかもしれないなあ」
と思ったのだった。
吉本ばななさんの例を持ち出すまでもなく、ある世代以降の小説へのマンガ(特に少女マンガ)の影響は大きい。会話、キャラクターからストーリイまで、マンガからとって来たものが多いのだ。だが、同じ題材で勝負するなら、どう考えても小説よりマンガの方が上だ。少女マンガの影響を受けた、少女マンガ以下の小説の氾濫――そういうのはもう止めにしてくれないかなあ、そう思っていた矢先、ぼくは山本さんの小説に出会ったのだった。
大島弓子や高野文子や萩尾望都や(ずっと昔なら)岡田史子といった先駆的な少女マンガ家たちがやったのは、マンガという武器を駆使して、少女たちの繊細な感受性の奥深いひだにまで分け入ることだった。それは、同時代のどんな小説もできなかったことだということは認めなくちゃならない。
しかし、マンガにできて、小説ではできないのか? ぼくはかねがねそんな疑問を抱いていた。だが、いまは確信を持っていえるだろう。山本昌代のようにやればできるのである。
鱈子さんは「バリリロロニ四肢機能全廃」という病気で足が動かない。時々、詩を書いている。お姉さんの可李子さんは三十三歳で独身で、時々バイトをして、小説を書きたいと思っている。おとうさんの明さんは六十二歳で、ある会社を定年退職して、カルチャーセンターで文学を受講したり、「歩こう会」という会に入って、朝早く出かけて歩いてきたりしている。そのうち、明さんが悪性腫瘍にかかっていることがわかる――と粗筋を書くと、すっごく暗い話に見えるが、別に暗い話のわけではない。なにもかもがすごく淡々と書かれているのである。
「少し明るい知らせがあるといいわね」
可李子がひとりごとのように眩いた。
「どんな」
鱈子さんは瞳を上げた。
「たとえば、……鳥の卵が艀るとか」
「鳥?なんの鳥」
「なんでもいいのよ、ふふ」
可李子が笑い出したので、鱈子さんもつられて笑い出した。卵が殴れて、ひよこが生まれてくる情景が、目の前に浮かんだ。殻の帽子を頭にのせたまま、ひよこは元気よく、好きな方向に走り去った。
生まれたばかりで、そんなスタスタ走れるはずはないのだが、大層頼もしいひよこであった。
簡潔な描写と抑制された会話。この言葉の「刈り取られ」具合は、少女マンガの(傑作の)描線に似ている。しかし、同じ簡潔な描写と抑制された会話でありながら、私小説はほとんど少女マンガと共通性がない。このことの不思議さについては、またいつか。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする