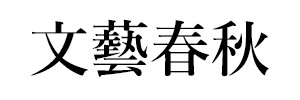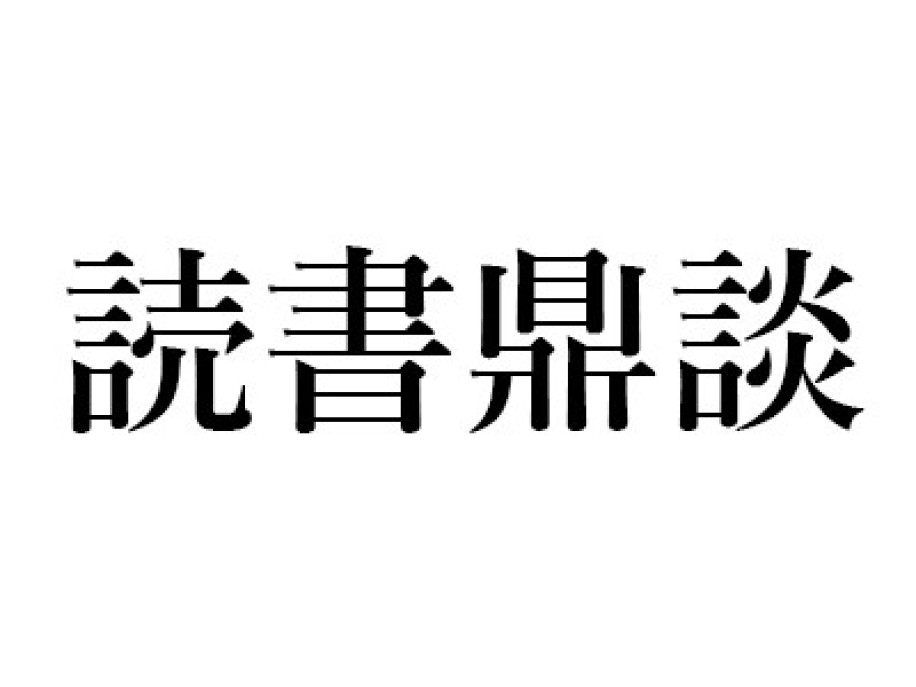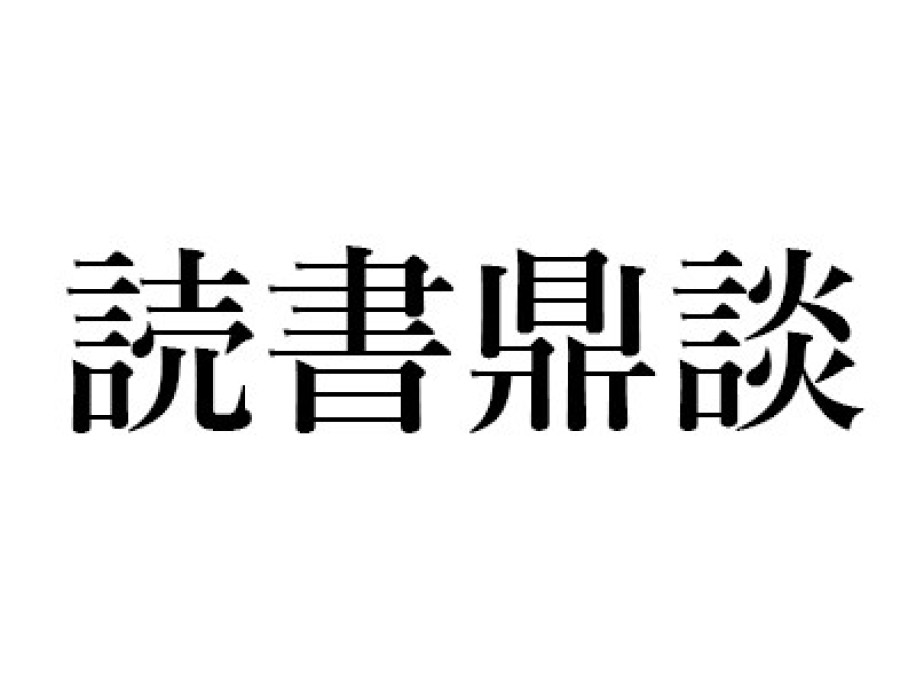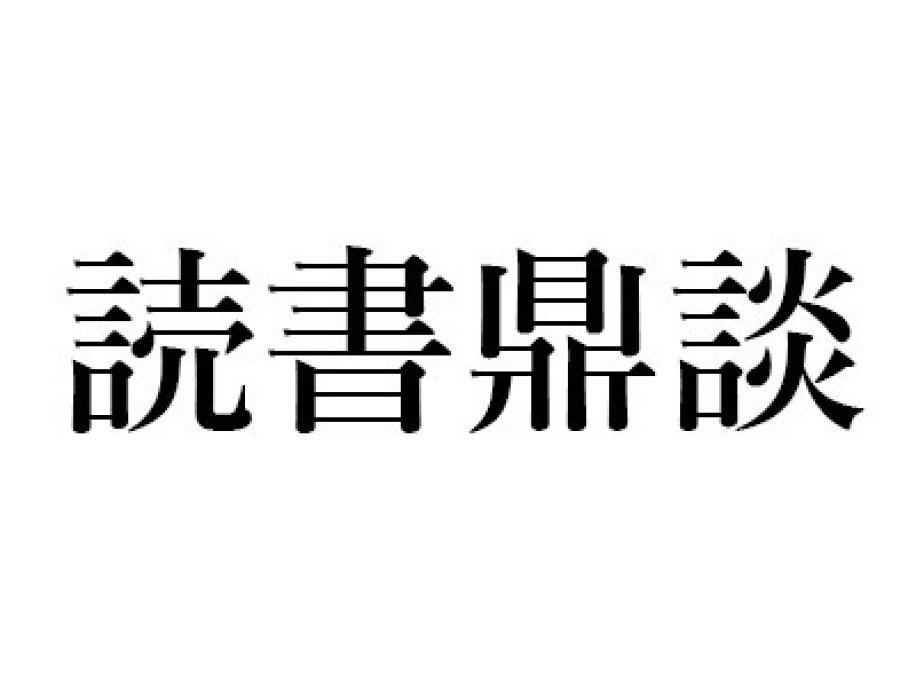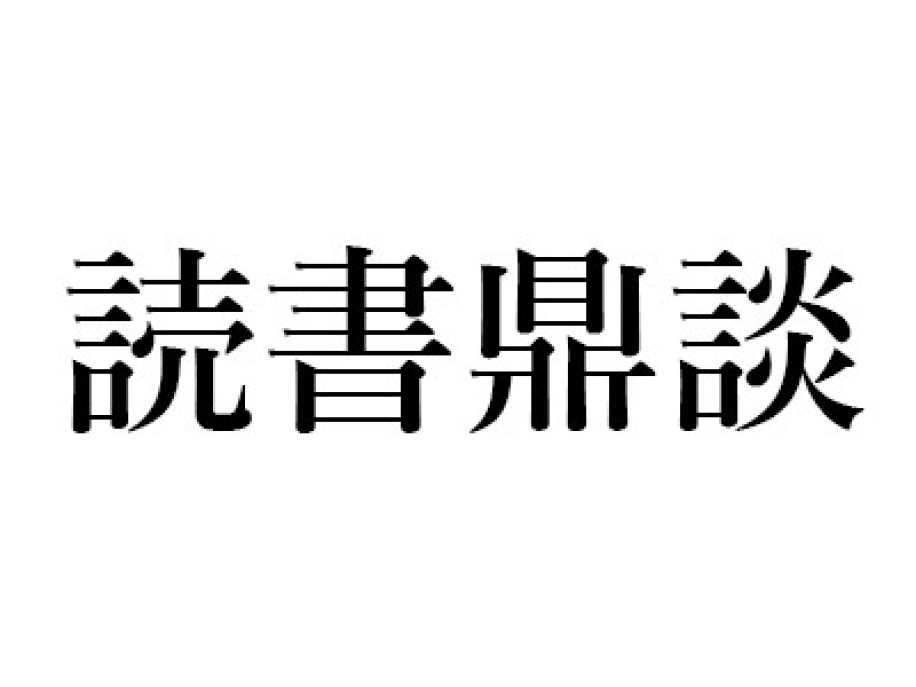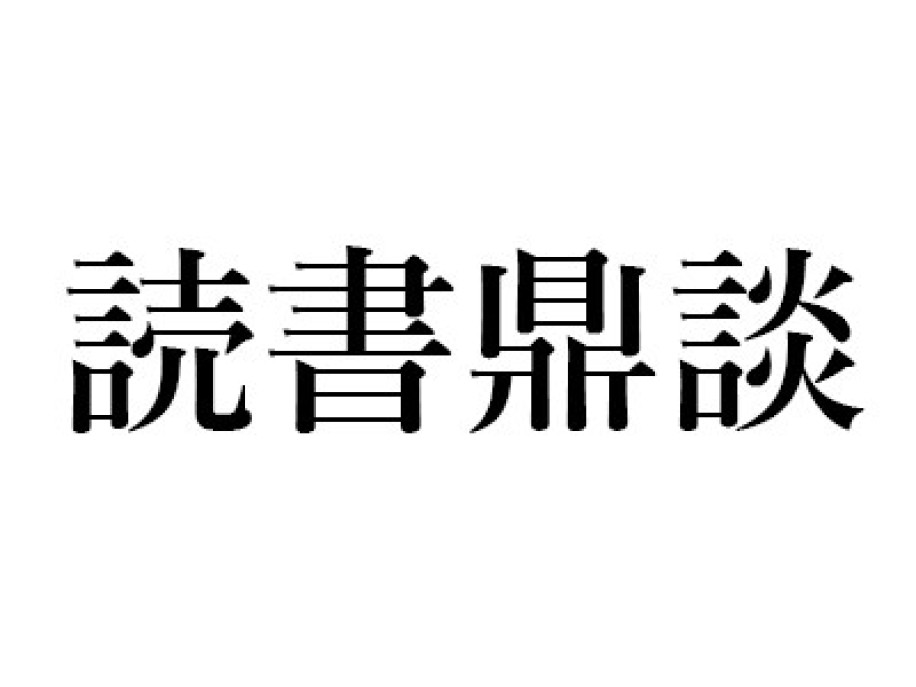対談・鼎談
下村 満子『アメリカの男たちは、いま』(朝日新聞出版)
※ALLREVIEWS事務局注:文庫化にあたり『男たちの意識革命』に改題
木村 この本は、現代アメリカの男たちが直面している厳しい状況を通して、アメリカの家族のあり方を考察したものです。
アメリカでは現在、離婚率が五・二%という高さで、日本の約四・五倍、二組に一組は離婚をする。これは女性運動の影響によるところが少なくないのですが、その女性運動が男たちにどういう翳(かげ)を落としているか、というのが著者の執筆の動機です。
この本は二つの部分に分れていますが、前半は、妻から離婚を言いわたされ、崩壊寸前になった男たちをルポルタージュしています。ある日突然、妻が「私自身になりたい」「自分に正直に生きたい」と離婚を宣言する。相手の夫たちは、概して中産階級のマジメな働きバチであり、伝統的なアメリカンマンとしての価値観を身につけている。それに対して妻のほうは時代の流れに乗って変化している。このギャップが男の地獄を作り出していくわけです。
いざ離婚となると、子供の保護養育権は九五%妻のほうに、裁判所によって与えられる。夫は別れた妻に、生活費(慰謝料)と子供の養育費を払い続けなければならず、また大抵、家も車もペットまで妻に取られ、判決がでてから二十四時間内に自分の家から追い出される。しかも弁護士料は、妻の分も払わせられるという“男性差別”があるわけです。
しかしながらアメリカの男たちはひたすら耐えに耐え、子供の養育のためには転勤拒否もいといません。それが今日、アメリカ社会の移動率を鈍化させる一因になっているそうです。子育てパパの実態が紹介されていますが、厖大な労力と時間を必要とする子育てをしてみてはじめて分ったことは、セックス意欲が低下することと、女がなぜこれまで芸術家として大成しなかったか、ということだと、(笑)そんな感想も出てきます。
しかし後半は、その追いつめられた男たちが、いかに反撃していくかという姿でありまして、女性運動への反発として起った男たちの意識革命、新しいライフスタイルの模索追求ぶりが報告されています。
男が、男の厳しい義務から解放されるには、女性の解放も支持しなくては嘘である。「オレたちはカネを稼ぐ機械じゃないぞ」と叫ぶためには、女性にも男性と同じく収入を得る平等の機会を与えなければならない。典型的「男の生き方」「女の生き方」という虚像を捨ててこそ、新しい男女関係の糸口が把めるのではないか。現在のアメリカの家庭を襲っている混沌と苦悩は、その壮大な実験の避けられないプロセスである――というのが著者の結論です。
この本は、現代アメリカ人の、特にベトナム戦争後のメンタリティがよく分ると同時に、私たち日本人の将来像を多少示唆しているかもしれないという点で、興味深い本でした。
丸谷 本そのものは、大変よくできていますね。調査と報告に徹し切っていて、それ以外、あるいはそれ以上の領域には決して入らないようにうまく抑制してある。なかなか頭がいいと思いました。
いかにも新聞記者らしく、常に具体的、実証的に書いていますし、話術も巧みで、実にスラスラと頭に入るように書いている。ことにいいのは、女の人の書いた本でありながら、男と女に対して大変公平である。
山崎 ハハハ……。ここにちゃんと「笑い」と入れておいて下さい。(笑)
丸谷 「山崎」と書いて「笑い」と入れるのよ。僕が笑ったんじゃないですよ。
木村 アハハハハ。
丸谷 しかもこの公平さが、冷たい公平さではなく、温い感じの公平さである。これは大変なことだと思います。著者がこれだけ温い公平さをもって書くことができたのは、この方は独身なのか結婚していらっしゃるのか、私は知りませんが、とにかく側にいる男の人が、よほど立派な人なんじゃないか、と思いましたねえ。
木村・山崎 ハハハハ。
丸谷 そういう意味で大変感心しました。にもかかわらず、題材が題材なんで、読んでて辛くて仕方がないんですねえ。面白い本を読みたいという人には勧められない……。(笑)
ただ、現代世界について、不愉快なことではあっても、いちおう考えようという人には、「お読みになるのもいいでしょうね」といいたい。
こういう男と女の関係が、もうすぐ日本に渡来するとすれば、これはやっぱり迷惑な話だと思いました。その迷惑な感じというのが、正直なところ、僕の最大の読後感ですねえ。(笑)
山崎 お二人がお褒めになった、かなりの部分に私も同感です。それを前提にして不満を述べるならば、なるほど調査と実証という点では精密ですが、一体何を調査し実証しようというのか、少しはっきりしない。
つまり、男と女という人類普遍的な問題を、アメリカという先進的ケースにおいて観察しようとしたのか、あるいは、特殊アメリカ的で日本の事情とは対蹠(たいせき)的なことが書いてあるのか。同じく実証するにしても、この二つは別の主題ですが、そこがいささか混同されています。私が読んだ範囲で言うならば、ここには何ら男と女の普遍的問題は描かれてなくて、特殊アメリカ的な、しかもアメリカの二流の人物たちが苦しんでいる現象が描かれているだけで、日本人としては大いに安心いたしました。(笑)ですから、丸谷さんも木村さんも、どうぞ胸を撫でおろしていただいていいのではないか、と私は思います。
木村・丸谷 ……(爆笑)
山崎 冒頭のエピソードをお読みになれば分ります。著者は飛行機で隣りあったアメリカ人の技術者から、離婚の話を聞かされるわけです。題に曰く「妻に捨てられた男の悲痛な告白」だというのですが、ここに書かれた範囲で見る限り、この男は、相当に単純な知性の持ち主です。まず最初の結婚では、愛情と黒人解放運動というイデオロギーを混同しています。そういう軽率な結婚をして破綻がくるのは当り前です。二度目の妻に対しても、相手の心理に立ち入って、向こうが自分をどう思っているかという観察が全くありません。こういう男が捨てられるのは別に珍しいことではないでしょう。(笑)
その上に、この男は子供に対するばかげた所有欲を持っていて、ただただ子供に会いたいと願っている。こういう弱い立場に自らを置けば、女に振り回されるのは当然だろうと思います。
そのあと出てくる例をずっと見ましても、大体において、二流、三流のアメリカ人というものが、いかに人間関係において単純素朴であるかということがわかるばかりです。
実は、これを裏返すと日本人の問題になります。私は、かねがね日本人は不機嫌な民族であるということを言っているんですが、不機嫌というのは「不定型」の気分なんですね。責任をもって表現された感情でもないし、自己分析に立った主張でもない。しかしそういう不定型の気分のレベルで、日本人はコミュニケーションができるんです。不定型の気分において自己を表現できる能力があり、かつ相手側もそれを解読する能力がある。日本のもっとも横柄な男といえどもそのくらいは分るんです。
ところが気の毒なことに二流のアメリカ人には、その能力がないようです。彼らにとっては、極めて大げさなキスか、それでなければ憎悪のかたまりか、どちらかになってしまう。その間にある微妙な感情の襞(ひだ)、ニュアンスというところで日頃コミュニケーションする能力がないので、ある日突然爆発してしまう。
男たちが、それまで幸せだと思っていた家庭の中で妻がある日反逆する。「なぜ」と驚いてますが、日本人から見れば、それまで兆候が分らないやつは鈍感だといわざるをえません。そういう無神経がかなり沢山いることは認めますが、しかしあえていえば、私がつきあっているアメリカ人の中で、こういう問題をおこしている人間は一人もいませんね。もちろん離婚した人はいます。しかし、たいへん上手に解決していて、こんな悲惨なことになっているのは、まずいない。
木村 そこが私は面白かったのです。二流というか、平均的アメリカ人の生真面目さ加減ですね。夫と妻がとことんまで言い尽し、言い分が合わないとそれだけで別れてしまう。こんなことはヨーロッパ人、特にカトリック系のヨーロッパ人にはないですね。
山崎 あの人たちは、いい意味で図々しいから。(笑)
木村 大体、男も女も独立の人格、法の下に平等、などということを言挙げしません。強いていうと、男も半人前、女も半人前で、一緒にうまいものを食い、共同生活をして、はじめて一人前、人間的な営みが出来ると思っているわけですね。男と女のあいだに助け合い、いたわり合いがあって、日本人に似ています。
ところがアメリカ人には、お互い角(つの)突き合わせることで、自分が生きている証しを見出したいという気持があります。
丸谷 まさしくそうですね。アリエスの本に、アメリカ人の死に方は、十八世紀啓蒙思想の延長である、という説がありましたね。啓蒙思想という、ヨーロッパ史の中で一番観念的なものが移植され、勝手にグングン伸びて、枝を広げ、花を咲かせた。それがアメリカ文明というものだった、という気がするんです。
そのことが男女の仲にも、法律にも、はっきり表れている。その男女の仲と法律とが悲劇的に出会うわけですから、アメリカの離婚はひどいことになる。
木村 そうそう。
丸谷 これは、そういう現代アメリカの悲劇性を症例集的に描いた本、という気がするんです。セックスの悩みについての精神分析の症例集があるでしょう。ああいうのを読むと、アメリカ人というのは本当に度し難い連中だ、何でこんなつまらないことに悩むのだろう、という気がする。あの感じと、この離婚症例集は似ていますね。
木村 アメリカという国は共通の文化も人種もない国でしょう。タテマエ、理念に生きるより仕方がない。タテマエでいうと「男は強く女は優しく」となる。このタテマエがそのまま法や裁判になって、離婚の場合、必ず女性が被害者となり、子供を育てるのは母であるとなる。それを“男性差別”だといって、いまアメリカの男は嘆いているわけですが、しかしそれはアメリカの女のせいではなく、男たちがそうしてきたんです。つまりこれまではジョン・ウェインの西部劇のように「力は正義」とインディアンを薙(な)ぎ倒していく、夫婦の間に破綻が生じれば、妻を離別し、子供を捨てて、独り西部に旅だち、そこで新しい女性と新しい家庭を築く――というのが、一つの理想だったはずです。
それがベトナム戦争後、アメリカン・マインドに変化がおこって、いまや子供に恋々として、子供と一緒に暮したいという「クレイマー、クレイマー」みたいな雰囲気を生じた。
その点では現在のヨーロッパも日本も共通していると思います。
最近のフランスの若者の合言葉に「VVF(ヴェヴェエフ)」というのがあるんです。「ヴィラージュ(村)、ヴァカンス、ファミーユ(ファミリー)」。夏休みには家族ぐるみで村へ行こう――これがつい昨日までの若者なら、夏休みには親から離れて「太陽のもと砂浜で恋をしよう」、英語で「サン・セックス・サンド」というんですが、(笑)これが合言葉だった。フランスでも親と子が一緒にいるのが幸せ、という気持が一般的になっているんですね。
実は日本でも同じで、大学生のUターン現象も、要するに親と一緒に暮したいということですから、親子の結びつきがこんなに強くなった時期はないと思いますね。
山崎 二流の――とあえて言いますが――アメリカ人には、よかれあしかれ無邪気な連中が多いんです。一ぺん思い込むと、感情の曖昧な部分を切り捨てて極端までいく。ところが極端までいって「これはまずいな」と思うと、また戻ってくる。この本の中にも、ある女性が離別した夫からは「お金、お金」と慰謝料をとっていたのに、別の男が好きになって、この男が前妻からひどい目にあっているのを知ると、今度は義憤にもえて男性の権利のために戦う、という例がでていますね。そういうところがアメリカの強さでもあるし、弱さでもある。ウーマン・リブが極端にまでいくと「父親の権利」を叫ぶ女性が出てくる。日本では常識の中で三十度くらいで揺れてはもどるのが、アメリカでは百八十度振れないと、均衡が保てない。
たとえば、レーガン政権になって離婚率が減ってきたんですが、中曾根内閣になったから離婚率は下がったなんて、それほど日本人はナイーヴじゃない。(笑)
丸谷 この本を読んでいてヘンに思うのは、アメリカ人の子供崇拝ですね。子供がかわいいとか、一緒に暮すのは愉しいといった、ごく健全な常識とは少し違って、病的な感じがする。
山崎 そう、ほとんどイデオロギーにも近い崇拝ですね。
丸谷 変態的な少女愛を描いたナボコフの『ロリータ』がアメリカを舞台にしているのは、意味のあることだという気がしますね。
一方、『トム・ソーヤーの冒険』とか『ハックルベリー・フィンの冒険』という小説を思い出しても、主人公の両親が彼らをどんなふうにかわいがったか、なんて、記憶は全然ない。両親に関係なくスクスク育っているという感じがするんだなあ。子供のそういう面は厳然としてあると思う。ところでその面まで、この離婚した父親たちは拘束しようとしているようで、なにか不健康なんですね。
木村 子供受難時代ですよ。それは文明の成熟したところでおきてくることですね。一方で子供の数を制限する。しかし生まれた子供は溺愛する。どっち道、子供にはえらい迷惑ですね。
山崎 これは既に多くの人が指摘していることですが、アメリカにおいて弁護士の流している害毒について、下村さんも正確に見ていますね。アメリカはもともと法的契約の国であり、建国の原理自身が法的契約であって、それ以外の地縁、血縁、暗黙の常識というものが支配しない国です。その結果としてか、今、弁護士が異常にふえている。一流大学を出た秀才たちがみんな弁護士を志すものだから、科学技術者や大学教授になる人間がいない、というのが実は問題なんです。この弁護士連中は何で飯を食っているかといえば、法的トラブルで食っているわけで、この連中が離婚を捏造(ねつぞう)しているというのは正しい指摘ですね。
したがって、これは特殊アメリカ的な現象であって、ヨーロッパにも日本にもあまり関係がない。ちなみに申しますと、日本は戦後、民主主義になってから、人口対比の弁護士の数は減っているんです。それほど日本人は良識的に行動していますから、こういう馬鹿げた現象にはたぶん感染しません。(笑)
木村 最近のアメリカでは離婚の増加傾向がとまったようですが、たしかに低成長のなかで、セックス第一主義とか個人の自立よりも、家族の結びつきが大事だという考え方に戻ってきているのかもしれません。
著者は、アメリカは新しい家庭を模索しているのだと、好意的に見ようとしているわけですが、それには一抹の疑問もあります。たとえばある再婚した女性が語る“家族パーティ”の様子ですが――
〈私たち夫婦、私の先夫とその妻、私と先夫との間にできて私が育てている二人の娘、私の今の夫と先妻との間の子供二人、私と今の夫との間にできた三人の子供、私の先夫の今の妻が前の結婚で生み、連れている女の子、そして彼らの新しい子供たち二人、と計大人四人、子供十人という大人数になりました〉……(笑)
こうなるとどうでしょう。新しい家庭というより、家庭の混乱ではないかと思いますね。昔の王侯貴族がこうですね。
丸谷 そう、ルイ十四世とか徳川将軍とか、ああいう暮し方はまさしく家庭喪失ですものね。
山崎 アリエスがいっているように、現在の家族のイメージは十八世紀にできたもので、わずか二百年しか続いていない。これはひょっとしたら、壊れるかもしれません。日本でもシングルがふえているというし、そんなことはちっともかまわないと私は思う。ただその過程で、この本にあるような男女間の悲喜劇、無用な葛藤がおこるかというと、これは特殊アメリカ的であって、おそらく他の国ではまずおこらないだろうと思います。
木村 日本では「亭主は丈夫で留守がいい」なんていいますからね。(笑)アメリカではいつも一緒にいて、理解し合おうとするから悲劇になる。その点、日本では良識が働いているから大丈夫だ。(笑)
【この対談・鼎談が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする