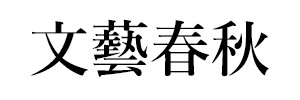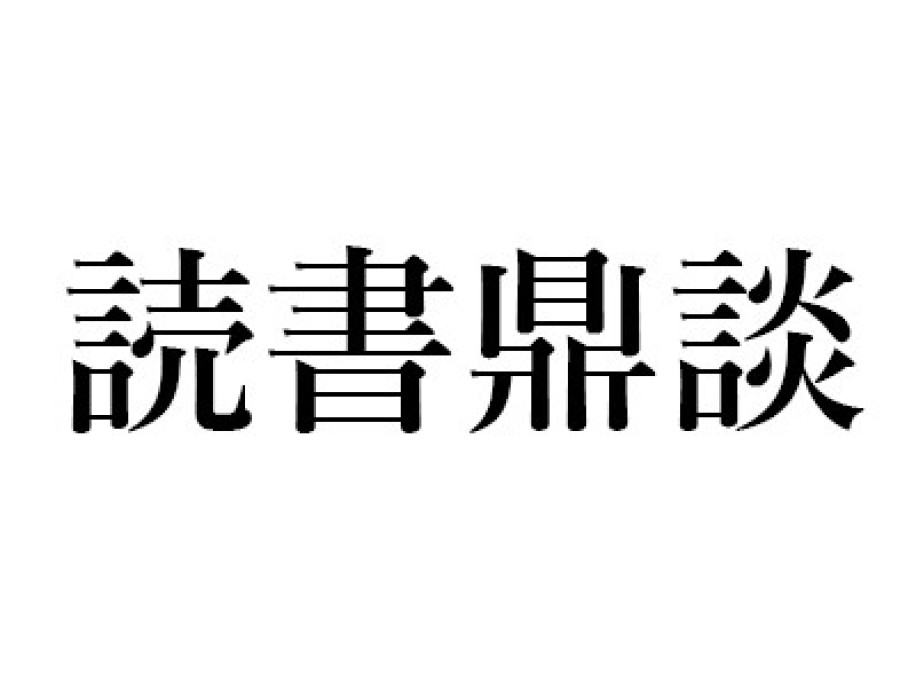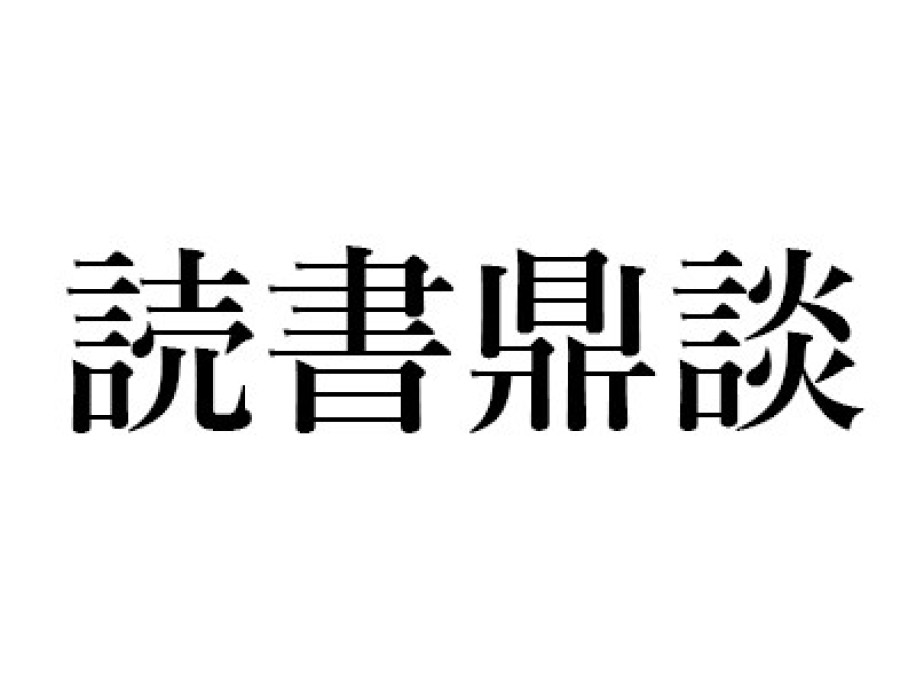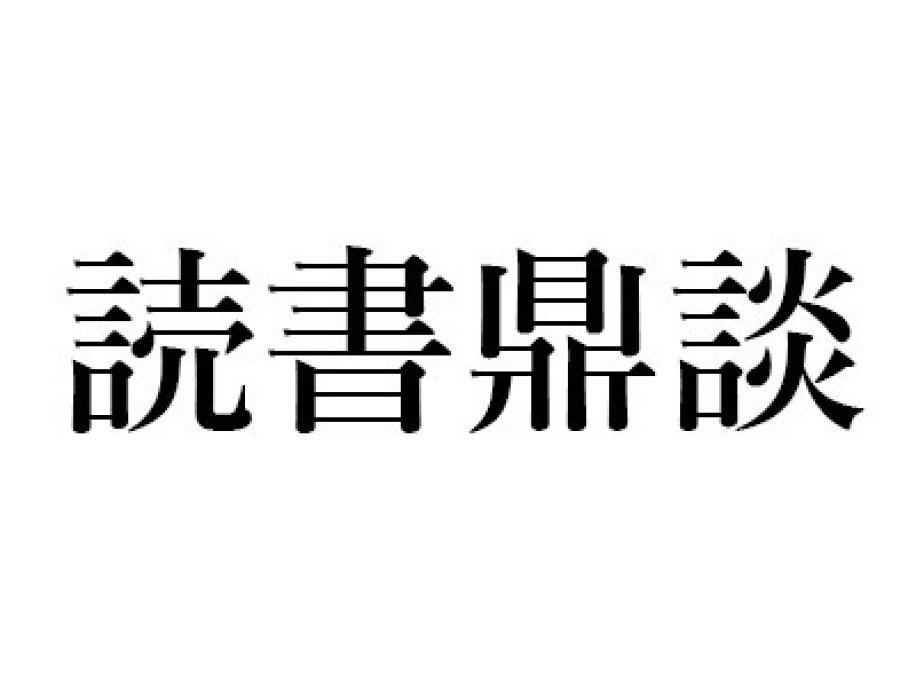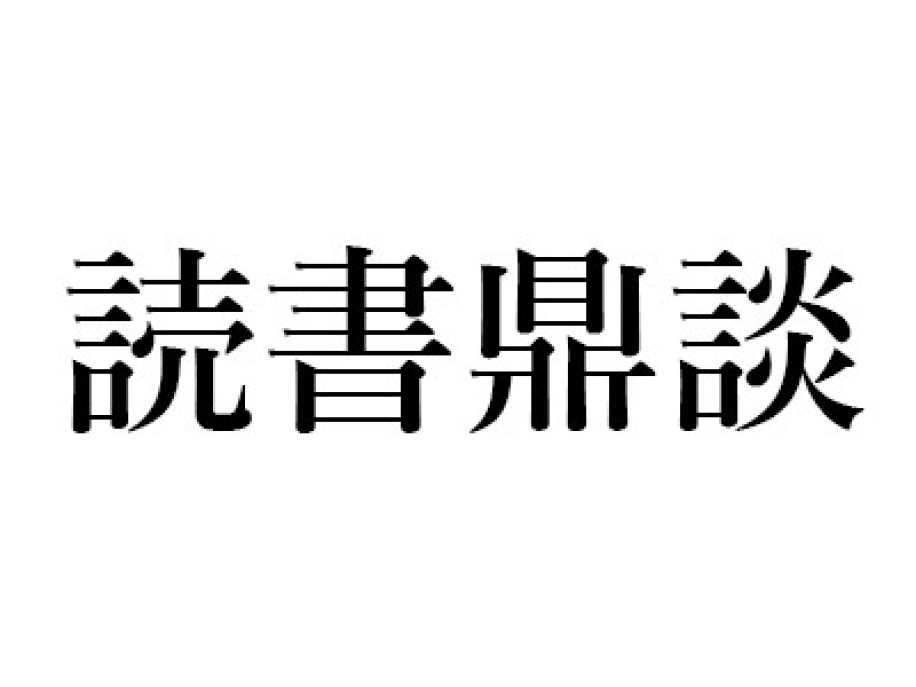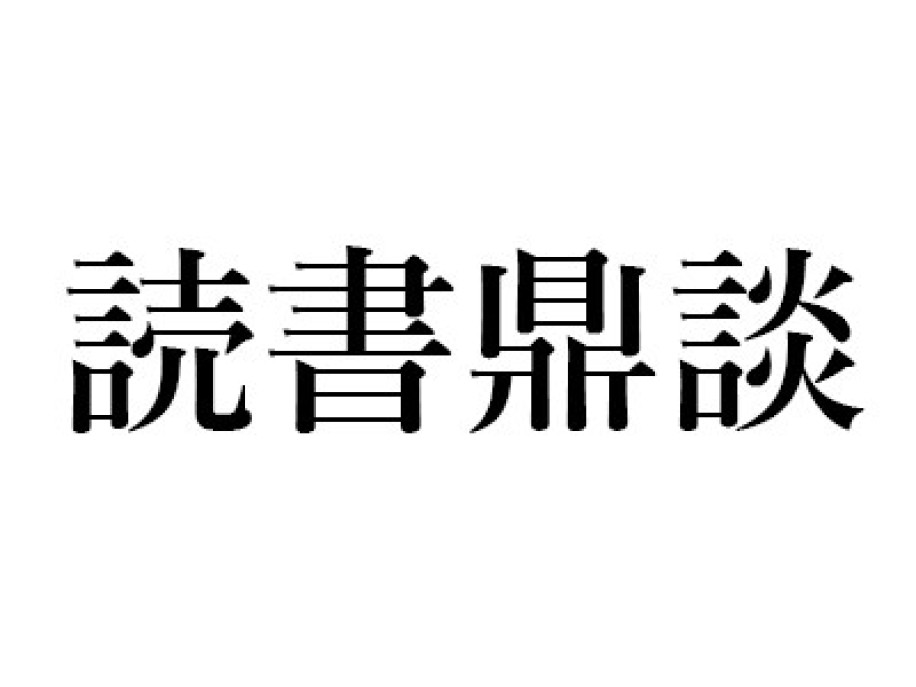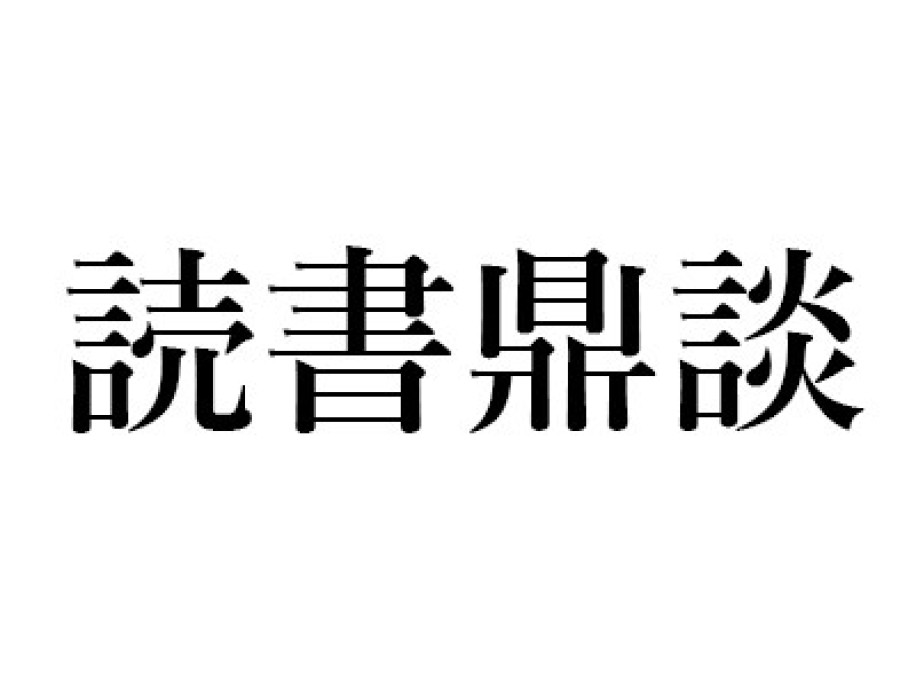対談・鼎談
ホイチョイ プロダクション『見栄講座』(小学館)|丸谷 才一+木村 尚三郎+山崎 正和の読書鼎談
山崎 先の本が高度に屈折したユーモア精神の書だとしますと、これは、極めてあからさまな諷刺文学であります。
内容を一言で説明しますと、現在の社会は、才能も容姿も十人並みで、しかし、楽しく生きたいと願っている若い世代がうようよしている。そういう人間にとって、実質を磨くとか、理想を描くというのは、無理でもあり無意味であって、所詮、女の子を引っかけるための見かけをつくろうほかはない。しかもいまの若者はいつも団体で行動している。その中で群を抜いて見えるようにするにはどうすればよいか、その実践的戦略をお教えします――という体裁で、実は毒々しい諷刺を若者たちに突きつけているわけです。
テニス、フランス料理、モーターバイク、軽井沢、外国旅行などの楽しみかたという項目を立てて、その中でありそうな現代の軽薄なる風俗を徹底的に誇張することによってからかおうという趣向なのです。 ついでに感想をいうと、今日、諷刺するに足る対象は、実は大衆のほかにはないのかもしれませんね。かつてのような権力者とか大金持ちとか、直接に攻撃できないようなこわい相手はいなくなってしまった。そうすると、わざわざ持って回って諷刺をするほど恐しい相手は、ひょっとすると大衆しかいない。
丸谷 なるほど、うまいことを言うなあ。
山崎 もう一つ。諷刺というのはただの批判とは違って、自分の内部にも浸透している敵に対して向ける武器なんですね。自分自身がその中に巻きこまれている敵。まさに大衆こそそういう存在ですね。
実際にこの著者たちも、自分がその諷刺の対象である若者の仲間だということを告白しています。たとえばブスと埼玉を毒々しく軽蔑する点において、著者自身、まさに現代の見栄っぱりの若者の態度そのものをとっていますし、怪しげな横文字を羅列し、安手のジョークを連発します。しかもそれが安手であるということも、ちゃんと自認しています。
さらに手のこんだことに、著者の自己紹介によれば、文章を書いた馬場康夫氏は、〈米マサチューセッツ工科大学を首席で卒業後、ハーバート・ビジネス・スクールに三年間学び、見栄ライフスタイルの概念を生みだした。現在、情報工学の研究に従事する傍ら、脚本家、映画監督、作家としても活躍。テニス、スキー、スキューバ・ダイビングはプロ級の腕前。元ミス・カリフォルニアの夫人とともに東京都「港区」に在住〉
一方、絵を描いた松田充信氏は、〈カリフォルニア芸術大学(カル・アーツ)を卒業後、主として「ニューヨーカー」誌を舞台にイラストの腕を振う。世界のトップレベルの芸術家と親交があり、特にサルバドール・ダリとは「松っちゃん」「ダリ坊」と呼びあう仲である〉。(笑)
つまり、自分自身をもこうやって戯画化するのであります。 そして最後に、この人たちはなぜかオジサンであることを気取りまして、一席のまじめなお説教を垂れます。見栄をはるのは結局はばかばかしいことである。そこから一歩踏みだして、自分自身に対し見栄をはる“美学(ダンディズム)”へと発展すべきである、と。
前回取りあげた『地球ドライブ27万キロ』でも、三十代の著者が現代の若者に対し、老成した焦燥を感じているのを見たのですが、この著者たちもそうでして、どうもいまそういう一群の中年増がいるらしい。そうすると、われわれ本当のオジンは世の中についてあまり心配する必要がないのかもしれません。(笑)
丸谷 六〇年代の途中からのち、硬直した真面目主義ではどうもいけないという風潮が日本に生じたわけです。真面目の押し売りをやめて、笑いとユーモアで行ったほうが世の中や人間がずっとよく見えるし、うまく生きることができる。そういう認識が広まったと思うんです。これは大変な進歩だったんですね。 しかし、笑いとユーモアにもいろいろカテゴリーがあって、趣味のよいのもあれば、趣味の悪い低俗な笑いとユーモアもある。
ちなみに、戦前にあって、戦後の日本になくなった言葉に、この「趣味」がありますね。もちろん「新郎は多趣味な方でありまして」とか「趣味は田中角栄」とか、(笑)そういう意味での趣味(ホビー)はありますよ。でも「あそこの家(うち)はどうも趣味が悪くてね」とか「それは悪趣味だよ」とか、そういう意味での「趣味(テイスト)」はなくなった。
戦前の日本がもっていた「美的な洗練」をデモクラシーと引き替えに失ってしまったんですね。 こんど、この本を読んでみて、やはり現代日本の趣味ってものは、やはり僕が思っていた程度のものだったんだなあと安心したり、寂しい思いをいだいたりしました。
吉行淳之介さんの訳した、キングズリー・エイミスの『酒について』という本があります。酒を題材に、真面目なことは何も書かないで、しかも実用的に論じようという長編評論ですね。ジャンルとしては『見栄講座』も『酒について』もまったく同じです。しかし、趣味という点でいうと次元が違う。 そのことについて、僕はこの著者たちを非難しようとはちっとも思いません。笑いとユーモアによって人生と世界を捉えるということは、日本人がつい十年前か二十年前から習い始めた領域なんですから、このくらい未熟で、程度が低く、幼稚なのは当り前だと思うんです。
木村 丸谷さんはいま、非難しようとは思わないとおっしゃいましたが、私は声を大にしてこの本を非難したい。(笑) まず第一に、私はいままでフランスでも日本でもレストランに行くと、まずキールを、それからボージョレーを注文していたんです。(笑)
山崎 まさに『見栄講座』にすすめてあるとおりですね。(笑)
木村 そうです。ところがこの本が出てから、私はキールもボージョレーも注文できなくなった。(笑)
二番目に、これが一番大事な点ですが、この本には本当と冗談、無知・半知が断わりなしに入り混っています。これは若い人に与える害が非常に大きい。
たとえば「見栄海外旅行」の章で、観光客と旅行者の区別が書いてある。観光客は〈ヨソ行きのスーツにピカピカの黒い革靴。期待と不安の入り混る中にも嬉しそうな表情を隠すことができない〉。旅行者のほうは〈ジーンズにボタンダウンシャツとセーター、ちょっとそこまでという雰囲気が大切〉。これは確かに旅慣れた人とそうでない人との区別をよく捉えたもので、私も評価します。
ところが半面、最近は外国のホテルでも日本語のわかるフロント係がいるから〈まず初めに「この変態野郎」とか「うすらハゲ」などと悪口をいって、様子を見ること〉というんですが、「変態」とか「うすらハゲ」とかいえば、相手は日本語が分らなくても、こちら側の態度、表情で、悪口を言ったなとすぐに分ります。(笑)本当に相手をののしる場合は別として、こんな言葉を軽々しく絶対に言ってはなりませんね。
それからシャンパンの話。〈栓を抜くポーンという、あのかわいた心地よい音は男と女の夜の冒険の始まりを告げる号砲の響き〉であると書いてありますが、ポーンと音をさせるのはアメリカ人のやることでヨーロッパでは下品の極致ですね。
丸谷 アメリカではいいんですか?
木村 アメリカ人は安シャンパンしか飲んでないから。(笑)ヨーロッパでは音を立てず、少ォしずつ少ォしずつ気を抜くのが品の良いやり方です。
もう一つ、ビストロの語源として、〈「ビストロ」というのは、もともと「早くしろ」という意味のロシア語で、ナポレオンのモスクワ遠征の際、フランスの兵士たちがこの言葉を覚え、料理の出の遅いレストランで面白がって「ビストロ、ビストロ」と連発したため、「料理店」を意味するようになった〉……。
丸谷 ぼくもこれは初耳でした。本当ですか?
木村 普通は「ビストゥイユ(安酒)」という言葉からきているといわれるのですが、定説ではなく、語源はよく分りません。ただ、モスクワ遠征は一八一二年でしょう。ビストロという言葉が出てくるのは一八七〇年以降、あるいは十九世紀末のことで、この本の説はちょっとおかしい。
山崎 これはジョークでしょう。
木村 そうだったら断わり書きがほしいところですね、二十代の純情な人は信じますよ。
三番目に、港区民の話がでてきます。港区民はブルジョワの遊び人で、身体の九〇%はコレステロールでできており、階段を二階分歩いて登ったら心臓マヒになる、とか。これはジョークでしょうが、港区民の人は、多少迷惑してるんじゃないかと思う。(笑)
山崎 著者たちは、一所懸命背伸びをして、若者たちを見下げようとしているのか、あるいは本性、保守的で、いまの若者に対し心底怒っているのか、いずれにせよ相当に意地が悪いんですよ。たとえば「見栄バイクのまとめ」のところに〈もしも事故を起こしてしまったら、見栄ライダーたるもの、力の限り大きなケガをして派手に血を流し、見物人を喜ばせてあげるようにしましょう。特に、頭をグジャッと割って脳ミソを露出させ、大腿骨が皮膚から突き出すような骨折をしたりすると、ヤジ馬が感動してくれます〉
読者に対するこの毒々しい悪意から見ると、シャンパンの音を高らかにたてろというのも、ナポレオンの軍隊がビストロという言葉を発見したというのも、同じような悪意から出た創作だろうと思いますね。
先ほどの丸谷さんのご批判に対しても、私は半分賛成で、半分異論がある。この本のジョークは甚だ質の高くないものです。しかしエイミスが『酒について』を書いた時代、その読者は大衆化社会の始まる前のイギリス人で、いわゆる本当の意味の中産階級、あるいはそれよりも上の知識階級だったんですね。そののち、大衆社会が到来した。
ことにわが国には甚だしい大衆社会が出現したわけです。多分、エイミスとともに酒を飲んだ人間の何十万倍もの人間が、いまやエイミスが飲んだのより高いブランドの酒を飲んでいる、この混沌は恐るべきものですね。いまエイミスをつれてきて、現代日本に皮肉を投げかけても、太平洋に香水を一滴たらすようなものでしょう。
こういう時代の申し子である著者たちは、非常に粗々しい諷刺を社会にぶつけることによって、出直そうとしている。つまり、日本は生産社会から消費社会になりつつあるわけですが、消費というのは生産と同じくらい骨が折れることだ。会社勤めより遊んでいるほうが大変だよ、ということをこの著者たちはいっている。これはやはり意義のあることで、どんな高級な文化もこういう粗野なところからスタートするわけです。
たとえば日本の茶道も、最初に成り上がりの大名が、お茶を飲んでどんちゃん騒ぎをしていた。それがやがて佗(わ)びの茶になっていく。その間、あんがい早いもので数十年しかかかっていないんです。
丸谷 それは僕の言ってることと同じでしょう。だから、僕は決して非難はしない……。(笑)
山崎 なるほど。(笑)もう一つ面白いのは、いまは個別化の時代で、みんながひとりひとり、深くて狭い専門的知識をもち始めたんですね。週刊ポストに「ウンチク漫画」という連載があります。どうでもいい知識をやたらに披瀝するオジサンが登場する漫画で、どこが面白いのかさっぱり分らないけれど、妙な人気がある。いまや蘊蓄(うんちく)時代なんです。この本もそういう感覚で書かれている。軽井沢や外国旅行の箇所は確かに底が浅いけれど、バイクやテニス、サーフィンの章などは相当調べて書いてありますね。
木村 調べてはあるけれど、調べの足りないところもある。そこが問題です。この本は前半のほうが面白いですね。
丸谷 後半俄然弱くなりますね。後半が弱い本を書くのは、素人っぽい人か、体力のない人か、どっちかなんですよ。
山崎 だって素人なんですから。(笑)
木村 加藤秀俊さんに伺ったんですけど、こういう本はすでにアメリカにあるんだそうですね。
山崎 六〇年代の終りに『ヒッピーのためのハンドブック』という本が出ていて、ヒッピーになる方法が具体的に書いてある。そして最後に、おまえたちは病院に行くことを拒否しなければならぬ、なぜなら病院は体制に属しているからだ。最後は伝染病にかかって死ね、と書いてある。(笑)そういう毒々しさをこの本は受けついでいるんですね。
丸谷 グレアム・グリーンが弟と一緒に書いた『スパイズ・ベッドサイド・ブック』という本がありますが、一体に英米文化には手引書、入門書という形式で冗談をいう形式があるのね。かなり、たちが悪い。
木村 十四、十五世紀のヨーロッパは低成長が始まった時代ですが、ホイジンガの『中世の秋』によると、当時のブルゴーニュの貴族たちは、絢爛豪華な衣服を着て儀礼を重んじ、見栄をはって生きていた。現代もやはり低成長時代で、実質よりは外見を飾る、見栄の時代になっています。そういう時代相を表しているという点では、これは象徴的な本ですね。
山崎 われわれは実質を信ずることの危険を――唯物論にしろ、観念論にしろ――知ったわけで、そうすると残るのは見かけですよ。ただ見かけをどこまで深化して捉えるかということが問題です。この著者もそのへんのとば口までは気がついているように思います。
丸谷 見栄ってやつを捨ててしまったら、文化は成り立たないですからね。見栄は大事なんですよ。ぼくも今日は『見栄講座』を論じるので、ちゃんとボウ・タイをしてきました。(笑)
【この対談・鼎談が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする