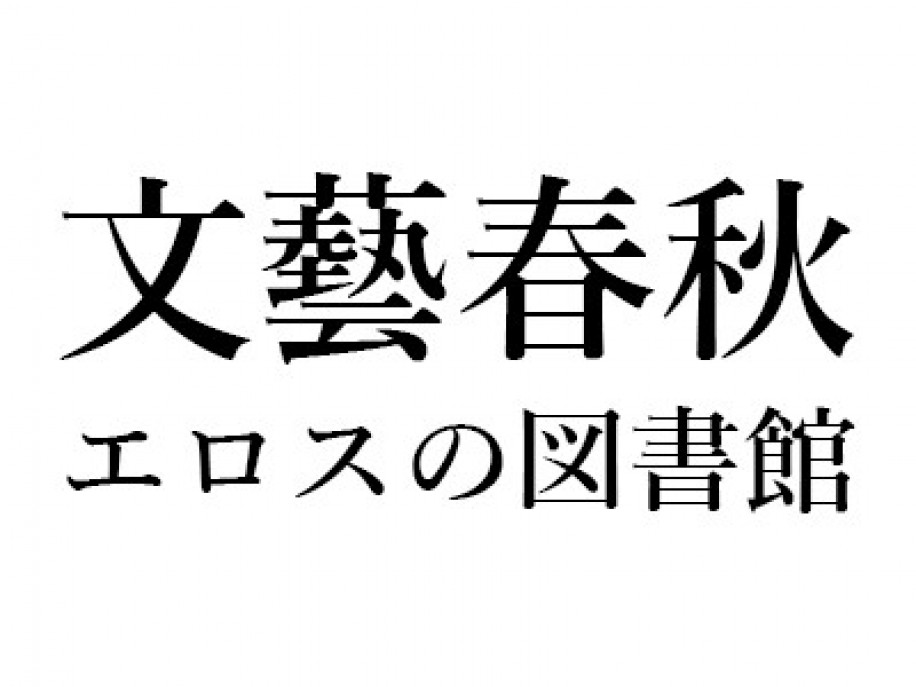書評
『その道のプロに聞く生きものの持ちかた』(大和書房)
大人も子どもも思わず指が動く
虫に遭遇すると、へっぴり腰になる。自分の指を差し出してみたくなるのはてんとう虫かホタルくらい。庭に柑橘(かんきつ)類の木があるから黒アゲハがときどきやってくるが、つかまえたりはせず、ひらひら飛んでいるのを目で追って楽しむだけだ。生きている蝉(せみ)を最後に持ったのはいつだったか、それもなかなか思い出せない。夏の終わり、道の途中に転がっている蝉が踏みつけられてしまうのが哀れで、そっとつまみ上げて土の上に移したりはするけれど。なのに、『生きものの持ちかた』にわくわくするのはどうしてだろう。指先にかすかに残っているカマキリ、クワガタムシ、トンボなんかの感触がなつかしいからだろうか。いや、違う。単純に知ってみたいのだ。そんな気持ちが自分のなかにあることも、ちょっと新鮮だ。
ページをめくりながら、「あ、知ってる!」「へぇそうだったの!」の連続だ。言葉ではなかなか説明しきれない持ち方の勘どころが実例写真で示してあるので、(わたしにも)よく理解できる。こんな感じかな、と指を動かしてシミュレーション。カブトムシを持つときは、小さなツノの部分。メスにはツノがないから、羽の横。クワガタやバッタは前胸。“草むらのチンピラ”カマキリは、細い胸と関節を同時に持つと、「すべての攻撃を防げる」らしい。赤いザリガニ、これはやっぱりなつかしい。そうそう、子どもの頃、そっと後ろから近づいて、硬い殻を指で挟んでえいや!と確保したっけ。ザリガニ獲(と)り、好きだったんだ。
著者は、生きものを専門に撮影するカメラマンで、生きものを持つ必要に迫られることが多い。とはいえ、「生きものをわざわざ持ったりはしない」。むやみに触らないのは「自分を守るためでもある」。しかし、不意に出くわして、あらぬ攻撃を加えられたらなんとしよう。本書は、「触るススメ」ではなく、身近な動物を知る入門書としての一冊。
生きものの体の構造、性質、運動能力はもちろんのこと姿勢、音、ニオイ、殺気などの今、目の前でおこっているすべての情報を集め、行動を予測することが重要なのだ。
いろんな記憶が蘇(よみがえ)ってくる。道を歩いていたら急降下してきたカラス。沖縄の離島で、不意に草むらから出現したハブ。いきなり攻撃してきたハチ。恐怖ばかりが先立ち、ついパニックに陥ってしまう。でも、「持ちかた」という視点を手に入れておけば、あわて方もすいぶん違う気がする。実際には持たなくても。
イヌやネコ、ウサギ、プレーリードッグ、セキセイインコもいれば、一生絶対持たない(持ちたくない)生きものも登場する。ハリネズミ。タランチュラ。オオトカゲ。ヒョウモントカゲモドキ。アシナシトカゲ。スッポンは、緊急対策としては、甲羅の後ろ側を両手で必死で持てばいい、と頭に叩(たた)きこんだ。スッポンを食べることだってあるし、ご縁があるから、いちおう念のため。
ALL REVIEWSをフォローする