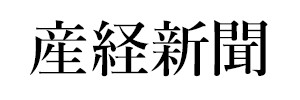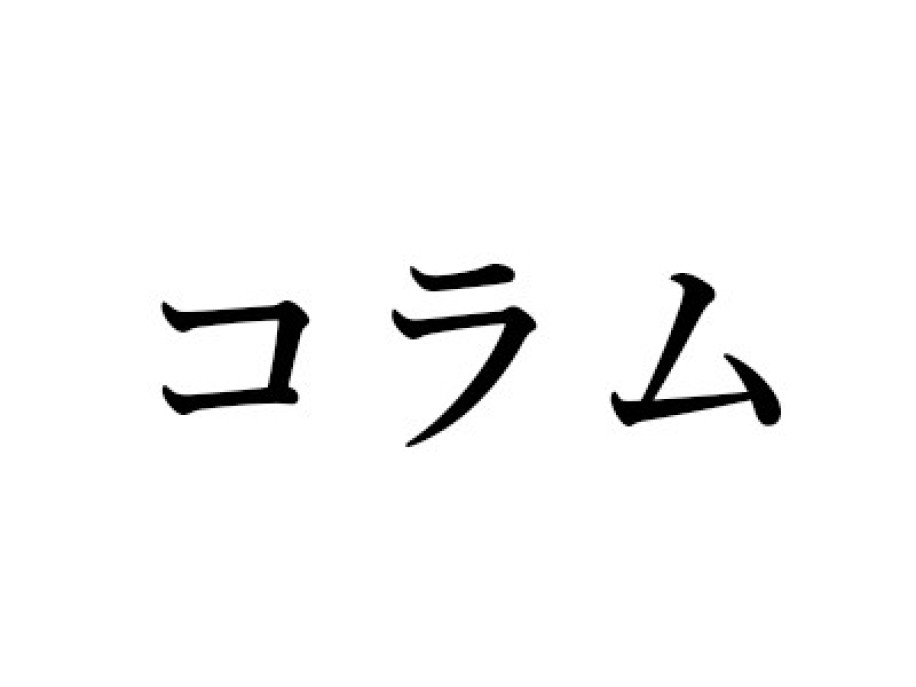書評
『口笛を吹きながら本を売る: 柴田信、最終授業』(晶文社)
毎日を「普通」に懸命に
柴田信は現在85歳にして現役の書店員(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2015年6月。柴田氏は2016年10月12日、死去されました)。神保町にある岩波ブックセンター代表として、週に4日、自宅から1時間以上かけて通勤する。教師からトラック運転手を経て書店員という変わり種で、本に関わって半世紀を経た。本の街・神保町をそぞろ歩けば、あちこちから柴田に声がかかる。そんな「顔」に2年も密着し、話を聞き出してできたのがこの本だ。
著者は、出版業界紙で長く記者をしていた経験を生かし、柴田の書店人生と、現状について細かく話を聞き出す。「本には不思議な魅力がある、関わっている人をあきらめ悪くさせる」。これが著者と柴田の共通認識だ。
柴田が本書でくり返しこだわるのは「普通の本屋」であること。昨今の新刊書店では雑貨を売ったり、喫茶部を併設することで売り上げを補填(ほてん)する。あるいは、カリスマ書店員と祀(まつ)り上げられ、雑誌やテレビで本を推薦する。そういう風潮が柴田はイヤなのだ。「いつもどおり、いままでどおり、毎日を一生懸命にやる」ことが、柴田の言う「普通」だ。
芳林堂書店時代、店長だった彼がみんなに言った言葉が、本書のタイトルになっている。つまり「口笛を吹きながら本を売ろう」だ。そのために、本を売るための強い仕組みを裏側で作るというわけだ。そこが今は難しいと著者は食い下がるし、地方の駅前書店の経営者が聞けば、冗談じゃないよと怒るかもしれない。柴田の書店論は必ずしも正解ではない。正解を目指してはいないと言うべきか。
しかし、教師として子供とつきあった日々、トラック運転手で汗まみれになった体験が、すべて生かされて書店員としての柴田がある。だから言葉が生きている。
「自分で好きなことで誰かにしてやれることが、人柄といわれるものをつくる」などの名言が随所に登場して、読む気持ちにはずみをつける。「平凡であることに自信をもっている」柴田の「非凡」を引き出したのは、生徒役・石橋毅史の力量である。読み終わった後、また最初から読み返したくなる本だ。
ALL REVIEWSをフォローする