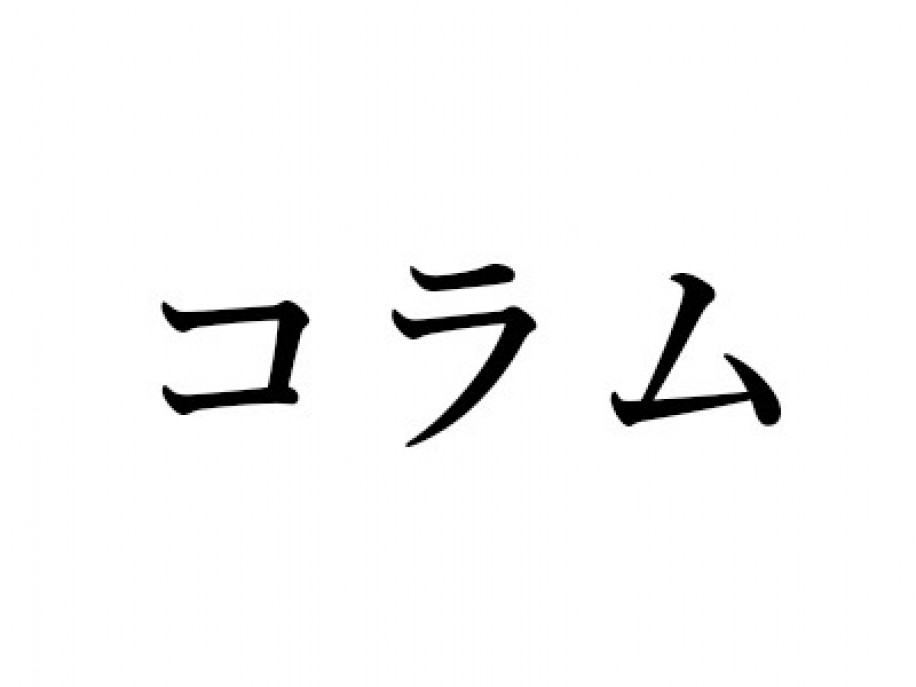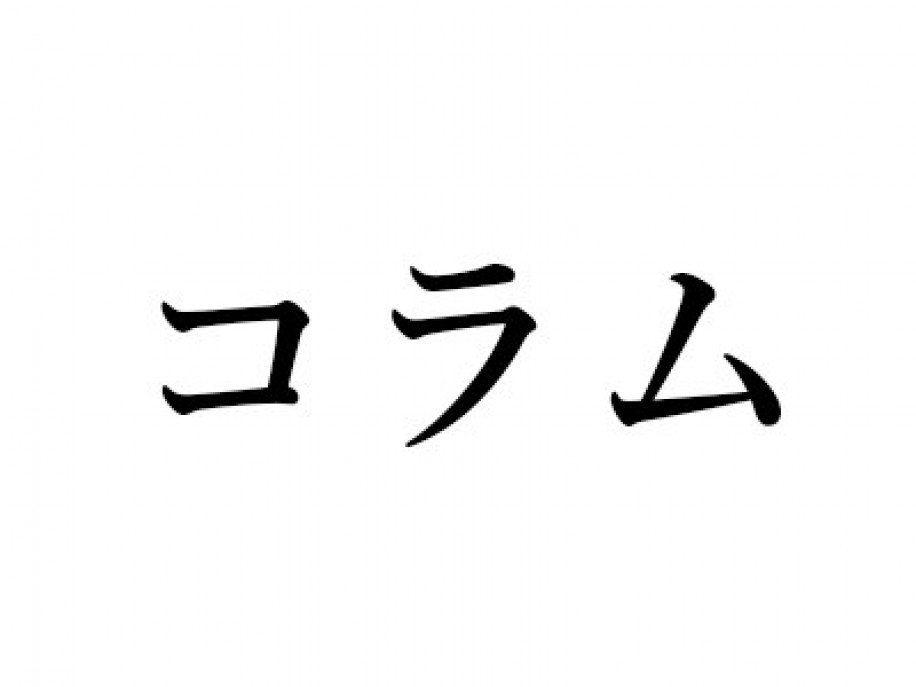書評
『細雪』(新潮社)
「細雪」の妙子
『細雪』は、言うまでもなく、谷崎潤一郎の代表作である。その「文豪」というイメージにとっては、『蓼喰う虫』や『吉野葛』だけでも充分かもしれないが、初期の「あくどい」短編群や『鍵』などの印象が強烈なだけに、ややもすると、耽美的という以上に、倒錯的な性を描いた作家という認識に偏しがちになる。本作が備えている重みは、決してないがしろには出来ない。しかし、見方を変えるならば、それだけ『細雪』は、谷崎らしくない小説だとも言える。まず長さが異例であり、谷崎好きを公言していても、実はこれだけは読み通せなかったという人もいる。傑作か否かについても、当然と考える人のいる一方で、思いの外、異論のある人も少なくないことを、私は昨年の没後五十年をきっかけとした議論で知った。
私自身は、その歴史的意義に鑑みても、この作品を軽んずる気持ちはさらさらなく、読んでいて退屈はしないのだが、谷崎の代表作としては、『痴人の愛』や『春琴抄』など、他にもっと良い作品がある気がする。
私がこの小説に今ひとつのめり込めないのは、何よりも、はっきりとしない主人公の雪子の性格に魅力を感じないからである。
蒔岡(まきおか)四姉妹の人物造形は、あまりに世代論的なグラデーションになりすぎているのではあるまいか。しかも、例えばトーマス・マンの『ブッデンブローク家の人々』のような一族四代にわたる長大なクロニクルではなく、保守的過ぎる長女の鶴子から、次女幸子、三女雪子を経て「近代娘らしい」末っ子の妙子に至るまでの年齢差には、時間的なダイナミズムが欠けていて、むしろそれを、物語的にはあまり必然性のない東京と阪神間の空間的な移動で補っている観がある。
幸子は、谷崎夫人松子がモデルだったせいもあり、その理想的な女性像のようにも語られてきたが、しかし、妙子と恋仲にあった板倉が、脱疽(だっそ)のために死に瀕し、悶え苦しむ姿を見ながら、これで妹が「氏も素姓も分からない丁稚上りの青年」と結婚せずに済むと、ほっとするくだりなどは、幾ら時代が時代とは言え、なかなか今日すんなりとは共感しがたい。作者である谷崎自身の、ほとんど化け物扱いのような板倉の描写もヒドい。
肝心の妙子も、湿っぽい悲嘆からは無縁なのだが、しかしこの辺りから、彼女の性格には谷崎作品でおなじみの「あくどさ」が滲み出てきて、とりわけ、残り四分の一ほどになって、赤痢に罹(かか)る辺りからは、俄然、存在感を増してくる。この時の妙子の「不健康さ」を描く谷崎の筆もまた情け容赦なく、彼の根本的な価値観に触れるようで面白いが、そこから露わになってくる妙子の「一種のヴァンパイア」的な放恣(ほうし)さは、否応なく『痴人の愛』のナオミや『鍵』の主人公の妻、『瘋癲(ふうてん)老人日記』の颯子(さっこ)など、お馴染みの女たちを連想させる。
私が『細雪』を本当に面白いと思うのはこの辺りで、四姉妹の中では、やはり妙子が一番のお気に入りである。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする