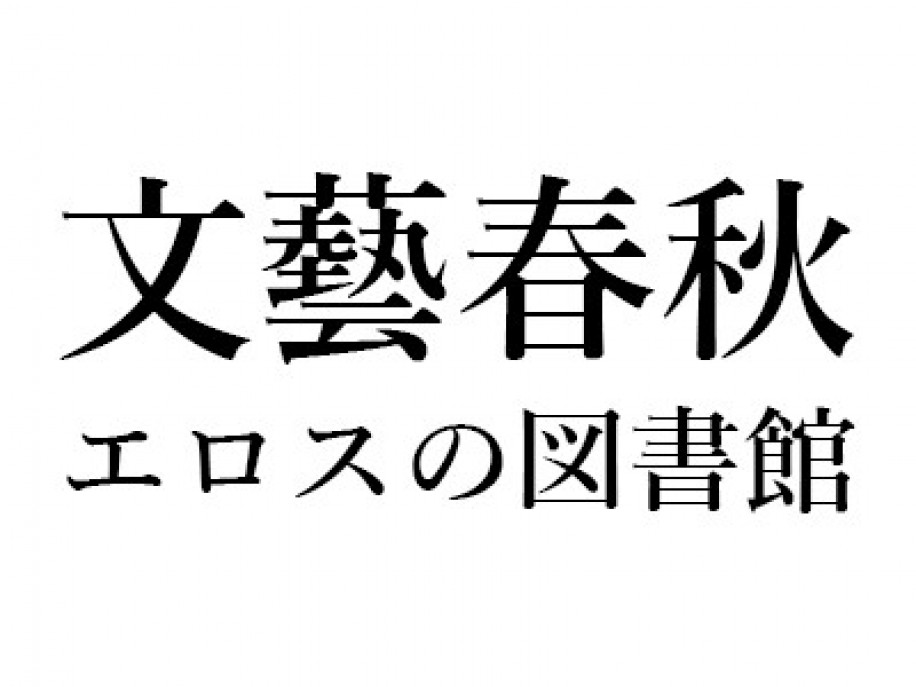書評
『ブロッケン山の妖魔―久野豊彦傑作選』(工作舎)
霧と光の作用で山頂に現れる大きな人影――ブロッケン山の大入道としてよく知られる現象をモチーフにしたエロティックな幻想譚が、久野豊彦傑作選の表題作だ。ブロッケン山の妖魔の正体を見届けるため、黒人の彼氏を伴って入山したきり戻らない美女スプリシオ。心配した「僕」は彼女の母親一行につきそって山頂を目指す。そこで彼が見たものはスプリシオの巨大な影。
やがて、やはり大入道と化した彼氏の〈怪腕が、濃霧のなかを潜って、彼女の背後の方へ廻ってゆくと、自然に巨大な痴情の活劇が、霧の人間によって始まり〉だす。空に映し出される巨人サイズのポルノ映画。エロティックなんだけれど、どこか可笑しみもともなうこのくだりの描写が絶品だ。
あるいは「シャッポで男をふせた女の話」の荒唐無稽さはどうだろう。大連の街角で〈薔薇の花の香水を泳いできた外套の女〉と出逢う〈私〉。誘われるまま家までついて行った〈私〉に、〈魚花娘〉と名乗る女は自分の生い立ちを語りだす。〈――日露戦争とロシアの革命がなかったなら、今頃、妾はどうしているでしょうか。父のおかげで、妾は屹度(きっと)、トントン拍子に女実業家となり、東洋の舞台を切りまわしたそのあとで、今度は宗旨をかえて女角夫になっていた筈なのです。〉
なぜ女角夫? わからない(笑)。しかも、この奇天烈な発想の持ち主は〈猫を蒸して、前足そろえたままのを一匹ぐるみに皿に盛ってきて、これでお腹を膨らしてくれと云う〉のである。その上、大変な艶福家でもあり、屋敷の中に大勢の内縁の夫を飼っている。でもって、彼女と二人で風呂に入っていた〈私〉を、嫉妬に狂った男どもが襲撃するのだ。真っ裸の〈私〉は咄嗟に飛び込んだ樽から手足を出すなんて漫画みたいな格好で逃げ出すのだが、翌朝新聞を開いて驚嘆する。彼女が〈黒ん坊に擽(くすぐ)られながら遂に致死した〉という記事を発見して――。
大正から昭和初期にかけて、川端康成ら新感覚派が頭角を現した時代に、モダニズムの尖端的作家と称されながら、たった一〇年間しか作品を発表せず、その後、忘れ去られてしまった久野豊彦。鈴木一誌による装幀も美しいこの作品集を読むと、かつて豊彦が文壇から理解されず、批評の対象になりにくかった理由がよくわかる。圧倒的に新しすぎたのだ。発想が、文体が、エズラ・パウンドの詩の構成を下敷きにしたという作品の結構が。豊彦が文学界から姿を消して約七〇年。ようやく時代が彼の新しさに追いついた。編者に深く感謝したいと思う。このような天才の残欠を、日本文学史という豊かさの中にも所々虚ろな洞を抱えた地層から掘り起こしてきてくれたことに。二一世紀の快挙と呼ぶべきだ。万歳三唱。
【この書評が収録されている書籍】
彼女の耳は、世界のクエスチョン・マアクである。彼女の鼻の穴は、瓦斯(ガス)タンクである。彼女の顔の輪郭は、三角形の大破片である。彼女の乳房は無限の円のなかの紅い一点の太陽である。彼女のオルガンは、汽船から黒煙を吐きだしている。
やがて、やはり大入道と化した彼氏の〈怪腕が、濃霧のなかを潜って、彼女の背後の方へ廻ってゆくと、自然に巨大な痴情の活劇が、霧の人間によって始まり〉だす。空に映し出される巨人サイズのポルノ映画。エロティックなんだけれど、どこか可笑しみもともなうこのくだりの描写が絶品だ。
あるいは「シャッポで男をふせた女の話」の荒唐無稽さはどうだろう。大連の街角で〈薔薇の花の香水を泳いできた外套の女〉と出逢う〈私〉。誘われるまま家までついて行った〈私〉に、〈魚花娘〉と名乗る女は自分の生い立ちを語りだす。〈――日露戦争とロシアの革命がなかったなら、今頃、妾はどうしているでしょうか。父のおかげで、妾は屹度(きっと)、トントン拍子に女実業家となり、東洋の舞台を切りまわしたそのあとで、今度は宗旨をかえて女角夫になっていた筈なのです。〉
なぜ女角夫? わからない(笑)。しかも、この奇天烈な発想の持ち主は〈猫を蒸して、前足そろえたままのを一匹ぐるみに皿に盛ってきて、これでお腹を膨らしてくれと云う〉のである。その上、大変な艶福家でもあり、屋敷の中に大勢の内縁の夫を飼っている。でもって、彼女と二人で風呂に入っていた〈私〉を、嫉妬に狂った男どもが襲撃するのだ。真っ裸の〈私〉は咄嗟に飛び込んだ樽から手足を出すなんて漫画みたいな格好で逃げ出すのだが、翌朝新聞を開いて驚嘆する。彼女が〈黒ん坊に擽(くすぐ)られながら遂に致死した〉という記事を発見して――。
大正から昭和初期にかけて、川端康成ら新感覚派が頭角を現した時代に、モダニズムの尖端的作家と称されながら、たった一〇年間しか作品を発表せず、その後、忘れ去られてしまった久野豊彦。鈴木一誌による装幀も美しいこの作品集を読むと、かつて豊彦が文壇から理解されず、批評の対象になりにくかった理由がよくわかる。圧倒的に新しすぎたのだ。発想が、文体が、エズラ・パウンドの詩の構成を下敷きにしたという作品の結構が。豊彦が文学界から姿を消して約七〇年。ようやく時代が彼の新しさに追いついた。編者に深く感謝したいと思う。このような天才の残欠を、日本文学史という豊かさの中にも所々虚ろな洞を抱えた地層から掘り起こしてきてくれたことに。二一世紀の快挙と呼ぶべきだ。万歳三唱。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア

Invitation(終刊) 2003年6月号
ALL REVIEWSをフォローする