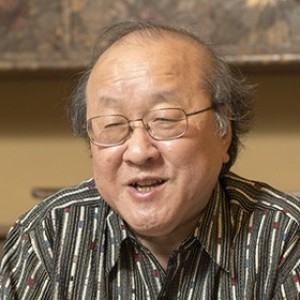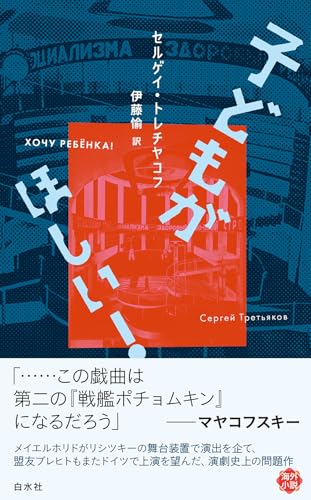書評
『けものたちは故郷をめざす』(岩波書店)
人間が存在することの不透明さ
安部公房が亡くなってから、もう二七年が経つ。生前は現代日本を代表する作家として活躍し、ノーベル文学賞の有力候補とも目されたが、その後の目まぐるしい流行の変遷を経て、過去の作家として文学史の中に安置されてしまった、という印象を受ける。しかし、彼の切り開いた文学の地平は、同時代の純文学の主流から際立って異質であっただけでなく、いま読んでも驚くほど現代的であり、最先端の世界文学を半世紀以上も前から先取りしていたように見える。『けものたちは故郷をめざす』は一九五七年に刊行された初期作品で、『砂の女』(一九六二)のようにいち早く多くの外国語に翻訳されて世界的に読まれたわけではない。しかし、砂漠、辺境、境界、故郷喪失といったテーマを正面から扱った、安部公房の原点ともいうべき作品であり、現代のわれわれにも鋭く問いかけてくる――そもそも、故郷とは、日本とは何なのか、と。
主人公は満州の地方都市に住む久木久三という少年。十六歳のとき終戦を迎え、関東軍が撤退して崩壊した満州国に取り残され、ソ連兵のもとで孤児として二年半以上暮らしたが、ある日意を決して脱走する。しかし無政府状態となった満州では、八路軍(中国共産党軍)と国府軍(国民党軍)が激しい内戦を繰り広げており、久三はたまたま出会った正体不明の高石塔(こうせきとう)という人物とともに、生と死の境をさまよいながら、満州の荒野を徒歩で南へと下っていく。こうして二人は「敵と味方の境界線」上を進んでいったわけだが、高石塔の言うように「なんといっても一番危険なのが境界線」であり、「こういう御時世には、どうしても境界線の幅がひろがってしまう」のである。そして久三は筆舌に尽くしがたい苦難の末に瀋陽にたどり着いて日本人居住区に行っても、「日本人があんなに黒い顔をしているもんか」と罵られて、締め出されてしまう。最後にようやく密輸船に乗り込ませてもらい、海路日本を目指すのだが……。
故郷を目指す久三の放浪の旅は、エンターテインメント性の高い冒険小説として読むことができる。しかし岩波文庫版に新たに解説を寄稿したリービ英雄が指摘する通り、「主人公は哲学用語を一つも口から発しないのに、ディティールが重なれば重なるほど『世界の中に人間が存在すること』の不透明さ」に迫っていくのである。この主人公を待っているのは、衝撃的な結末だ。主人公は高石塔とともに船艙(せんそう)に閉じ込められ、日本に上陸することも許されず、こう考える――「まるで同じところを、ぐるぐるまわっているみたいだな……いくら行っても、一歩も荒野から抜けだせない……もしかすると、日本なんて、どこにもないのかもしれないな」。
解説を書いているリービ英雄はアメリカ人でありながら、中国の辺境に分け入り、その経験を日本語で小説にするという、現代世界文学の中でも稀に見る越境者だ。その彼が師としたのが、川端でも三島でもなく、安部だったのは偶然ではないだろう。リービの解説は、こんなふうに結ばれている――「『日本』をめざした逃亡の果てに発せられた久三の絶叫は、『日本』だけを指しているのではない(……)。『砂の女』とはまた違った、もう一つの世界文学がここにあった」。
ALL REVIEWSをフォローする