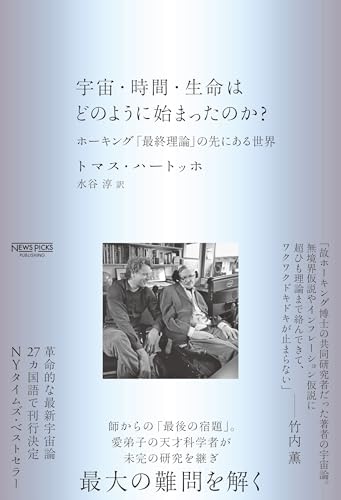書評
『空を見てよかった』(新潮社)
ひとりひとりに与えられた空間
包みから2センチほどの厚さの純白の本が出てきた。右端に小さく銀色に光る文字が置かれている。新型コロナウイルスの感染拡大によって、普通の暮らしができなくなり、重苦しい気分になっていたところに、思いがけない贈り物が届いたと思えた。
開く前に、手を洗った。ウイルス感染を避けるために行っている手洗いとは違って、心の置き場所を変えるための儀式として丁寧に洗い、真っ白い表紙を開いた。
ひかり あさ まばたき ふとん
りんご やま かけあし のはら
何でもない言葉だけれど、ああ私はこんなふうに暮らしているんだ、いや、暮らしたいんだと再確認し、気持ちが落ち着いた。
内藤礼の作品に初めて触れたのは2001年。瀬戸内海に浮かぶ直島の≪このことを≫家プロジェクト「きんざ」である。古い家屋の天井や床を除いた建物の中に一人で入り、15分間観賞する。外壁の下側にある小さな明り取りから入る自然光が、少しずつ動いていくのが心地よかった。
この作品につけられた言葉が本書にある。「生まれて来るひとはひとり、足をそろえ、足先だけを見つめ、それは一心に降り立つ。と、そのためらいのない着地に、はからずも自らの影とともにひとつの空間が生まれ、以来そのひとは、ごくわずかな広さともいえない、けれども、永遠に独自の、立つための地上の大きさを受け持つ」
ひっそりと、しかしわたしとして自分の足で立っていたいと願う者には、わたしの空間が与えられるのである。そこに答えがあるわけではないのだが、与えられてよかったと思える空間である。
東日本大震災の後、著者は初めて「ひと」を作った。軽いバルサ材の10センチにも満たない小さなひとは、展覧会場のあちこちにぽつんと置かれ、私が見ているようでもあり、見られているようでもある。多くの人が想定外と呼んだ災害の前で無力感にさいなまれているときに出会った小さなひとははかなげでありながら、わたしの空間を与えてくれるものだった。
内藤礼の作品は、これ以上の静謐さがあるだろうかと思わせるものでありながらどう生きたらよいのだろうと悩むときに多くを語りかけてくれる。ここでは作品と同じ静けさをもつ文が語り掛ける。
パッと開いたページのどこにも「ひとりにひとつ与えられている」空間を感じることができ、そこに招き入れられる心地よさを味わえるのである。
地上に存在していることは それ自体 祝福であるのか
著者が問い続けている問いである。本書の読者はともにこの問いに向き合わなければならないのだが、ここにある曖昧さやもどかしさは決して不快なものではない。むしろ爽やかである。
ここにはもうすでに空間があるというのに、なぜそれに触れようとしているのだろう。なぜものを置こうとしているのか。(中略)この世界に人の力を加えることがものをつくるという意味だと言うのなら、私はつくらない。
あまりにも小さすぎてその存在にすら気づかずにきたウイルスに振り回される体験をした後も、私たちはまだ物をつくり続けるのだろう。その時に、この言葉を思いながらつくることにしたいと思う。
ALL REVIEWSをフォローする