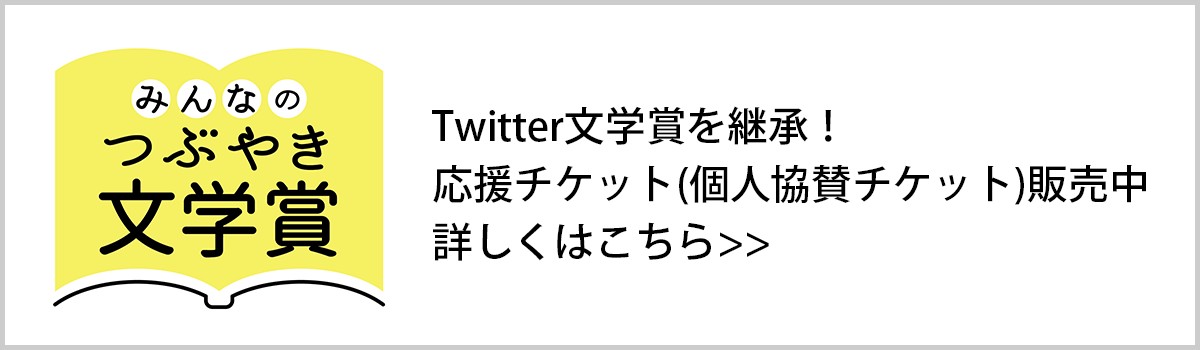書評
『ディディの傘』(亜紀書房)
韓国の現代史を背景に癒えない痛みと沈黙の重みを伝える
静かな、しかし言い表せないほどに大きな悲しみと怒り。目を細めて過去と未来を眺めたときに、胸に満ちる昏さ。韓国社会で息をしている人々の痛切な思いが、この1冊の本に綴じられた二つの中編から届いてくる。彼女・彼らが抱える決して癒えない「疼痛」が、神経を伝って、ページを握る指から手、そして身体を痺れさせる。「d」と題された一つ目の作品は、愛する人を喪ったdという人物の物語だ。dは同窓会でかつての級友のddと再会し、恋人となり、同棲を始める。だが、痛ましい事故で、ddは命を落としてしまった。小説全体には、dの深い孤独と寂寞の念が重く立ちこめている。作者は、こうしたdというひとりの人物の個人的な感情を、社会全体の痛みと融和させ、質量のある切実なものとして描き出すのである。
老女が語る朝鮮戦争の記憶。かつて人々がそこに理想を求めたものの挫折に終わった韓国初の住商複合施設に附帯する郷愁――それも再建により消滅しようとしている。光化門広場で行われるセウォル号事件を巡るデモ。韓国のいま・むかしを彷徨するdは失望を象った亡霊のようだ。
dは言う。「僕は自分の幻滅から脱出して、向かうべき場所もない。」絶望的なまでの「幻滅」は、しかし、その強さゆえに大衆を結びつける。二番目の作品「何も言う必要がない」には、そのことの希望と、同調圧力のなかで失われた声が描かれている。
小さい頃から遠くで見ていたソ・スギョンに「私」が話しかけることができたのは、ある学生運動で拘束されている最中だった。以来、二人の間に芽生えた愛は消えることがない。だが、「私」たちは、女性、そして同性愛者であることから、差別的な眼差しで世間から見られている。物語は、「私」の視点を通じて、マジョリティの立場に立つことで見えなくなっているものを、捉え返していく。
例えば、作中に「墨字の世界観」という言葉が出てくる。点字とは対照的に、インクで記された文字を墨字と呼ぶのだが、その言葉を私たちは普段、必要としない。けれど、それは「見ることができる」ことが自明となっている世界を「常識」としてしまっていることを意味する。そうではない世界は、なぜ、当たり前ではないのか。そのことを問う小説は、ナチスに迫害された同性愛者たちの苦しみを見つめ、権威となっているものを訴追する。
韓国社会に対する失意が民衆を結束させた「キャンドル革命」のエネルギーが活写されるラストは眩ゆいが、作者はそのために堪えなければならなかった痛みも映し出すことを忘れない。社会の変革が達成された瞬間にあげることのできなかった悲鳴を刻印しているのである。
傷痕が乾かぬ社会。蔓延する閉塞感。諦念。他人事ではない。だからこそ私たちは、dや「私」の沈黙に耳を傾け続ける必要があるのだ。
週刊金曜日 2020年10月30日号
わたしたちにとって大事なことが報じられていないのではないか? そんな思いをもとに『週刊金曜日』は1993年に創刊されました。商業メディアに大きな影響を与えている広告収入に依存せず、定期購読が支えられている総合雑誌です。創刊当時から原発問題に斬り込むなど、大切な問題を伝えつづけています。(編集委員:雨宮処凛/石坂啓/宇都宮健児/落合恵子/佐高信/田中優子/中島岳志/本多勝一)
ALL REVIEWSをフォローする